


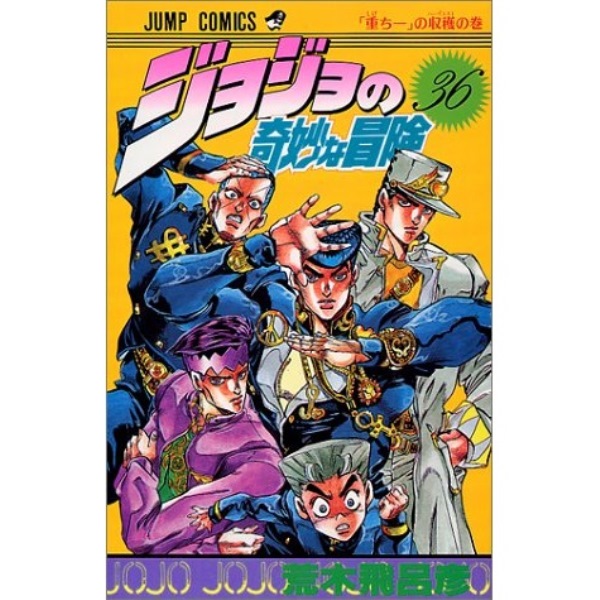
今回取り上げるのは荒木飛呂彦。代表作『ジョジョの奇妙な冒険』で、「少年ジャンプ」に永らく君臨し続けた作家の一人です。
前衛アートのような特異な作風でありながら、極上のエンターテイメント性で人気を獲得し、強豪ひしめく全盛時代の「少年ジャンプ」を走り抜けました。熱狂的なファンも多く、アート方面からの注目度も高い作家です。2010年にはルーヴル美術館からの正式なオファーにより、フランスでフルカラーの描きおろしマンガも刊行されました。
荒木の代表作である『ジョジョの奇妙な冒険』は、総計100巻を超える大長編ですが、数巻から二十数巻にわたるセッションごとに舞台や主人公が変わっていき、ジョースター一族と不死者ディオとの代々にわたる戦いの物語が延々と語られていきます。
こうした壮大な一族の物語を、代々にわたって語っていく手法は、フォークナーやマルケス、あるいはエミール・ゾラの「ルーゴン・マッカール叢書」を思わせますが、ご本人によると、スタインベックの『エデンの東』をヒントにしたそうです。
とにかく、この粘り気のあるしつこさが荒木作品全体にみなぎる一つの特徴をなしていて、物語が芋づる式に果てしなく続いていく展開は、チャカポコチャカポコとどこまでも続くキチガイ地獄外道祭文を聞いているようです。
というわけで、『ジョジョ』は、最初の巻から順番に、長い長い叙事詩を追いかけていくのも結構ですし、面白そうなところだけつまみ読みしてみる、というのでもいいでしょう。
たとえば、スタンドが初めて登場する第三部や、映画にもなった第四部は、日本人が主人公になって活躍するということもあり、一般的な人気も高いシーズンです。また、初期の波紋シリーズ(第一部・第二部)をこよなく愛するファンもいますし、作者の大好きなイタリアを舞台にしてマフィアの世界を描いた第五部、ギャル系のお姉さんを主人公に、中二病全開のセカイ系的な妄想が炸裂する第六部も根強い人気があります。
さて今回は、私が個人的にお気に入りの、第四部「ダイヤモンドは砕けない」からの一ページを模写してみました。
荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険」模写
(出典:荒木飛呂彦『ジョジョの奇妙な冒険』46集英社)
第四部「ダイヤモンドは砕けない」のクライマックス、宿敵・吉良吉影vs仗助・億泰コンビの戦いが、いよいよ最終ラウンドを迎えるシーンを描いてみました。
仗助は、かなりの重傷を負っているようですが、物語上、ほとんど問題にされていませんね(笑)。とにかく「ジャンプ」キャラといえば、腕や足がちぎれかけたり、腹に槍が貫通する程度のことは日常茶飯事なので、これぐらいの怪我でウダウダ言っている暇はありません。
仗助の全身から血が噴き出していますが、この粘菌のようなねばねばした血の表現は、原哲夫直伝の描き方です。
顔に強い陰影をつけるのはアメコミ風を思わせますが、『ジョジョ』の、どこかバタ臭いイメージに合っていますね。舞台は日本で、登場人物も全員日本人ですが、どう見ても【日本人には見えません】。仗助の顔は、外国のファッションモデル、それも女性モデルを参考にしていると思われます。
【ドドドドド】という謎の擬音が入っていますが、これは、いわば映画の効果音のようなものです。ドラムの音のようなものですね。荒木作品には、非常によく出てくる表現です。
また、一コマ目の二人の立ち姿が、いわゆる【ジョジョ立ち】と言われる独特のポーズです。どうやったら上手く描けるのかわかりませんでしたが、元の絵より、ぐっとオーバーに描いたつもりで、ちょうどいい感じでした。
コマ割りも、なかなか斬新です。
コマを斜めに切ること自体は、さして珍しくありませんが、外枠まで斜形化してしまうのは独特です。こうした、ページごと斜形化するような極端なコマ割りは、第三部から第六部にかけて、特に多くなります。
とにかく『ジョジョ』の絵は、どこからどこまでも独特でアクが強く、一目見ただけで、すぐに『ジョジョ』の絵だとわかります。それこそが、作者・荒木飛呂彦の望んでいたことなのでした。
■梶原一騎と横山光輝
ジャンプの系譜上における荒木飛呂彦の位置づけは、平松伸二から原哲夫につづくリアル路線のバイオレンスものの系譜を受け継ぎつつ、独自のタッチを確立したものと言えます。そして、荒木の確立した、極端なパースや、ねじれたプロポーションなどのバロックな画風が、鳥山明のタッチと融合することで、尾田栄一郎『ONE PIECE』などに流れ込んでいきました。
それにしても、荒木の、この独特の画風は、いったいどこからやってきたのでしょう。
荒木が、子供の頃好きだったマンガの筆頭に、梶原一騎と横山光輝を挙げているのは面白いところです。
特に、淡白でフラットな印象すらある横山と、こってりとした荒木とでは、作風が全然違うようにも見えるのですが、デビュー当時の荒木作品を見てみると、あながち似ていなくもありません。
『ゴージャス・アイリン』(集英社)などに収録されている初期作品を見ると、のちの荒木作品に見られるような粘液質な、ドロッとしたところはなく、むしろ硬ささえ感じさせるほどの几帳面なタッチです。そして絵に淫するというよりは、トリッキーな仕掛けを凝らすことの方に、精力のほとんどを使っているようにも見えます。
(荒木飛呂彦『ゴージャス・アイリン』集英社)
一方、梶原一騎は、極めて暑苦しい熱血マンガの人でした。
梶原の資質を最も効果的に引き出した作家の一人に『巨人の星』の川崎のぼるがいます。川崎の絵には、どこかパースの狂った、おかしな感覚があるのですが、あの独特の遠近感は、どこをどう描いたらそうなるのか、よくわからないところがあります。あの奇妙なタッチが、梶原の過剰な情念をうまく掬い上げていたのです。
(梶原一騎・川崎のぼる『巨人の星』⑤講談社)
確かに荒木飛呂彦の中には、梶原一騎と横山光輝という相反する成分が共存しています。
『ジョジョの奇妙な冒険』には、梶原的なマッチョイズムも横溢していますが、一方で、横山光輝の歴史マンガのように、盤上の駒を淡々と眺めているような冷めた視線も感じられるのです。
■最初はよくわかっていなかった私
ところで、私自身の『ジョジョ』とのつき合いを正直に述べておきますと、最初から注目していた、というわけではありませんでした。むしろ連載開始当初は、先行する『北斗の拳』に絵がそっくりだな、という印象を受け、ちょっと距離を置いていたように思います。
クセのあるセリフまわしや、デフォルメの効いたタッチなど、個性の片鱗は感じられましたが、まだ十分に開花しきっておらず、むしろ『北斗の拳』との差異化を図るため、無理してヘンなことやってる、と私には思えました。例の「オラオラオラ」だって、要するに「あたたたた」のパクリじゃん…と、『北斗の拳』信者だった私は、ヒヤヤカ~な目で見ていたものです。
この頃の原哲夫の影響力は、とても大きく、『北斗の拳』っぽい絵柄のマンガは、よく見かけられました。先輩格の宮下あきらまでが、だんだん影響を受け始めていたほどです。
『ジョジョの奇妙な冒険』も、そうした原哲夫エピゴーネンの一つのように、私は感じていたのです。
とはいうものの私自身、「ジャンプ」の定期購読者ではなかったので、横目でチラチラ見ていただけなのですがね。しかし、周りの人たちが、なにかというと「スタンド、スタンド」と言い出すので、気になって単行本を最初から読み始めた記憶があります。ということは、どんなに早くても第三部が始まって以降の読者ということになります。
ヒヤヤカな読者が、いつ頃から軟化し始めたのかは、もう記憶もおぼろですが、少なくとも第四部・杜王町編が始まったころには、すでに「参りました」という心境になっていました。
■いかにも今どきな第四部
第四部は、今振り返ってみても、やはり一番面白いですね。なんといっても日本が舞台になっているだけあって、どのキャラも生き生きしています。
特に岸辺露伴と吉良吉影の二人は、それまでのシリーズ作品にはちょっと見受けられない個性があって、目を引かれました。
この二人は、どちらも特異なキャラを持ちながらも、あまりそれを主張しようとはせず、市井の片隅でひっそりと暮らしていこうとしているところが共通しています。
とりわけ吉良吉影などは、一応、このシーズンのラスボスにあたるわけですが、それまでのラスボスであったディオとは対極的な、後ろ向きな性格に特徴がありました。
この男は快楽殺人を繰り返す極悪人であるのですが、その一方で「植物のように平穏な人生」を望む人物でもあります。
対人コミュニケーションが超苦手で、さりとて引きこもりながら生活していけるほどの才覚もないので、やむなく宮仕えなどして日々をしのいでいる私みたいな人間には、吉良みたいなタイプの気持ちは手に取るようによくわかります。
とにかく静かに暮らしたい、放っといてほしい、ただそれだけ…。
しかし、放っといてほしいと言ったって、吉良の場合、自分が妙齢の婦女子を放っとかないから、いろいろ面倒なことに巻き込まれるのだから自業自得ではあります。
あくまで平穏な人生を望む吉良吉影は、犯罪の痕跡を完全に抹消することで、自分の静謐な暮らしを維持していこうとするのですが、ふとしたことから主人公・仗助たちの知るところとなり、彼らとの闘いに巻き込まれます。
しかし、本人には自業自得などという自覚は全くなく、絶えず繰り返されるのは、「なんてオレはついていないんだ…今日は厄日だ…」という呪詛の言葉ばかり。
こうした、自分の全能感だけを大事にし、それ以外のものは全く目に入らないタイプというのは、なんだか今どきな感じがします。
先ごろ、完結した「エヴァンゲリオン」の主人公の父、碇ゲンドウなんて、まさにそのタイプでした。
別に世界をどうにかしたいわけではない。しかし自分の気持ちをどうにかするために結果的に世界がメチャクチャになってしまうことは、やぶさかではない……。
壮大な野望の核心は、膝が抜けるほどつまらないものでした。
これは『鬼滅の刃』のラスボス鬼舞辻無惨にも感じられます。彼にも、世界に向かって外に開いていく野心は希薄で、結局、自分の全能感が満たされさえすればいいのですね。物語終盤の彼は、ひたすら「お前ら、うっとうしいんだ」と毒づきながら、降りかかる火の粉を払いのけることのみに終始し、最後は赤ん坊のようになって自滅していくのですが、ラスボスらしからぬ閉じたメンタリティには憐れみすら覚えました。
■編集者との二人三脚
おそらく岸辺露伴と吉良吉影という二大キャラは、荒木先生の好みのタイプらしく、どちらにもスピンアウト作品があります。なにほどかは自己が投影されたキャラクターなのでしょう。
(荒木飛呂彦『岸辺露伴は動かない』②集英社)
しかし荒木飛呂彦は、ヘンリー・ダーガー<1>のように、うちに引きこもって自分だけの闇の王国を創り上げていく、というタイプでもありませんでした。荒木飛呂彦の感性は最初から開かれていたのです。
そんな彼が選んだ主戦場は「少年ジャンプ」という雑誌でした。
「少年ジャンプ」といえば、とにかくアンケート至上主義で、「友情・努力・勝利」の方程式にのっとった同工異曲の作品ばかりを載せているように思われがちですが、決してそのようなことはありません。
古くは諸星大二郎や星野之宣のような作家を世に出したことからもわかるように、積極的に異色の作家を発掘しては世に問うてきた雑誌なのです。
そして各編集者が、これぞと思った新人を見つければ、徹底的に指導し、たとえアンケートの結果が芳しくなかろうと、他の編集者から「ジャンプ」らしくないと言われようと、決して怯むことなく二人三脚で、どこまでも食らいついていきました<2>。
むしろ、レジェンド級の作家を生み出した名物編集者と言われる人ほど、いかに「ジャンプ」らしくない作家、「ジャンプ」の方程式を突き崩すような作家を、鵜の目鷹の目で探していたかがわかります。
ハイブロウなアメコミ風マンガを描いていた鳥山明を徹底的にシゴいて『Dr.スランプ』を成功に導いた鳥嶋記者、『北斗の拳』の原哲夫や『シティーハンター』の北条司とのタッグで知られる堀江記者。まつもと泉、萩原一至、冨樫義博などを世に送り出した高橋記者といった辣腕編集者たちは、ジャンプに新風を吹き込む作家を見出しては鍛え上げ、ジャンプの新しいセオリーを創り上げていった人たちです。
荒木飛呂彦を最初に見出した椛島記者もそうした編集者の一人でした。新人・荒木利之(当時)クンの原稿を見て「こいつはイケル」と踏んだ椛島記者は、徹底的に彼をシゴキ上げます<3>。
こうして世に送り出された『魔少年ビーティ―』は、あえなく十週打ち切り。続く『パオ―来訪者』も短期で打ち切りとなりました。この両作品とも、ジャンプの成功セオリーから、大幅に逸脱した破格の作品だったのですが、内外の反対を押し切って連載に持ち込んだ企画でした。それが大方の予想通りの惨敗に終わったのです。
(荒木飛呂彦『魔少年ビーティ―』『バオー来訪者』②集英社)
それでも荒木の才能を1ミリも疑わなかった椛島は、荒木に、さらなる脱皮を促すべく、彼をヨーロッパ取材旅行に連れ出します<4>。二作連続でコケた新人作家に、ここまで入れ込む椛島編集者の信念には脱帽せざるを得ません。
しかし、この先行投資は、結果的に費用対効果としては最大限と言っていいほどの成功を収めました。
今では有名な話になっていますが、イタリアで見たルネッサンス芸術の数々に圧倒された荒木は、「自分の進むべき道はここにある」と悟ったのです。のちに「ジョジョ立ち」とも呼ばれる荒木の独特の画風がこうして生み出されたのでした。
■他者の声
しかし、荒木飛呂彦の、あの独特のタッチや作風は、決して芸術的な感興にまかせて作り上げている、といったものではなく、あくまで読者を楽しませるためのサービス、ということで徹底しています。
“『ジョジョの奇妙な冒険』が「王道漫画」だと言うと、「え!?『ジョジョ』は異作じゃないの?」と思う人が多いかもしれません。(中略)けれども僕自身は、「『ジョジョ』は王道漫画だ」という自信をもって描き続けてきました。”(荒木飛呂彦『荒木飛呂彦の漫画術』集英社)
あくまで読者を楽しませるための王道マンガを描いていくこと。それこそが荒木の望んでいたことでした。そのためには他者の意見に耳を傾けることは重要です。
荒木飛呂彦ほどの大先生となると、若い編集者などは、つい平伏して「玉稿、頂戴いたします!」という態度になりがちなのですが、そんなとき、荒木は
「ちゃんと意見を言ってくれッ。それがキミの仕事だ」
と叱咤するそうです。
あくまで読者ファーストな荒木飛呂彦にとって、作品とは自分が描きたいものを描きたいように描くものではなく、お客さんを喜ばせるものなのです。そのためには、他人からの忌憚のない意見に耳を傾けることは、必須の要件なのでした。
そういえば、前々回紹介した高橋留美子も、徹底的に打ち合わせをして、編集者の意見を積極的に取り入れるタイプでした。
■バトルと智略
だからといって、もちろん人の言うことなら、なんでもホイホイ聞いている、というわけではありません。ときには「そんなのは絶対受けない」と言われても、それこそが自分の思う「王道だ」との信念があれば、何が何でもそれを貫き通そうとしました。
荒木の思う「王道」とは、第一に、謎とその解決でした。
それを最もストレートに打ち出したのが、最初の連載作である『魔少年ビーティー』だったのですが、これはあえなく討ち死にとなりました。
しかし、それでも荒木の信念は変わりません。
やり方さえ間違えなければ必ず成功する。こうした試行錯誤の上に誕生したのが『ジョジョの奇妙な冒険』だったのです。
強大な敵に、気力と根性のメガトンパンチで乗り切る車田正美イズムに、機智と計略で応酬するコンゲーム的要素を加えた『ジョジョの奇妙な冒険』は、ジャンプ式バトルものに新生面を切り開くことになります。
これが、トーナメントバトルものにありがちな敵のインフレーションを防ぎ、作品を長続きさせることになりました。
こうした理知的でパズル的な要素は、『幽遊白書』、『デスノート』、『暗殺教室』、『約束のネバーランド』といった作品に受け継がれ、新しいジャンプカラーを作っていくことになります。
限定された条件と、特殊なルールのもとで戦い続けるジョジョたちの姿は、つねに瞬間風速としての結果を求められるジャンプ方式のルールの中で、決して独自のスタイルを崩すことなく挑み続けた荒木自身の姿勢にダブるところがあります。
まずは、自分で、絶対解けないような難問を案出し、その次に、その難問を悪戦苦闘しながら自分で解く、という、いわば詰将棋のような一人二役を、荒木飛呂彦は常に自分に課し続けてきました。
第四部のラスト、対吉良戦(模写したシーンです)など、「これはもう、どう考えても主人公負けるしかないじゃん」というところまで作者も追い込まれたそうです。とことん自分を追い詰めた結果が、あのみごとな幕切れだったのです。
そして、こうした難問設定のレンジが極限にまで達したのが第六部「ストーンオーシャン」でした。
「ストーンオーシャン」では、作者の想像力の先の先のさらに先…と歩を進めていった結果、最終的には、ニーチェの永劫回帰や運命愛の哲学を思わせるような、とてつもない次元にまで突入していきます。まさか『ジョジョ』を読んでいて、こんなところに連れていかれるとは思ってもみませんでした。
『ジョジョ』の結末はどうするつもりなのかと聞かれると、荒木飛呂彦は、「それは一度も考えたことはない」と答えるそうです。
難問に挑みつつ生々流転しつづける『ジョジョ』の姿は、まさに、突然変異と自然淘汰というシンプルなルールだけを頼りに自己創出を繰り返す生命の姿そのものです。
◆◇◆荒木飛呂彦のhoriスコア◆◇◆
【日本人には見えません】88hori
きうちかずひろタッチが流れ込んでいる億泰が、かろうじて日本人ぽい顔に見えます。
【ドドドドド】77hori
原哲夫の「ゴゴゴゴ」の発展形でしょう。そして「ゴゴゴゴ」も、よく使われます。
【ジョジョ立ち】95hori
インスタなどでリアルにやるのが流行っているそうですね。
<1>ヘンリー・ダーガー
1973年、シカゴの片隅で身寄りのない老人が、ひっそりと息を引き取った。彼のアパートの遺品を処分しようと中に入った家主は、そこで大変なものを発見することになる。1万5000ページを超えるテキストと300点の絵画からなる狂気の一大サーガ『非現実の王国で』であった。この男は皿洗いや清掃夫として暮らしながら、誰に知られることもなく60年ものあいだ、この作品を作り続けていたのである。今では彼はアウトサイダーアートの巨匠と認知されている。
<2>大場つぐみ&小畑健という『デスノート』コンビによって描かれた『バクマン。』は、こうした少年ジャンプ編集部の内幕を、ある種のバトルマンガの舞台として描いた異色作でした。
<3>当時、荒木と似たような独特の作風により一部で人気のあったジャンプ作家に巻来功士がいます。彼が荒木ほどの成功を収められなかった原因の一つに、いい編集者に巡り合えなかったことがあるようです。ご興味のある方はぜひ、巻来功士『連載終了!』(イースト・プレス)を読んでみてください。
<4>実は、このとき荒木飛呂彦の取材旅行に同行しパリを案内したのが、留学中の学生だった若き日の中条省平氏でした。(中条省平『マンガの教養』幻冬舎より)
アイキャッチ画像:荒木飛呂彦『ジョジョの奇妙な冒険』36集英社
堀江純一
編集的先達:永井均。十離で典離を受賞。近大DONDENでは、徹底した網羅力を活かし、Legendトピアを担当した。かつてマンガ家を目指していたこともある経歴の持主。画力を活かした輪読座の図象では周囲を瞠目させている。
桜――あまりにもベタな美しさ◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一
今回のお題は「桜」である。 そこで、まず考えたのは、例によって「マンガに出てくる桜って、なんかなかったっけ」だった。(毎回、ネタには苦労しているのだ) しかし、真っ先に浮かんでくるのは、マンガよりも、むしろ映画やア […]
【追悼】鳥山明先生「マンガのスコア」増補版・画力スカウター無限大!
突然の訃報に驚きを禁じ得ません。 この方がマンガ界に及ぼした影響の大きさについては、どれだけ強調してもしすぎることはないでしょう。 七十年代末に突如として、これまでの日本マンガには全く見られなかった超絶的な画力とセンスで […]
今月のお題は「彼岸」である。 うっ…「彼岸」なのか…。 ハッキリ言って苦手分野である。そもそも彼岸なんてあるのだろうか。 「死ねば死にきり。自然は水際立っている。」(高村光太郎) という感覚の方が私にはしっくりく […]
さて、今回のテーマは「鬼」である。 「鬼」を描いたマンガはないか…と問われるならば、今ならやはり『鬼滅の刃』を思い浮かべる人が多いだろう。 ある意味で非常に古典的な、ストレートに怖い、「鬼」らしい「鬼」を […]
斎藤なずな「このマンガを読め!」ランクイン記念増補版【マンガのスコア】
『このマンガを読め!』(フリースタイル)というランキングものをご存じでしょうか。『このマンガがすごい!』 (宝島社)とタイトルがそっくりですが違うのです! 定期刊行形態としては、実は『読め!』の方がちょっとだけ早い。今 […]



