私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。




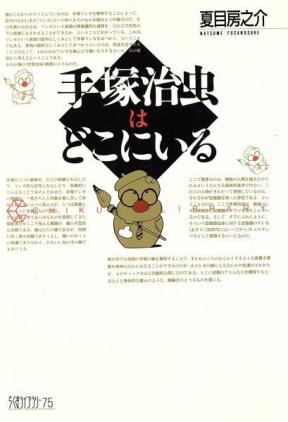
★バックナンバー:
手塚の描線の特質については、いろいろ語られていますが、ここでは夏目房之介さんの論考を紹介しておきましょう。夏目房之介『手塚治虫はどこにいる』(1992年)は、マンガコラムニストとして活躍していた夏目氏の、初の本格的批評の書であると同時に、以後のマンガ評論のスタイルを革新した歴史的名著でもあります。
それまでのマンガ批評は、主に文芸批評の方法にならった、作家の主題や内面にせまるテーマ批評がメインでした。そうした中、実作者ならではの視点から、マンガの表現構造そのものにフォーカスをあてた夏目氏の批評スタイルは大変斬新なものとして迎えられました。ゼロ年代以降、隆盛を迎えるアカデミックな方面でのマンガ研究に与えた影響は絶大なものがあります。
さて、この本の中で夏目氏は、手塚の描線の問題について興味深い指摘をしています。手塚は、その生涯を通じて丸みを帯びた描線を維持し続けたわけですが、同じ丸い描線といっても1950年代までと60年代以降とのあいだには大きな断絶があると指摘しています。
一見すると70年代以降、明白に劇画の影響でリアル化した描線の変化の方に眼がとらわれがちですが、それはむしろ表層的な変化であり、本質的断絶は月刊誌時代から週刊誌時代へ移行しつつあった60年前後にあったと見るのです。それは、内側へ閉じていこうとする求心的で内圧の強い線から、解放的でのびやかな流麗な線への変化です。
この夏目先生の分析、なかなか説得的ではありますが、実際のところどうなんでしょう。さっそく試してみようと思います。題材は今回も『火の鳥』です。
私たちがよく知っている『火の鳥』は、1967年「COM」誌上の連載から始まるバージョンですが、実はそれ以前にも手塚は『火の鳥』を描いています。1954年「漫画少年」版と1956年「少女クラブ」版です。ここでは同じ「黎明編」ということで、54年と67年の火の鳥を並べて描いてみました。


『火の鳥』より二点模写(引用元:角川書店版第1巻p7、第12巻p259)
実際描いてみてあきらかなのは、67年版の方が圧倒的に描きやすいということです。自然な手の動きになじんでいて、ラインが取りやすい。それに対して54年版の方は、慎重に方向を定めつつ、自覚的に線を引いて行かなくてはなりません。身の締まったパンのような、ふっくらしているんだけど重たい感じです。
それに対して67年版の方は、軽くてスピーディです。実際ペンを走らせる速度も1.5倍ぐらいは速くなりそうです。そして、筆圧にも違いがあります。それも紙に向かう筆圧というより、握るペンの方に力が入る感じです。ゆっくりと力を入れて、きれいな丸を描かなくてはならない。これは疲れます。
現代の多くの人は、鈍重で古めかしい感じがする54年の絵よりも、軽やかでスピード感のある67年の絵の方に好ましさを感じるのではないでしょうか。しかし50年生まれの夏目氏は、この描線の変化をリアルタイムに経験しており、それを子ども心に、はっきりと手塚の堕落として感じとったと言います。
記号性が強まった分、解読が容易で、一見すると表現が豊かになっているようにも見える。私自身、後年の手塚の流麗なタッチには、手になじんだ職人性のようなものが滲み出ていて、好ましさを感じます。しかし、その分、絵に淫するという感じは弱まっている。システマティックに、ばんばん描き飛ばしている感じです。
このような描線の変化に、どのような外部要因があり、また、そこに内在化された手塚自身の作家的資質の変化とはいったい何であったのか、夏目氏の著作では、それらが多数の図版資料ともに説得的に展開されていて、のちの夏目スタイルが、この時点ですでに確立されていることが分かります。ご興味のある方は是非そちらにもあたってみてください。
LEGEND01手塚治虫③
アイキャッチ画像:夏目房之介『手塚治虫はどこにいる』(筑摩書房)
堀江純一
編集的先達:永井均。十離で典離を受賞。近大DONDENでは、徹底した網羅力を活かし、Legendトピアを担当した。かつてマンガ家を目指していたこともある経歴の持主。画力を活かした輪読座の図象では周囲を瞠目させている。
山田風太郎『人間臨終図巻』をふと手に取ってみる。 「八十歳で死んだ人々」のところを覗いてみると、釈迦、プラトン、世阿弥にカント・・・と、なかなかに強力なラインナップである。 ついに、この並びの末尾にあの人が列聖される […]
文章が書けなかった私◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一
デジタルネイティブの対義語をネットで検索してみると、「デジタルイミグラント」とか言うらしい。なるほど現地人(ネイティブ)に対する、移民(イミグラント)というわけか。 私は、学生時代から就職してしばらくするまで、ネット […]
桜――あまりにもベタな美しさ◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:堀江純一
今回のお題は「桜」である。 そこで、まず考えたのは、例によって「マンガに出てくる桜って、なんかなかったっけ」だった。(毎回、ネタには苦労しているのだ) しかし、真っ先に浮かんでくるのは、マンガよりも、むしろ映画やア […]
【追悼】鳥山明先生「マンガのスコア」増補版・画力スカウター無限大!
突然の訃報に驚きを禁じ得ません。 この方がマンガ界に及ぼした影響の大きさについては、どれだけ強調してもしすぎることはないでしょう。 七十年代末に突如として、これまでの日本マンガには全く見られなかった超絶的な画力とセンスで […]
今月のお題は「彼岸」である。 うっ…「彼岸」なのか…。 ハッキリ言って苦手分野である。そもそも彼岸なんてあるのだろうか。 「死ねば死にきり。自然は水際立っている。」(高村光太郎) という感覚の方が私にはしっくりく […]






コメント
1~3件/3件
2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。
2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ
ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。
山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。
2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。