『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二
セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!
目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!




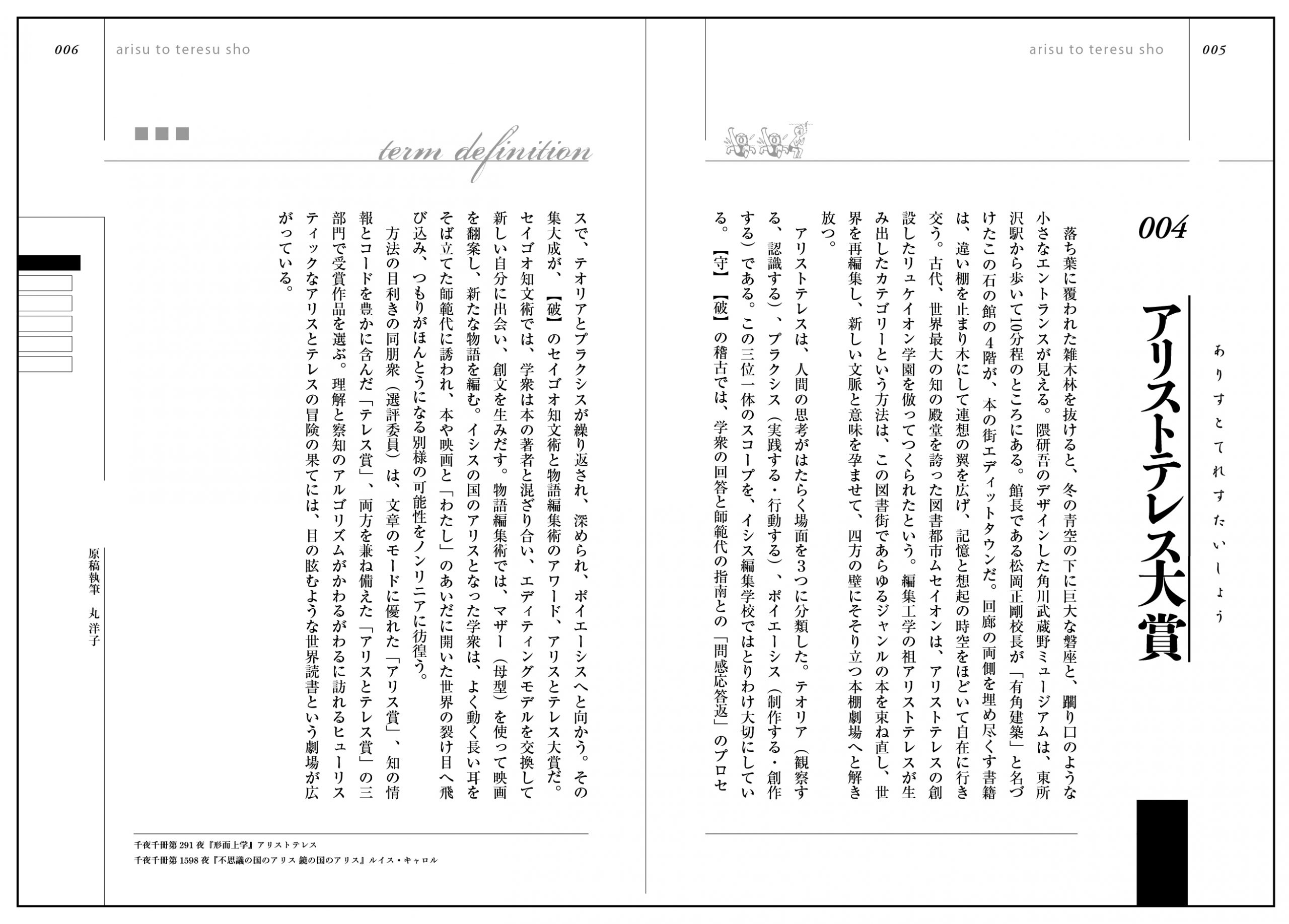
落ち葉に覆われた雑木林を抜けると、冬の青空の下に巨大な磐座と、躙り口のような小さなエントランスが見える。隈研吾のデザインした角川武蔵野ミュージアムは、東所沢駅から歩いて10分程のところにある。館長である松岡正剛校長が「有角建築」と名づけたこの石の館の4階が、本の街エディットタウンだ。回廊の両側を埋め尽くす書籍は、違い棚を止まり木にして連想の翼を広げ、記憶と想起の時空をほどいて自在に行き交う。古代、世界最大の知の殿堂を誇った図書都市ムセイオンは、アリストテレスの創設したリュケイオン学園を倣ってつくられたという。編集工学の祖アリストテレスが生み出したカテゴリーという方法は、この図書街であらゆるジャンルの本を束ね直し、世界を再編集し、新しい文脈と意味を孕ませて、四方の壁にそそり立つ本棚劇場へと解き放つ。
アリストテレスは、人間の思考がはたらく場面を3つに分類した。テオリア(観察する、認識する)、プラクシス(実践する・行動する)、ポイエーシス(制作する・創作する)である。この三位一体のスコープを、イシス編集学校ではとりわけ大切にしている。【守】【破】の稽古では、学衆の回答と師範代の指南との「問感応答返」のプロセスで、テオリアとプラクシスが繰り返され、深められ、ポイエーシスへと向かう。その集大成が、【破】のセイゴオ知文術と物語編集術のアワード、アリスとテレス大賞だ。セイゴオ知文術では、学衆は本の著者と混ざり合い、エディティングモデルを交換して新しい自分に出会い、創文を生みだす。物語編集術では、マザー(母型)を使って映画を翻案し、新たな物語を編む。イシスの国のアリスとなった学衆は、よく動く長い耳をそば立てた師範代に誘われ、本や映画と「わたし」のあいだに開いた世界の裂け目へ飛び込み、つもりがほんとうになる別様の可能性をノンリニアに彷徨う。
方法の目利きの同朋衆(選評委員)は、文章のモードに優れた「アリス賞」、知の情報とコードを豊かに含んだ「テレス賞」、両方を兼ね備えた「アリスとテレス賞」の三部門で受賞作品を選ぶ。理解と察知のアルゴリズムがかわるがわるに訪れるヒューリスティックなアリスとテレスの冒険の果てには、目の眩むような世界読書という劇場が広がっている。
千夜千冊第291夜『形而上学』アリストテレス
https://1000ya.isis.ne.jp/0291.html
千夜千冊第1598夜『不思議の国のアリス 鏡の国のアリス』
丸洋子
編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。
八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]
公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]
千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。 グノーシスとは「原理的 […]
木漏れ日の揺らめく中を静かに踊る人影がある。虚空へと手を伸ばすその人は、目に見えない何かに促されているようにも見える。踊り終わると、公園のベンチに座る一人の男とふと目が合い、かすかに頷きあう。踊っていた人の姿は、その男に […]






コメント
1~3件/3件
2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二
セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!
目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!
2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。
配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。
昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。
2025-07-07

七夕の伝承は、古来中国に伝わる星の伝説に由来しているが、文字や学芸の向上を願う「乞巧奠」にあやかって、筆の見立ての谷中生姜に、物事を成し遂げる寺島ナス。いずれも東京の伝統野菜だが、「継承」の願いも込めて。