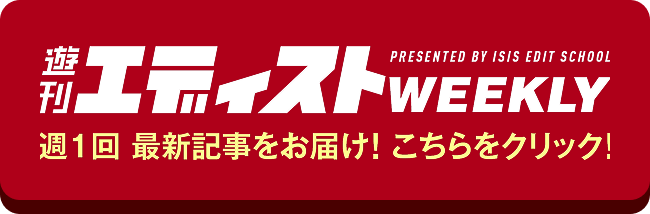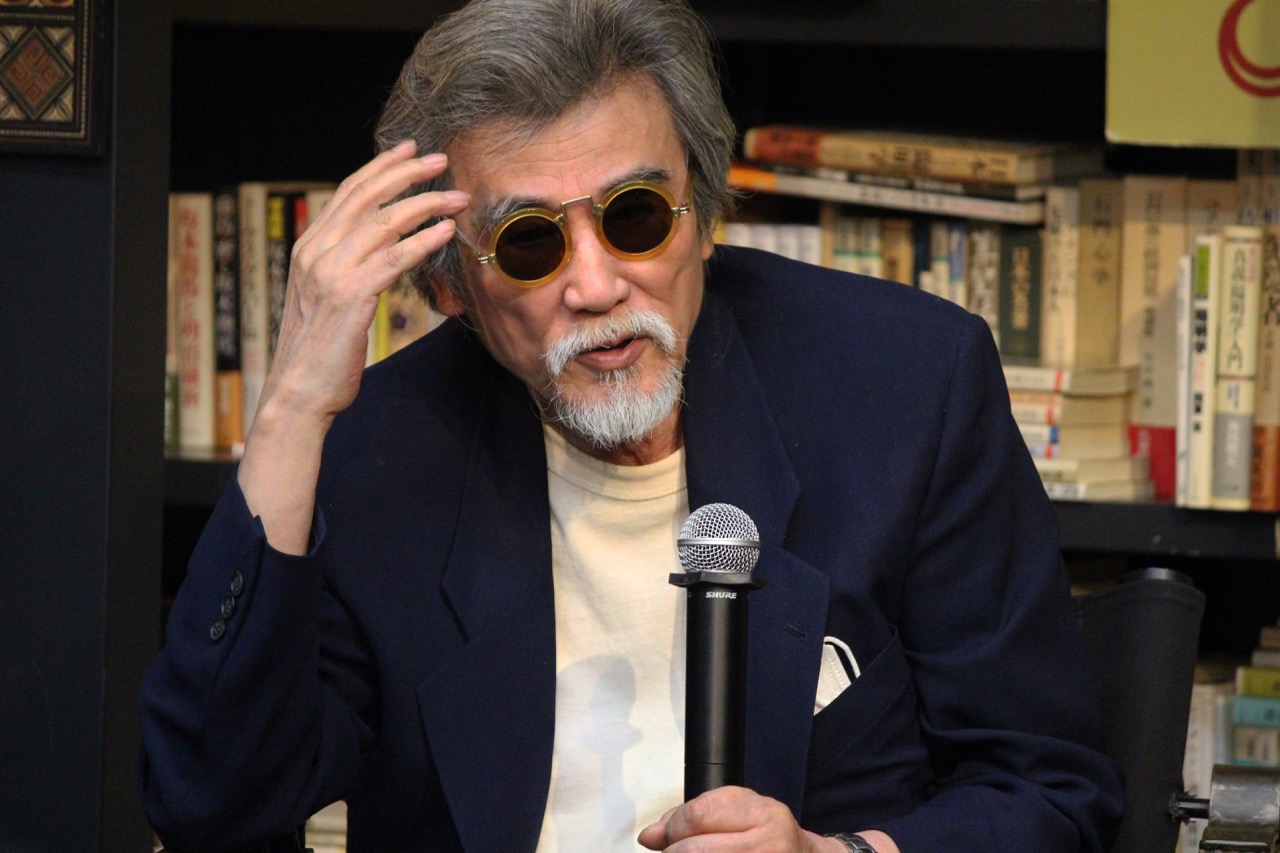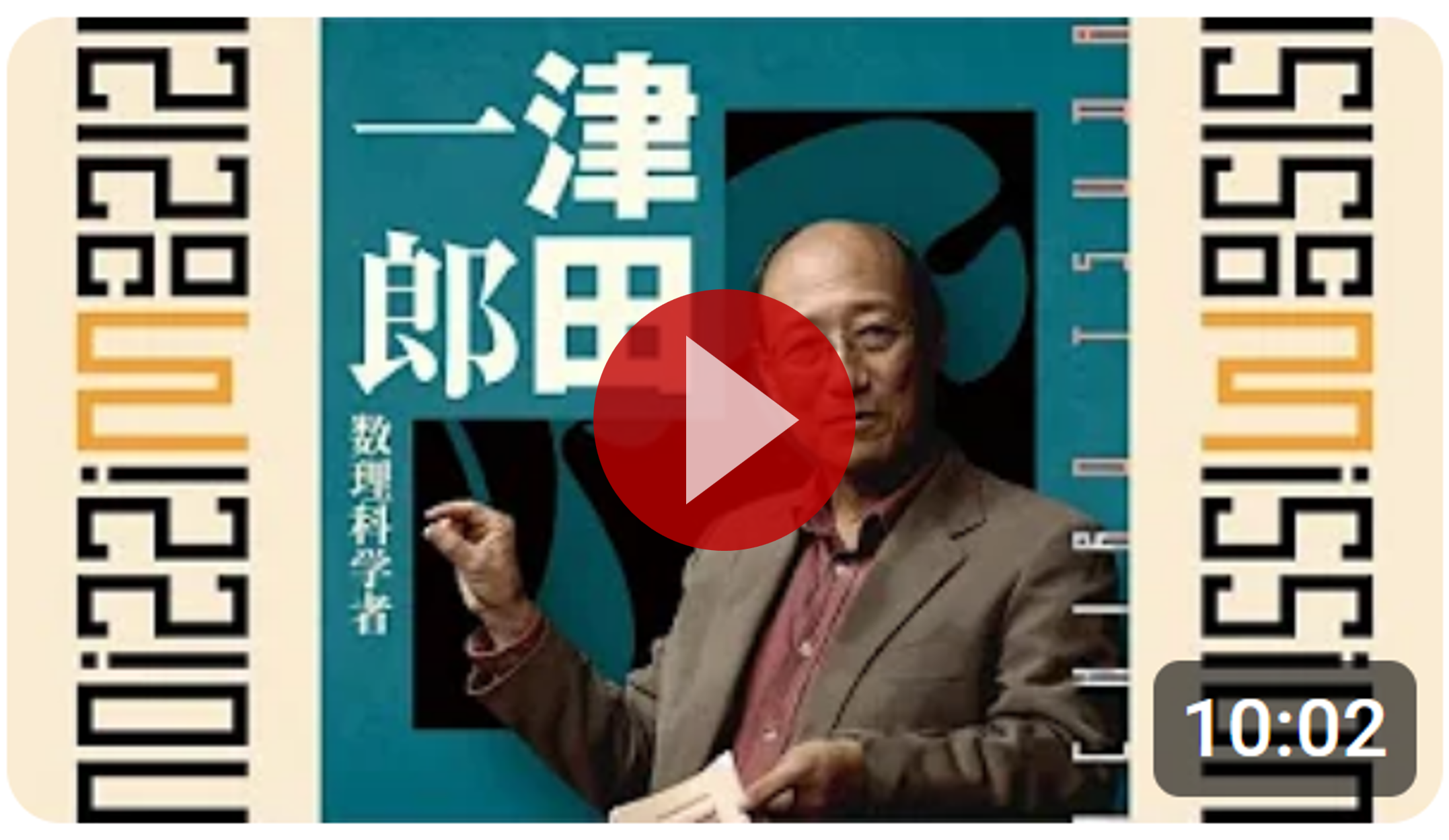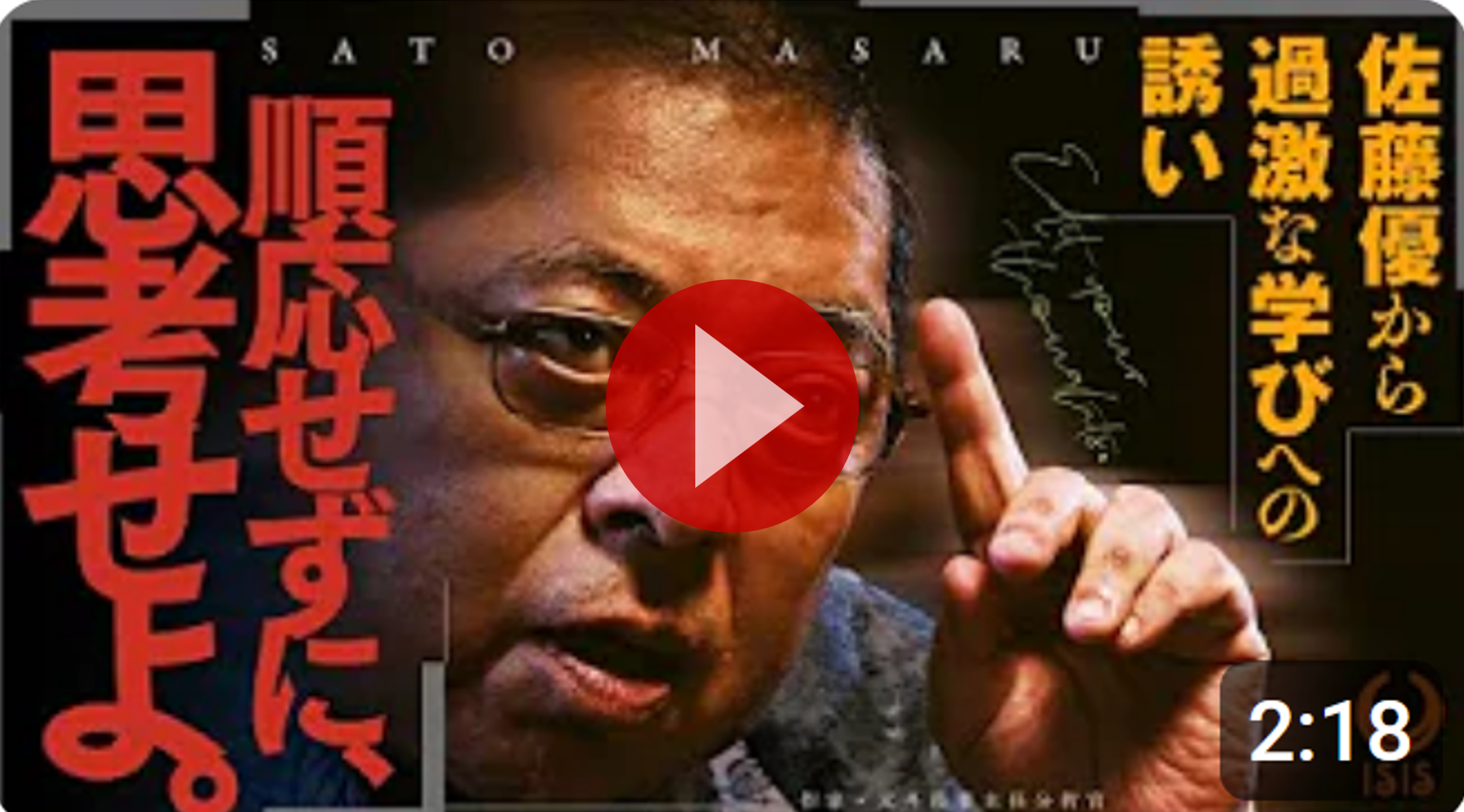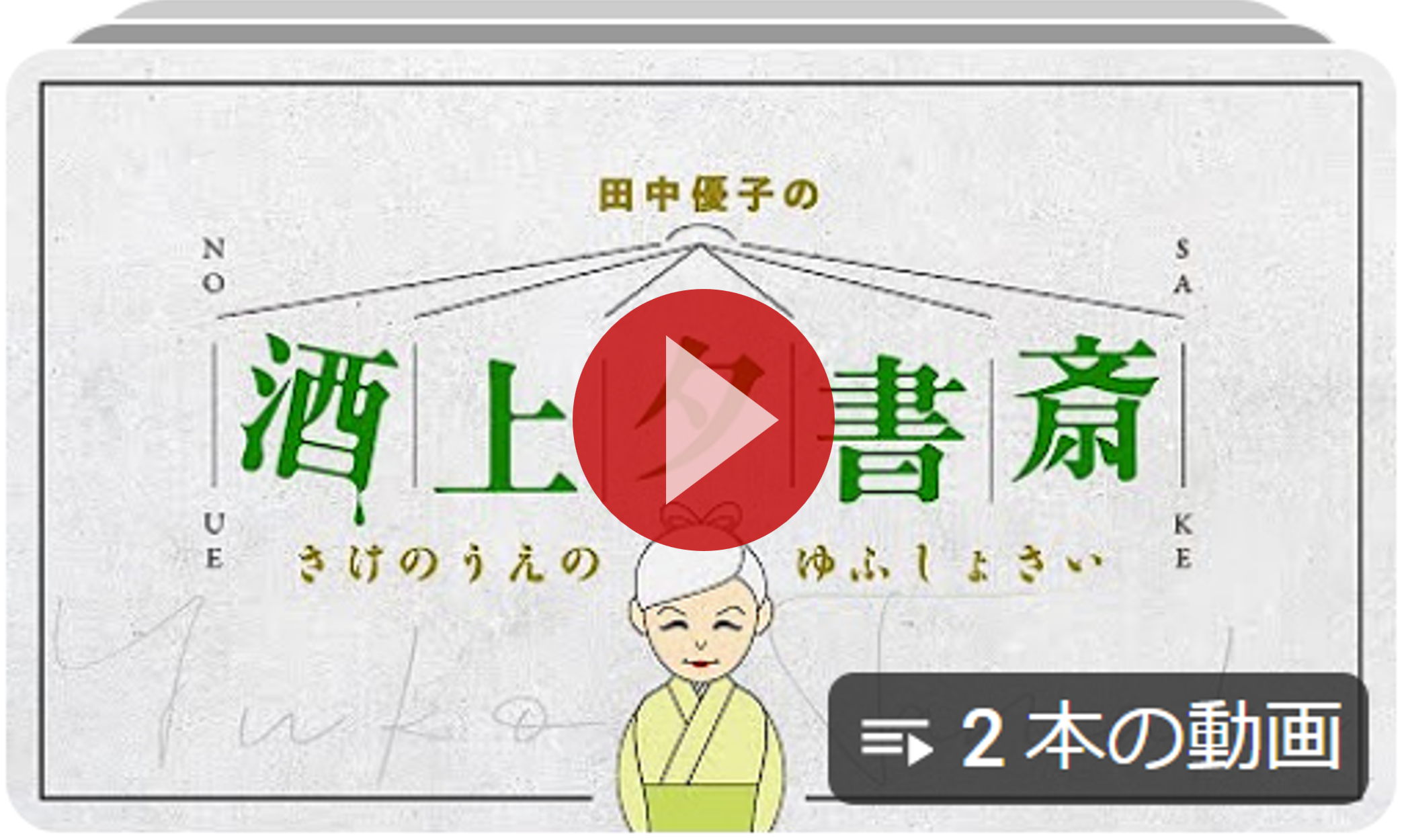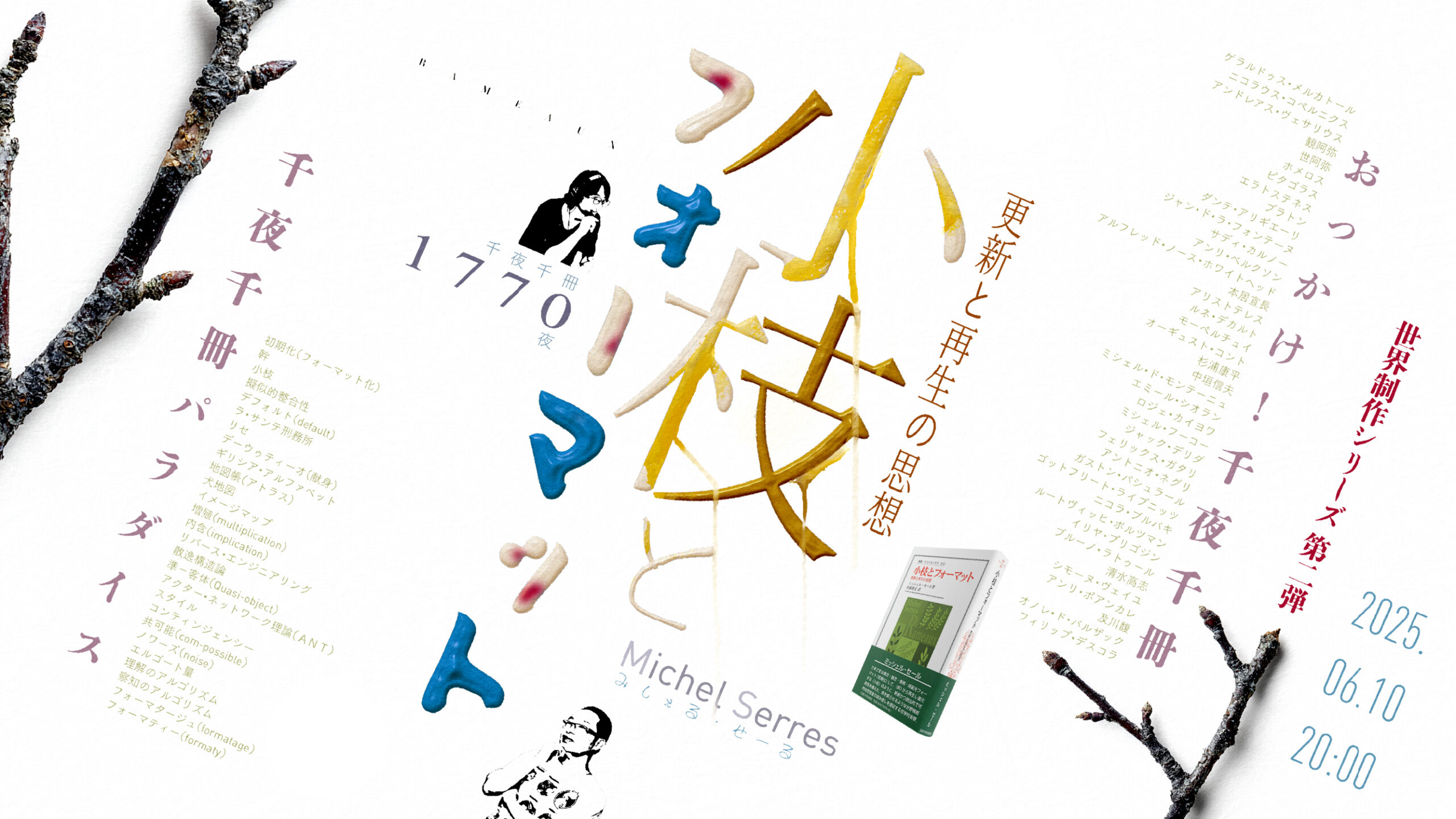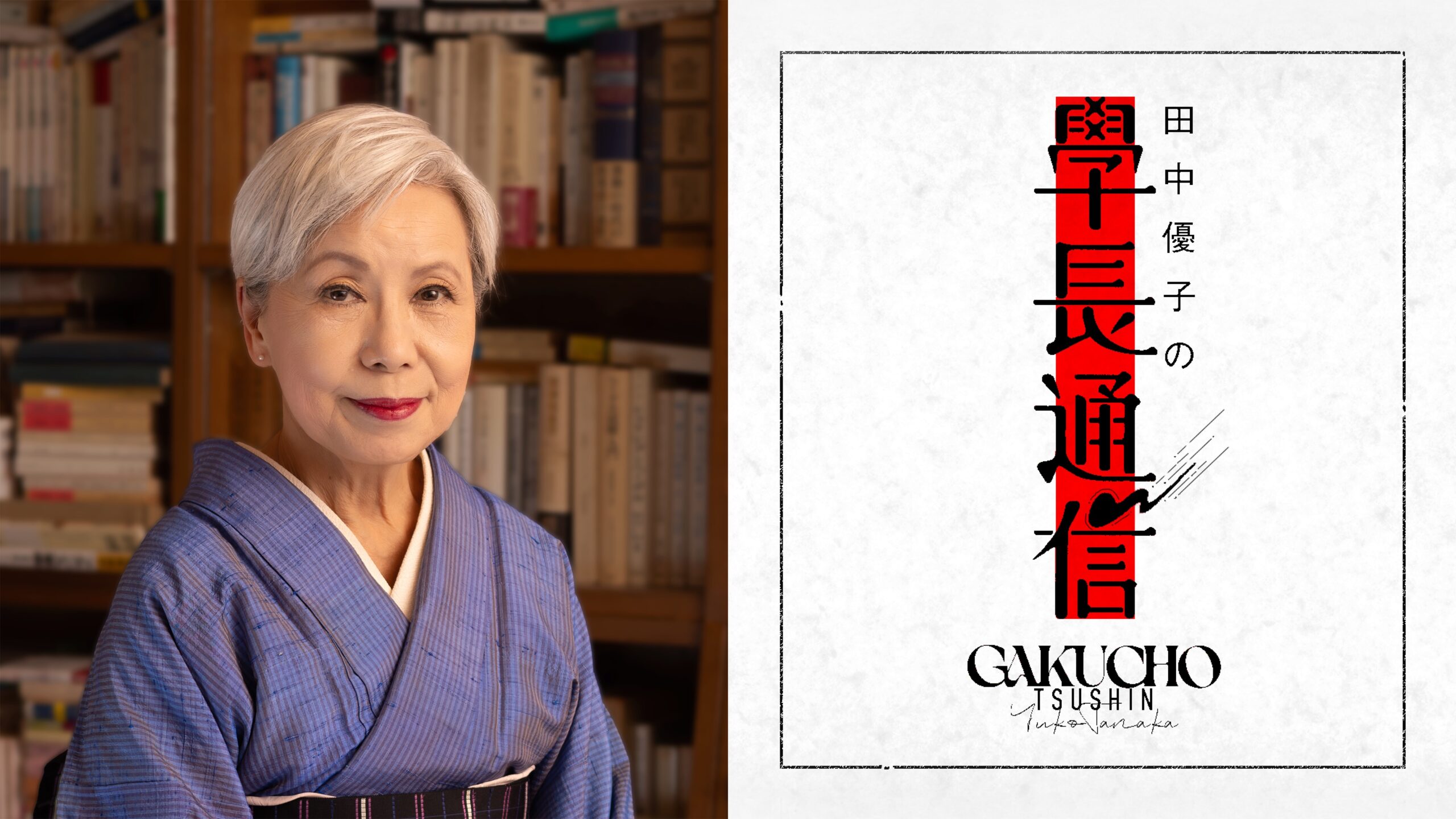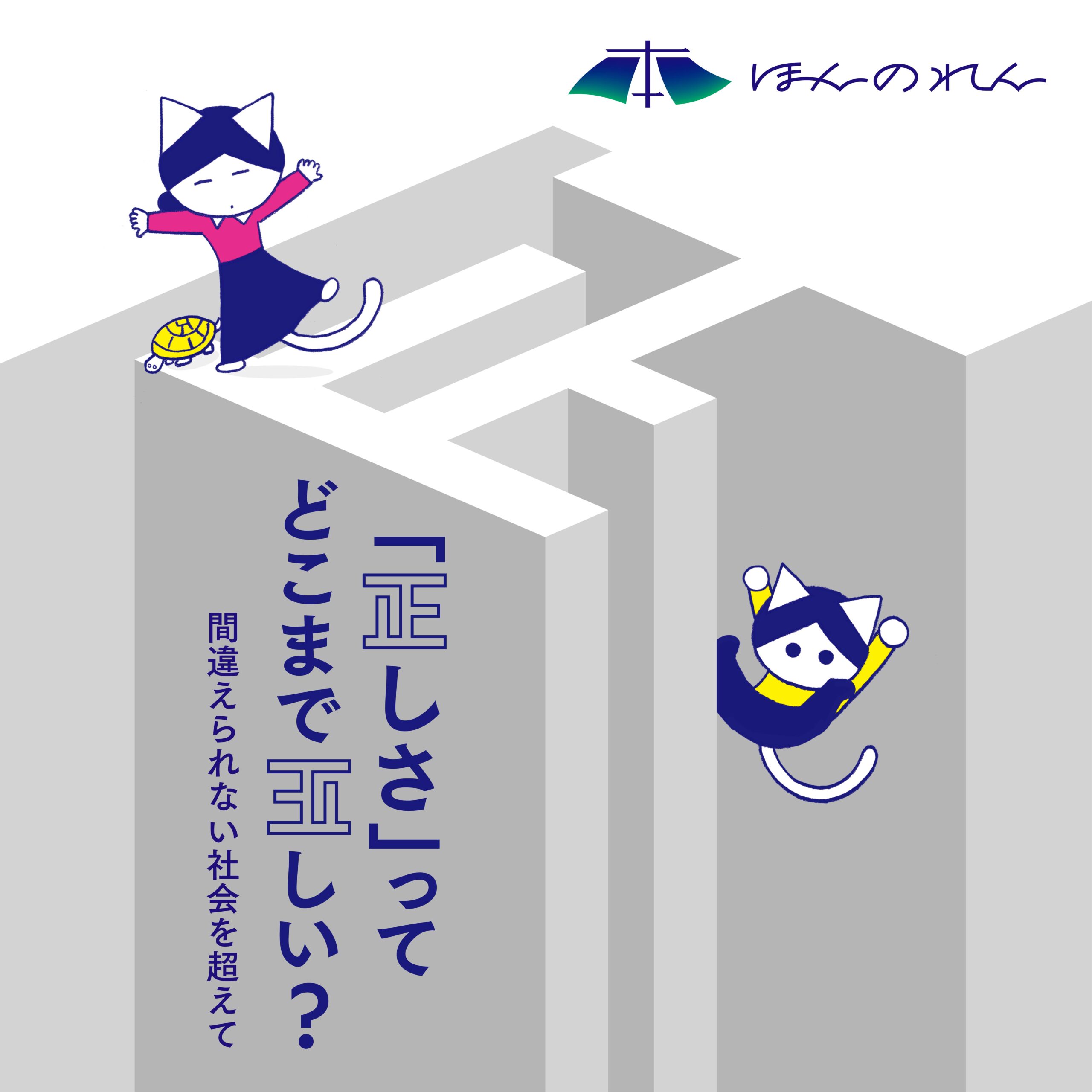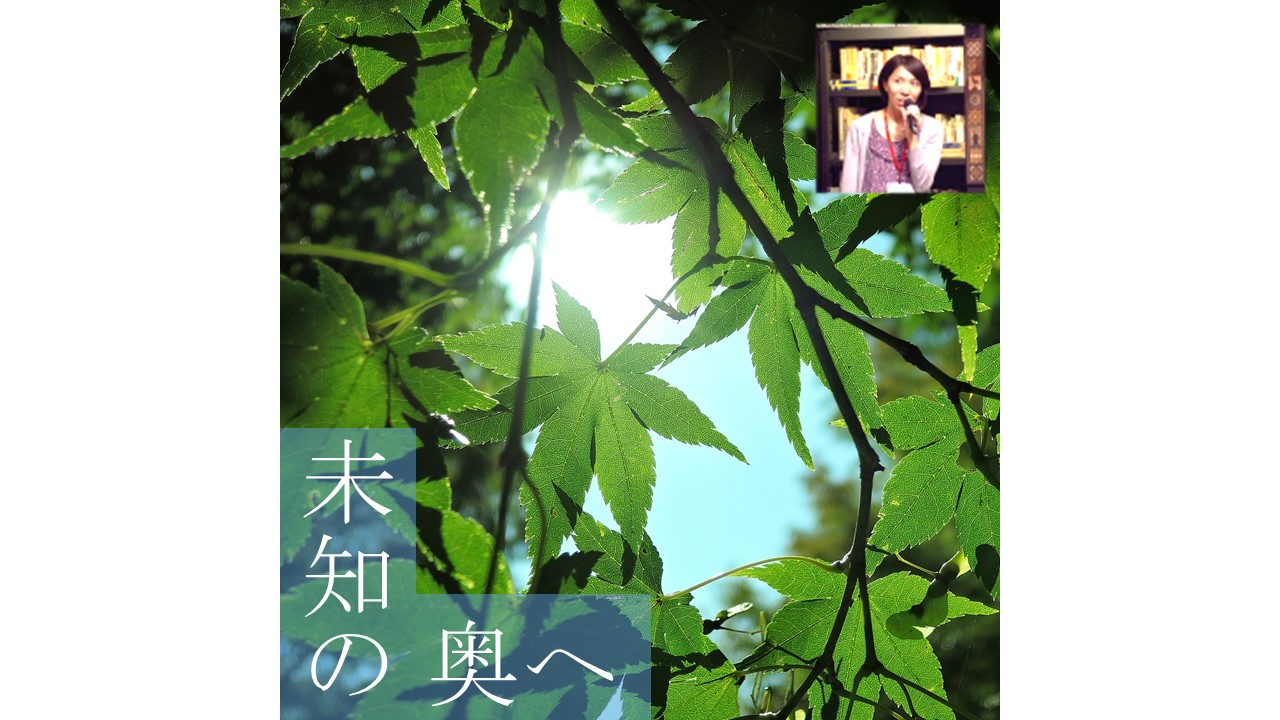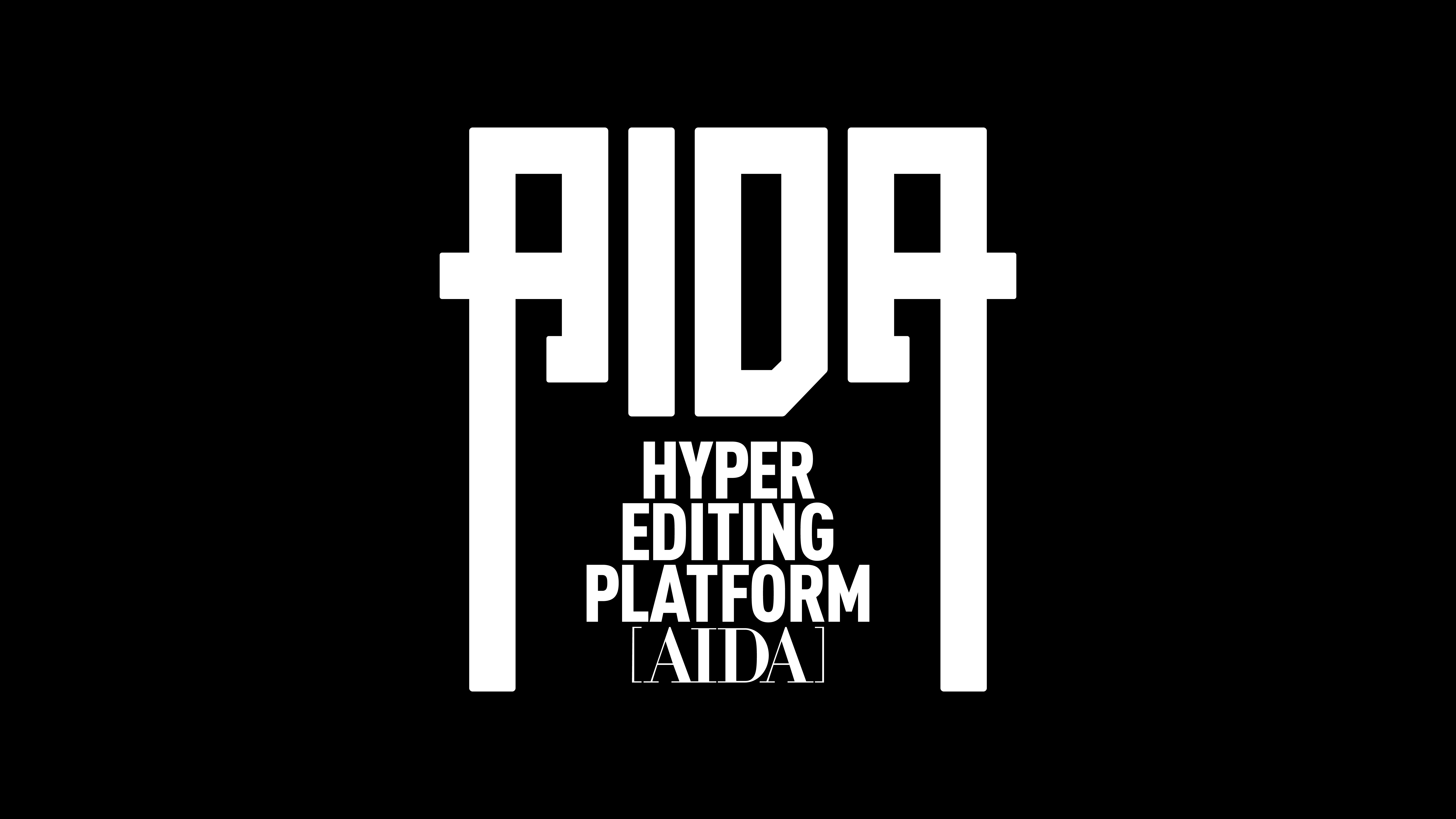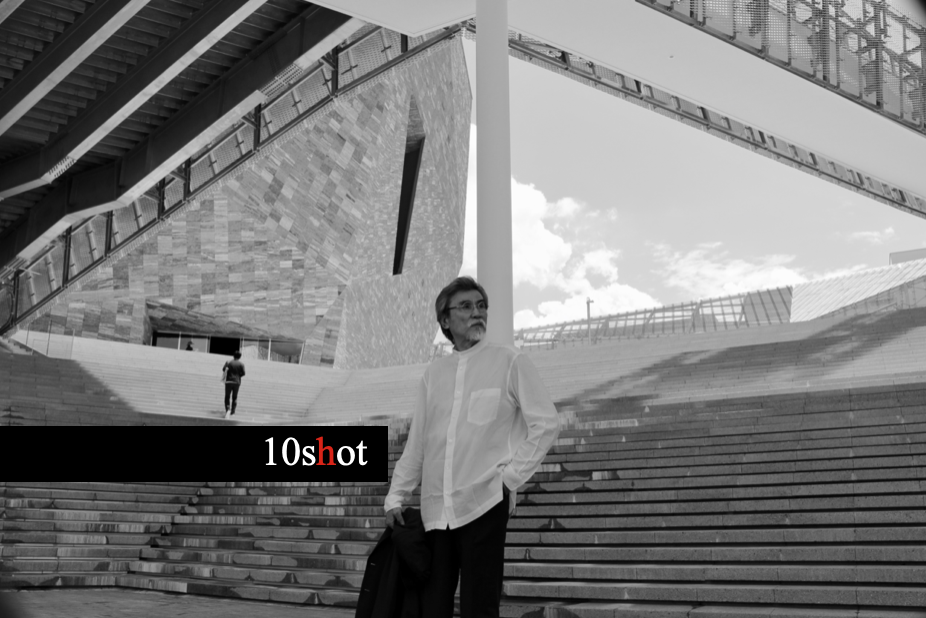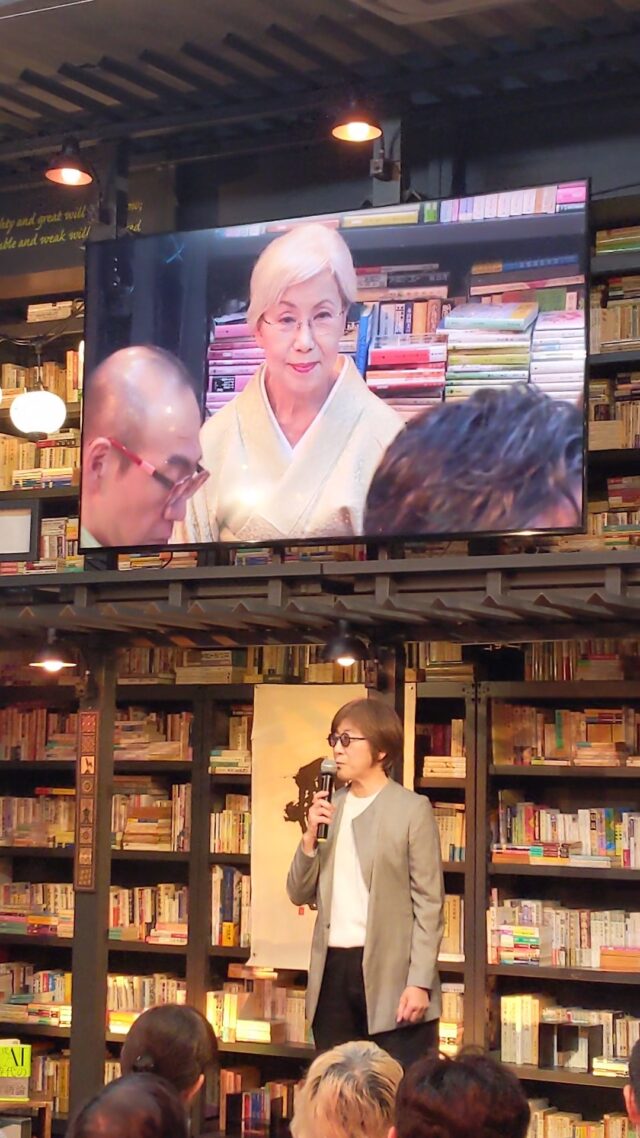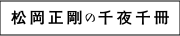-
編集かあさんvol.29 虫のセンス・オブ・ワンダー
- 2021/12/11(土)07:39
-


「子どもにこそ編集を!」
イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、
「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。
子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。
子供たちの遊びを、海よりも広い心で受け止める方法の奮闘記。
一ぴきから始まる
8月の上旬、ニンジンの記録写真をチェックしていた長男(13)が、小さなイモムシが写っているのを見つけた。
「防虫ネットをかけていたのに、なぜ」
庭に出てネットをめくる。目を凝らすと、小指の先ほどの大きさのエメラルドグリーン色のイモムシが何匹もいる。
「ちょっと今いい? 手伝ってくれへんかな」
家庭菜園の仕事で、かあさんが助けを求められるのはこの時だけである。二人の目と手でできるかぎり捕殺した。

ニンジンの葉のイモムシ
しかし逃げきった個体がいたらしい。数日後、2つのプランターのうち一つの葉と茎がぜんぶ食べられてしまった。まるはだかになった地面を這っていたそのイモムシはふたまわりぐらい大きくなっていた。種をまきなおすことになった。
ヨトウムシとの闘い
ヨトウムシかなと見当をつけていると、果たしてそうだったらしい。ある程度大きくなると、夜にだけ活動するようになるので「夜盗」の名がついている。昼には姿を見せなくなり、夜10時を過ぎてからヘッドライトを使って探しに行くと「いる」。その段階になると、体色は茶色に変わっている。葉につかまる力が増していて、身をよじらせて抵抗する。

深夜のヨトウムシ
慣れていても捕り逃すことはしばしばだ。10月中旬まで気温が高かったからか、菜園の野菜が次々と食害にあった。
ハクサイ、ダイコン、キャベツ、コマツナ、ホウレンソウ、カブ、エンドウ、ネギ。これまでヨトウムシはアブラナ科の葉を食べる虫だと思っていたが、さまざまな科の葉を食べることを今年初めて知った。特にエンドウとネギは意外だった。
10月下旬になると、気温の低下もあってようやくヨトウムシが姿を消した。一部は蛹になって地中にもぐったのだろう。
虫が虫をよぶ
植物が虫をよぶだけではない。家庭菜園を通して、虫が虫をよぶということも知った。
無農薬のベビーリーフを鉢ごともらったことがある。ベランダに出しておくと、数日後、数えきれないほどのモンシロチョウの幼虫が生まれていた。
あまりにもたくさんいるので食べることをあきらめ、脱皮の模様などを動画で撮ったりして観察していた。ある日、長男が「たいへんなことになってる!」と駆けこんできた。
アオムシが、うす黄色の繭のようなものをいくつも抱えて弱々しく動いていた。
「寄生バチだ」
寄生バチのなかまは生きたアオムシにたまごを産む。幼虫はアオムシの汁を栄養に成長する。十分に育ったころアオムシは皮だけになって死ぬ。一見元気に見えていたアオムシたちは、実は体内に寄生バチの卵を持っていたのだ。

寄生バチの繭を抱えて弱々しく動くアオムシ
セリにキアゲハの幼虫がいるなと思っていると、アシナガバチがやってきて肉団子にして持って帰ってしまったこともあった。小学生だったころの長男はその様子を庭でずっと見ていたという。
未知なる虫たち
毎年のように未知の虫が現れる。長男は記録写真を撮る。写真を見ながら、本棚の『イモムシハンドブック』(文一総合出版)を開いて名前を調べるが、同定がむずかしい。ネット検索もするが、脱皮したり変態したりして姿が変わっていくことも名前調べを難しくしている。
雑食のヨトウムシには驚かされたが、たいていは虫には好みがある。サトイモにはサトイモを好む虫、ナガイモににはナガイモを好む虫がつく。
ナガイモのイモムシは少し枯れたナガイモの葉にそっくりの模様をしている。そうして鳥を欺いているらしい。サトイモのイモムシは逆で、黒字に黄色いドット模様という目立つ姿をしている。毒がある他の虫に似せているのかもしれない。名前がわからなかったので、「夜行列車」というあだ名をつけた(アイキャッチ画像)。
虫にはもちろん恩恵も受けている。なにより人工受粉させずとも種ができるのは、虫たちのおかげである。

病気を媒介するハダニ

受粉の助けになる、飛ぶ虫たち
ところでなぜ防虫ネットをしていたのにヨトウムシの幼虫が多数入りこんだのか。
長男が読んだ仮説が、成虫が防虫ネットに産卵したというもの。うまれたての幼虫はとても小さいのでネットをすり抜けてポトポト落ちながら入ってくるらしい。
日高敏隆さんの『チョウはなぜ飛ぶか』にも、アゲハチョウにネットごしにカラタチを見せてみると網に次々に産卵しはじめたという実験が紹介されていたから、おおいにありうる話だと思う、
虫たちは数ある植物の中から、どのようにして自分が好む葉、産卵する葉を区別しているのだろう。
嗅覚か、視覚か、それとも「別」の感覚器官か。我が家の庭は虫の目にはどう見えているのだろう。人間の数百分の一の大きさで、高速飛行しながらブラウジングし、すかさず「マレビト」としてやってくる、彼らの感覚センサーに驚いている。

秋冬野菜が育つ庭
<編集かあさん家の本棚>
『イモムシハンドブック』1~3
安田守 著/高橋真弓・中島秀雄 監修/文一総合出版
『チョウはなぜ飛ぶか』
日高敏隆 著/岩波少年文庫