草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。
「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。




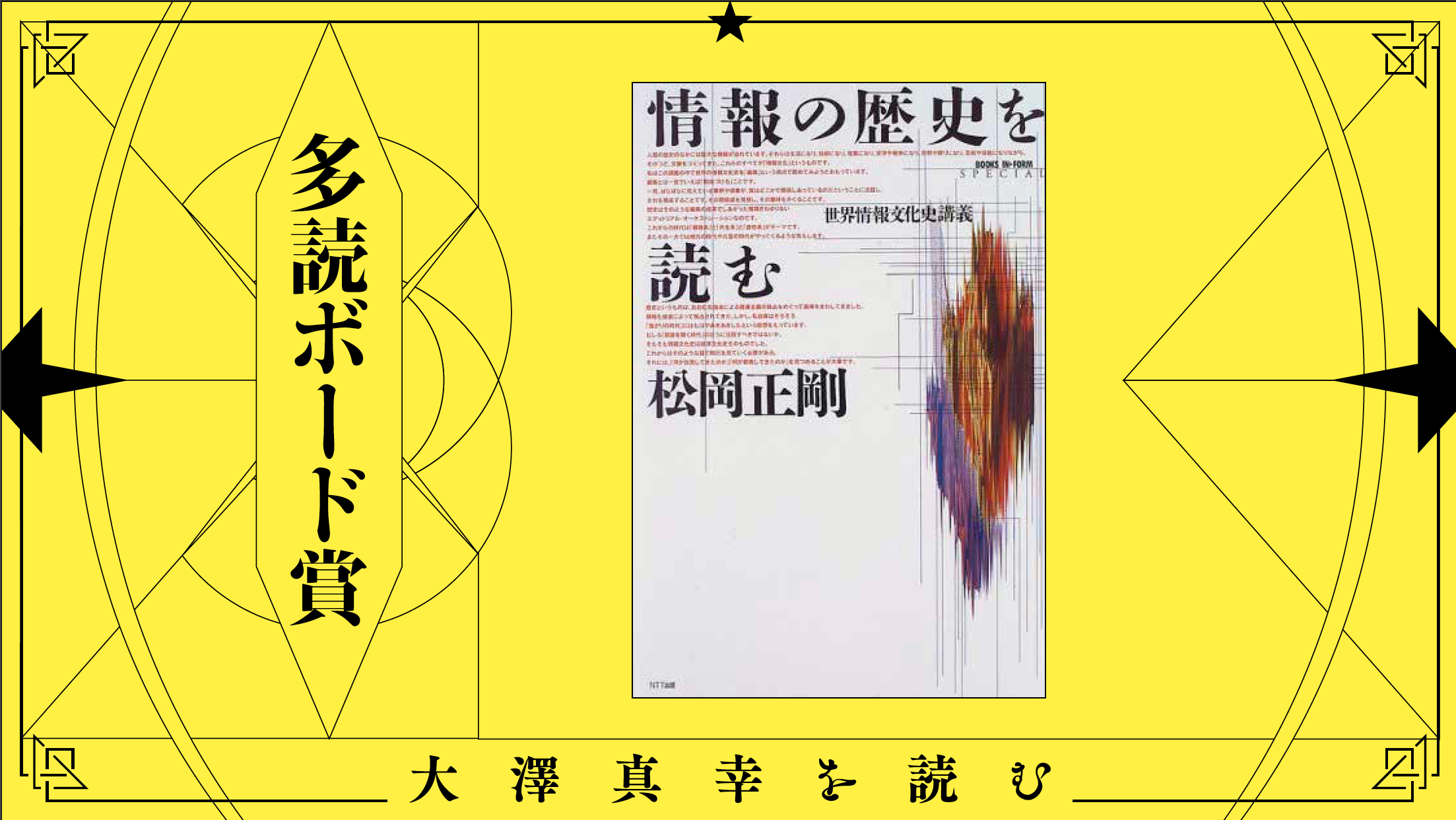
多読ジムSPコース「大澤真幸を読む」の読了式で【冊匠賞】【多読ボード賞】【大澤真幸賞】の受賞者が発表された。大澤真幸賞の梅澤光由さん、冊匠賞の林愛さんに続いて、多読ボード賞の猪貝克浩さんの読創文を全文掲載する。
東洋の眼差しの先にあるもの 繕う者と破る者 (猪貝克浩)
◉目 次◉
第一章 こころの「小部屋」は取りのぞけない。
第二章 恐怖の眼差しに潜むもの
○「カニバリズム」における恐怖(「おぞましさ」)と欲望
○人間を食う社会と人間を吐く社会
○恐怖と贈与
第三章 天を修繕する西王母
○北極星と西王母
○「幇」という社会単位
第四章 ブッダの穏やかな眼差し
○「母的なもの」へ
○他者の<眼差し>の排除
○「デミアンの母」
第一章 こころの「小部屋」は取りのぞけない。
こころの「小部屋」の奥底に、影を潜めているひとつの苦い思い出がある。幼年時代のある出来事のために、わたしは一時期こころを閉ざしてしまった。そのせいだろうか、それ以前の記憶は確かにあるのだが、それ以後数年間の記憶はわたしの中から消えている。
小学1年生のわたしはやんちゃで目立ちたがりだった。同級生の女の子たちを驚かせて、はしゃいでいたことを覚えている。ある日、路上に放置されていた自転車を乗り回して遊んでいたときだ、大柄で近所の子どもたちから恐れられていた2歳年上のガキ大将が、この自転車は自分のもので、お前は泥棒だと告げてきた。さらに学校で出くわしたときなど、「泥棒、泥棒」とはやし立てるように言ってくる。こうして、その年上の少年の存在がひとつの恐怖としてわたしの前に出現した。学校では、その少年に見つからないことが最大の関心事となり、泥棒であるわたしはいつ警察につれていかれるのだろうかとおびえる日々が続いた。些細な過ちだったと今では言えるが、当時は咎める他者の眼差しを恐れ、罪の意識に苦しめられていたのだった。そうした苦境を母に言い出すことはできず、そして、母もわたしのおびえに気づくことはなかった。人前に出ることを避け、おとなしい、目立たない少年として小学校時代をやり過ごした。何事もなかったように成長して高校生になり、ヘルマン・ヘッセの『デミアン』を読んで驚愕した。そこには、わたしの体験と同じような話が描かれていたのだ。
それは主人公ジンクレエルの幼年時代の出来事である。明るい家庭に育ったジンクレエルは、悪童のクロオマアによって、暗い悪の世界に引き込まれる。虚言がもとで、クロオマアに支配されたジンクレエルは盗みを強要され、恐怖と罪の意識に苦しめられる。ジンクレエルも母に言い出すことができない。人はなぜ、救いを求めることができないのだろうか。それは自分を罪人であると告げることであり、自分の罪を母に知られたくないからだ。その些細な過ちを誰かに申し出さえすれば、救いの手が差し伸べられる可能性があろうことなど、子どもにとって思いもよらぬことだったに違いない。むしろ自分の居場所がなくなってしまうと思っていた。子どもにとって処世術を覚えるのはまだ先のことなのだ。だから、恐怖に体調を悪くしてしまい、具合を心配されても黙っているしかない。『デミアン』ではある日突然、ジンクレエルの恐怖の原因は取り除かれる。ジンクレエルの友となった、もう一人の誘惑者であるデミアンが手を回して、ジンクレエルの預かり知らぬところで、クロオマアとの関わりを断ち切ったのだ。また、もとの明るい世界が戻ってきた。だが、ジンクレエルは世界が変わってしまったことを知っている。
当面の恐怖がなくなっても、なぜ恐怖から生み出された罪の意識は消えないのだろうか。この問いを考えるには、恐怖と罪の意識を分けて考えてみた方が良いだろう。ここで、罪の意識を直接に規定しているものはジンクレエルが「悪魔と握手した」という思いである。自身の窃盗や虚言ではなく、クロオマアの言いなりになったことなのだ。ジンクレエルは、母にすすんで懺悔をしたわけではなかったし、また、クロオマアに自分から対峙して道を切り開いたわけではなかった。ジンクレエルはデミアンによって自分を苦しめていたクロオマアの束縛から解放された。だが、ジンクレエルを取り巻く環境が変わって、恐怖の原因が取り除かれたとしても、一度生まれた罪の意識は、普段は意識されることはなくなっても心の中に残っている。平穏な日々を取り戻したかにみえるが、こころの奥に「小部屋」が生まれた。この部屋の中に罪の意識が住み着くのである。それは、何かの折に意識されるものなのだ。とりわけ、生きるうえでの選択を間違ってしまったと思うようなときに、「小部屋」は自分が罪人であると思い出させる。
第二章 恐怖の眼差しに潜むもの
○「カニバリズム」における恐怖(「おぞましさ」)と欲望
大澤真幸は『<世界史>の哲学 近世篇』(第3章 聖地の受肉 3カニバリズムへの嫌悪)においてカニバリズムとカトリックの聖餐式との類似について次のように示す。
そして、その類似を見出したところで、彼ら(侵略者たち)は、安心するのではなく、逆に強い嫌悪を覚えている。つまり、彼らが忌避しようとしていたのは、彼らが無意識のうちに直観した、先住民との(幻想の)類似性である。(p80)
ここで、侵略者である西洋人が嫌悪を感じた類似性とは、どのような内容なのだろうか。インディオの習慣にはカニバリズムがあり、それはカトリックの聖餐式とよく似ていたと感じたのだ。西洋人にとって、最後の晩餐の反復として、聖餐式でぶどう酒を飲むことはキリストの血を飲むことであり、パンを食べることは、神の受肉によって「聖別されている」キリストの肉を食べる行為である。
ところで、レヴィ=ストロースは『悲しき熱帯Ⅱ』で、宗教的な儀式として、インディオの食人の習俗を紹介している。それは、死者の徳を身に着け、死者の力を無力にするため、親や祖先の体の一部や敵の死体の一片を嚥下するという行為である。カニバリズムの分析を通して、レヴィ=ストロースは社会の二つの型を示した。ひとつはアントロポファジー(人間を食うこと)の慣行をもつ社会、もうひとつがアントロペミー(人間を吐くこと)の社会だ。前者では脅威となる力を持つ個人を食うことでその力を無力化し、さらに活用するものと考えられた。一方後者では、脅威となる者を施設に隔離し、社会の外へ追い出すのである。(中公クラシックスp376~p377)
レヴィ=ストロースの分析によればヨーロッパはアントロペミーの社会であった。だが、もともとヨーロッパはアントロペミーの社会だったのだろうか。ミシェル・フーコーは『狂気の歴史』の第一章《阿呆船》のなかで、17世紀までのヨーロッパは、狂人を排除・隔離する社会ではなかったことを示した。つまり、脅威となる力を持つ者も社会の一員として暮らしていたのだ。ヨーロッパが明確にアントロペミーの社会に転換したのは17世紀であり、近代の始まりとともに「大いなる封じ込め」の時代が始まった。社会は「分割・排除・浄化」を目指して、脅威となる力を持つものを「監禁」していった。
『水滸伝』には、食人を指し示す記載があって読んでいてぎょっとさせられる。『水滸伝』は、明代に書かれた長編白話小説で、時代設定は北宋末期、様々な事情でアウトローとなった好漢(英雄)百八人が、梁山泊に集結する。この間に大小いくつもの戦いがあり、やがて汚職官吏や不正悪徳官吏を倒すべく好漢たちは立ち上がり、救国を目指す。不正が横行し、悪徳官吏ばかりの世を好漢たちは憤るが、「天命」によって代表される皇帝への信頼が揺らぐことがないのはいかにも中国らしい。内容には反権力的な傾向が随所にあり、何度も発禁となり、書き換えもなされている。食人を思わせる記載はところどころに現れる。居酒屋では人間の肉まんじゅうが供される場面に出くわすこともあるが、おおむね敵対する相手を倒して、「肝を鍋に入れて食べてやる」と豪傑たちが豪語するのだ。これはレヴィ=ストロースの例でみれば相手の力の無力化と活用に他ならない。
レヴィ=ストロースによれば、アントロポファジーの社会では、食人によって相手と同一化したいという欲望が潜んでいる。先に見たカニバリズムとカトリックの聖餐式との類似性は死者の力を取り込みたいという欲望のことである。聖餐式の場合は言うまでもなくキリストの血と肉を分かち合うことでの一体化と言えよう。西洋人は、自分たちにはカニバリズムと思えるインディオの儀式を目の当たりにして、そのおぞましさに恐怖を感じながら、死者との一体化を欲望する自分自身の姿を見ていたのである。
○人間を食う社会と人間を吐く社会
近代化の遅れた東アジア社会においては、アントロポファジーな心性は社会の一部に色濃く残っていたのではないだろうか。いま一度、レヴィ=ストロースの分析にもどるならば、社会は二つの型に分けられる。ひとつはアントロポファジー(人間を食うこと)の慣行をもつ社会で、もうひとつがアントロペミー(人間を吐くこと)の社会だ。人間を吐く社会とは、差異を認めたものを区別して、隔離することで社会の一員から切り離す社会である。一方、人間を食う社会とは、差異を認めたなかで差別はあるにしても、同じ社会の一員として居場所を残す社会である。
家族や親しい人と一緒に食事を摂ることは、時と場所を共にし、食べるという行為を通じて一体感を深めていく経験であり、その積み重ねである。「同じ釜の飯を食べる」ということばがあるように、ここには、共同体としての帰属意識を植え付けていく作用がある。日本のかつての村落共同体における年中行事では、行事食として神々へ捧げた供物を共に食していた。村落共同体の中にあった「村八分」という決まりは、隔離のように見えるけれど、村八分された者にも居場所を残す仕組みであった。村八分は村社会の中で、掟や秩序を破った者に対して課される制裁行為であり、一定の地域に居住する住民が結束して交際を絶つことであるが、葬式の世話と火災時の際の消火活動という村の生活での二分を残していた。
アントロポファジーな心性を強い帰属意識と共同体を志向するものと言い換えるならば、(差異のある一部の人々を隔離するようになった)近代以前の時代の心性を特殊なものとして退けなくてもよい。そのうえで、中国社会における「幇」をアントロポファジー的という視点で見てはどうだろうか。「幇」とはパーソナルな関係を支配する原理であり、その内部では構成メンバーそれぞれの利己性は完全に滅却されている。「幇」の内部と外部が排他的に分類されるものだとしても、拡大された単一の自己である「幇」をひとつの紐帯と見なすならば、それは社会の単位として考えることができるのではないだろうか。
○恐怖と贈与
恐怖を与える側にはなんでもないことであっても、恐怖を受け取る側は、大変な事態であって、手をこまねいていては苦しみが続くばかりである。恐怖を与える側と恐怖を受け取る側の関係は贈与するものと贈与を受け取るものとの関係に似ている。恐怖を与えるとは贈与であるといって良いのかもしれない。そうであるなら、なんらかの形でその借りを返さなければ、一度生まれた関係、恐怖の束縛から解放されることはない。だが、はたして借りは返せるのか。争いの応酬も、贈与と反対贈与の関係とみなすことができる。片方が贈与を断ち切らない限りは、永遠に争いは続いていく。恐怖の場合は、受け取った恐怖を贈ってきた相手に返しようがない。そのため、恐怖を自分のなかで抱え込むことになり、恐怖に拘束された状態が続いてしまう。仮に、別の相手に反対贈与として恐怖を与えたとしても、自分が受け取った恐怖は消えることはなく、むしろ恐怖の連鎖がひろがるばかりだ。恐怖の根本原因を取り除くよりほかに解決の方法は見つからない。
第三章 天を修繕する西王母
○北極星と西王母
中国史全体を通じて、母的なものへの崇拝が、特に農民たちの間では持続している。赤眉の乱や黄巾の乱では西王母を拠り所としていた。ではなぜ農民反乱において、西王母は呼び出されてきたのか。すでに、天である北極星を戴く中国の皇帝権力は確立されていた。「母の時代」から「父の時代」へと時代は移り、家族内の権力も変化した。この交代は、マルセル・ネグラの説によれば紀元前11世紀の後半から紀元前1000年頃にかけて起きたものだ。この時期、中国の王朝は商から周へ移る。中国古代王朝の交代劇の裏には母系社会から男系社会への移り変わりを含んでいる。商の儀式では、神への反対贈与として、自らの代わりに捕虜を生贄として神に捧げた。神への負債感、負い目の感覚の延長上にこそ、やがて、皇帝の権力が抽出されると大澤は『東洋篇』で分析する。商は、供犠の相手となる神々をたくさん持っていたという。「天」という概念は、そうした神々が、やがて単一の神へと収斂し、さらに理念として純化されていくなかで生まれた。この「天」という第三者の審級が皇帝の支配には必要だった。そして、社会的、自然的秩序が順調であることが、皇帝に天命が下っていることを保証するのである。
社会の底辺にあって反乱を起こす農民たちが頼りとするものは皇帝権力へ向かう「父の原理」ではない。「母的なもの」の中にこそ、天を覆す力を秘めているとの直感があったのではないだろうか。それでは、西王母とはなんであったのか。西王母は不死の女神、大地母神であって織女の統轄者としてイメージされてきた。機織りの神として、日本神話のアマテラスへとイメージが連なる。また、養蚕技能に富んだ四川の古代巴蜀文化は戈族や羌族によって担われていた。羌族は商によって、神への生贄として狩られた者たちであった。つまり、西王母は四川文明を継ぐものである。そして織る神であって、殻を破りまた修復する者であった。
岡田英弘は、皇帝は、女を自らの身体の中に統合することで、天子として君臨できたという。大地母神と帝の関係を次のように説明する。秦による統一前の多くの都市国家では、守護神として祀られていた大地母神が天の神の妻となり、都市国家の始祖を生んだ。各地の大地母神たちを妻として与えられる正式な配偶者が「天の神」であり、それが「帝」の本来の意味である。
そうであるならば、帝から大地母神が離れてしまえば、帝を成り立たせていた権威は減じてしまうのではないか。農民反乱では「母的なもの」が「帝」の権威を破って暴れまわるのだといえる。以上のことから、中国の農民反乱における母的なものの突出は、統合されていた皇帝権力の破れとして現れたものだと考えられる。女媧は崩れかかった天を修繕したという神話こそその傍証に他なるまい。
○「幇」という社会単位
老荘思想はどちらかというと現実逃避的なイメージが強い。表の儒教的世界での敗者が、裏の道教的世界で癒され、「母的なもの」に包まれる。現世的ともいえる道教が、どうして農民反乱を起こすことができたのか。前節で、西王母や女媧は皇帝権力の破れを農民反乱という形で補修する機能を代弁するものであることを見てきた。では、その反乱を担った者たちはどういうひとたちであったのか。
黄巾の乱は、後漢末の184年、「蒼天はすでに死せり、黄天はまさに立つべし。歳は甲子にありて、天下大吉ならん」とのスローガンのもと、太平道の教祖、張角が蜂起した反乱をいう。信者達を6,000人~10,000人ずつに分けて「方」と名付け、36の方を編成して、その軍事力を背景に後漢王朝に反旗を翻ひるがえしたのだ。岡田英弘によれば、人口の増加によって都市に流入した貧民層が縁故を頼って互助組織を作ったと述べている。これが中国における秘密結社の起源で、「道教も仏教も、この時期の中国の下層階級の、出身地別を超えた団結の指導原理として、秘密結社の地下組織を通じてひろまった。」(岡田英弘『倭国』p57)
アントロポファジー(人間を食うこと)を考察した際に、中国の「幇」を取り上げた。中国においては、その広さに対応して水平に伸びる皇帝権力のなかにあって、「幇」は属人的なひとつの社会の単位を形成する。道教を信奉する秘密結社である太平道の信者たちもそのつながりの根本はパーソナルだ。地上に苦しみがあり、苦しみからの解放を目指して人々を駆り立て、決起させるエネルギーが「幇」の構造的なメカニズムのなかにあったのではないだろうか。西王母という旗印を得て、反乱というかたちで皇帝権力を揺さぶるのである。中国の歴史は、単一の中央政権によって全体が統合されている状態(準固体状態=ゲル)と、激しい戦争が続く無秩序状態(流動状態=ゲル)との繰り返しであるという。この中国史の統合と分裂のメカニズムを動かす最小の単位が「幇」であった。
第四章 ブッダの穏やかな眼差し
○「母的なもの」へ
大室幹雄は『正名と狂言』において、中国における母的なものの原型として『荘子』に描かれている「混沌」を取り上げる。混沌は七日かけて目耳鼻口といった七つの竅を穿たれたことで死んでしまう。七つの竅、目耳鼻口をもたない混沌のイメージは世界卵に通じるものだ。始原の世界にあっては、男と女、上と下、前と後、陰と陽、といった反対物はいまだ存在しない。混沌は嬰児同様に宇宙の「中央」にいるのであった。
大室は始皇帝における不死の神薬探求に父殺しと母性回帰を認めている。不死の霊薬を服用することは、大地母神が彼女の子宮のうちに胎児として再び受け入れてくれることを意味する。ここでいう、母性回帰とは、始皇帝の「幼年期から青春期にかけての十年間をあたたかく包んでくれた母、美貌で性愛的な邯鄲の美姫との秘めやかな一体化の状態」を恢復してくれることだ。これはまさしく、胎児的な、あるいは卵状の一体化であるといえる。さらに、母性的イメージについて、大室は次のようにいう。
歴史的にみればこうも考えられるだろう。ウロボロスが併呑する父性的と母性的の二側面のうち、老荘家が後者を原初的イメージとして想起したのは、儒家をはじめとする強力な父性的原理があまりにも徹底的に浸透し支配している彼らの歴史的時代に対して、また韓非を典型とする粗野かつ精密な現実主義がこころのやさしさを閉殺する荒々しく男性的な鉄の時代に対して、反感をいだいていた彼らに固有の脱社会・脱政治・脱歴史・脱文化への志向の必然的結果であった。(『正名と狂言』p183)
母的なものへの回帰はこの志向の先にあるものだ。
○他者の<眼差し>の排除
大澤真幸は仏教の「空」を分析する中で、仏教と一神教(キリスト教)のこれまでの常識的な見方を大きく転換させる。大澤は仏教と一神教(キリスト教)には根本的な違いがあるが、その違いは、一般に信じられているものとは逆であることを示す。仏教は悟りを開くことを目指しているわけであるから、「無」の境地こそふさわしい。一方、キリスト教は唯一の神を信仰する。ところが、単一の存在を前提としているのが仏教で、存在に先立つ、「無」と呼ぶべき何かを志向しているのがキリスト教だという。大澤はナーガールジュナの「中論」を俎上に載せる。「中論」では縁起は論理的な相互依存の関係だった。あらゆる「法」は相互依存のネットワークに還元され、実体としては存在しないことになる。これが「空」で、ここでは縁起と空は同じことの言い換えとなる。さらに輪廻と涅槃も同じものとなる。大澤は仏教の中観派の理論を紹介した後、その問題点を次のようにいう。
実態を縁起(関係性)へと還元することによって、存在が空へと転換する。『中論』はこのように説く。だが、精密に事態を捉え返してみると、実体を縁起に移し替える認識の操作において、縁起=関係へと転化されることのない一つの実態の存在が、主題化されざる前提となっていることがわかる。縁起=空への還元は、その還元から逃れている、ある実体の存在を暗黙の前提にしないことにはなりたたないのだ。(『東洋篇』p242)
仏教の教理には隠れた矛盾があり、大澤は認識の対象としては、最初から排除されている同一性があることを示す。さまざまな差異(関係)は、最初から、その同一的な基盤のなかでの差異だったというわけだ。こうして、大澤は仏教が排除しているものは何かと問い、次の仮説を示す。「ブッダや菩薩のいかにも寛大そうな「眼差し」は、何ものかの排除を前提としているのではないか。」そして、その排除しているものは、他者の<眼差し>であるという。ブッダは贈与を束縛ととらえた。贈与の連鎖が作り出す束縛からの解放を、その連鎖から離脱することに求めたのだ。つまり贈与の連鎖の外に出ることである。それは贈与に欲望が潜んでいるからで、その欲望が贈与と反対贈与を行わせているのである。ブッダの穏やかな眼差しが排除しているものは、この欲望に他ならない。
和辻哲郎の『古寺巡礼』の出版によって、仏像は美であり鑑賞の対象となった。だが、仏像はもともと宗教的な目的をもって作られたものだ。仏教が涅槃を目指すのであれば、仏像もまた、その目的を促進する機能を担っていたに違いない。現在の仏像鑑賞が本来の仏像のあり方から離れてしまったとはいえ、仏像には宗教的なオーラが備わっているのではないだろうか。むしろ現代の仏像への興味は本来のありかたに戻っているのかもしれない。京都や奈良の古都を旅し、寺社仏閣をめぐる人々が仏像のまえに佇んで感じているのは古代日本の仏教美術の芸術性というよりは、古都という歴史的空間のなかに醸し出される癒しなのである。和辻が「愛らしく、親しみ易い、優雅な、そのくせいずこの自然とも同じく底知れぬ神秘をもったわが島国の自然は、人間の姿に現わせばあの観音となるほかない。」と言ったのは奈良中宮寺の弥勒菩薩(伝如意輪観音)であった。人は弥勒菩薩のまえに立って、穏やかな眼差しとその微笑みに癒され、至福のときを感じるのだ。これまでの論を敷衍して言えば、弥勒菩薩の眼差しの前にあって、人は贈与と反対贈与の束縛からの離脱を共にするのである。
○「デミアンの母」
第一章で引用した『デミアン』では、ジンクレエルは神の世界と悪魔の世界を知り、飲酒と放蕩に浸った。その後、自らベアトリーチェと名づけた少し年上の、成熟した気品のある少女と出会い、明るい世界に戻る。大学に入学したジンクレエルはデミアンと再会し、デミアンの母であるエヴァ夫人を知る。ここは文字どおり男と女の関係を示しているのだが、ジンクレエルはエヴァ夫人の持つ「母的なもの」に包まれたと表現した方が正確であろう。すでに登場人物の名前から、ヘッセの意図を読み取ることができる。ベアトリーチェとはヨーロッパの理想的女性像であり、ダンテの『神曲』では煉獄から天国へダンテを導く霊魂であった。エヴァは言うまでもなく人類の母である。『デミアン』をドイツ文学の伝統の中に置いてみれば、ゲーテの『ファウスト』が思い起こされる。地獄をめぐるファウストの魂を救済するのは、「かつて、<グレートヒェンとよばれた女>の願いを栄光の聖母」がききとげることでなされたのだ。
であるならば、『デミアン』のエヴァ夫人こそは人類のマザーであり聖母であるに違いない。『デミアン』では、「鳥は卵からむりに出ようとする。卵は世界だ。生まれようとする者はひとつの世界を破壊せねばならない。鳥は神のもとに飛んでゆく。その神は、アプラクサスという。」という言葉が重要なメッセージになっている。卵は生まれ出る胎児を包みこむ母的なものの象徴であり、世界は混沌として一体である。新たな一歩を踏み出すために、卵は破られなくてはならない。ジンクレエルはエヴァ夫人に包まれながら、旅立ちの時間を迎えていた。すでに、世界はひとつの破局に向かおうとしていた。第一次世界大戦がはじまり、ジンクレエルは戦場で負傷してこの物語は終わる。聖母としてのエヴァ夫人に包まれることで、ジンクレエルはそれまで抱えてきた孤独から解き放たれた。こころの「小部屋」は消えてなくならないにしても、この時、こころのなかは喜びに満たされ、自らを肯定する力を強く感じ取る。
では、「母的なもの」は恐怖に打ち勝つことができたのかと問うてみたとき、答えは打ち勝つことができたとも、できなかったともいえる。とはいえ、「母的なもの」に包まれることで大いなるエネルギーと勇気を受け取り、次なる階梯に進んで行くことができたのだ。最後に『デミアン』について付け加えておくならば、世界は光り輝くものだと感じたのは、エヴァ夫人を知った後ではない。初めてエヴァ夫人に会いに行く道々で、すでにジンクレエルは本来の自分のいるべき場所に戻れる喜びを感じていた。二人が顔を合わせたとき、ジンクレエルはこの出会いをふるさとへの帰還に譬える。これは、人に備わる予感であろうか。この未来への眼差しの先にこそ、こころの「小部屋」を開放する鍵があるに違いない。
Info
⊕多読ジムSPコース「大澤真幸を読む」⊕
∈課題図書:『<世界史>の哲学 東洋篇』/講談社
∈スタジオ◇シン・カオス(吉野陽子冊師)
⊕参考図書⊕
∈『<世界史>の哲学 中世篇』大澤真幸/講談社
∈『<世界史>の哲学 近世篇』大澤真幸/講談社
∈『<世界史>の哲学 近代篇2』大澤真幸/講談社
∈『デミアン』ヘルマン・ヘッセ/岩波文庫
∈『悲しき熱帯』レヴィ=ストロース/中公クラシックス
∈『完訳 水滸伝』吉川幸次郎・清水茂訳/岩波文庫
∈『狂気の歴史』ミシェル・フーコー/新潮社
∈『正名と狂言』大室幹雄/せりか書房
∈『千夜千冊エディション 文明の奥と底』松岡正剛/角川ソフィア文庫
∈『中国文明の歴史』岡田英弘/講談社現代新書
∈『倭国』岡田英弘/中公新書
∈『初版 古寺巡礼』和辻哲郎/ちくま学芸文庫
猪貝克浩
編集的先達:花田清輝。多読ジムでシーズン1から読衆として休みなく鍛錬を続ける日本で唯一のこんにゃく屋。妻からは「人の話が聞こえていない人」と言われてしまうほど、編集と多読への集中と傾注が止まらない。茶道全国審心会会長を務めた経歴の持ち主でもある。
<多読ジム>season11・夏の三冊筋のテーマは「虫愛づる三冊」。虫フェチ世界からのCASTをつとめるのは渡會眞澄、猪貝克浩、田中泰子の面々である。夏休みに引き戻してくれる今福龍太・北杜夫から生命誌の中村桂子へ、虫眼 […]
<多読ジム>Season09・冬の三冊筋のテーマは「青の三冊」。今季のCASTは小倉加奈子、中原洋子、佐藤裕子、高宮光江、大沼友紀、小路千広、猪貝克浩、若林信克、米川青馬、山口イズミ、松井路代。冊匠・大音美弥子と代将・金 […]
〇色と結ぶ笑い 徳川の世は文武両道を奨励したが、『好色一代男』は女色男色の両刀使いの活躍だった。色事の早熟、苦心惨憺な色事修行、お大尽としての遊蕩三昧と続く世之介の一代、前半生は女難の連続といっていい。 横恋慕した女 […]









コメント
1~3件/3件
2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。
「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。
2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二
セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!
目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!
2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。
配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。
昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。