鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。




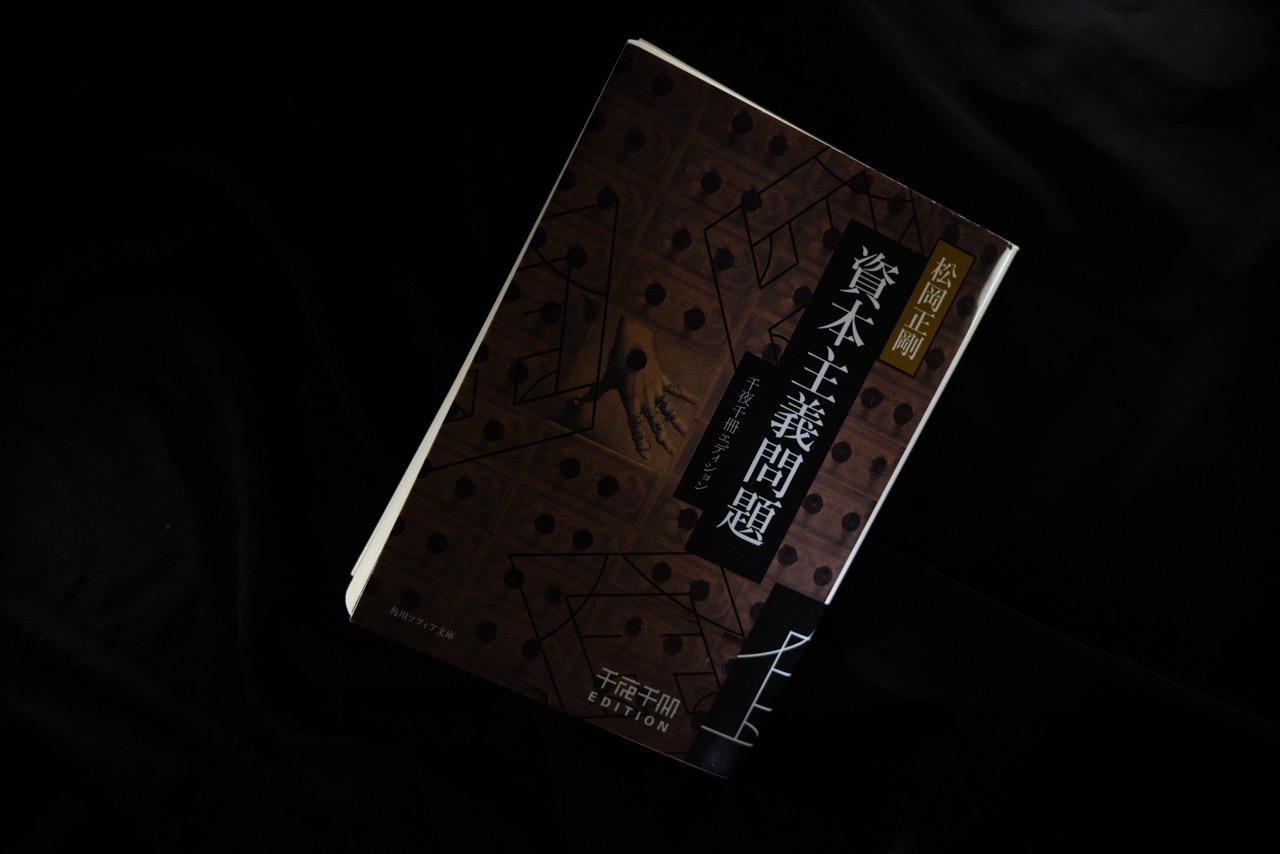
一枚の写真には、いくつもの選択が詰まっています。「写真は創造ではなく、選択であるとはよく言われる指摘である」とは中平卓馬の言葉。中平は「一枚の写真も、それは選択の結果である」とも言います。何かを撮影しようと思ったら、5W1Hはもちろんのこと、露出(絞り、シャッター速度、ISO感度)、ホワイトバランス、フレーミング、構図などを決めて、撮影後もレタッチ(写真編集)がある。プリントしようと思ったら、どこでどうやってプリントするか。サイズや用紙や色合いはどうするか。さらに展示やコンペに挑戦しようと思ったら、枚数は?配置は?順番は?タイトルやステートメント、キャプションはどうするか?際限のない選択の連続が待ち受けています。つまり、一枚の写真は編集であり、写真を撮る行為は編集稽古なのです。
多読ジム×倶楽部撮家《一人一撮 edit gallery》は、第4弾を迎えました。2024年春・Season18は『資本主義問題』がエディション読みのお題。今回エントリーした読衆は7名でした。有志たちはどんな選択をしたのは?それでは作品をみていきましょう。
◇
「忘れられた神々」北條玲子
「資本主義は輝かしい時代を終えて、忘れられた神々」と見立てた北條さんの作品。ご自宅?の一角を神棚に仕立てたのですね。ベトナム紙幣に伸ばしている手は表紙の手と呼応しているのか。右上の影は、何かを捕えるための縄なのか。見るほどに意味を勘ぐりたくなる1枚です。左に写っている指?はなくても良かったかも。しかし、これまでのデザイン性を重視された撮り方から、今回はより物語性にチャレンジされた姿勢◎ ライティングはなかなか大変だったかと思います。次はどんな光と影を演出されるのか楽しみにしてます。
「漕ぎたくなる資本主義」和泉隆久
ノスタルジックな作風は和泉さんの一枚。前回に続き、光、色、構図、いずれもたいへんにバランスの取れた作品です。資本主義を「簡単に離れることができない鎖」と読み替えて、たどり着いたのはブランコの鎖。ブランコに乗ると漕ぎたくなる、漕ぎすぎると怖くなる。そんな一面も資本主義と重ねられました。それならば、少しブランコを揺らしながら、シャッタースピードを落として撮ると、揺らぎや不安、恐怖などがより一層感じられたかも。そんな一枚も見てみたいと思った作品です。和泉さんにはぜひ千夜千冊エディションの撮影を全制覇してもらいたく。
左上「錬金術」右上「ノマドたちの足音」
左下「すべては広場から始まった」右下「パンかサーカスか」
山口イズミ
国外で、しかも4枚もエントリーされたのは山口さん。開放感のあるお写真は見ていて心地が良いです。砂漠もイタリアなのでしょうか?乾いた空気感がこの本にピッタリくるのは意外な発見でした。砂粒を言葉、情報、資本と見立て、砂の海に立てられたのは秀逸。帯と砂漠のラインが揃っているのも収まりが良く。トリミングを気にされていましたが、このくらいで良かったと思いますよ。4枚あるなら、砂漠の一枚はもっと引きで撮っても良かったくらい。本を崖っぷちに置くと、なぜか凛々しく見えるのも不思議な発見。上の2枚に比べると下の2枚は本が少し苦しそうかな。
「資本主義ー脅威なのか?契機なのか?使い用では?」
大澤正樹
ロケ派の大澤さん、今回は横浜の開港記念会館で撮影されました。この会館が完成した頃、本格的に近代資本主義が到来した・・。ご本人にご縁のある場所と『資本主義問題』を紐付けての一枚。関係線の引き方は良かった、でも本がピンボケしているのが惜しい。この場所でしたら、ステンドグラスの真正面から、本にピントをあわせて撮影するのもありかも。次回のロケチャレンジもお待ちしてます!
「日々績々問題」松井路代
どさりと積み上げられた古新聞と掛け合わせたのは松井さん。古紙っぽく折り目をつけたのも、あえて積み上がっているところをフレームインしたのも、新聞を逆に配置したのも、大見出しを綺麗に全部入れなかったところも、すべて◎ 一見何気なく見えるお写真ですが、これまで以上に遊びのある作品になりました。こうしてみると『資本主義問題』が新聞の見出しに見えるから面白い。松井さん、この調子で遠慮なく遊んでみてください。
「夢みるお金」渡會眞澄
よく見るとここは都内の宝くじ売り場。「資本主義をおちょくりたい」と選ばれた場所です。モデルさんがポスターの3人目のように佇んでいるところに渡會さんのユーモアを感じます。この企画でモデルさんを起用されたのは初めての試みですね。こういう挑戦はどんどんしてほしいです。「本が目立っていない」と呟かれておられましたが、写真の中の情報量が多いのでモデルさんのバストアップでトリミングするだけでも効果がありそうです。
「どこもおりられない」石井梨香
「幹線道路のロードサイドはどこも同じ風景、そこには資本の論理がある」と読み、撮影に臨まれたのは石井さん。こうして、みなさんが考えられる設定が回を重ねるごとに少しずつ深くなってきて、この企画の手応えを感じます。”写真”フィルタでいつもみている景色を覗くと「目で見えているよりも寂しげ」という発見◎ それならば、より寂しさを強調するか、いつも見ているような景色を追い求めるか。撮影しながら方針に微調整を加え、いろいろな構図やフレーミングも試してみると更なる新しい発見を楽しめそうです。
◇
『資本主義問題』を撮るという難題に、みなさん力まれるかもな?と当初は案じていました。しかし、今回の作品は妙な力みが薄れてきて、のびのびと撮影を楽しまれているように感じました。引いては撮影における選択の仕方が増えたとも言えそうです。
次回、Season19のエディション読みは『ことば漬』がお題です。どのような作品が顔を揃えるのか?次号の公開をお待ちください。
今回のエントリー作品はイシス編集学校Instagramでも公開しますのであわせてチェック!
イシス編集学校Instagram(@isis_editschool)
https://www.instagram.com/isis_editschool/
おまけ
アイキャッチ画像は筆者の撮影。『資本主義問題』を亡霊っぽく不気味に撮りたいと、真っ黒の背景で、いくつかの懐中電灯を駆使しました。その割にパキッとしすぎて、なんだか整然としてしまいました。ノイズをもっと入れた方が良かったかもしれません。
Back Number
後藤由加里
編集的先達:石内都
NARASIA、DONDENといったプロジェクト、イシスでは師範に感門司会と多岐に渡って活躍する編集プレイヤー。フレディー・マーキュリーを愛し、編集学校のグレタ・ガルボを目指す。倶楽部撮家として、ISIS編集学校Instagram(@isis_editschool)更新中!
熊問題に、高市内閣発足。米国では保守系団体代表が銃撃された。 イシスの秋は、九天玄氣組 『九』、優子学長の『不確かな時代の「編集稽古」入門』刊行が相次いだ。11月にはイシス初の本の祭典「別典祭」が開催され、2日間大賑 […]
エディスト・クロニクル2025 #02 松岡校長一周忌 ブックウェアを掲げて
酷暑の夏、参院選は自公過半数割れで大揺れ。映画「国宝」は大ヒットした。 8月は、松岡正剛校長の初の自伝、書画集、『百書繚乱』と3冊同時刊行で一周忌を迎える。田中優子学長は近年の読書離れを嘆き、YouTube LIVE […]
エディスト・クロニクル2025 #01 田中優子学長、師範代になる!
新横綱の誕生に、米トランプ大統領の再選。米の価格が高騰する中、大阪・関西万博が開幕した。編集学校では、54[守]特別講義に登壇したISIS co-mission 宇川直宏から出題された生成AIお題に遊び、初めて関西で開 […]
写真というアウトプットにコミットする俱楽部 多読アレゴリア「倶楽部撮家」第3期目は、さまざまなものや先達から肖り、写真をより楽しむことをテーマにします。 第1期目の夏シーズンは、自身の幼な心からはじめ、お盆にはもう会 […]
『方法文学』を写真する PHOTO Collection【倶楽部撮家】
本にはなんだって入る。世界のまるごと入ってしまう。写真にもなんだって入るだろう。世界がまるごと入った本だって入る。 今夏刊行された『百書繚乱』(松岡正剛/アルテスパブリッシング)では、こう締めくくられている。 &nb […]








コメント
1~3件/3件
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。
2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥
LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。