ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。





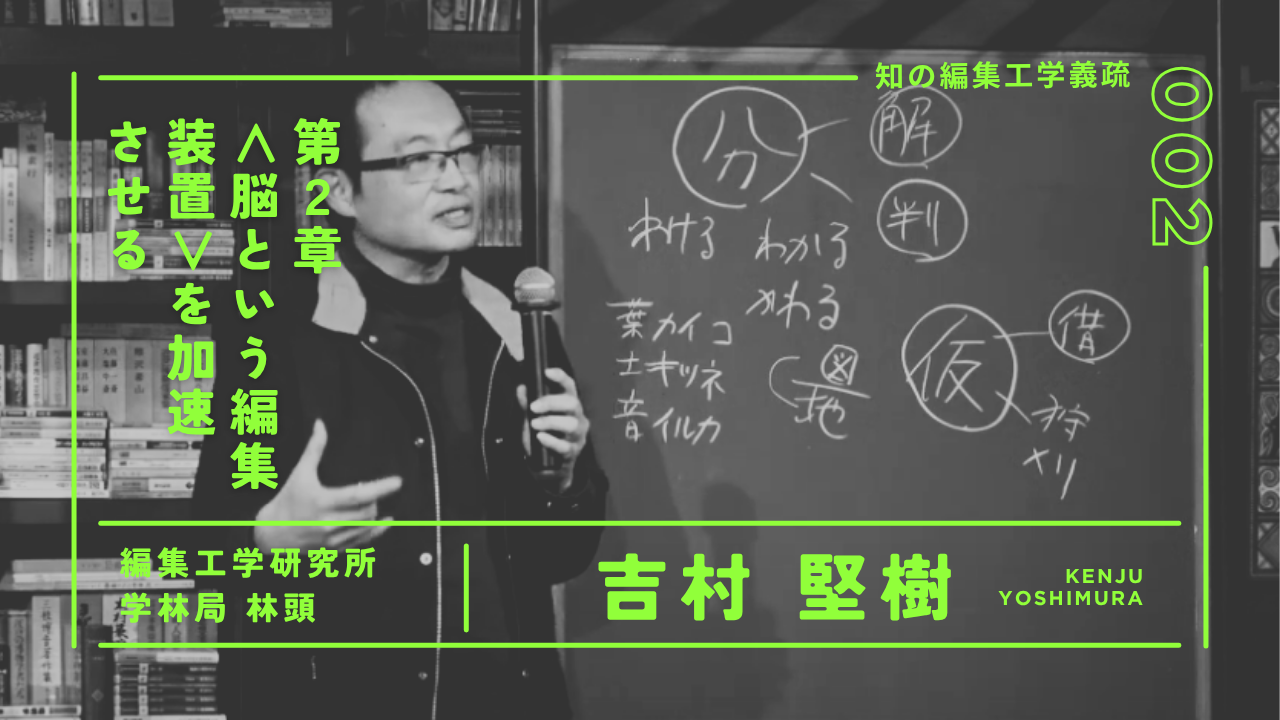
松岡正剛が旅立って一年。
今こそ、松岡正剛を反復し、再生する。
それは松岡正剛を再編集することにほかならない。これまでの著作に、新たな補助線を引き、独自の仮説を立てる。
名づけて『知の編集工学義疏』。義とは意見を述べること、疏とは注釈をつけることを意味する。
聖徳太子の「三経義疏」に肖り、第一弾は編集工学のベーステキストでもある『知の編集工学』を義疏する。連載の二回目は、「第二章「脳という編集装置」を独自に読み解く。2022年AIDA講義のダイジェスト映像とともにご覧ください。
(映像制作:編集工学研究所 山内貴暉)
0.要約コンデンス 一、二章
第一回目では、第一章を『知の編集工学』義疏しました。始まりと終わりのあいだ、インプットとアウトプットのあいだにあるのが「編集」だということ、ということは、つまりあらゆるところに「編集」があるのだ、ということから始めました。物事が動的になっているのであれば、そこには「編集」があります。前回は、編集は不足から生まれる、対話から生まれる、遊びから生まれる、の3つの点から、第一章を捉え直しました。
・脳という編集装置ダイジェスト
今回の第二章<脳という編集装置>は、「考え方とは何か」「分節する情報」「記憶と再生のソフトウェア」の三節からなります。
最初の節の「考え方とは何か」は、要約≒ダイジェストについて書かれています。情報は必ず圧縮(condense)されます。最初に編集は、情報に「注意のカーソル」(attention of cursor)を向けることから始まります。次にカーソルがあたった情報の「地」と「図」を確認する。そこから情報が、連想ゲームのようにハイパーリンク状態で「意味のネットワーク」になっているのをみる。この「意味のネットワーク」のジグザグを辿ることが「思考」なのです。ISIS co-missionで社会学者の大澤真幸さんが、その名もずばり『思考術』(河出ブックス)という本を書かれていますが、『思考術』でも一旦、結論めいたことを宙吊りに、判断を保留しながら、思考を迂回させていくことの重要性が説かれています。
思考のプロセスを辿る例として、コンピュータのプログラミング、怪我をした時に寝返りをどううつか、喪失した記憶の再生プロセスがとりあげられています。私はギックリ腰になったことがあります。ギックリ腰は動かすと激痛ですが、そのままにしていると褥瘡になりますから、体位を変える必要があります。どこを支点にして、どこを固定し、どう回転するのかはとても重要なのです。これらの行為には、IF/THEN/AND/OR/NOTのダンドリが必要だというのが、第一節「考え方とは何か」でした。
第二節「分節する情報」は、情報の海を前にして、オーダーをつけること、句読点を打つこと、つまり「分節化」することが先行するのだということが示されました。数も言語も生命の起源も、「分節化」が先行する。類人猿は、親指に四指が対向することで数が数えられるようになりました。Digit=指を折るというのがdigitalの語源になっています。
言語にも分節化が重要な役割を果たしています。喉によって音が分節化され、母音と子音が区別できるようになったことによって、飛躍的に表現できる言葉が増えたわけです。さらに、生命の誕生も分節化が始まりです。A・G・ケアンズ=スミスの驚くべき「テイクオーバー仮説」というのは、無機物(柔らかい粘土的鉱物)の鋳型に情報が出入りすることで、複製能力をもったのが生命の最初ではないかという説です。無機物のシステムに情報のインプットとアウトプットが起こり、そのうちにDNA/RNAの有機的遺伝情報が生体膜によって守られ、外側と境界が区切られて生命様式が発生したというわけです。前回の編集のin/outモデルが生命の根本であって、編集をしていることが生命であるわけです。
第三節では、まさに「情報の編集」がテーマです。さきほどの遺伝情報システム、コロナ禍で一気に注目された免疫情報システム、そして、中枢神経系、中枢編集装置の脳。脳では、ニューロンとニューロンがシナプス連結していて、電気情報を化学情報に変換して意味が編集されています。その中で「記憶と再生」、短期記憶から長期記憶への変化に着目しています。そのメカニズムとして、5点挙げられていました。一つ目が注意のカーソル、二つ目がプロトタイプやカテゴリー、三つ目がマーヴィン・ミンスキーの提唱したフレームとスキーマ、4つ目が要約は編集構造だということ、5つ目がモダリティです。
1.「分」という思想
さて、第二章では、3つの漢字で捉え直してみようと思います。一つ目の漢字は「分」です。これは分節化(articulation)のことです。分節化した情報に「注意のカーソル」があたることから編集が始まると言いましたが、この「注意のカーソル」が奪われている。アテンション・ビジネスとして社会やシステムが注意を奪い合っていて、一方的に注意喚起する情報が送られてくる。IN-OUTのINが、恣意的に与えられていていいの?ということですね。
この「分」は、どう分けるかということが重要です。この分け方に固有性が出る。民族性や言語性も出る。しかし、近代以降その分け方はデファクトスタンダードが用意されるようになりました。国境、宗教、民族など、どこに境界を引くかで差異が強調され、差別や憎悪が助長される場合もあります。また、共通のものさしをもつという利点はありますが、企業価値や偏差値、度量衡など指標やスコアなどの価値基準がそれしかないもののように固定化していく。太陰暦や尺貫法などから遠ざかることで、身体とスコアが切り離されていくという弊害も生まれました。
イシス編集学校のコピーに「わけるとわかる」「わかるとかわる」「かわるとわかる」というものがあります。分け方によって、見え方が変わって何かが解る。わかるというのは、「分」でもあって、「解」のわかるでもある。またどう分けるかを「判」断し、決断しているのです。
でも日本語は、グローバルスタンダードと違って、わかりやすくはなっていません。例えば概念ひとつとっても、「いき、通、だて、いなせ、おきゃん」とか、これらは違いがわかりにくい。九鬼周造が『いきの構造』で、「いき」を媚態、意気地、あきらめに分けて説明したのも、海外ではその感覚が伝わりにくいからでしょう。
でもそれが言語の本来性ではないでしょうか。言語というのは正確性を目指しているものではありません。伝えたいことは伝えきれない、そのままは伝えられない、その不完全性のまま私たちは交わしあっている。特に日本語は、差し掛かった状況や相手によって意味が真逆になることもあれば、主語という責任の所在も曖昧にしてお互いさまにしています。そういった日本語は特殊な言語であるように見えるけれども、言語としての普遍だろうということです。日本語には「いき」とか「通」とかいってモードごとで微妙にわかる集団性や高速性がある。それは言語の本来であって、社会の将来であるように思えるのです。
余談ですが、ここで女子高生風『枕草子』をご紹介しましょう。
春のアレヤバい。
なんか山のところの紫のやつヤバい。雲ヤバい。
夏はなんかアレ。
光るやつ、虫の。アレヤバい。をかし。雨も。
秋も相当パない。
夕方ごろ鳥めっちゃ飛んでる。びびる。超すごい。あと夜もすごい。虫すごい。
冬寒い。明け方超寒いけど雪好き。
これはやばい笑。貧弱な語彙力を揶揄したパロディですが、できるだけ語彙を少なくして、見事に圧縮コンデンスしています。
話を戻しますが、江戸の日本には「分」の思想というものがあります。江戸文化研究者である田中優子先生のご専門です。自分、身分、本分、持分、気分、武士の一分、分をわきまえろという言い方もする。これらは「分」で固定化されてしまったみたいな見方をされがちですが、それだけではありません。「分」の後に編集が動くことが起こります。江戸時代では、身分ごとに武士道、商人のための石門心学が育ったのは一例です。
2.「仮」という見方
二つ目の漢字は「仮」です。注意のカーソルがあたった情報は「仮」の親になり、次々に子ラベルを、さらにその子ラベルが仮の親になって孫ラベルを引き出していきます。『知の編集工学』のサブタイトルのように「情報はひとりでいられない」し、「一人でいていない」わけです。注意からの編集のプロセスは『知の編集術』で「編集十二段活用」として解説されていますので、参照してみてください。
区別することは、仮の切断をしたということです。分けられた情報は、必ず仮の「地と図」をもっています。この「地と図」が情報では必ずセットになっている、という意味でも「情報はひとりでいられない」のです。分けた時点で「地」をどこかから「借」りてきているわけですから。次の情報の連想を「狩」りしているし、由来や歴史を含めた情報を「刈」りとってきている。情報の分節化は、いつも「かりぐらしのアリエッティ」です。たとえば、コップという情報は、地を動かしてみると商品、製品、燃えるゴミ、日用品、糸電話、おもちゃ・・・と変わっていく。これらはすべて「仮」の姿です。
情報の地というのは、仮であって動かせるものなんだけれども、現代社会ではこのかりそめだったはずの地がなかなか動かせません。新しい資本主義という掛け声も、新しい「地」になったようにはみえません。2020年に話題になったデビッド・グレーバーの『ブルシットジョブ』というのは、自分も役に立っている実感をもてなくて、くそつまらない仕事と思っているけれどもその仕事を辞められないという話です。それが特にホワイトカラー層に広がっているということでした。
千夜千冊475夜 ダニエル・ベル『資本主義の文化的矛盾』では、以下の七つの現代病が指摘されています。
(1)解決不能の問題だけが問題になる病気
(2)議会政治が行き詰まるから議会政治をするという病気
(3)公共暴力を取り締まれば私的暴力がふえていくという病気
(4)地域を平等化すると地域格差が大きくなる病気
(5)人種間と部族間の対立がおこっていく病気
(6)知識階級が知識から疎外されていくという病気
(7)いったん受けた戦争の屈辱が忘れられなくなる病気
解決不能の問題だけが問題になる病気、公共暴力を取り締まれば私的暴力がふえていくという病気、地域を平等化すると地域格差が大きくなる病気などというのは、「地」を固定化して、一つひとつの課題解決型のソリューションにしようとするから、全くうまくいかない。根治していないから、一つの解決に向かうと別の問題が噴出します。
「仮」の問題は、社会や組織だけではなく、「自己」という仮の中心とも関係があります。生物は「自己」という、情報自己の仮設をしました。ところがこれが「仮」なのに、近代社会が自己同一性を求める方向をもっているため、個人も強い自己として動かなくなる。私は私だ、私らしさ、自分探しになっていってしまいます。
でも本来は、葉っぱかいこ、土キツネ、音イルカみたいに、情報や相手、対象ごとの自己が「仮」で動いていく、動的な自己で、相互的な自己なはずです。これを編集工学では「エディティング・セルフ」という言い方をしています。外側の花の蜜と中の昆虫のセンサーが情報科学的には同じものになっているのと同じように、私たちもスマホわたしとか、会社自分とかになっているでしょう。ヴァルター・ベンヤミンの『パサージュ論』は、パリのアーケイドであるパサージュがパリの人々の内側に影響し、人の内側なる欲望が外側のパサージュになっているということが、さまざまなディティールと共に描かれています。
とはいえ、なかなか動かない「仮」をどうすればいいか。社会も国家も自己も「仮」ですが、全体を挿げ替えようとするとなかなかうまくいかない。だから、この「仮」は「別」でいい。いい具合の「別」を仮に用意する。これが、芭蕉の「虚に居て実を行うべし」ということの一つの活用です。
3.「空」のシソーラス
最後は「空」=うつ、です。松岡正剛の『日本という方法』(角川ソフィア文庫)で詳述されているように、この「空」=うつからは、うつわ、うつつ、うつろい、うつし、うつくしなどといった言葉が派生します。うつは、「空」でもあれば、「全」という字をあてることもある。からっぽということでもありますが、うつわであって、情報がそこに出たり入ったりして充全になることもあります。
第二章3節「記憶と再生のソフトウェア」では、短期記憶から長期記憶に移行するには情報のリロケーション、脳の中の写像的なしくみが関与しているとありました。この「うつす」というのは「空」に情報が入ることであって、写す、映す、移す、遷す、です。類型のプロトタイプから、ステレオタイプの典型のようないくつもの例示や、歴史的起源に遡ったアーキタイプの原型にうつっていくというのもあれば、ミンスキーのフレーム、スキーマのように連想的にどんどんうつっていく場合もあります。特に場所や空間、モデルなどの編集構造ごとうつすというのが記憶と再生では大事なわけです。
この「うつす」というのは、「肖る」ということでもあります。「あや・かる」という言葉には「かる」=借りが入っていますが、生命や歴史や文化にある編集モデルが「あや」ですから、それを借りるということです。私たちは社会やサービスが用意し、教育された記憶と再生の装置を使っていますが、この考え方や分け方を空じて、肖りたいモデルにうつしていきたいわけです。
第二章を漢字一字で「分」「仮」「空」とみてきました。天台智義の摩訶止観では、「空・中・仮」という考え方があります。まず空じて、いろんな分け方を考えて、こりゃいいという仮を仮設するということです。第二章で論じたことはこれと重なります。
第二章の最後では、『情報宇宙論』の著者で美学者の室井尚さんの言葉が引用されています。「重要なのは、むしろ精神の編集性を逆手にとった新しい精神の形態の構築とでもよぶべき方向ではないだろうか」「精神の外化とその編集可能性という認識は、精神の自由な形態=構造をさまざまな場所につくりだすことができる可能性をもっているのである」。できの悪い「仮」は空じて、分け方を更新して、「別」にうつしたい。そう思わない人はいないはずです。
それを精神の外化とその編集可能性と言い換えられているわけです。では「精神の外化」とはどういうことか。どのように可能であるのか。それは第3回で義疏することにしましょう。
▼知の編集工学義疏
第2章 <脳という編集装置>を加速させる
第3章 <情報社会と編集技術>のキーワード ーComing soon
第4章 <編集の冒険>のための補助線 ーComing soon
第5章 <複雑な時代を編集する>方法がある ーComing soon
第6章 <方法の将来>に向かうために ーComing soon
吉村堅樹
僧侶で神父。塾講師でスナックホスト。ガードマンで映画助監督。介護ヘルパーでゲームデバッガー。節操ない転職の果て辿り着いた編集学校。揺らぐことないイシス愛が買われて、2012年から林頭に。
【オツ千ライブ!2/3 21時配信】記憶の迷宮イメージメント
千夜千冊絶筆篇 1859夜 田中純『アビ・ヴァールブルク』をオツ千ライブでおっかけ! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。1859夜 田中純『アビ・ヴァールブル […]
【オツ千ライブ!】「孟子と王子のキズナ伝説」1/29 17時配信!
千夜千冊のダブルヘッダー二夜を合わせて、1月29日17時から、おっかけLIVE開催! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。1478夜『ソーシャル・キャピタルの潜 […]
【オツ千ライブ!】才能を喧嘩で展く術 12/19 21時より配信!
千夜千冊のダブルヘッダー二夜を合わせて、12月19日21時から、おっかけLIVE開催! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。絶筆篇 1857夜 大友啓史『クリエ […]
【オツ千ライブ!】12/2 21時よりWヘッダー アーリア神話&贈与論をおっかけ!
千夜千冊のダブルヘッダー二夜を合わせて、12月2日21時から、おっかけLIVE開催! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。1422夜 レオン・ポリアコフ『アーリ […]
【オツ千ライブ!】10/24 22時よりルネ・ジラール&ケアンズ・スミス&ニック・ランドを三夜おっかけ!
千夜千冊をおっかけつづけて4年初めての二夜をおっかけLIVE開催から一ヶ月、次は3夜を一気におっかけます! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。492夜 ルネ・ […]







コメント
1~3件/3件
2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。
2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。