背中に異形のマレビトを背負い、夜な夜なミツバチの巣箱に襲来しては、せっかく集めた蜜を略奪するクロメンガタスズメ。羊たちが静まり返る暗闇の片隅で、たくさんの祭りのニューロンがちかちかと放電し続けている。





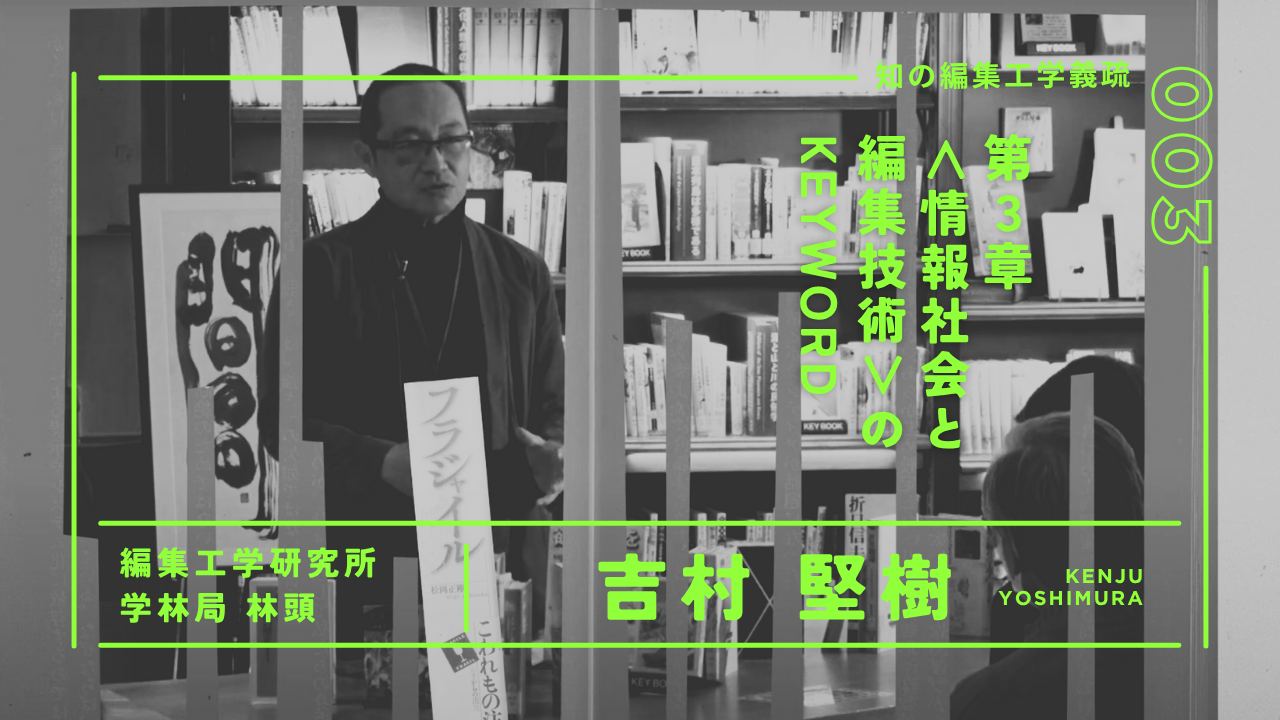
今こそ、松岡正剛を反復し、再生する。
それは松岡正剛を再編集することにほかならない。これまでの著作に、新たな補助線を引き、独自の仮説を立てる。
名づけて『知の編集工学義疏』。義とは意見を述べること、疏とは注釈をつけることを意味する。
聖徳太子の「三経義疏」に肖り、第一弾は編集工学のベーステキストでもある『知の編集工学』を義疏する。連載の三回目は、「第三章「情報社会と編集技術」を独自に読み解く。2022年AIDA講義のダイジェスト映像とともにご覧ください。
(映像制作:編集工学研究所 山内貴暉)
0.編集の入口の最後
・第一章と第二章を概観
『知の編集工学』は6章立てで、3章ずつにわかれていて、前半が「編集の入口」、後半が「編集の出口」となっていました。「編集の入口」とは何かというと、編集を始める前にここまでは知っておいてください、知ったうえで編集始めましょうということが書かれています。第一章は、一言で言えば「編集ってなんなの?」ってことでした。IN/OUTのあいだ、始まりと終わりのあいだには、すべて編集が動いているということでした。第二章は、そもそも脳自体が編集しているということがテーマでした。編集では、仮に分けているのを動かして、写(移、映、遷=空)していくことが、記憶の定着においても肝要であることを伝えました。第三章は、「情報社会と編集技術」です。
・情報化と編集化
まさにいまは、情報社会ですが、編集技術が必要だということを、『知の編集工学』の初版が出版された1996年から松岡正剛は警鐘を鳴らしていました。情報社会では、ハードの情報化/ソフトの編集化というように対比的に語られています。ただ、いまもソフトウェアは無料が当たり前と思っているのか、予算がつきにくいところにも、いまだに編集技術が十分に重要視されていないことがうかがえると思います。
第三章の冒頭は、「米ソによる冷戦構造があっけなく崩壊して」というところから始まります。1990年がベルリンの壁崩壊、1991ソ連解体です。そのころ日本は高度経済成長のあと、恥ずかしげもなく経済大国+生活大国を試みたけれど失敗したと書いてあります。この経済大国+生活大国は失敗したけれども、大きく目指している方向性は切り替わっていないんじゃないか。経済大国と生活大国というのは、言い換えると「消費大国」を目指しているわけです。大国はもはや無理かもしれないとうすうす気づいているけれども、「立派な消費人間」をつくろうというのはあまり変わっていないように感じています。消費人間というのは、みんなできるだけ同じほうが、消費させる側にとっては都合がいいんです。みんなが正解を求めている方が都合がいい。なぜなら、右向け右で効率よく消費してもらえるからです。でも、それではまずいですよーというのが第三章です。
1.キーワードは「文化」
・情報文化技術と経済文化
第三章の義疏には、松岡正剛が監修して、編集工学研究所が手掛けてきたブックウェア空間が参考になります。近畿大学ビブリオシアター、敦賀ちえなみき、角川武蔵野ミュージアムのエディットタウン、そしてかつての松丸本舗。第三章のキーワードは「文化」です。
・編集と文化の関係
「第三章では、「情報文化」と「経済文化」という言葉が何度もでてきます。まず最初に「情報文化」ですが、「情報文化技術」という書かれ方をしています。情報化というのはビッグデータに代表されるように、ハードウェアで処理できるようにするということ。もう一つの「文化技術」というのが「編集技術」です。文化にするためには編集が必要なのだということです。
・「文化」とはなにか
じゃあ、「文化」って何なのか。
「文」というのは「×」印であって、文身(ぶんしん)=刺青のことです。共同体への加入式の儀礼のときの聖化の方法でもありました。また「文」=「あや」とも読みます。「あや」の言葉という言い方をするように、「文化」というのは「あや」がわかる人たちでつくられます。共同体の成熟した人間、人間になった同士の交流やそれによって発現する表象であるわけです。だから「文」というのは呪能であって、共同体の世界と強く結びつけられるものであるわけです。
2.情報化・編集化・文化
・ずっと前からマルチメディア
最初に情報化があり、続いて編集化され、それが交わさせるようになって「文化」になります。現代はマルチメディア社会ですが、それは消費のためのマルチメディアです。サブカルアニメが、最初からマルチメディアでゲーム、おもちゃ、グッズ、ノベライズ、主題歌などで展開します。私たちはそれを消費するだけです。歴史のなかではマルチメディアの掛け算が起こっているからそれを見たほうがいいと記されています。情報化・編集化・文化で重要なこととして、『知の編集工学』で示されているのが、「ことば」と「しるし」です。
・ことばとしるしの再生装置
オラルコミュニケーションの語り部による伝承に始まり、それが文字になることで、古事記、ホメロスの神話、司馬遷の史記になっていった。「ことば」によって物語として保存され、伝達されていきました。
一方で、建築や彫刻、図像や文様といった「しるし」としても保存されていきます。これは聖書が教会建築になったり、空海が経典を両界曼荼羅にすることなども、まさに「しるし」です。
中世から近世にかけての「情報文化技術」として紹介されているのが、ひとつは「系譜の発見」です。由緒をつくっていくストーリーstory(物語)から、ヒストリーhistory(歴史)をはっきりさせていった。もうひとつは「劇場の活用」で、シェイクスピアの世界劇場、世阿弥の能舞台が代表例として挙げられます。世界劇場では知識、技術などが知のデータベースとしてアドレスされていました。
これらは何度でももとに辿ることもできれば、何度も上演することもできる。情報を編集化するということは、再生装置をつくるということで、その再生が「文化」になるのです。
3.経済と文化の相似
・経済も文化も交換である
情報文化技術を取り戻すのに重要なのが「経済文化」という捉え方出会って、経済と文化を切り離さないということだと書かれています。経済学者のカール・ポランニー(弟が暗黙知のマイケル・ポランニー)は、非市場社会では「経済が社会に埋めこまれている」とみたわけですが、現代の市場社会においては経済に社会が埋め込まれるようになってしまいました。
実は「経済」も「文化」も、交換であり交流です。古代中世においては、シルクロードやステップロードといった道を通って、ノードとなる市で、貨幣、奴隷、情報といったコードを交換する。そこでエクスチェンジ、インターチェンジする約束というコードとモードがありました。少し整理すると、地域ごとに独自のモード(様式)とコード(情報)をもっている。他地域と交わるノード(結節点)においてコードが交換され、お互いの地域のモードに変換されるというわけです。
・エディティングモデルが先行している
そのときの交換を編集工学では、「エディティングモデルの交換」がされているとみます。記憶では編集構造が先行しているというのが第二章にありましたが、コミュニケーションのモデルも編集構造が先行しています。コミュニケーションでは、情報がエンコードされたものを受け取ってデコードして受けとるのではなくて、私たちは文化的背景ごと、それぞれの世界の編集構造=エディティングモデルごと交換しているわけです。
・世界編集としての文化
経済文化のモデルとして紹介されているのが、「コーヒーハウス」と「茶の湯」です。コーヒーハウスは17世紀末のロンドンで流行して、そこからジャーナル、株式会社、政党、保険、広告、クラブ、結社といった別様の可能性を次々生みました。茶の湯は茶室や茶道具の好み、織部や遠州はプロダクトとしても流通させていきました。
経済と文化がひとつになる経済文化モデルの特徴は、店主や亭主がいて、そこに「好み」があること、客が自己編集する余地があるということ、雑談(ぞうだん)からつぎつぎに別様が生み出されていくということがありました。
そのあと近代になって以降は、百科全書、マスメディア、万国博、百貨店になっていくわけです。あらゆるものを扱うようになり、店主側が全てを用意するようになる。経済文化モデルの条件が落ちていっていることが見えます。
4.新たな世界状態の提案
・情報文化と経済文化の起こりにくさ
亭主の好みがしめせなくなって、どこも似たようにフラットになっていく。大衆化するとみんなが気に入るものばかり揃えるようになる。さらに現代のようにコンプライアンスが気になると、ますます突出はしにくくなる。主客が入れ替わるようなことはなく、客が編集する余地はなくなり、選択肢から消費するだけになる。そうすると、情報文化技術=編集技術は磨かれなくなっていきます。
経済と文化が切り離されると、経済効率、経済効果を上げることが最優先になります。そうすると正解を探すようになる。正解というのは編集不可能性のことです。正解があるのであれば、その正解を行えばいいわけで、編集をする必要がないわけですから。
・フラジャイルという処方箋
松岡正剛の著作に『フラジャイル』(ちくま学芸文庫)がありますが、第三章の最後に「フラジャイル」が持ち出されています。次の時代の情報文化技術と経済文化を考える上で「フラジャイル」をベースにするのがいいのではないかという意外な提案です。
フラジャイルというのは弱さとか壊れやすさということです。弱いことを前提にしていると、情報や相手を丁寧に扱うようになる。弱さというのは、別の情報を呼び込んだり、他者の関与を招き入れやすくなる。困っている人を見かけたら助けてあげようと思ったりする。正解がないような弱い問いは、あれかこれかの連想を招き入れやすくなる。弱さは相互作用、相互編集を生むわけです。
・新たな世界状態へ
もう一度戻ると、「文化」がなぜ大事なのかとあらためて言えば、「文化」というのは相互作用であって、エディティングモデルの交換であるということ。つまり「文化」は、誰もが世界にコミットしているという世界編集のことであるからなのです。
情報文化技術と経済文化をベースにして新たな世界状態へ向かうというのが、編集の前提だということです。これが第三章が「編集の入口」のラストにある意味なわけです。ようやくこれで「編集」を始められる前提が揃いましたので、次回は「編集の出口」である第四章に向かいます。
▼知の編集工学義疏
第2章 <脳という編集装置>を加速させる
第3章 <情報社会と編集技術>のキーワード
第4章 <編集の冒険>のための補助線 ーComing soon
第5章 <複雑な時代を編集する>方法がある ーComing soon
第6章 <方法の将来>に向かうために ーComing soon
吉村堅樹
僧侶で神父。塾講師でスナックホスト。ガードマンで映画助監督。介護ヘルパーでゲームデバッガー。節操ない転職の果て辿り着いた編集学校。揺らぐことないイシス愛が買われて、2012年から林頭に。
【オツ千ライブ!】才能を喧嘩で展く術 12/19 21時より配信!
千夜千冊のダブルヘッダー二夜を合わせて、12月19日21時から、おっかけLIVE開催! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。絶筆篇 1857夜 大友啓史『クリエ […]
【オツ千ライブ!】12/2 21時よりWヘッダー アーリア神話&贈与論をおっかけ!
千夜千冊のダブルヘッダー二夜を合わせて、12月2日21時から、おっかけLIVE開催! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。1422夜 レオン・ポリアコフ『アーリ […]
【オツ千ライブ!】10/24 22時よりルネ・ジラール&ケアンズ・スミス&ニック・ランドを三夜おっかけ!
千夜千冊をおっかけつづけて4年初めての二夜をおっかけLIVE開催から一ヶ月、次は3夜を一気におっかけます! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。492夜 ルネ・ […]
【オツ千ライブ!】本日10/3 22時より『まつりちゃん』をおっかけ!
千夜千冊絶筆篇 1855夜 岩瀬成子『まつりちゃん』をオツ千ライブでおっかけ! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。1855夜 岩瀬成子『まつりちゃん』、オツ千 […]
【オツ千ライブ!】9/25 20時より初のWヘッダー蕪村&ボームをおっかけ!
千夜千冊をおっかけつづけて4年150夜を超えて、初めての二夜をおっかけLIVE開催! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。850夜 与謝蕪村『蕪村全句集』&10 […]








コメント
1~3件/3件
2026-01-06

背中に異形のマレビトを背負い、夜な夜なミツバチの巣箱に襲来しては、せっかく集めた蜜を略奪するクロメンガタスズメ。羊たちが静まり返る暗闇の片隅で、たくさんの祭りのニューロンがちかちかと放電し続けている。
2025-12-31

鳥は美味しいリンゴを知っている。リンゴに鳥が突っついた穴がある。よってこのリンゴは美味しい。
──「これは美味しいから」といただいた農家さんからのオマケ。切れば甘味成分ソルビトールが沁みていた。覗いてみたくなる世界は尽きない。
2025-12-30

ほんとうは二つにしか分かれていない体が三つに分かれているように見え、ほんとうは四対もある脚が三対しかないように見えるアリグモ。北斎に相似して、虫たちのモドキカタは唯一無二のオリジナリティに溢れている。