自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。





編集は変化なのである。編集はつねに変化しつづける「そこ」にさしかかって仕事をする。(中略)「かわる」と「わかる」は、必ずや「そこ」においてこそ成立するもので、「そこ」にさしかからないでは何もおこらない。
松岡正剛&イシス編集学校『インタースコア』P.17より
イシス編集学校の入門者はこれまで3万人を優に超える。その全員が必ず最初にまたぐのが[守]の門だ。その道中のお守りに『知の編集術』とともに手渡される一冊に『インタースコア』がある。500ページを超えるボリュームに、これから何が始まるのかワクワクしながら開講までの日々を過ごした人も多いだろう。
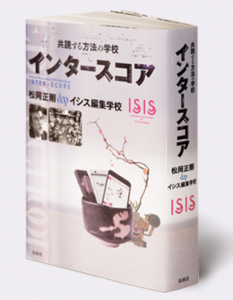
4月26日の正午、「これより第47期[守]基本コースを開講いたします!」という通知を合図に、編集稽古の門が開いた。
途端に飛び込んでくる「勧学会」「学衆」「師範代」といった聞き慣れない言葉。仕事帰りにメールチェックをすると、師範代からの投稿の連打に、名前しか知らない教室メンバーからの点呼や回答の数々。PCやスマホ越しに周囲の様子を見回したくなるような気持ち。こうした連続にとまどいつつも、門の先で広がる未知に期待を寄せている人も多いだろう。
そうした「とまどい」や「未知」こそが、編集の起点たる「そこ」にさしかかる編集の契機なのだ。
あえて自分をとまどいのなかに置いてみる勇気が、私たちを「次」に導いてくれます。
(同上 P.293より)
イシス編集学校で「そこ」に向かう一番の方法は、なんといっても「お題」だ。「ゲーム感覚でサクッとお楽しみください」「5分を目安に軽快にね」「肩慣らしのつもりで」「まずはウォームアップのつもりで」と、師範代からもお題回答への一歩を後押しする言葉が、学衆におくられる。
イシスのしくみの基本である「問感応答返」の「問い」は、すでにお題から始まっている。お題を読むと何かしらの気持ちが動くはずだ。「これってどういう意味だろう」「こういう使い方ができそう」など感じることがあふれでたり、「思ったよりもうかばない」「意外と難しいな」などの想定外にとまどう事態も起こる。そうしたものを応じつつ、回答として返していく。このプロセスの中で、変化=編集が起こっていく。こうした問感応答返を、師範代は編集術を通じてひもとき、指南として学衆に返していく。
こうして文字を打っている間にも、あちこちの教室で、「そこ」への一歩を踏み出した学衆に師範代が指南を手渡しはじめている。
編集学校はめっぽうおもしろい。どんな学習体験にも似ていない。(中略)ただ、本書を手にしただけで編集学校を覗いたことのない諸君には申し訳ないが、このおもしろさは「そこ」にさしかかってもらわないかぎりは、伝わりにくい。
(同上 P.23より)
『インタースコア』で[守]のページにつけられたタイトルは「型の原点 稽古の原郷」。
2000年の開校以来、型の原点 稽古の原郷でありつづける[守]の編集稽古は、今はじまったばかりだ。
上杉公志
編集的先達:パウル・ヒンデミット。前衛音楽の作編曲家で、感門のBGMも手がける。誠実が服をきたような人柄でMr.Honestyと呼ばれる。イシスを代表する細マッチョでトライアスロン出場を目指す。エディスト編集部メンバー。
11/23(日)16~17時:イシスでパリコレ?! 着物ファッションショーを初披露【別典祭】
本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]
第89回感門之盟「遊撃ブックウェア」(2025年9月20日)が終了した。当日に公開された関連記事の総覧をお送りする。 イシス校舎裏の記者修行【89感門】 文:白川雅敏 本を纏う司会2名の晴れ姿 […]
「松岡校長のブックウェア空間を感じて欲しい」鈴木康代[守]学匠メッセージ【89感門】
読書することは編集すること 「読書」については、なかなか続けられない、習慣化が難しい、集中できずにSNSなどの気軽な情報に流されてしまう――そうした声が少なくない。 確かに読書の対象である「本 […]
第88回感門之盟「遊撃ブックウェア」(2025年9月6日)が終了した。当日に公開された関連記事の総覧をお送りする。 なお、今回から、各講座の師範陣及びJUSTライターによる「感門エディストチーム」が始動。多 […]
「松岡正剛の方法にあやかる」とは?ーー55[守]師範陣が実践する「創守座」の場づくり
「ルール」とは一律の縛りではなく、多様な姿をもつものである。イシス編集学校の校長・松岡正剛は、ラグビーにおけるオフサイドの編集性を高く評価していた一方で、「臭いものに蓋」式の昨今のコンプライアンスのあり方を「つまらない」 […]




コメント
1~3件/3件
2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。
2026-01-12

午年には馬の写真集を。根室半島の沖合に浮かぶ上陸禁止の無人島には馬だけが生息している。島での役割を終え、段階的に頭数を減らし、やがて絶えることが決定づけられている島の馬を15年にわたり撮り続けてきた美しく静かな一冊。
岡田敦『ユルリ島の馬』(青幻舎)
2026-01-12

比べてみれば堂々たる勇姿。愛媛県八幡浜産「富士柿」は、サイズも日本一だ。手のひらにたっぷり乗る重量級の富士柿は、さっぱりした甘味にとろっとした食感。白身魚と合わせてカルパッチョにすると格別に美味。見方を変えれば世界は無限だ。