昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。




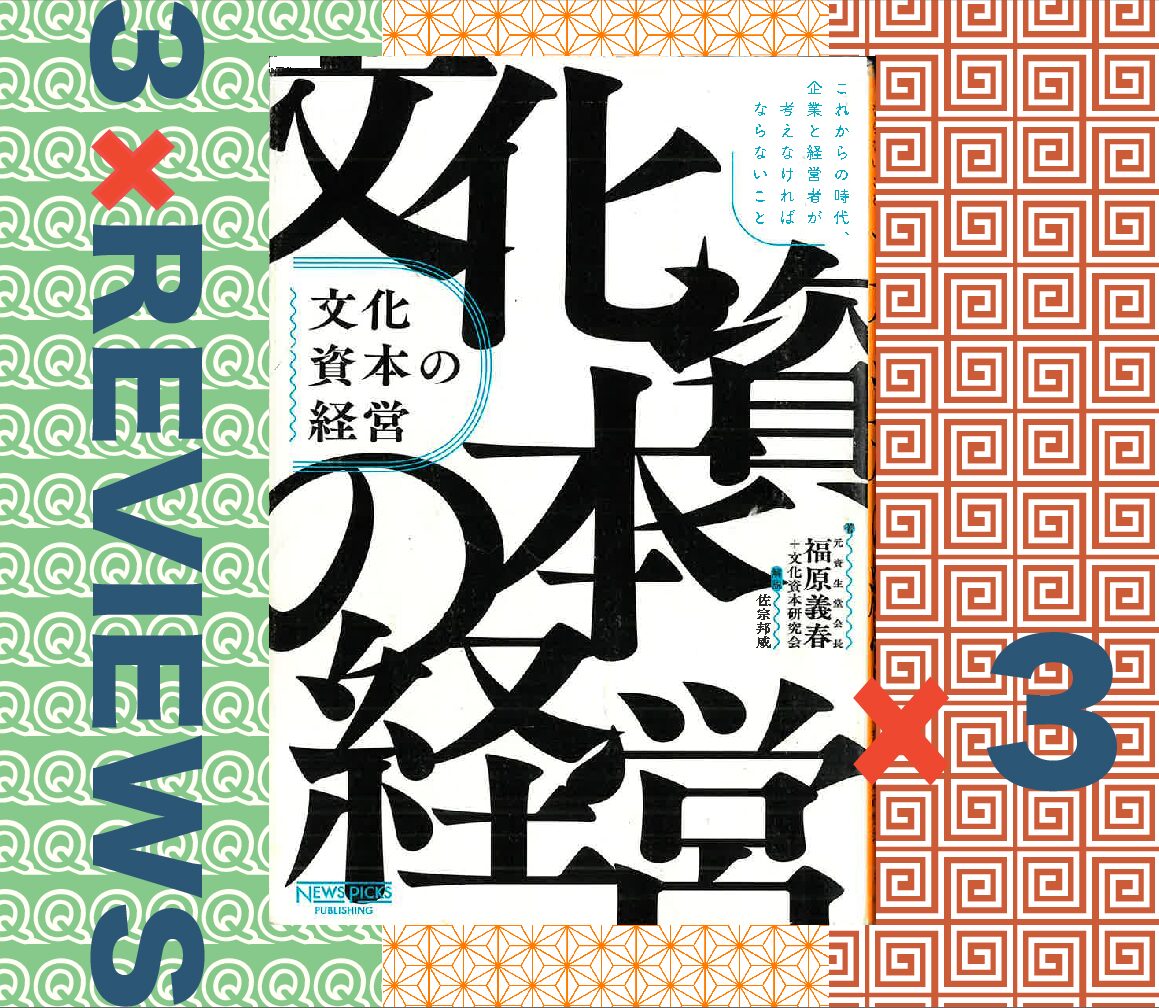
松岡正剛いわく《読書はコラボレーション》。読書は著者との対話でもあり、読み手同士で読みを重ねあってもいい。これを具現化する新しい書評スタイル――1冊の本を3分割し、3人それぞれで読み解く「3× REVIEWS」。
今回は、デザイナー界隈の中でも注目が集まっている、文化が主役の経営にフォーカスした『文化資本の経営』(NewsPicksパブリッシング)を取り上げます。推薦者は、チーム渦のメンバー・柳瀬浩之さん。「人材育成も組織開発も、企業文化に影響されます。でも、目に見えない文化って、操れるものなんでしょうか」。
●●●『文化資本の経営』×3×REVIEWS
1章 文化経済の時代の到来
2章 新しい経営アイデアが湧いてくる場所
企業経営において資本といえばお金だ。だが本書は、お金の代わりに文化を資本とする経営のコンセプトを打ち出した。現在から四半世紀前のことである。なぜ文化は、企業活動の元手になりうるのか?

かつて、文化は見えづらく、経済的に換算しがたく、商売にならないとされた。しかし現代では、より文化的な満足の得られるものが求められている。
見えづらい文化は、すでに私たちの中にある資本である。言葉で語り、表象し、場をつくり形成していくものだと著者は言う。そうやって異質な物事との出会いによって生み出される文化では、混交による葛藤も対立もふんだんに生じる。それこそが文化資本の原動力になる。そもそも人もその他の生命体も、自他非分離状態の場所に根拠を置いて生きているのだから。
見えない価値を信じ、相互に関係しあう場でこそ「何かが起こる」という期待が生まれる。その出会いを、まるで師範代のように自覚的にマネジメントしようとする。それが文化資本の経営だ。(大濱朋子)
3章 世界を丸ごとデザインできる経営を
4章 文化資本経営は新しい環境空間を演出する
文化を資本にして「期待」を生み出す。ではその文化とは何だろう? 日本企業が目を向けるべきは、母語である日本語だ。
例えば「展覧会を開きたい」は主語が強すぎる。「我が社が」「社長が」と主語の意志が気になってしまう。「展覧会を開きます」くらいにすると、「我が社が根付いたここで」「これが気になる関係者で」と参加者が増える。述語が意志を持ち始める。
述語的意志は、個ではなく場を動かす。このとき、主語が曖昧だからといって、主体は何も引き受けなくていいのだろうか? 否。企業とはその時代と地域の語り部である。「耕す」と言うだけで春のあらゆる事物を語る季語のように、伏せられた主語の大きさを述語で担う。これが文化資本経営だ。(吉居奈々)

5章 新しい経営を切り開くビジョンとは何か
補章 文化資本経営の理論
企業が述語的な意志を持つことめざすならば、舵取り役の経営者はどうか。自身も経営者である柳瀬は、何をめざす?

「物語の舞台という水槽の中のキャラクターを観察し、小説を書く」。これは、芥川賞作家、村田沙耶香氏の方法である。この方法が、これからの経営のヒントになる。そう思った。
リーダーの必読書の1つに「人を動かす」(D・カーネギー)がある。しかし、そもそも「人を動かす」という言葉には、リーダーの意図通りにメンバーを動かしたいという前提があるが、本書では、こうした管理統制する企業の時代は終わったと言う。「社員が社会的生命力をもつように場づくりをせよ」と。言うは易しだが、では「人を動かす」のような具体的な方法論があるのか。そのヒントは物語創作の方法にある。顧客や社員が多様なアクション・コミュニケーションを起こす舞台を創造する。これが文化資本経営だ。(柳瀬浩之)
『文化資本の経営 これからの時代、企業と経営者が考えなければならないこと』
福原義春/文化資本研究会 著/NewsPicksパブリッシング/2023年12月26日発行※1999年刊行の書籍を復刊/1,980円
■目次
巻頭解説 佐宗邦威
文化資本経営が企業の未来を切り開く――はじめに
1章 文化経済の時代の到来
2章 新しい経営アイデアが湧いてくる場所
3章 世界を丸ごとデザインできる経営を
4章 文化資本経営は新しい環境空間を演出する
5章 新しい経営を切り開くビジョンとは何か
補章 文化資本経営の理論
■著者Profile
福原義春(ふくはら・よしはる)
1931年東京生まれ。1987年、資生堂の代表取締役社長に就任。直後から大胆な経営改革、社員の意識改革に着手し、資生堂のグローバル展開をけん引した。2001年名誉会長に就任。企業の社会貢献、文化生産へのパトロネージュなどに尽力した。著書多数。2023年8月、92歳で逝去。
「リーダーは企業文化をどうしたら操れるのか」。この問いを持って、本書と向き合った。ただ早々に自分の傲慢さに気づいた。「操る」ではない。問うべきは「文化を資本として活用するには、どのような場づくりが必要か」である。人ではなく、場をマネジメントするのが、これからのリーダーの仕事なのだ。(柳瀬浩之)
エディストチーム渦edist-uzu
編集的先達:紀貫之。2023年初頭に立ち上がった少数精鋭のエディティングチーム。記事をとっかかりに渦中に身を投じ、イシスと社会とを繋げてウズウズにする。[チーム渦]の作業室の壁には「渦潮の底より光生れ来る」と掲げている。
数学にも社会にも「いい物語」が必要―津田一郎 56[守]特別講義
数学は、曖昧さを抱え、美しさという感覚を大切にしながら、意味を問い続ける学問だ。数学者津田一郎さんの講義を通して、そんな手触りを得た。 「数学的には手を抜かないように、それだけは注意したんです」 講義終了後、学林局 […]
巻き込まれの連鎖が生んだもの――宇野敦之のISIS wave #73
イシスの学びは渦をおこし浪のうねりとなって人を変える、仕事を変える、日常を変える――。 「いろいろ巻き込まれるんです…」と話すのは、[守][破][物語][花伝所]とイシスの講座を受講した宇野敦之さん。一体何に巻き込まれた […]
新しいことをするのに躊躇していたという増田早苗さんの日常に、突如現れたのが編集稽古でした。たまたま友人に勧められて飛び込んだ[守]で、忘れかけていたことを思い出します。 イシスの学びは渦をおこし浪のうねりとなって人を […]
【書評】『熊を殺すと雨が降る』×5×REVIEWS:5つのカメラで山歩き
松岡正剛のいう《読書はコラボレーション》を具現化する、チーム渦オリジナルの書評スタイル「3×REVIEWS」。 新年一発目は、昨年話題をさらった「熊」にちなんだ第二弾、遠藤ケイの『熊を殺すと雨が降る 失われゆく山の民俗』 […]
正解のないことが多い世の中で――山下梓のISIS wave #71
イシスの学びは渦をおこし浪のうねりとなって人を変える、仕事を変える、日常を変える――。 上司からの勧めでイシス編集学校に入ったという山下梓さん。「正確さ」や「無難さ」といった、世間の「正解」を求める日常が、 […]













コメント
1~3件/3件
2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。
2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。
2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。