棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。




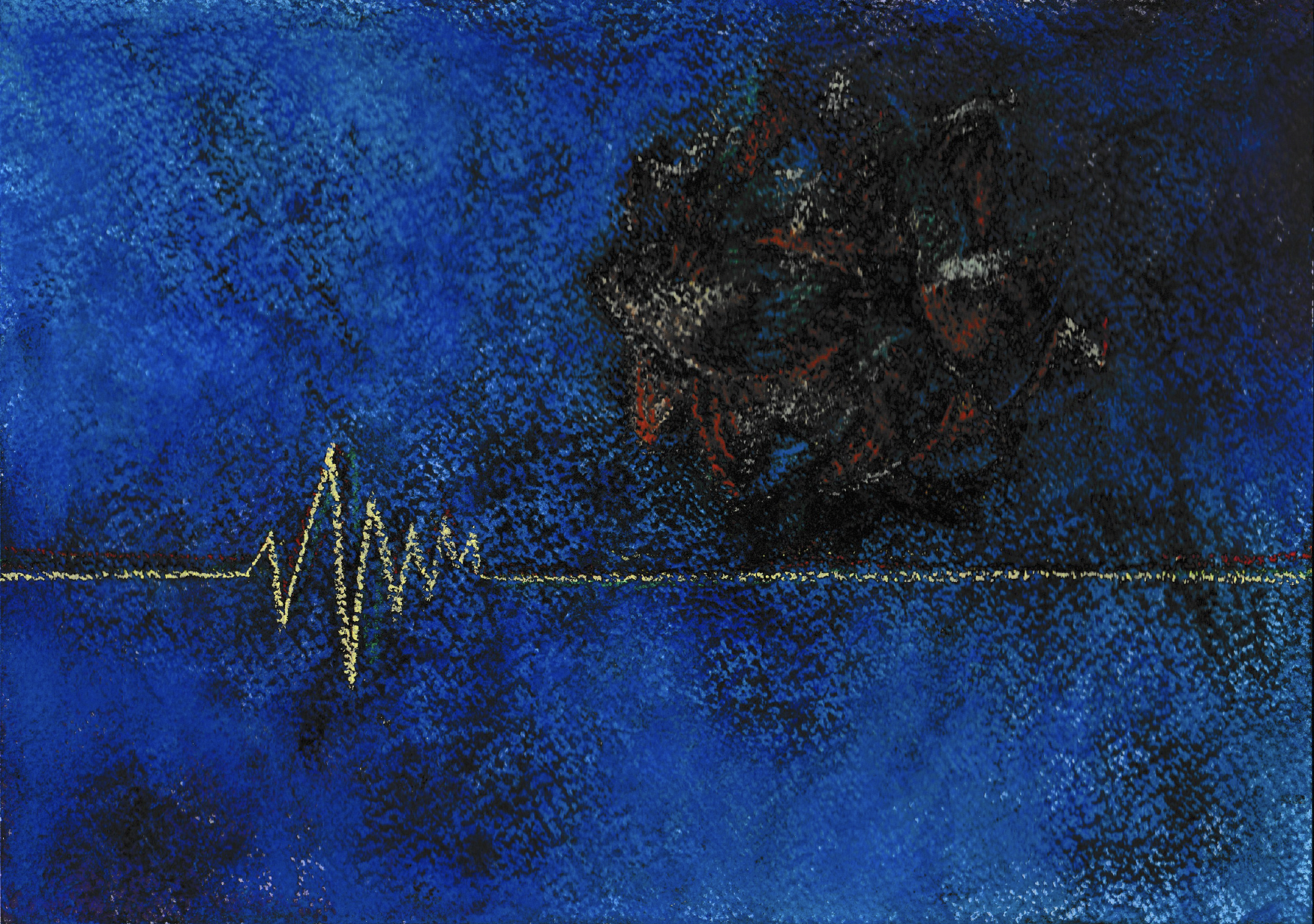
▼ソクラテスには、「内なるダイモン(デーモン)」がいたらしい。小林秀雄の「悪魔的なもの」(『小林秀雄全作品21 美を求める心』に収録)に詳しい。古代ギリシャでは、ダイモンとは神と人との中間者を意味した。個人の運命を導く神霊的な存在で、その人本来の性格にない善い行いや悪い行いをさせたという。ソクラテスは自分にとりついている霊を「格下のダイモン」という意味で「ダイモニオン」と呼んでいた。ちょっとポケットモンスターみたいだ。大モニョン・中モニョン・小モニョン……。
▼ソクラテスのダイモンは、宿主の味方だった。プラトンの「ソクラテスの弁明」にはこうある。「これは一種の声であって、いつも何かしようとしているのを止める。何かをせよ、とすすめることはない」。
現在ではデーモン(悪魔)と言うと、悪い道へ誘惑する厄介なイメージが強いけれど、そういう存在ではなかったようだ。
小林秀雄は、ソクラテスとダイモニオンの関係をこんな風に書いた。「ソクラテスはダイモンの俘囚(とりこ)ではない。むしろダイモンがソクラテスの意識を目覚ますのである」。
ダイモンは合図なのだ。命令ではない。無視することもできる声に、ソクラテスは耳を傾け続けた。
▼ダイモンの「何かしようとしているのを止める」声は、ソクラテスの「疑う力」を支えていたのではないかと小林は読んでいる。
ここからは私の想像だけれど、「AはAである」という事実を見て「ああ、そうね、AはAだよね」と受け流しそうになった時に、内なるダイモンの声が「ちょっと待て……」と耳の奥に響く。ダイモンはきっとそれ以上は何も言わない。「AはAではない」とも言わないし、「AはBである」とも言わない。そこから先はソクラテスに、もっと言えば哲学対話に、委ねられる。ダイモンの声は、立ち止まるきっかけだ。点滅する青信号みたいなものかもしれない。もちろん、これはダイモンのごくごく一部だけを捉えた想像だろうけれど。
▼さてこんなダイモンが、どうしてキリストを誘惑するサタン化して「悪魔」になっていったのかーーそれは、神の創造した世界に悪が存在する理由を「悪魔のせい」にせざるをえなかったキリスト教界の事情だった。(この点については「ほんのれんラジオ」のエピソード11-3で詳しく紹介しているので、ぜひご一聴ください。)
▼デーモンは元々「悪い魔」ではなく超自然的な存在を指していた。この点では、デーモンは日本の「鬼」に似ている。
『鬼とはなにか——まつろわぬ民か、縄文の神か』(戸矢学・著)によると、中国から「鬼」という漢字がやってくる以前から、日本には「おに」というヤマト言葉があった。その頃の「おに」は、畏敬すべき何者かを指した。「おに」は「かみ」と同類だったともいう。それが、死者を意味する漢字の「鬼」を当てはめられたことによって、次第に鬼と神が分離していった。
▼元々は「かみ」でもあった鬼が、気づけば豆を投げつけられ、外へと追い払われる存在に。こうなったのには、わけがある。ヤマト政権によるイメージ戦略だったのだ。今風に言えば、プロパガンダが「鬼は外」を生んだ。ヤマト政権は、自らに従わない人々を「まつろわぬ民=ヤマトの神を祀らない人々」と呼び「鬼」と見立てて、征伐対象とした。恐ろしく忌まわしい者というイメージを貼り付けて、退治していい相手としたのだ。
▼キリスト教によって悪者にされていったデーモンと、ヤマト政権によって排外された鬼。ソクラテスのダイモンが元々「疑う力」の根底を支えていたことを考えれば、支配者にとって「ダイモン的なもの」が恐怖対象になるのも自然なことかもしれない。
思えばソクラテス自身も、時の権力によって裁判にかけられ、毒盃を傾けさせられた。ただ、この毒盃を手にしたとき、不思議なことにソクラテスのダイモニオンは何も合図を送らなかったという。「止めろ」と言わなかった。その先に待つ世界を、ダイモンは知っていたのかもしれない。
▼小林秀雄はこんなことも言っていた。「彼(ソクラテス)にとって、自意識とは、よく生きんが為に統一され集中された意志に他ならず、この意識は不知なるものの大海に浮んではいるが、その不知なるものが、人間の意識なぞより、遥かに巨大な、完全なもう一つの意識であることを否定する理由は少しもないのである」。
▼いま、私たちの多くは「内なるダイモン」を見失ってしまった。その一方で、悪魔や鬼を根絶やしにする桃太郎役は飽和している。鬼退治は、もはや中央権力の専売特許ですらなくなってきた。SNS監視社会では、誰もがスマホに齧り付くエセ桃太郎だ。ちょっとでも叩けるものがあればヨダレを垂らして大集合。
自分自身の内なる鬼を見失い、外に敵や他者を次々見つけ出しては、薄っぺらな正義感で束の間だけ気持ちを癒す。そうして、だんだんと心の在処も自分の正体も分からなくなる。いま世界をつまらなくしているのは、闇堕ちした桃太郎軍団なのかもしれない。ならばそろそろ、鬼らしい鬼が銀河系の彼方から到着してもいい頃だ。
▼しかし果たしてノイズまみれのこんな時代に、内なるダイモンの声を再発見することなんてできるのだろうか。世間を見渡せば怖気付くことだってある。だけど、思い返せばソクラテスだって、ペロポネソス戦争の大混乱期にソクラテスになったのだ。危機や混沌の中でこそ、内なる銀河に耳をすませてみたい。ダイモンは見失われているだけで、いなくなってはいないのだから。
▶︎関連記事
Business Insider Japan 連載:ほんのれん旬感本考
この社会の息苦しさはどこから来るのか。鬼才・岡本太郎の言葉と5冊の本で読み解く「無鬼社会」の歪み
ーーーーー
◢◤山本春奈の遊姿綴箋
秘密のサンタクロース(2023年12月)
地の中の龍(2024年1月)
ソクラテスの「内なる鬼」(2024年2月)(現在の記事)
◢◤遊刊エディスト新企画 リレーコラム「遊姿綴箋」とは?
ーーーーー
山本春奈
編集的先達:レオ・レオーニ。舌足らずな清潔派にして、万能の編集ガール。定評ある卓抜な要約力と観察力、語学力だけではなく、好奇心溢れる眼で小動物のごとくフロアで機敏な動きも見せる。趣味は温泉採掘とパクチーベランダ菜園。愛称は「はるにゃん」。
田中優子×安藤昭子 特別対談「AI時代の編集力」– AIの思考プロセスが可視化された今、人間を支える命綱は「編集力」
ChatGPTの最新モデル「GPT-5」が登場し、いよいよAIとの共生方法が問われるようになってきた。特に意識せずとも、AIを活用した技術にすでに囲まれて暮らしている私たち。こうした時代において、AIがもたらす情報群の中 […]
【変革期のリーダーたちへ】学びに”没入”させる仕組みとは?——Hyper-Editing Platform[AIDA]の「場づくり」の秘密《後編》
〜オンラインなのに“空気”が伝わるのはなぜか?––––「黒膜衆」の編集力〜 既存の枠組みを超えて思考するビジネスリーダーのためのリベラルアーツ・プログラム「Hyper-Editing Platform[AIDA]」(以下 […]
【変革期のリーダーたちへ】既存の思考を”壊す”––Hyper-Editing Platform[AIDA]が示す新たな学び《前編》
〜教えない、導かない。でも変わる——“一座”で学ぶ[AIDA]の挑戦〜 複雑なものを複雑なままに——動的な世界を相手にする力を、物事の「間(あいだ)」に注目することで身につける「Hyper-Editing […]
[AIDA]ボードメンバーからのメッセージ公開。なぜいま「AIDA」が必要か?
編集工学研究所がお送りする、リーダーたちの本気の学び舎、Hyper-Editing Platform[AIDA]。 [AIDA]では毎期、各界の有識者のみなさまに「ボードメンバー」としてご一緒いただきます。 […]
【プレスリリース】佐藤優が直伝、激動時代に生き残るための「情報のつかみ方」と「世界の読み方」。「インテリジェンス✖️編集工学」を身につけるプログラムを開催します。
混迷時代を生き抜くために、「インテリジェンス✖️編集工学」が必要だ。 この夏、作家・元外務省主任分析官の佐藤優さんと編集工学研究所のコラボ講義が目白押しです。 6月30日(月)に編集工学研究所から配信したプレスリリースを […]












コメント
1~3件/3件
2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。
2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。
2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。