ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。





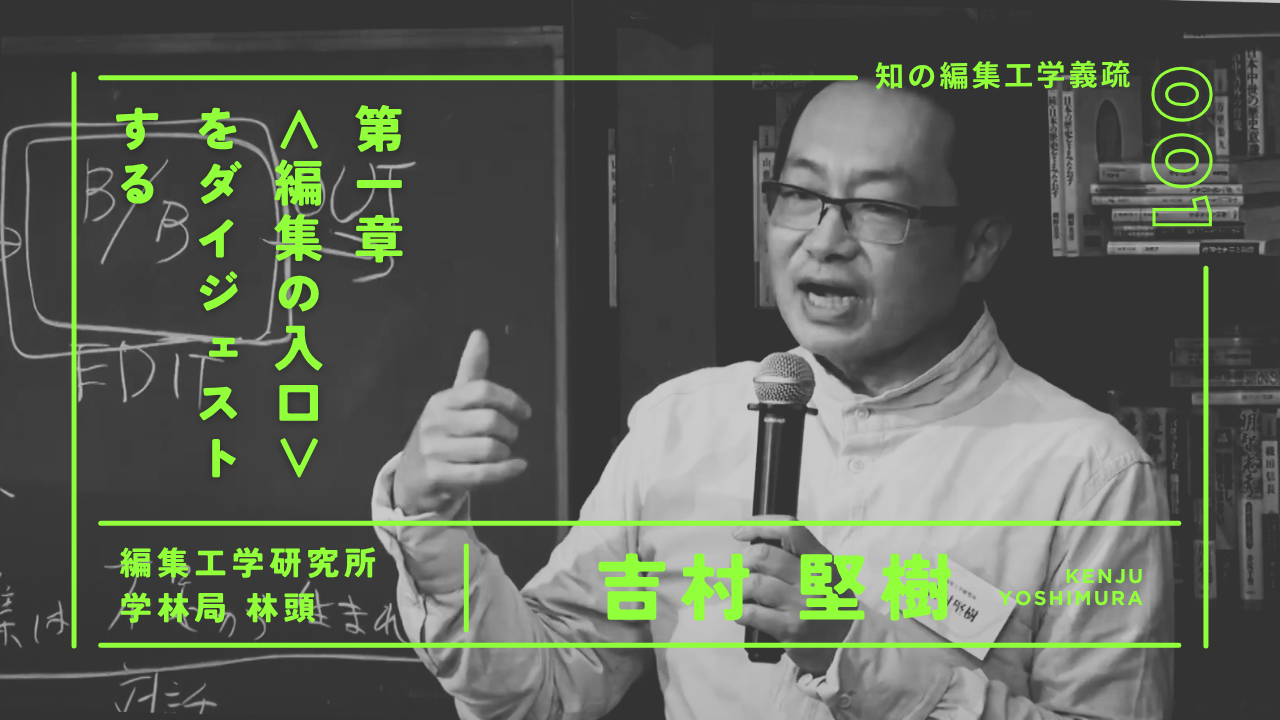
今こそ、松岡正剛を反復し、再生する。
それは松岡正剛を再編集することにほかならない。これまでの著作に、新たな補助線を引き、独自の仮説を立てる。
名づけて『知の編集工学義疏』。義とは意見を述べること、疏とは注釈をつけることを意味する。
聖徳太子の「三経義疏」に肖り、第一弾は編集工学のベーステキストでもある『知の編集工学』を義疏する。連載の一回目は、第一部である「編集の入口」をテーマに「第一章 ゲームの愉しみ」を読み解き、「編集」のいろはを伝える。
2022年講義のダイジェスト映像とともにご覧ください。
『知の編集術』(講談社現代新書)の冒頭に掲げられた「編集は不足から生まれる」「編集は対話から生まれる」「編集は遊びから生まれる」を起点に、既知からいかに未知を生み出すのか、境界線をどのように引くのか、単語の目録・イメージの辞書・ルールの群れをどのように更新するのかを語る。
(映像制作:編集工学研究所 山内貴暉)
0.『知の編集工学』を義疏する
・『知の編集工学』は原点
『知の編集工学』というのは松岡正剛が「編集工学」を創始した原点であって、このあと続いて、講談社現代新書の『知の編集術』が出版され、2000年にはイシス編集学校が開校しています。
この『知の編集工学』は非常にスコープが広い。生命からコミュニケーション、芸能から社会モデル、スポーツから方法日本までつながっている。初版は25 年以上前の本ですが、いまだにここに書かれている問題は未解決です。日本がヤバイという話しが書かれていますが、出版して四半世紀が経つ今でもまだ編集工学が広がっていない日本がヤバイと言ってもいいかもしれません。
・論・義・疏という方法日本
今回、『知の編集工学』義疏というタイトルは、東洋のリテラルな思考の進め方である、「論・義・疏」という三位一体から来ています。論というのは一つのテーマについて筋道を立てて解釈して、まとめて打ち立てるものです。仏教で言えば倶舎論とか秘密曼荼羅十住心論とか、ISISco-missionで社会学者の大澤真幸さんには「電子メディア論」とか『現代宗教意識論』という著書もあります。それに対して「義」というのは問いです。まだ明快な結論まで出ていない意見や疑問、仮説を検討する。「疏」というのは注釈であって、ゲーム作家で文筆家の山本貴光さんが『マルジナリアでつかまえて』という本への書き込みに関する本を出されていますが、注釈を書き込んでいくということを指します。
かつて、聖徳太子が『三経義疏』と言って、法華経、勝鬘経、維摩経義疏という3つの経典を選び、これは日本にうまく合いそうだとか、ちょっと違う、私はそう思わないとか言いながら「義疏」した。十七条憲法とともに日本の礎にしようとしたわけです。
それに肖って、『知の編集工学』を経典とすると、そこに問いを立てたり、注釈を書いて、松岡正剛を反復し、再生したいという試みです。
・目次とカバーから入る
『知の編集工学』のカバー、タイトルを見てみてください。表紙を見て気づかれることは何でしょうか。旧版の文庫では松岡正剛がやたら若いとか眼鏡を二つ持っているとか、増補版では機械になったりコップになったりたくさんのりんごが並んでいます。サブタイトルにはどちらも「情報は、ひとりでいられない」とあります。
次にページを開いてもらって目次を見てください。一.編集の入口、二.編集の出口とわかれている。全部で六章あります。こちらを 1 章ずつ取り上げていきますが、まず第一章「ゲームの愉しみ」。「情報は、ひとりでいられない」「編集の入口・出口」、「ゲームの愉しみ」が今回のお題です。
1.編集は不足から生まれる
・第一章プレイバック
第一章の最初の節は「編集はどこにでもある」。映画監督の黒澤明、ラグビーの平尾誠二、民俗学者や情報学者である梅棹忠夫が「編集」について語っている言葉を引用し、続いてメディアのなかの編集である見出しやタイトルといったアトラクティブ・フラッグの話、さらに美山荘や瓢亭と言った京都の老舗料亭、料理だけでなくイヴァン・イリイチがいうお母さんがたのシャドウ・ワークも「編集」だとしています。つまり、あらゆることが「編集」で、「編集」はどこにでもあるということです。
次の節の「連想ゲームの中で」はりんごから始まる連想ゲーム、そして遊びにある「編集」の話、3節目の「情報はつながっている」は、人間ができてコンピュータができないことが5項目に渡って書かれ、ニューロコンピュータの問題点に及びます。今ならきっとAIができないことが列挙されるでしょう。
さて、『知の編集工学』の次に書かれた『知の編集術』(講談社現代新書)では冒頭に
・編集は不足から生まれる
・編集は対話から生まれる
・編集は遊びから生まれる
という言葉がかかれています。
・情報の IN/OUT を動的にする
まず「編集」とは何か言えば、なんでも「編集」なんですよね。もう少しいうと、始まりがあって終わりがある、情報のインプットとアウトプットがある、そのあいだには編集が動いている。あいだには編集があるということです。<IN→BlackBox→OUT> 、このブラックボックスで起こっているのが EDIT=編集なわけです。例えば、対話をしていて相手が話す言葉を聞き、次に返す言葉を考えている。そのときは、インプットしてアウトプットするあいだで頭の中で「編集」が起こっている。パソコンでタイピングする、そうするとモニターに映る。そのあいだである P C の中で編集が起こっている。料理だと、材料を買ってきて刻んで、調理して、盛り付けて出す。この料理が仕上がるまでのプロセスが「編集」です。『知の編集工学』の目次構成には、編集の入口、出口とにあったのもうなずけるのではないでしょうか。
何かをインプットしてアウトプットするというのは、もっともシンプルな生命モデルです。自分自身を考えてもわかるはずです。吸って、吐いて、呼吸をしている、食物を摂取して、排泄をする。細胞レベルでも、細胞膜を通して情報を出し入れしている。「編集」のプロセスというのは情報を動的にするモデルでもあるのです。
・編集の前段階に着目する
「編集」は動的なモデルなのですが、まずこの「編集」の最初の情報のインプットが起こらないと編集は始まりません。ではどうやったら始まるのか。このインプットというのは、異質性を取り込もうとするということです。先ほどの<IN→BlackBox→OUT>、この境界線の内側で欠如しているもの、足りないものがあるとインプットしようとする。そして、新奇性があるものはインプットしたくなる。未知の情報です。お腹がすいたら、食事をする。新しいニュースは、知りたくなる。醤油が切れたら、お店に買いに行く。
ところが、現代ではSNSやプラットフォームなどからフィルタリングされた新情報が次々とプッシュされてくる。そうすると、自ら内側の既知から外側の未知を想定する必要がなくなってくる。外側の未知をつくれなくなってきてしまいます。下世話な話ですが、長年付き合っているカップルがいます。そうするとだんだん飽きてくる。これは相手のことをもう知っていると思っているからですよね。しかし、知っているけども知らないところもあるかもしれない。隠れて何かやっているかもしれない(笑)。未知があると思うことが重要なわけです。既知から未知を生むということは、どんな状況、場面においても重要です。
これが、『知の編集術』で紹介した、「編集は不足から生まれる」ということです。編集を始めるには、欠如や未知といった「不足」がないと始まらない。でもいまはその「不足」を外から押しつけ、突きつけ、見せつけられてしまう。広告とか評価とか流行といった社会適合型の「不足」がやってくる。本来、「不足」は内側に用意する必要がある。また「不足」は埋めきっちゃだめで、自己や組織や関係、次々に不足を生むような仕掛、仕組、仕立がいるわけです。
・内と外を分ける境界を動かす
この図でもう一つ注目してもらいたいのがこの 「編集=E D I T 」を囲む境界ですね。これが内と外、自他を分けているわけです。
ウクライナとロシアの戦争も、エネルギー資源の問題も、関税の問題も、この境界線の問題です。どこまでを内として、どこからを外とするのか。
人間は状況によって、皮膚に囲まれた自分自身から、自己の境界を家族や、会社、国家というように動かしています。このように地を動かすのがコンピュータには難しいというのが第一章三節で指摘されていたことです。推しや萌えや恋人、家族のこととなると感情で自己境界が拡張すること、役柄や役割が変わっていったり、切り替えたりするのがコンピュータには難しい。
このコンピュータが苦手なことのように、人間の境界も外側から規定されて、自在に動かせなくなると鬱っぽくなっていってしまう。自己境界をこの皮膚でつつまれた身体だけに限定しすぎると、他者評価、社会評価が気になりすぎて苦しくなるわけです。
2.単語の目録・イメージの辞書・ルールの群れを独特にする
・情報はひとりでいられない再考
「単語の目録・イメージの辞書・ルールの群れ」という独特な言葉が『知の編集工学』第一章に登場しています。子どもが言葉を覚えるときにも「単語の目録」と「イメージの辞書」を、これ何?とか指さし、確認して、対応させて、ママの言葉を聞きつつ、次第に文法という「ルールの群れ」が身についてくる。たとえば、『知の編集工学 増補版』のカバーデザインもタイトルや著者名や内容のシソーラスといった「単語の目録」があり、一方で編集工学の楽しげなイメージも再生させている。そのときに必要な情報の軽重やレイアウトといった「ルールの群れ」があるわけです。
アントニオ猪木さんが2022年に亡くなりましたが、プロレスというのは「単語の目録・イメージの辞書・ルールの群れ」をまさに独特にしていますよね。燃える闘魂やアントニオというキャッチやリングネームもあれば、コブラツイスト、卍がため、延髄斬りといった技名とかたち、マスクやパンツ、ガウンのイメージ、反則やリングアウト、フォール、ギブアップといったルールがある。この「単語の目録・イメージの辞書・ルールの群れ」は私たちの文化や日常の問題でもあります。日本語力、国語力の低下について昨今問題にした声が聞こえますが、確かに「単語の目録・イメージの辞書・ルールの群れ」が相互に交わせるかどうかは、意味や価値の問題と関わります。コミュニケーションは、連想的なつながりを媒介にしていると『知の編集工学』に書かれていますが、コミュニケーションというものは何か互いに共有しているものがないと成立しません。
「単語の目録・イメージの辞書・ルールの群れ」がある程度共有されていると、情報は連想ゲームのように、次の情報を呼び込んできます。<りんごーマック>というとコンピュータという情報が、<りんごーほっぺた>で赤ちゃんとかりんご病とか、<りんごー毒>で白雪姫とか、また情報が必ず読み込まれていく。そしてまた、その関係情報が次の情報を読み込む。次に欲しがる情報の方向性も出てくる。コミュニケーションは、連想が動いてずれながら、情報が前に前に進んでいくわけです。これが「編集は対話から生まれる」にあたります。「単語の目録・イメージの辞書・ルールの群れ」をユニークにすると、独特な世界が生まれてきます。
3.編集は遊びから生まれる
・なぜ遊びから生まれるのか
独自の世界をつくるといえば「遊び」なわけです。情報連鎖を自覚的に活用する編集技術が必要であること、中でも「遊び」に注目するといいと強調されている。ロジェ・カイヨワが遊びを分類した<アゴン・アレア・ミミクリー・イリンクス>や<パイディアとルドゥス>も紹介されています。ヨハン・ホイジンガも『ホモ・ルーデンス』=遊ぶ人間として遊びを重要視している。「編集は●●から生まれる」はどれも大事ですが、特に「編集は遊びから生まれる」は特別です。『知の編集術』でも唯一章タイトルにもなっています。
遊びでは、「単語の目録・イメージの辞書・ルールの群れ」が新たに別に編集されてきます。既存の世界の「単語の目録・イメージの辞書・ルールの群れ」が外れるから、新たな世界を産む編集状態に入っていけるわけです。シンプルな例を出すと、鬼ごっこのときには社会のルールは適用されません。平社員でも社長にタッチして鬼にするのはOKです。
「遊び」は、方法的だというのも、遊びを特別にしています。遊びをしているときには、ミハイ・チクセントミハイがいうフロー状態だったり、スポーツ選手が極度に集中したゾーンに入ることに近い状態になる。これは自己に対する評価から開放されて、どうすれば面白くできるか、どうすれば勝てるかという「方法」に注目するからです。方法だけにはいっていける。このときに、私たちはもっとも充実している状況を味わうことができるように思います。
『文字逍遥』に収録されている白川静さんの「遊字論」では冒頭に「遊ぶものは神である。神のみが、遊ぶことができた。遊は絶対の自由と、ゆたかな創造の世界である。それは神の世界に外ならない」の書き出しで始まります。遊ぶこととは、世界を創ることであって、それはまるで神の所業のように世界にコミットすることです。「世界を創る」ことについては、後の章で詳しく話していきましょう。
▼知の編集工学義疏
第1章 <編集の入口>をダイジェストする
第2章 <脳という編集装置>を加速させる ーComing soon
第3章 <情報社会と編集技術>のキーワード ーComing soon
第4章 <編集の冒険>のための補助線 ーComing soon
第5章 <複雑な時代を編集する>方法がある ーComing soon
第6章 <方法の将来>に向かうために ーComing soon
吉村堅樹
僧侶で神父。塾講師でスナックホスト。ガードマンで映画助監督。介護ヘルパーでゲームデバッガー。節操ない転職の果て辿り着いた編集学校。揺らぐことないイシス愛が買われて、2012年から林頭に。
【オツ千ライブ!2/3 21時配信】記憶の迷宮イメージメント
千夜千冊絶筆篇 1859夜 田中純『アビ・ヴァールブルク』をオツ千ライブでおっかけ! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。1859夜 田中純『アビ・ヴァールブル […]
【オツ千ライブ!】「孟子と王子のキズナ伝説」1/29 17時配信!
千夜千冊のダブルヘッダー二夜を合わせて、1月29日17時から、おっかけLIVE開催! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。1478夜『ソーシャル・キャピタルの潜 […]
【オツ千ライブ!】才能を喧嘩で展く術 12/19 21時より配信!
千夜千冊のダブルヘッダー二夜を合わせて、12月19日21時から、おっかけLIVE開催! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。絶筆篇 1857夜 大友啓史『クリエ […]
【オツ千ライブ!】12/2 21時よりWヘッダー アーリア神話&贈与論をおっかけ!
千夜千冊のダブルヘッダー二夜を合わせて、12月2日21時から、おっかけLIVE開催! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。1422夜 レオン・ポリアコフ『アーリ […]
【オツ千ライブ!】10/24 22時よりルネ・ジラール&ケアンズ・スミス&ニック・ランドを三夜おっかけ!
千夜千冊をおっかけつづけて4年初めての二夜をおっかけLIVE開催から一ヶ月、次は3夜を一気におっかけます! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。492夜 ルネ・ […]







コメント
1~3件/3件
2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。
2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。