鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。




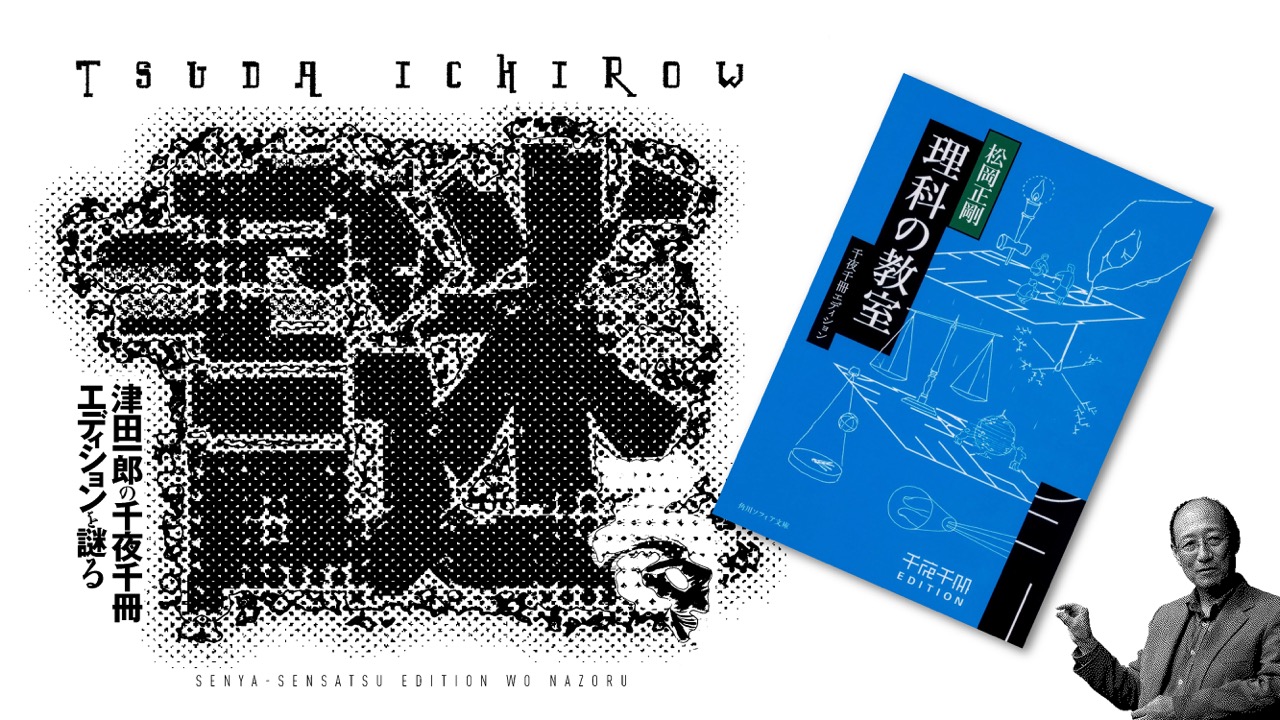
ポアンカレのカオス
松岡さんはアンリ・ポアンカレ『科学と方法』に対しても簡潔で的を射た手入れを行った(第18夜、『理科の教室』pp.38-46)。いよいよ来た、ポアンカレである。かのアインシュタインもポアンカレの『科学と仮説』を友人から誕生日プレゼントに貰い歓喜した、あのポアンカレである。我々カオスを研究する数学者、物理学者にとってポアンカレはカオスの母と呼ぶにふさわしい学者である。本当の生みの親だ。1899年出版の『天体力学の新しい方法』で天体の3体問題の解の中に非常に複雑で超越的な振る舞いをするものが存在することを一般に公表した(証明は1890年発表の論文誌に最初に載った)。この解をポアンカレは二重漸近解と呼んだ。これが今日カオスと呼ばれているものと等価な運動を表現する。決定論的方程式から得られる予測不能で非決定的な解の学問的な最初の発見である。この発見には実は紆余曲折があった。
もともと天体力学において2体問題はケプラー問題といって、ヨハネス・ケプラーが天体観測から発見したものだ。この2体問題においては、楕円運動、双曲線運動、放物線運動の三種類しかないことがニュートンによって厳密に証明されていた。もう1体加えた3体問題は難問であり、満足のいく解答が得られていなかった。スウェーデン王兼ノルウェー王だったオスカー2世の還暦を1889年に祝うために、その4年前の1885年に天体力学の3体問題が懸賞金付きの問題として提案された。制限付きではあるがこの問題を解いたのがアンリ・ポアンカレである。1889年にいったん解答を出したが、受賞後に証明が不完全であることに気づいたポアンカレは約束されていた一年後の出版までに何とか証明を完成させた。ポアンカレは最初カオスのような非周期解が存在しないと仮定して問題を解いていたのだが、その仮定を外して証明を完成させたのだった。この時発見したのが二重漸近解で、これが今日のカオス研究の端緒となった。論文発表は1890年である。後に書かれた『天体力学の新しい方法』の第3巻(1899年出版)によって、数学者以外の研究者にも二重漸近解=カオス解の存在は知られるようになったのである。
三体問題のシミュレーション。上図は初期値が横軸一直線に三惑星が並んでいるのに対して、下図は緑惑星の初期値だけが左下方に少しだけずれている。オスカー2世の懸賞金問題は、最初の位置関係=初期値がほんの少しずれただけでこれだけ結果が変わってしまうような現象に、はたして法則性などあるのかという問いかけでもあったのだ。
出典:JavaLab
三体問題は特殊な解を与えると図のような軌跡を示す。ポアンカレによって周期解は理論的に無限に存在することが証明されており、これまでオイラー、ラグランジュ、ポアンカレなど名だたる数学者たちが特殊解を発見し続けてきた。具体的な解は現在一万以上発見されている。
ポアンカレの謎
松岡さんは、ポアンカレに「数学の快感」を見た。そして、ポアンカレとバートランド・ラッセルのある逸話を紹介している。ラッセルはポアンカレを当時フランスで一番偉大な人物として評価していたということにまつわる話である。このことを私は知らなかったが、『科学と方法』を読むとなるほどと思うところがある。ポアンカレの方がラッセルの数学、数理論理学を非常に高く評価していたのだ。特に『科学と方法』(岩波文庫、1953年改訂版の1973年7月10日第23刷)207ページに「ツェルメロの公理の意義を見事にラッセル氏が解説した」とある。これは「選択公理」(Axiom of Choice)のことだ。ただし、そこにはその名はないので「選択公理」という名は後に付けられたようである。ポアンカレも書いているように当初は「ツェルメロの公理」と呼んでいたようだ。
選択公理をポアンカレに従って、簡単に説明しよう。それは「どんな集合の中からでも、あるいは集合の集合に属する各集合の中からでも(たとえ集合の集合が無限に多くの集合から成っていても)、その集合の代表になるような各々一つの要素を選び出すことができて、その要素の集合を作ることができる」と表現される。この公理の意義は分かりづらいが、ラッセルはそれを見事に説明した。それをポアンカレが紹介している。自然数の数と同じだけの靴のペアーがあって、そのペアーに1から無限大までの番号をつけることができるとする。この時、靴の数はいくつだろうか?ペアーの数と靴の数は同じだろうか?各ペアーにおいて、右足の靴と左足の靴を区別できるとしよう。この時、ペアーの番号nに対して、右靴を2n-1、左靴を2nと対応付ければ、ペアーの数と靴の数は同じだと結論付けることができる。では、右靴と左靴を区別できないとしたらどうか?この時、靴を数え上げるために選択公理が必要になる。右靴と左靴が区別できない場合でも、選択公理によって代表元が存在すると仮定してよいのだから安心してエイヤーと一つ靴を選び、これを右靴だと決めればよい。残ったのが左靴だ。そうすればペアーの数と靴の数は同じになる!
選択公理をこんなに鮮やかに説明したものを私は見たことがない。ポアンカレがラッセルを尊敬していたのがよく分かるのである。そうなればラッセルも悪い気はしまい。ポアンカレを褒めたたえたのである。私もポアンカレを褒めたたえているのだが、一つだけわからないことがある。ポアンカレの三部作を出版年の若いほうから順に書くと、『科学と仮説』(1902年)、『科学と価値』(1905年)、『科学と方法』(1908年)である。『科学と方法』はアインシュタインの特殊相対性理論が出た1905年より3年も後の出版である。当然、ポアンカレもアインシュタインの業績を知っていたはずだ。しかし、『科学と方法』で「相対性原理」について述べているところでは、ローレンツの研究には言及するもののアインシュタインには一切言及していない。むろん、(特殊)相対性理論はローレンツ変換が根底にあり、それによって物体の進行方向の長さや物体の固有時間にローレンツ収縮が起こることはすべてローレンツの仕事である。光速度だけが相対的ではないとしたところにアインシュタインの独創性があると私なんかは思っていたが、ポアンカレ自身が光速度は一定であるという仮説を立てていたことから、アインシュタインの評価を下げたのかもしれない。この辺りの事情は分からないが、今の感覚からすると何とも不思議なことである。
各靴箱から靴を一つ適当に選ぶことは当たり前に見えるが、数学ではここでいう靴が物理的にさわれない概念となるため「右の靴を選ぶ」というように手を伸ばして掴む操作を数学的に定義しなければならない。「その数学的集合(=靴箱の中の要素たち)における『右』とはなんだ?」がわからない場合、靴そのものの定義までできなくなってしまう。こうした構成主義的立場に対して選択公理は定義が不要であるとした。おかげで数々の数学的発展がもたらされてきた。
アブダクションと直観のポアンカレ
松岡さんはポアンカレの直観力を仮説を作る能力とみてポアンカレにアブダクションの原型を見た。そして、ポアンカレ自身の経験「突如として訪れる啓示」を通して、「数学的発見における精神活動の関与」としての「無意識下で継続する思索」に着目した。このポアンカレの「無意識下で継続する思索」をマイケル・ポランニーの「暗黙知」(1042夜、『編集力』pp.156-167)と対比させ、ポアンカレを暗黙知の数学の発見者だと言った。これは少し分かりにくいかもしれない。なぜなら、「暗黙知」という日本語訳は“暗黙の知識”という意味合いを想像させるからである。これではポアンカレの無意識の下で起こっている思考を表現しているとは言えまい。暗黙知のもともとの英語表現はtacit knowledgeも使われてはいるがそれよりもtacit knowingの方に重きがあると思われる。すると、日本語訳とはニュアンスが違ってくるのではないだろうか。Tacit knowingなら、むしろ“(意識には出てこないのでまだ知らないのだが)すでに知っているかのようである状態を作り出す何らかの作用”というニュアンスになるのではないか?そうならば、ポアンカレと結びつく。「暗黙知」という日本語から想像されるこの言葉の意味合いではポアンカレとは結びつかないのである。松岡さんは当然「暗黙知」はtacit knowingを含意していることを知っていたので、ポアンカレと結びつけることができたのであろう。
私も何度か鮮やかな天啓を経験しているし多くの人が経験することだと思うが、意識を集中させてある問題を考えていてどうしてもわからないときは、無関係の事をやったり、リラックスしたり、遊んだりしているうちにふっと何かが下りてきて解決のアイデアが訪れることがある。特に、天啓が訪れるときに何らかの身体的な動きが伴っていることは興味深い。緊張と緩和のバランスが身体動作と結びつくところに天啓が訪れるのだ。この緩和の時に無意識下での思索が継続する。私は『心はすべて数学である』(文藝春秋、2015年;文春学芸ライブラリー、2023年)で、数学とは心(すなわち精神)だと言った。数学という学問は人間の心の動きそのものだと言った。この考え方の先駆者はポアンカレだったのだ。私はポアンカレを大学生の時に読んで、大方の中身を忘れていたが、松岡さんのエディションを見て、再読することでこの認識を得た。もしかしたら、私の無意識下でポアンカレが思索し私にあの本を書かせたのかもしれないとさえ思ったのである。これもtacit knowingである。
アブダクションを謎る
せっかくなので、「アブダクション」についてもすこしだけコメントしておこう。アブダクションは編集工学の骨子でもあるので、『編集力』を謎るときにじっくり論じることにしたい。ここでは、論理学の中での演繹論理、帰納論理、仮説論理の構造を述べる。仮説論理を使う推論がいわゆるパースの言うところのアブダクションと関係する。演繹論理は前提Aに対して推論規則「AならばB」であるならばBが得られるという論理である。すなわち(Aかつ(AならばB))ならばBである。”かつ”、“ならば”をそれぞれ記号、⋀と→で表すことにする。それぞれの命題の真理値を二値として(したがって、二値論理とも古典論理ともいう)、真ならば1,偽ならば0を各命題に割り振ると表(1)のような真理値表が得られる。注意しなくてはならないのは、このような古典論理では偽の命題からは何でも導くことができて、結果の真偽を問わず導出自体は真になるという点である。ここが一般の人には特にわかりにくいところだろう。「前提が嘘なら何でも言える」ということ自体は正しい、すなわち真である、と考えれば納得していただけるだろうか。もし納得できない人がいたら次のように考えたらどうだろうか。「AならばB」は「AじゃないかBであるかのどちらか」と等価である。もしAが真ならば「Aじゃない」ではないのでBが真である。他方、「Aが真じゃない」ならBの真偽に関係なく上の命題は成り立つ。重要なことは、演繹論理では前提Aが真でも偽でも常に論理自体は真であるということだ。これをトートロジーという。次に帰納論理は、結論Bと推論規則「AならばB」から前提Aを導く論理である。すると、表(2)のようになり、トートロジーではない。偽の前提を真なる結論から正しく導いてしまう可能性があるからである。この時、推論規則「AならばB」自体はAが偽でも正しいことを思い出そう。仮説論理は前提Aと結論Bから推論規則「AならばB」を導く論理である。この真理値表を表(3)に書いた。明らかに仮説論理はトートロジーである。
ここで、多くの人たちが混乱する。アブダクションが仮説を生成する機能を持つ以上、アブダクションは必ずしも正しいとは限らない。これと仮説論理がトートロジーであるということとどう関係するのかという問題である。この問題は、慎重に細心の注意を払って議論しないと誤解が生じやすい問題である。これは『編集力』を謎るときに説明したい。
演繹、帰納、アブダクションに関する真理値表。論理学においては、仮説もまた論理の一形態なのである。(著者作図)
図版構成:梅澤光由
津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る
⑤『理科の教室』で思索の庭を謎る
津田一郎
理学博士。カオス研究、複雑系研究、脳のダイナミクスの研究を行う。Noise-induced orderやカオス遍歴の発見と数理解析などで注目される。また、脳の解釈学の提案、非平衡神経回路における動的連想記憶の発見と解析、海馬におけるエピソード記憶形成のカントールコーディング仮説の提案と実証、サルの推論実験、コミュニケーションの脳理論、脳の機能分化を解明するための拘束条件付き自己組織化理論と数理モデルの提案など。2023年、松岡正剛との共著『初めて語られた科学と生命と言語の秘密 』(文春新書)を出版。2024年からISIS co-missionに就任。
津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑨ 『編集力』で負を謎る
アフォーダンスと環世界 アフォーダンスは編集工学の3Aの一つだ。環境が生物に与える行動的意味や価値のことだ。アフォーダンスは知覚者の状態には依存しない。ギブソンの本来の考えとして、アフォーダンスは生物と環境の間にある行為 […]
津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑧ 『編集力』で真似るを謎る
富田のLIFEとエディトリアル 松岡さんは、折に触れ「オリジナリティー」よりも「真似る」ことの重要性を強調してきた。『編集力』でもこのことを強調する箇所が多々ある。そもそも「アナロジー」や「ルイジとソージ」、「擬き」など […]
津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑦ 『編集力』で言語の境界を謎る
生成系AI(LLM) v.s. チョムスキー 今や多くの人が生成系AI(以下、AIと略す)を使って何らかの仕事をする時代になった。編集にも、論文校正にも、ちょっとした疑問点にも、研究にも参考になる視点を与えてくれる。人に […]
津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑥ 『編集力』でアブダクションを謎る
推論=心? 『編集力』には編集工学の技法がいっぱい詰まっている。この450ページを超えるエディションを読み込めば、松岡さんの思想と技法が会得できるのではないか。だとすると、これは恐ろしいエディションである。謎ることすら気 […]
イシス編集学校アドバイザリーボード ISIS co-missionメンバーより、これから「編集」を学びたいと思っている方へ、ショートメッセージが届きました。なぜ今、編集なのか、イシス編集学校とはなんなのか。イシスチャンネ […]






コメント
1~3件/3件
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。
2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥
LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。