誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)




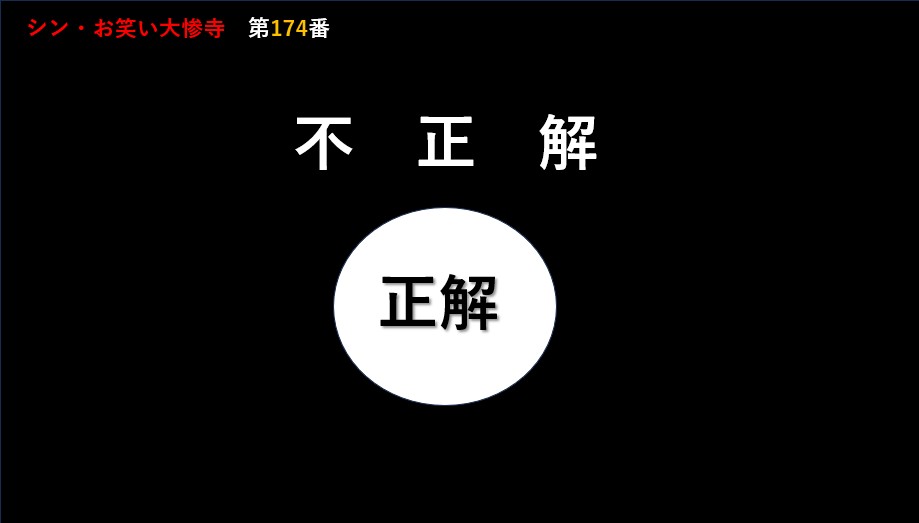
与えられる問いから作りだす問いへ。
昨年『問いの編集力』(安藤昭子・著)が発売されたことは記憶に新しいが、問い(お題)をどう作るかということは、イシスでも世の中でも大きな関心を持たれているトピックのひとつである。AI全盛時代、人が人であるための最後の砦が「問い」なのかもしれない。
それでいうとお笑い大惨寺には、「お題制作の方法」を考えるためのヒントがいくつも転がっている。寺で起きている祭りの別名は、「足掛三年隠遁廿年脳内欣快超一千日興行」(あしかけさんねんいんとんにねんのうないきんかいちょういっせんにちこうぎょう。一息でリズミカルに読み上げたい)。すなわち第1000番に至るまでこの進撃は止まらず、出題はほぼ毎日だ。そう、大惨寺境内には問いがあふれている。
これだけの量の問いを大入道2000がいかにして生産しているのか、その原理は未だ謎につつまれているが、ひとつひとつのお題の仕組みを方法的に紐解くことはできる。粋を重んじる場において散文的分析が野暮であることも承知しつつ、試みに、あるお題の内部構造をちょっと本気でリバースエンジニアリングしてみよう。
◆ クイズであってクイズでないもの
一般に「問い」というカテゴリーの中には、謎々・質問・疑問・設問・課題…など、それぞれ重なりつつも性質の異なる様々なQが含まれる。そんな中で今回注目したいのは、「クイズ」という問いのかたちである。
クイズ? 「答えがない問い」を探究してきたイシスにあって、クイズほど食い合わせの悪いものはない。問いと答えとが1対1の蜜月を成し、揺るがぬ絶対的正解がエラそうに待ち受けているクイズ世界の窮屈さにはもうウンザリ。そう思って、編集学校に入門した人も少なくないはずだ。
しかし、「イシスの川向う」を標榜する大惨寺のこと、一筋縄ではいかない。実はこのお寺では、すでにもう何度もクイズが出題されている。それも数問どころではなく、「なんとなクイズ」という人気シリーズまで存在し、「なんクイ」の愛称で親しまれている。
けれどもお笑い大惨寺が、ごくごく普通のクイズを出すはずもない。そこで展開されているのは、クイズでありながらクイズでない、キメラのごとき問いである。
某名探偵の口上をもじるまでもなく、「正解はただひとつ!」なのがクイズの特徴である。誰がやってもおんなじひとつの答えに収斂するクイズを、編集的な広がりをもつ「お題」へトランスフォームさせるには、一体どんな工夫が要るだろうか。
その秘策を教えてくれるのが、第174番である。
シンお笑い大惨寺足掛三年隠遁廿年脳内欣快超一千日興行第二部174番。本日は近代種目。
◆クイズです。3つの回答に「これぞ不正解」という回答をしなさい。
Q:徳川幕府で「暴れん坊将軍」といえば誰?
普通の不正解「 」
天才の不正解「 」
バカの不正解「 」
では、どーん。
正解ではなく不正解を答える問い! なるほど、「正解はただひとつ!」なら、「不正解はほぼ無限!」だ。そしてクイズの正解に個性は宿らないが、不正解には個性が宿る。後者に問いの矛先を向ければ、個々人の見方に応じた不正解(という解)を得られよう。間違いや誤りのうちにこそ人間の業(ごう)が滲みだすことに着目し、クイズという形式を逆手に取ったお題だ。論理学でいうところの「Aまたは非A」を応用した排中律的お題生成法でもある。
機械的だと思われてきた一問一答式のクイズ空間も、こうして「正解の孤島」の外に広がる「不正解の大海原」に目をやれば、たちまち人間味のあるオープンクエスチョンへ転じる。これはもちろん、「あるもの」よりも「ないもの」のほうが情報的には豊かだという、[守]で早々に学ぶ型の延長線上にあるだろう。
とはいえ、「正解でないもの」に制約がないわけではない。このお題の難しさは、単に回答者が思いつきで不正解を繰り出せばいいのではなく、「他人がいかにもやりそうな不正解」を想定しなければならない点にある。大前提として「不正解らしさ」の略図的イメージを頭の中に描かなければならず、しかもこれが「普通」と「天才」と「バカ」という3つのレイヤーで要求されているのだから、なんとも非常に悩ましい。
とくに「天才の不正解」というのは、いったい何なのだろうか。天才がしそうなうっかりミス? それとも、天才的な外し方をしたバカボンばりのズッコケ解答のこと? いやむしろ、不正解であってもなお、知性の輝きを感じてしまうブリリアントな間違え方のことか?
かくして「天才の」という形容が、われわれを多義的解釈の深淵に引きずり込む。「丸い三角」や「やわらかいダイヤモンド」とも比肩しうるアンビヴァレンツの只中で、大惨寺民は煩悶せずにはいられない。(実際どんな回答が寄せられたかは、境内へ行ってご覧あれ。なお、つづく第175番でも「Q.雷が光るのは誰のせい?」というクイズの「不正解」が問われている。)
人間の人間臭さを「間違え方」のうちに見いだしたお笑い大惨寺。「だめになってもためにならない」がモットーのお寺だが、このようによく目を凝らせば「ためになってしまう」方法もそこかしこに落ちている。それでは逆に、ためになったらだめになるのか、ためになってもだめにならぬのか……。真相は出武将の腹の中。これぞ面妖なる川向うのアンビヴァレンツだ。
文・アイキャッチ:白馬ッ苦連(バニー)
シン・お笑い大惨寺 遊夕番遊夕番
編集的先達:一休宗純、川上音二郎、椿三十郎、四方赤良。イシスと社会の狭間に生まれし「シン・お笑い大惨寺」。この河原から毎夕声を発するは人呼んで「遊夕番」。時には抜き身の刀のごとくギラギラと、時にはヌメヌメ艶っぽく、この世もわが身も笑い飛ばす。髑髏を蹴飛ばしオッペケペぇ、雨降らば降れ風吹かば吹け。
どこの誰かは知らないけれど、イシスの誰もが知っている。みんなにお馴染み、千日興行中の大惨寺は、にゃんと折り返しを迎えました。不定期連載【タダ漏れ大惨寺】にて、500番のお題と回答を、無限にダダ漏れ/無料でタダ漏れしちゃい […]
どこの誰かは知らないけれど、イシスの誰もが知っている。月光仮面さながらに、みんなにお馴染み大惨寺は、ついに400番を迎えました。千日興行の足跡は川向うに村を成し、折々の祭りも経ながら着実に成長しています。 […]
大惨寺新章 -口伝の世紀へ-【第三回焼きそば会*焼きそば比丘尼ック】
活字に行間あり。セリフに間合いあり。シン・お笑い大惨寺はエディットカフェを飛び出し、新たな間の創造に向けて船出した。 2月大寒波の連休最終日、この世から消えゆく「B面の権化」大惨寺のトンチキ集団による焼きそば会が本楼で敢 […]
世の中から「B面」が消え失せつつある。 A面・B面という言葉のもととなったレコードやカセットが廃れたからということもあるだろうが、それだけが理由ではない。 「B面」という語 […]
20分の8である。打率にすれば大谷翔平も口をあんぐりの4割バッターだ。 何が打率4割か。 明日28日いよいよ幕を開ける54期めの[守]講座。その教室をあずかる20名の師範代のうち、なんと8名がお笑い大惨寺出身なのである。 […]










コメント
1~3件/3件
2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。