私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。




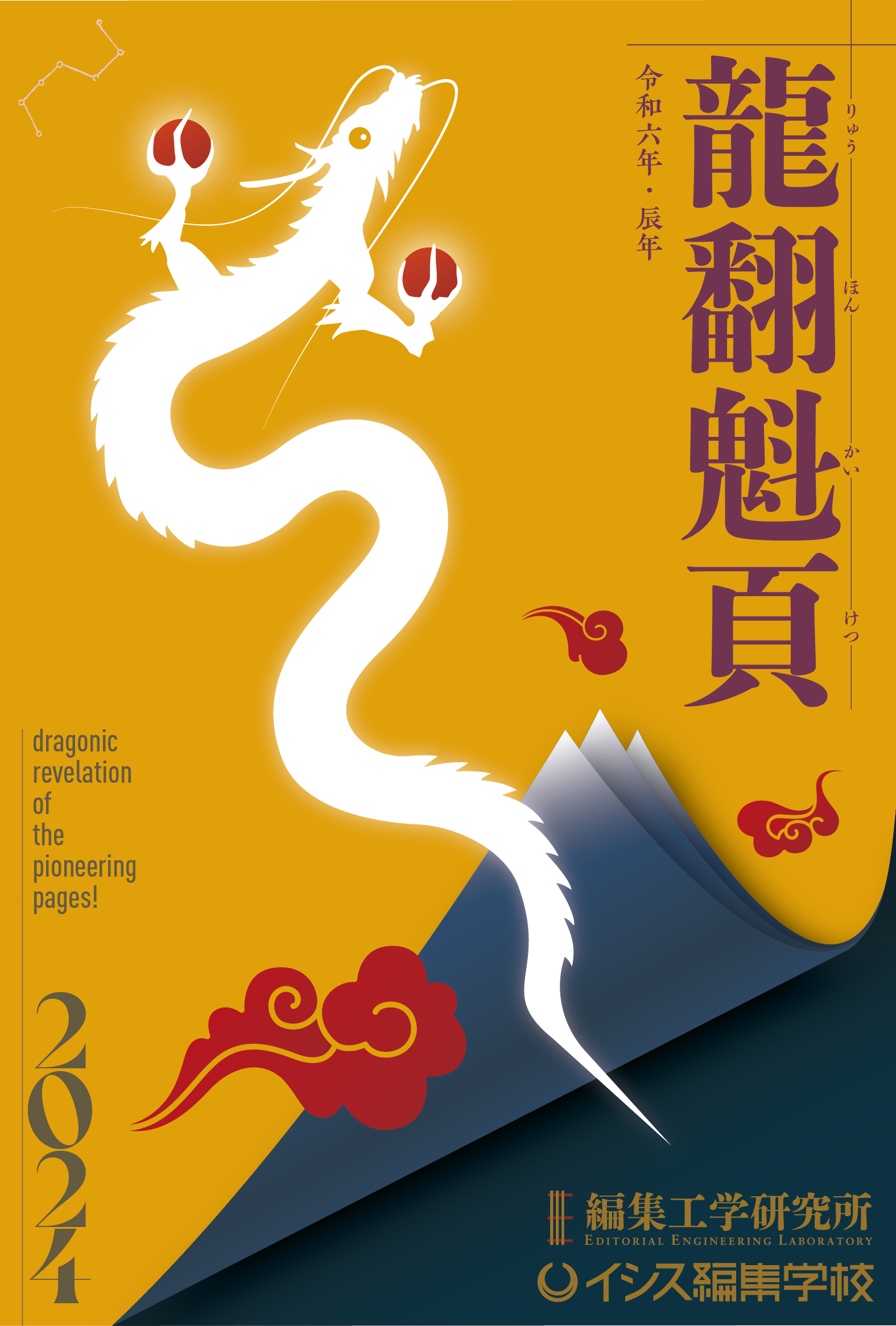
遊刊エディストの新春放談2024、其の参をお届けします。3日目は2023年年末からはじまった大企画の立役者、レジェンドなこの方をゲストにお迎えしました。
◎遊刊エディスト編集部◎
吉村堅樹 林頭, 金宗代 代将, 川野貴志 師範, 後藤由加里 師範, 梅澤奈央 師範、上杉公志 師範代,穂積晴明 方源, 松原朋子 師範代,
◎ゲスト◎
放送研究家、ラジオディレクター、落語ディレクター
川崎隆章 師範代(第2期)
吉村 さて、次のゲストは、2023年のクリスマスからシン企画を起こして下ったこの方、デーブ川崎こと、川崎隆章さんです。
川崎 どうもどうも。お笑いシン大惨寺、はじまりましたよ!クリスマスに始まったのに名前は“寺”です(笑)
クリスマスの朝から大興行「シン・お笑い大惨寺」
吉村 盛り上げてくださって、ありがとうございます。ぜひイシス編集学校歴から、ご紹介していきたいのですが。
川崎 私は2期の師範代からスタートしています。
川崎隆章を知るなら、この3本!!!
ISIS 20周年師範代リレー[第2期 川崎隆章 一字一句うちこんだお題]
ヘビー級エディスト川崎隆章、長崎の人気ラジオ番組に旋風!
「炭男」を言祝ぐ【九天玄氣組年賀2022】
吉村 最初から師範代をされた、つまり学衆経験がないということで、最近、はじめて[守]を学衆として受講されたわけです。51[守]で、でしたね。川崎さんはイシス編集学校が始まる前から松岡校長とは一緒にされてきたのですよね。
川崎 ISIS編集の国プロジェクトから関わっていたんですよ、99年の松岡校長のお誕生日前後だったと思います。「編集の国ISIS」というフレーズに決まる前は、「ミームの国」という仮の名前がついていました。そのときに、古典芸能や大衆演芸に詳しい人はいないかといって一緒に関わるようになりました。当時、編工研は青葉台にあって、そこに行ってたんですよ。
ウメ子 お題づくりに取り組まれていたのですか?
川崎 もともと落語や、寄席の大喜利でやる頓智問答が好きだったんです。それと、江戸雑排、江戸の言葉遊びに興味があってルールを集めていたので、たくさんお題を出して答えてもらうという、お題が出題されること自体がコンテンツだという企画を具現化したのが、「お笑い大惨寺」と呼ばれる企画でした。質問が最高のコンテンツだというところからスタートしたわけですね。
上杉 編集学校自体が、問いから始まる学校ですからね。
川崎 90年代の終わりにいわゆるネット大喜利がはやった時期があって、毎日お題にむらがって答えを出すというサービスがありました。当時は掲示板を使っての企画でしたが、その形式をもうちょっと洗練させようかということで、初代ISISの企画の中でやりました。
上杉 まだインターネットなんて、まだ広がってないですよね。
川崎 インターネットはかなり普及しはじめていたんですが、今のようにアプリケーションをダウンロードするのが難しかったので、郵便で(笑)CD-ROMを送って、それを読み込むと画面が出てきて、クリックするとお題がある、というしくみにしました。答えが蓄積されて、師範が週に1回指南をするというサービスだったんです。その後、師弟関係のコミュニケーションを重視しようという方向になって、今のスタイルができあがっていきました。
吉村 [破]の飛び道具は、川崎さんがつくられたと聞いています。
川崎 そう、もともと私が本にしようと思っていたものを書き直したものが、プランニングのお題として最後まで候補に残っていたものなんです。採用されたのは編工研で以前から使われていた方法“よもがせわほり” だったのですが、私が組み立てていた方法は飛び道具にしておこう、となりました。
後藤 川崎さんが2期で師範代をされていたときは、今とは全然違いますよね。
川崎 そうですね、そうですね、ちょうど世紀跨ぎの年だったんですが、あの頃は世の中に編集学校的なものがなかったので、集まってくる生徒さんは、当時はまだ生徒と呼んでいましたが、自分が方法を持っている人たちがやってきたんです。何かの分野の師弟関係では自分が「師」にあたる人たちで、それが生徒として参加したものだから、師範代が運営をしていくと、生徒さんとの綱の引き合いになるんですよ。それが強く出た教室もあって、教室ごとに言い合いが多かったですよ(笑)
マツコ 2期の後はどうされたのですか?
川崎 5期の師範をやって、あいだがあいて、本座で戻ってきました。「お笑い大惨寺」は、編集の国プロジェクトがいったん暖簾をおろした後、江戸雑排専門のコミュニティとして再スタートして、その後、柳家小ゑん師匠を正式に宗匠として迎え、ISIS本座で「雑俳たわむ連」として復活させたんですよ。本座が幕を閉じるまでやっていました。
吉村 まだまだあります、川崎さんと言えば、ラジオ番組もされている。
川崎 最初に聞きはじめたのは5、6歳のころ。70年代以降のさまざまなラジオブームをすべてくぐってきて、95年にラジオ番組の制作者になりました。今は演芸番組が専門ですが、最初はリスナー参加型の双方向番組が専門で、リスナーとの駆け引きで番組をつくっていくことを体験しました。まさにライブ編集の醍醐味を感じています。中村まさとしさんともよく話すんですが、放送業界には、番組作りが好きな人と放送そのものが好きな人がいる。私自体は、放送というシステム全体が好きなんです。さらに言えば、社会システムの中の放送の在り方に関心があって、まさに双方向型の放送がいちばんおもしろいなと思っています。
ウメ子 今ではラジオよりインターネット・メディアが優勢ですが、どのようにご覧になっていますか。
川崎 双方向型の企画について言えば、放送・出版・イベント・ネットのどれも、モデレーターの力量が問われます。たとえば、参加者がワッと話を持ち込めるようなハードルの低さは大事ですが、モデレーターが「こちらの話題で盛り上がりませんか」と舵を切ると、展開がおもしろくなっていきます。しかし、舵取りが強すぎると参加者が減ってゆきます。話題ナンでもありにして、手放しでバラバラにすると、エントロピーの増大で内容がつまらなくなってゆきます。つまり、参加者を増やすことと、内容を詰めていくことを繰り返して、場に呼吸をさせる、そのリズムと塩梅が大事で、ラジオでもインターネットでもこれが一番大事だと思います。
金 なるほど、やはりツールの問題ではなくて、人の問題ですね。ある意味、師範代もそうですよね。
川崎 そうですね、類似していると思います。私の「直立猿人教室」はラジオの深夜放送みたいな教室だったと思いますよ。教室と勧学会(かんがくえ)に寄せられた発言数が同じぐらいだったということで、めずらしい教室でした。
吉村 師範代をやってから20年以上たち、学衆として初受講されて、そして、満を持して、「お笑い大惨寺」の再開ですね?
川崎 あの頃はまだ時代が早かったと思っていますね。あれからずいぶんお題投稿の世界も変わってきて、若い人たちがひねった答えを出すことをやるようになっています。編集学校にこれだけの人が集まって、その人たちは Edit cafe の ID をもっているわけですから、それはその人たちがふらっときて遊べるお祭り「大惨寺」をやろうという提案を考えました。
吉村 イシスから新たな企画が生まれてくるのはうれしいですね。今回の「お笑いシン・大惨寺」は、誰でもはいることができるのでしょうか。
川崎 誰でも、もちろん。開かれた状態をつくるために、どんな答えでもうけとめることを重視しようと思っていますよ。出題しながら、競い合うのが好きな人、いろんなタイプの人がそれぞれに楽しめるようにしたい。予定では1から1000本までお題を出す予定。
金 1000本ってスゴイですね。
川崎 でしょう。1000本まで答えた人には千日行ではないが、特別なものを提供したいと思っています。1000問を回答した方は、本楼の中にやしろをつくってまつってもいいと思っています、だってですよ、1000本の問いを打ち返すのは、それだけでも頭と根性にパワーがある。そういう人が ISIS のコミュニティにでてきたら、そこに光を当てて、むちゃくちゃな人を掘り出すきかっけにもできたらいいなと。もちろん、1日からでも楽しんでもらえたらと思っていますよ。
吉村 Edit cafe で開催ですね。
川崎 ええ。Edit cafe を使える人は、左側のラウンジメニューから「シン★お笑い大惨寺」というラウンジ名を探してください。メール配信はしてませんが、毎日覗いてお題を確認してくださいな。
それと同時に、Edit cafe に帰ってきていない人はFacebook にサテライト・コミュニティをつくって、お帰りなさいな人たちを呼び寄せるぞという計画ですね。
後藤 Edit cafe のラウンジは、23/12/31 23:48に2023年の回答が送られていて、ラウンジへの発言数(投稿数)は、すでに 817回答にも及んでいます。
金 それがまとまったものがEdistで記事になっていったりするといいですね。放送研究家、ラジオディレクター、落語ディレクターと様々な顔を持つ川崎さんだけに、ラジオ番組化していったり?
川崎 ネタが集まってくるとそれでラジオ番組が作れるんですよ。がんがんつくらせてもらおうと思っています。
川崎 集まった回答をもとに、それらをコントにしよう、物語にしよう、音楽にしよう、という展開があって、創作物が出てくるといいなと思っています。
後藤 これは、あらたな二次編集を期待したいですね。
川崎 落語が、もともとは5行の小話からできたということがあります。どんな大きな物語も、もとは数行のものだったりする。なので、大惨寺をインスピレーションにして色々なものをうみだしてほしいですね。それはモデレーターの役割かなと思います。
上杉 川崎さんがアイディアの宝庫に見えてきました(笑) もうちょっと聞いてみちゃいますが、温めている企画がありますか?
川崎 バーチャル・キャラクターをつくってもいいかな。それから、ISISの暦をつくるっていうのはどうですか? 1年間のスケジュールを立てると、毎日何かの記念日になると思いませんか。たとえば、校長の誕生日。千夜千冊を使って記念日をつくることもできる。二十四節季なんかとからめていくと、1年間の暦ができるんじゃないかな。
吉村 暦はいいですね、新しい生活のスタイルができてきますから。村祭りに参加するのは面倒だけど、暦でそう書いてあるので、しょうがないから腰を上げよう、となる。それでやってみると、意外に楽しかったねとなるのが祭りのよさで、そうしてつながってきた文化もあります。道具立てをしていろいろつくって、そうすると様々なノウハウが生まれていきます。この方法でこれができました、というお土産品ができてくる。大惨寺の暦を回していくことで、それこそ“ISISお土産の国”ができてもいいなと思いますね。
川崎 年末には、角山さんがカウントダウンの記事をエディストに連載してくださったのですよ。なんだかエディストを台風の目の中に巻き込んじゃったかもしれませんが、カテゴリーとしてはDUSTでもいいので、大惨寺ラウンジの動きを見て、エディストに記事をつくってくれたらありがたいですね。ぜひ、いじり倒して下さい。地方支部がうまく利用してくれても面白いし、競い合いがあっても面白いと思っています。
ウメ子 小さいところから大きいところに向かう壮大な構想が楽しみです。
川崎 後から参加した人もそれはそれでいい。1年遅れで、参加してもいい。蓄積型なので、答えてきてくれた方を、時期に関係なくもてなす、というように。みんなに喜んでもらおうという一心ですね。
吉村 たくさんの人たちに参加していただけますように!川崎さん、新春放談、ありがとうございました。
「シン・お笑い大惨寺」への参加方法
1)Edit cafe が使える方は、
左側のラウンジメニューから「シン★お笑い大惨寺」というラウンジ名を探してください。
メール配信はしてませんので、ご自身でログインして、毎日見に行っていただければ幸いです。
2)Edit cafe が使えない方は、
Facebook に「シン・お笑い大惨寺 分院」というグループがあります。
ここにまずはご参加いただき、楽しんでみてください。
※ゲスト三人目との放談は4日に公開。次回のキーワードは、”子供×編集”。
「其の肆」もお楽しみに!
————-
🎍2024年 新春放談🎍
其の壱 – 登り龍のごとく「E」が時代を翻す(1月1日 0時公開)
其の弐 – 方法の意識で良記事を次々と生み出すヒト (1月2日 公開)
其の参 – ISISな祭りを復活させるレジェンドなラジオ男(1月3日 公開)(現在の記事)
其の肆 – 町に、子どもに、大人に、編集の小さくて大きい種をまくヒト (1月4日 公開)
其の伍 (1月5日 公開予定)
————-
エディスト編集部
編集的先達:松岡正剛
「あいだのコミュニケーター」松原朋子、「進化するMr.オネスティ」上杉公志、「職人肌のレモンガール」梅澤奈央、「レディ・フォト&スーパーマネジャー」後藤由加里、「国語するイシスの至宝」川野貴志、「天性のメディアスター」金宗代副編集長、「諧謔と変節の必殺仕掛人」吉村堅樹編集長。エディスト編集部七人組の顔ぶれ。
イシス編集学校で予定されている毎月の活動をご案内する短信「イシスDO-SAY(ドウ-セイ)」。 梅雨があけた地域も出てきました、いよいよ日本列島に夏到来ですね!イシス編集学校でも熱い夏が始まります。7月のス […]
編集部が選ぶ2025年5月に公開した注目のイチオシ記事9選+α
公開されるエディスト記事は、毎月30本以上!エディスト編集部メンバー&ゲスト選者たちが厳選した、注目の”推しキジ” をお届けしています。見逃した方はぜひこちらの記事でキャッチアップを。 今回は、2025年5月に公開さ […]
田中優子の酒上夕書斎|第二夕『S/Z バルザック『サラジーヌ』の構造分析』ロラン・バルト(2025年6月24日)
学長 田中優子が一冊の本をナビゲートするYouTube LIVE番組「酒上夕書斎(さけのうえのゆうしょさい」。書物に囲まれた空間で、毎月月末火曜日の夕方に、大好きなワインを片手に自身の読書遍歴を交えながら語 […]
イシス編集学校のアドバイザリー・ボード「ISIS co-mission」(イシス・コミッション)に名を連ねる9名のコミッション・メンバーたちが、いつどこで何をするのか、編集的活動、耳寄りニュースなど、予定されている動静を […]
田中優子の酒上夕書斎|第一夕『普賢』石川淳(2025年5月27日)
学長 田中優子が一冊の本をナビゲートするYouTube LIVE番組「酒上夕書斎(さけのうえのゆうしょさい」。書物に囲まれた空間で、毎月月末火曜日の夕方に、大好きなワインを片手に自身の読書遍歴を交えながら語 […]













コメント
1~3件/3件
2025-07-03

私の28[花]キャンプは、吉阪隆正の建築思想【不連続統一体】の体験だった。場面ごとに異なる空間が次々と立ち現われてくる。よく分からないままに一周すると、ようやく建物を貫く原理のようなものが見えてくる。この「遅れて」やってくる全体性がたまらなかった。
2025-07-02

連想をひろげて、こちらのキャビアはどうだろう?その名も『フィンガーライム』という柑橘。別名『キャ
ビアライム』ともいう。詰まっているのは見立てだけじゃない。キャビアのようなさじょう(果肉のつぶつぶ)もだ。外皮を指でぐっと押すと、にょろにょろと面白いように出てくる。
山椒と見紛うほどの芳香に驚く。スパークリングに浮かべると、まるで宇宙に散った綺羅星のよう。
2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。