棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。




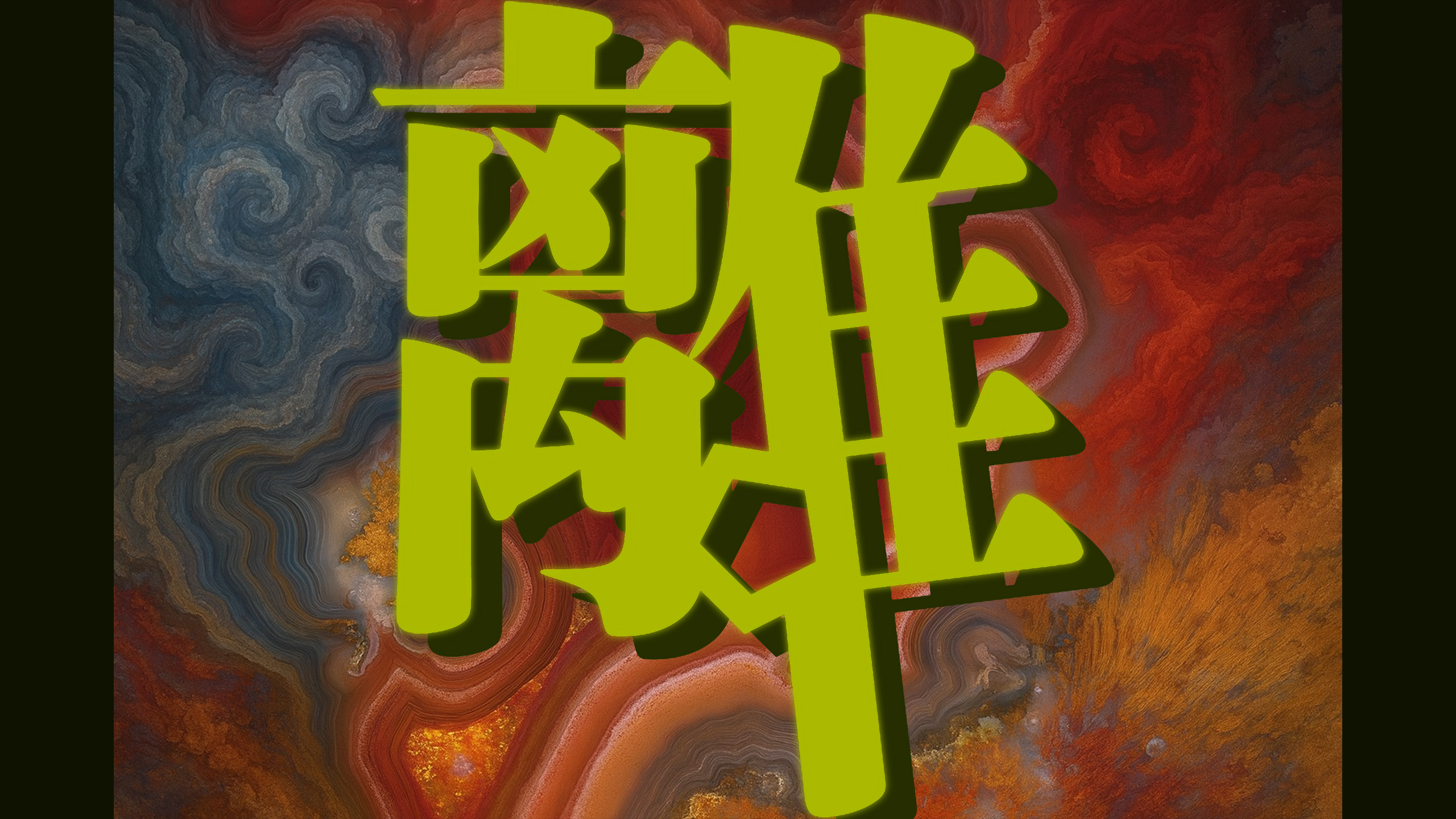
第十七季[離]で連離連行番(通称:連連番)を務めます梅澤です。連連番とは連離連行師(通称:連連衆)を束ねる者。連連衆とは学衆の回答を多角的に評価する目利きのプロフェッショナル集団です。しかし、[守]でも[破]でもたくさんの人が関わって、回答が出たり評価がなされたりしていますね。連連衆は離の仕組みとともにあるという点が他の講座と異なります。
[離]には松岡正剛校長が書き下ろした「文巻」という膨大なテキストがあります。お題の何倍もの量のベースとなる文章があり、これを読み回答を拵える。回答作成のため、一生かかっても歯がたたない難度の本を、七生かかっても読めないほどの冊数を探しにいくことにもなる。書く量だって圧倒的に増えてきます。
そうすると、自分の頭だけで考えている人は即座に行き詰まってしまうのですね。どこかから何某かを借りてこないといけない。教室の仲間から、歴史上の智者から、宇宙史・生命史における編集の名手たちから、なりふり構わず借りてくるのです。
だから[離]は[守][破]と違って人数が多い。一つの教室に十五人もの学衆と三人の指導陣がいます。個人で奮闘するお題もあれば、協働で編集するお題もある。人類史上のターニング・ポイントとなった協働編集について、その全貌を解き明かすために現代の私たちもまた協働編集を迫られる。ここまでくると、内容や概念だけでなく、過去から協働する方法まで借りてこなければならないわけです。
そんな祭り騒ぎの後、さらに方師や連連衆が加わって講評が行われます。評価の軸も多様になり、同じ回答をある人は絶賛し別の人は酷評することだってありえます。なぜそのようなばらつきが許されるのでしょうか。離学衆は「わたし」という器にありとあらゆる借り物をパンク寸前まで取り入れて回答にしていきます。そうして出てきた回答には、未だ名前すらついていない、見たことも聞いたこともない方法が宿っている可能性もある。その方法を評価する方法もまた、誰も見たことのない見方や言葉によって紡がれる。同じ回答に対する講評が千差万別に分かれてゆくのは当然なのです。
言葉にまでなりきれていない気持ちや、図解にまで落とし込められていないヴィジョンの中に、それでも爛々と輝く兆しが見つかるのは、連連衆の強烈に尖った好みを奮わせるなにかがそこにあるから。この兆す方法をなんとか励起させたいと思わせる何かが宿っているから。そんな回答から浮かんでくるあらまほしき姿をこそ講評とする。それが連連衆なのです。これは、原著者が書きたくとも書ききれなかった真意を言い当て、著者に成り代わって加筆してしまう千夜千冊の方法に倣っているのです。
これからの[離]はいっそう複雑化していきます。物質史と精神史を織り交ぜた文巻の上に、たくさんの離学衆と、多様な火元組や連連衆がざわめいていく。苛烈な稽古をともにした先に、「別様」という言葉の本当の意味を知る。そんな十七[離]の門が今開いています。光陰可惜、無常迅速、ただちに飛び込んできてください。
梅澤光由
編集的先達;高山宏。怒涛のマシンガン編集レクチャー、その速度と質量で他を圧倒。イシスの學魔と言われる。社会学研究者の卵とソムリエの二足の草鞋から、営業マンを経てITエンジニアに。趣味は火の動画(暖炉や焚き火など)を観続けること。
【近江ARS】高山宏<こころ>を語る ー 「還生の会」SEASON2 第1回報告
梅雨曇の中、狩野山楽が描いた松と滝を背に、學魔が来たりて高座にあがった。去る6/15、英文学者・高山宏を特別ゲストに迎え、近江ARS・還生の会は第二シーズンをスタートさせた。高山は三井寺・光浄院客殿一之間にて高速の独演 […]


コメント
1~3件/3件
2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。
2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。
2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。