タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。




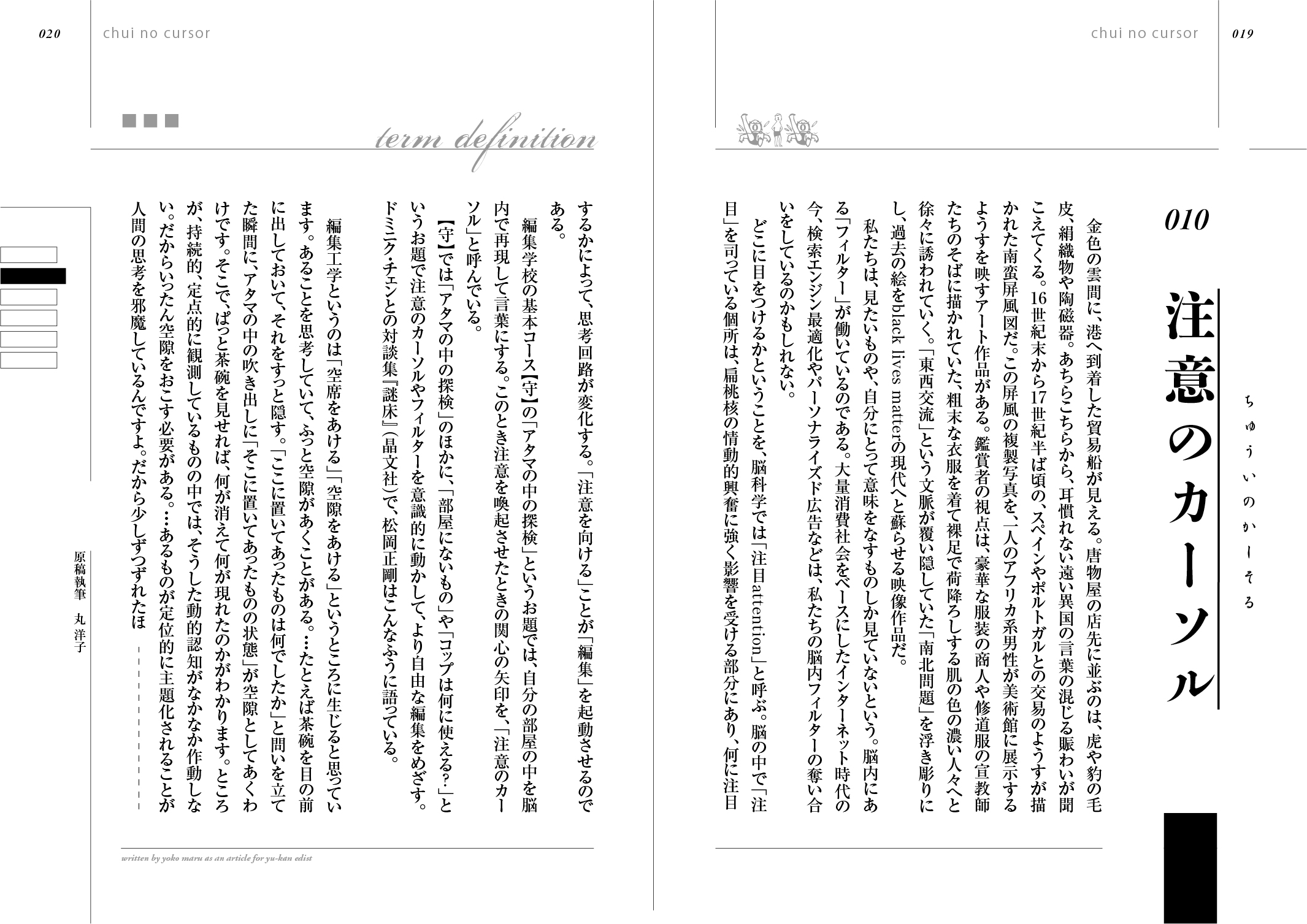
金色の雲間に、港へ到着した貿易船が見える。唐物屋の店先に並ぶのは、虎や豹の毛皮、絹織物や陶磁器。あちらこちらから、耳慣れない遠い異国の言葉の混じる賑わいが聞こえてくる。16世紀末から17世紀半ば頃の、スペインやポルトガルとの交易のようすが描かれた南蛮屏風図だ。この屏風の複製写真を、一人のアフリカ系男性が美術館に展示するようすを映すアート作品がある。鑑賞者の視点は、豪華な服装の商人や修道服の宣教師たちのそばに描かれていた、粗末な衣服を着て裸足で荷降ろしする肌の色の濃い人々へと徐々に誘われていく。「東西交流」という文脈が覆い隠していた「南北問題」を浮き彫りにし、過去の絵をblack lives matterの現代へと蘇らせる映像作品だ。
藤井光 『南蛮絵図』
https://www.hikarufujii.com/works/sothern-barbarian-screens/
私たちは、見たいものや、自分にとって意味をなすものしか見ていないという。脳内にある「フィルター」が働いているのである。大量消費社会をベースにしたインターネット時代の今、検索エンジン最適化やパーソナライズド広告などは、私たちの脳内フィルターの奪い合いをしているのかもしれない。
どこに目をつけるかということを、脳科学では「注目attention」と呼ぶ。脳の中で「注目」を司っている個所は、扁桃核の情動的興奮に強く影響を受ける部分にあり、何に注目するかによって、思考回路が変化する。「注意を向ける」ことが「編集」を起動させるのである。
編集学校の基本コース【守】の「アタマの中の探検」というお題では、自分の部屋の中を脳内で再現して言葉にする。このとき注意を喚起させたときの関心の矢印を、「注意のカーソル」と呼んでいる。
【守】では「アタマの中の探検」のほかに、「部屋にないもの」や「コップは何に使える?」というお題で注意のカーソルやフィルターを意識的に動かして、より自由な編集をめざす。ドミニク・チェンとの対談集『謎床』(晶文社)で、松岡正剛はこんなふうに語っている。
編集工学というのは「空席をあける」「空隙をあける」というところに生じると思っています。あることを思考していて、ふっと空隙があくことがある。・・・たとえば茶碗を目の前に出しておいて、それをすっと隠す。「ここに置いてあったものは何でしたか」と問いを立てた瞬間に、アタマの中の吹き出しに「そこに置いてあったものの状態」が空隙としてあくわけです。そこで、ぱっと茶碗を見せれば、何が消えて何が現れたのかがわかります。ところが、持続的、定点的に観測しているものの中では、そうした動的認知がなかなか作動しない。だからいったん空隙をおこす必要がある。・・・あるものが定位的に主題化されることが人間の思考を邪魔しているんですよ。だから少しずつずれたほうがいいんです。ずれた状態から再びそこに何かが入ってくることでアライメントが切りかわって、ぴったり同じのマッチング以上のもの、つまりコヒーレントなフィットが起こる。これは複合的オートポイエーシスです。
次にネーミングですね。「これ」が茶碗であるかどうか、そこから問い直したい。器かもしれないし物体かもしれない。商品かもしれず、母親の形見なのかもしれない。われわれはネーミングによって、あるものを定義づけているというより、固有して所有してしまっているのです。それを完全に解放するのはけっこう面倒くさい。たとえば、子どもならライターや灰皿を手に取って、その瞬間にライターは「電車」に、灰皿なら「空飛ぶ円盤」にすぱっと切りかえて世界に入っていける。
注意のカーソルやフィルターを意識的に動かせば、「主題」から視点が切り替わり、自由編集状態へと変化していく。これは、「見立て」という日本の方法にも重なる。定位的で固定的なものの見方をずらし、ものごとの別様の可能性を見出す見立ては、万葉の歌人らが好んだ寄物陳思――物に寄せて思いを陳べることでもある。
■見立てと寄物陳思
『謎床』で、松岡正剛は子どものことを「かなりの見立て派」だと述べ、注意のカーソルと見立てとの関係についても述べている。
見立ても、まずは「それを好きになる」「おもしろがる」「関心をもつ」というふうに重なっていくんです。そもそも寄物陳思は物(オブジェクト)に関心をもって注意のカーソルがそこへ向かうということに始まります。しかし、その「物」は辞書的に見えているだけではない。心や思いでも見ているので、「散りかけた桜」は「別れた人」に、「雨の屋根瓦」は「昔日の寺」にもなりえます。見立ては、この「何かにも見える」「何かにも思ゆる」ということを起点にして類感的に連鎖していくんですね。
たとえば庭石を亀に見立てることで、庭の光景全体の解釈系が起動するのだという。たった一つの石の様相が一瞬にして変貌し、想像力と記憶をかきたてながらイメージの渦に私たちを巻き込んでいく。「らしさ」を捉える方法である見立てについて、「分析対象としての情報体についての推論構造がずれていっても、そこにある本来の印象をずっと保持していくということです」とも語っている。対象に心を寄せ、関心を持ったり好きになったりして向かう注意のカーソルは、すでに名づけられ、編集された仮の世界の本来を直観し、奥行きを与え、創発や新たな文化を起こしていく鍵なのかもしれない。
■好みと共感
対象へ関心を寄せていく心の動きに伴う想像力と、類似の発見との間に、鮮やかな関係線を引いた一人の人物がいる。「美学」の体系を確立したカントに多大な影響を与えた18世紀のアイルランド人、エドマンド・バークだ。千夜千冊第1250夜エドマンド・バーク『崇高と美の観念の起源』には、本書を「美学の発端」であり、「感性学」の出発であると位置づけている。それまでの古典的な「美」の基準だった「均斉」や「調和」や「美徳」によらない、五感に基づく美学の道を切り拓いたのである。
バークは「『崇高』と『美』の起源を求めるうちに、類似のもつ普遍作用に気がついた」のだという。この一夜には、「新たなイメージは類似の発見から生まれる」という著者の画期的な主張が紹介されている。類似は想像力の本体であり、類似の発見から「模倣」が起こる。模倣は「共感」の拡張になっていき、ここから好みや趣味が生まれる。ではそもそも共感はどうやって生まれるのか。その端緒には「目新しさ」や「曖昧さ」が関与しているのだという。これらが注意のカーソルを起動させる。ここから感性が「美」や「崇高」に向かうというのだ。
「美」の本体は、「小ささ」や「僅かさ」から生じる。それが「繊細」に結びつく。「繊細」は対象物の構成部分が多様に変化することで保証されるのだという。このことを「細部に注意のカーソルが動く」と説明している。
いっぽう「崇高」の条件は、「曖昧」がもたらす不安な印象や、「欠如」や「闇のような力」や「恐怖」なのだという。そうした負が反転のダイナミズムを生むのである。好奇心や不安や恐怖を引き起こし、「注意」を生じさせる「目新しさ」や「曖昧さ」は、「異質」や「伏せ」、「空隙」、「不足」である。松岡正剛はこう述べている。
バークの美学は崇高と恐怖がネガポジであり、原型と模倣が「抜き型」で、そこには「小ささ」「僅か」「繊細」の回転扉が働いていたわけなのだ。そのきわどい相対性が感情の高揚をもたらし、「美」を感得させるということだったのだ。
類似や負を契機とした心の高揚――情動の興奮によって起動した五感の注意のカーソルが、アナロジーやアブダクションを生み出していくプロフィールが、見えてくる。
■注意のカーソルはいつでも動いている
『謎床』では、日常の一コマ一コマにも、アブダクティブな注意のカーソルが潜んでいることを、このように語っている。
「仮説をつくるって大変じゃないですか」と誰もが言うわけですが、そうではない。実際に私たちというのは、街を歩いていても本を読んでいても、恒常的にずうっとアブダクティブな編集状態になっているんです。駅に降りれば次に階段を探しているし、通りを渡るときは車や人の流れを感知している。本を読むときは次の展開を予想する。…だから、仮説的な状態をつくろうとしなくてもそれをうまく取り出すことができれば、仮説力は高まっていく。
『知の編集術』(講談社現代新書)には、注意のカーソルをどのような順でどこに動かしていけばよいかが、「編集十二段活用」のプロセスで記されている。
1.注意のカーソルを対象にむける。
2.注意の対象およびその周辺に少しずつ情報が読み込まれていく。
3.同義的連想が始まって、シソーラス性が豊かになっていく。
4.だんだん情報の地(情報分母)と図(情報分子)が分離できていく。
5.さらに階層化がおこり、情報の周辺をふくむ全体像が立体化してくる。
6.さまざまな情報がネットワーク化され、リンキングをおこす。
7.デフォールト(欠番構造)やスロット(空欄)が見え隠れする。
8.それがハイパーリンク状態になったところで、そこに筋道を読む。
9.筋道にあたるレパートリー(情報見本帳)を検索する。
10.カテゴリーが凝集し、ステレオタイプやプロトタイプが出入りする。
11.必要な情報のレリバンス(妥当性)を求める。
12.そのほかいろいろの編集(六十四編集技法)を加える。
「注意」を向けたところが「仮の親」(図)になり、子ラベル、孫ラベルが引きだされていく編集プロセスは、意味のふくみあいであるネットワークの中を行きつ戻りつ進んでいくのである。これが「考える」ということなのだと、『知の編集工学』(朝日文庫)には書かれている。
【守】で学ぶ「わける・あつめる」「つなぐ・かさねる」「しくむ・したてる」「きめる・つたえる」という4つの用法のあらゆる結節点で、注意のカーソルはつねに動き続け、多様な対象と交わり、複雑なものを複雑なままに捉えようとする。関係的発見をめざし、主題から方法へと向かう。そうやって「私」という主語を述語へと変容させ続けているのである。
参考文献:桑島秀樹著『崇高の美学』(講談社選書メチエ)
§編集用語辞典
10[注意のカーソル]
丸洋子
編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。
「この場所、けっこうわかりにくいかもしれない」と書かれた看板を手にした可愛らしい男の子のイラストが、展覧会場の入り口に置かれている。眉根を寄せて地図を見ているその男の子を通り過ぎ、中へ進むと「あなたをずっとまっていたのか […]
八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]
公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]
千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。 グノーシスとは「原理的 […]









コメント
1~3件/3件
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。
2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥
LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。
2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。