自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。




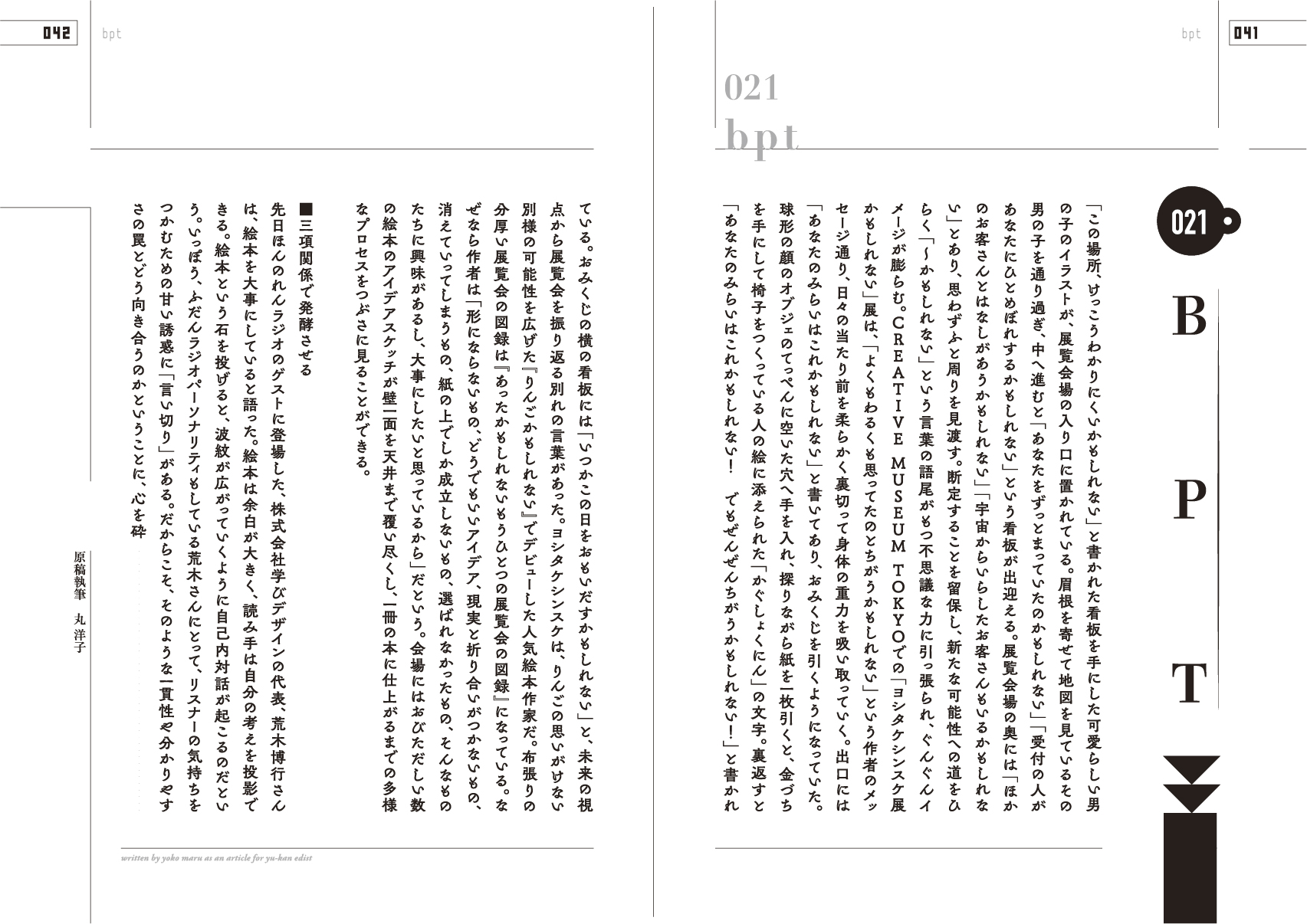
「この場所、けっこうわかりにくいかもしれない」と書かれた看板を手にした可愛らしい男の子のイラストが、展覧会場の入り口に置かれている。眉根を寄せて地図を見ているその男の子を通り過ぎ、中へ進むと「あなたをずっとまっていたのかもしれない」「受付の人があなたにひとめぼれするかもしれない」という看板が出迎える。展覧会場の奥には「ほかのお客さんとはなしがあうかもしれない」「宇宙からいらしたお客さんもいるかもしれない」とあり、思わずふと周りを見渡す。断定することを留保し、新たな可能性への道をひらく「~かもしれない」という言葉の語尾がもつ不思議な力に引っ張られ、ぐんぐんイメージが膨らむ。CREATIVE MUSEUM TOKYOでの「ヨシタケシンスケ展かもしれない」展は、「よくもわるくも思ってたのとちがうかもしれない」という作者のメッセージ通り、日々の当たり前を柔らかく裏切って身体の重力を吸い取っていく。出口には「あなたのみらいはこれかもしれない」と書いてあり、おみくじを引くようになっていた。球形の顔のオブジェのてっぺんに空いた穴へ手を入れ、探りながら紙を一枚引くと、金づちを手にして椅子をつくっている人の絵に添えられた「かぐしょくにん」の文字。裏返すと「あなたのみらいはこれかもしれない! でもぜんぜんちがうかもしれない!」と書かれている。おみくじの横の看板には「いつかこの日をおもいだすかもしれない」と、未来の視点から展覧会を振り返る別れの言葉があった。ヨシタケシンスケは、りんごの思いがけない別様の可能性を広げた『りんごかもしれない』でデビューした人気絵本作家だ。布張りの分厚い展覧会の図録は『あったかもしれないもうひとつの展覧会の図録』になっている。なぜなら作者は「形にならないもの、どうでもいいアイデア、現実と折り合いがつかないもの、消えていってしまうもの、紙の上でしか成立しないもの、選ばれなかったもの、そんなものたちに興味があるし、大事にしたいと思っているから」だという。会場にはおびただしい数の絵本のアイデアスケッチが壁一面を天井まで覆い尽くし、一冊の本に仕上がるまでの多様なプロセスをつぶさに見ることができる。
■三項関係で発酵させる
先日ほんのれんラジオのゲストに登場した、株式会社学びデザインの代表、荒木博行さんは、絵本を大事にしていると語った。絵本は余白が大きく、読み手は自分の考えを投影できる。絵本という石を投げると、波紋が広がっていくように自己内対話が起こるのだという。いっぽう、ふだんラジオパーソナリティもしている荒木さんにとって、リスナーの気持ちをつかむための甘い誘惑に「言い切り」がある。だからこそ、そのような一貫性や分かりやすさの罠とどう向き合うのかということに、心を砕いているのだという。多様性を削ぎ落した自分を打ち出すと、深まらない。ビジネスでは意思決定が必要だが、決定によって解消されなかった問いや、潰してしまった意見を残し、そうしたストックが発酵するプロセスを大切にしているという。
荒木さんの話を受けて、ほんのれんラジオのパーソナリティの一人、仁禮洋子は、Q→Eという編集工学の思考法に触れた。Q(問い)からA(答え)へ直線的に進むのではなく、Qから多様なE(edit)へと広げていき、決定したことは「仮置き」して、変わり得る可能性を残す方法だ。問いから答えへ直線運動をする「言い切り」ではなく、多様な「~かもしれない」可能性を残し、既知から未知へのプロセスを円運動のように発酵させていく豊饒な編集力を、イシス編集学校ではBPT(ベース・プロフィール・ターゲット)モデルで表す。出発点のベースから目標点のターゲットへと向かうあいだに潜んでいるプロフィール(すがた、ようす)というアナロジカルなプロセスを明示し、BTという二項を包摂したPを加える三項関係は、編集術の2+1モデルの一つと言えるかもしれない。[守]の講座では、このBPTの型を使って自在にイメージを扱う編集稽古をしながら、プロフィールの多様性や多義性を味わう。
■アナロジーで広げる
千夜千冊エディション『編集力』に納められている『類似と思考』(鈴木宏昭著)で、著者の松岡正剛は親友の「ソージ」(相似)と「ルイジ」(類似)との長年の付き合いを紹介している。
ぼくにはソージとルイジという親友がいる。ぼくより少し歳下だが、古い親友だ。ソージ君は人まねや物まねがうまくて、自己同一性に囚われていないところが気に入っていたし、ルイジ君は見立て話をさせるとめっぽうおもしろく、連想力に富んでいるところ、重ね着が似合うところが好きだった。そのうち編集力の推進にはソージとルイジが欠かせないと確信するようになっていた。
ソージ君は「似たものどうし」の視点で束ねた「相似率」として、雑誌『遊』の特別企画へと結実した。いっぽう、ルイジ君は「意識の変転や思考のプロセスに連接して躍動しているので、動的で連続的」で、「単体としてじっとしてくれない。連接的で包摂的で、また分岐的で拡散的で、つまりはいつも連想途中」なため、その正体はわかりにくく、摑まえどころが難しかったという。そんななかで『類似と思考』の一冊に出合ったのだという。
ルイジの奴、なんと本になっていた。鈴木はゲントナーの構造写像理論から借りた「ベースとターゲットによる類推思考プロセス」のしくみを説いて、それが準抽象化理論になりうると強調していた。連想や類推の動向を、出発点のベース(B)から目標点のターゲット(T)に向かうプロフィール(P)の軌跡として抽出する方法だ。編集工学ではBPTモデルと呼んでいる。勝手気儘で、しばしば暴れん坊のようにふるまうルイジがBPTの動向として説明できるというのだ。ルイジは認知のモデルなのである。
古来、表面的にはまったく異なる月と女性を結びつけるような類化性能は、新しいイメージを生み、人の心や文化を豊かにはぐくんできた。「らしさ」を捉える抽象化で異なる二つに対角線を引くこの認知活動によって、人は理解できなかった現象を理解できたり、解決できなかった問題を解決できたり、うまく説明できなかった事柄が説明できるようになったりする。そこから新しい価値や創発も生まれる。既知のベースと未知のターゲットという二つの異なるものを繋げていくために暗躍しているルイジ君は、思考を含めた認知全般を底支えし、人間の知性の起源にもなっているのだ。ではルイジ君とソージ君は、どのように連携しているのか。松岡正剛は次のように述べている。
類推は、類似と連想が次々にキャリーオーバー(carry-over)し続けていく状態の中に生じている思考の特色そのものである。ということは、ベースとターゲットのあいだを、たくさんのソージがたくさんのプロフィールとなって動き、これに付かず離れず随伴したルイジが接続や反転や包摂を次々におこしていたわけなのだ。
ベースとターゲットを繋げるために、似たものどうしを認知するソージ君を助けて、情報を整理したり領域を繋げていったりするのがルイジ君のようだ。
■試行錯誤で深める
何かを連想したり、類推したりするとき、人は当面の目標のもとで小さな単位の知識をあれこれ動員させながら、始発のベースから終点のターゲットへ向かっているという。
そのプロセスでは(つまりアナロジカル・プロセスでは)、「使えるリソースは何でも使う」というふうになっている。類推による認知は相互的で、冗長であり、協調的であって、重奏的なのだ。どうりで、ルイジは重ね着ファッションがうまいのだ。
類推的思考がベース(B)からターゲット(T)に向かうとき、われわれはベースにあったリソース(要素)のあれこれを、途中のプロフィール(P)をいろいろ動員させながら、なんとかターゲットに写像(mapping)しようとする。B→P→Tと動く。たとえば「エジンバラは京都っぽい町だと感じた」という場合では、ベースとしての京都がもっているリソース、主なものでいえば対象性(object)、属性(attribute)、関係性(relation)などがさまざまに動員されながら、エジンバラに向かってマッピングされ、京都がエジンバラのほうに引き寄せられていく。(千夜千冊エディション『編集力』『類似と思考』)
オツ千ラジオ[編集力vol.11にたもの兄弟が跋扈する(1642夜 鈴木宏昭『類似と思考』)]では、この「対象性、関係性、属性」を「要素・機能・属性」に言い替えて説明している。対象性類似は要素の類似、関係レベルの類似は機能の類似とも表せる。「要素・機能・属性」は、[守]の講座の中で、ものごとをシステムとして捉えるときに学ぶ3つのカテゴリーだ。
類推による認知は、そうした幾重ものプロフィールを経て、いったんはターゲットに至る。
認知科学ではこれを意思決定という。連想しっぱなしではないわけだ。連想がずうっと続くと、そのままでは夢見る夢子ちゃんの日々になる。われわれは結局は、お出掛けの服装をどうするか、お昼に何を食べるのか、会議で何を議論するのか、映画の感想をどう書くかということを、どこかで決断する。
こうしたBPTでは、コンピュータの知性と大きく違うところがあるという。
コンピュータは入力されたデータに依存するが、われわれの知性は記憶の中身や量に限定されることなく、思索そのもののプロセスから何かを生成する。これはニューロン・ネットワークの作用だけではなく、そこに身体性(embodiment)や他者の意識と行動がかかわっているせいだ。
たとえばコーヒーカップを手に取ろうとするときや、本のページをめくるとき、人の手は無意識に微細な自己修正のプロセスを踏んでいる。安藤昭子著『問いの編集力』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)によれば、この「マイクロスリップ」と呼ばれる無駄な動きやゆらぎこそが、「上手い役者」と観る人に認識させる要因にもなっているのだという。著者は、人間のコミュニケーションや思考においても、言いよどんだり、躊躇したり、言い直したりしてジグザグに進み、環境と自分とのあいだに「試行錯誤」を許容するインターフェイスをおくことが、編集力には欠かせないと説く。類推のベースは固定しているのではなく、そのつどその場で活動の目標に合わせてつくり直されている。類推のターゲットとなる事象を理解するために、その時点で明らかなターゲットの構成要素と関連するいくつかのプロフィールを検索し、仮想的なベースをつくりだしているのである。こうした動きを、先ほどの一夜でも類推思考における「ゆらぎ」と説いている。
いずれにしても、われわれの認知にはいつもいつも複数のシナリオ(編集的理解のためのストラテジー)が想定されているということなのである。いいかえれば、類推がイメージを生成するプロセスには、たえずこうした認知にかかわる「ゆらぎ」が発生しているということだ。
類推における構造は、類推を行う場面にあるさまざまな情報と相互作用しながら、さしかかったその場でつくりだされている。BPTはダイナミックなプロセスで、試行錯誤の道筋は非線形なのかもしれない。
■日本という方法とつなげる
先ほどのほんのれんラジオに登場した荒木さんは、仕事で一次産業に従事する人たちとかかわることがあるという。そうした人たちは、自分の力ではどうにもならないことに直面することが多く、おのずと自然という大いなる力にふっと身を委ねるようになる。環境と自己は切り離せないのだ。松岡正剛著『日本という方法』(NHK出版)によれば、一神教的社会と多神多仏社会にはそのジャッジ・スタイルに大きな違いがあるという。熱砂の砂漠では、道に迷ったら右に行くか左に行くかは生死を分ける判断になりかねない。だからリーダーは運を天に任せて、一人で結論を出さなければならない。いっぽうアジア的な森林型の社会の特徴は、次のようだという。
森林型の日々では拙速や浅慮は禁物です。むしろ周囲からたくさんの知識を聞き、動物に詳しい者の意見、キノコに詳しい意見、毒に詳しい意見、洪水に詳しい意見などをマンダラ的に組み合わせる必要がある。たくさんの情報を集める必要があります。そして時機を待つ必要がある。焦って動けばかえって事態が悪化する危険性があるのです。
四季のうつろいともに生きる日本人は、多様性や複雑性を取り込み、微細な変化や兆しに注意のカーソルを向けてきた。「精明心をもつこと、微妙な情報に敏感であること、それが本来の日本の神祇の感覚であり、同時に森や里山という環境での日本人の判断力の源泉だった」のだ。
うつろう自然が養った微細な心から生まれた連歌や茶の湯は、多様性によって一座を建立する文化だ。それは、ベースとターゲットのあいだをさまざまなプロフィールがうつろい、それぞれの好みや趣向が共鳴、共振しながら意味や価値が創発していく格別なBPTの文化でもある。
松岡正剛著『日本数寄』(ちくま学芸文庫)にはこのように書かれている。
連歌は日本の編集文化の最たるもののひとつであるが、とりわけ季節や主題や客人の様子をとらえてその場のモードを編集し、その編集のプロセスを互いに分かちもつことを遊んでみせたのだった。
プロセスを見せ合う主客相互的な日本文化の奥にあるものの一つを、この書では「語りの場」をめぐる編集技法に見ている。そもそも長らく文字をもたなかった日本が、漢字と倭語や和語の読み方や意味あいをどのように含意していくかという編集作業が、「ふくみあい」の編集術を創意工夫することになったと説いている。
日本の編集文化の原点には「意味のふくみあい」を成立させている「場の構造」がひそんでいたのである。そう、見てほしい。のみならず、その「意味のふくみい」を確認するにあたっては、主張を言いつのるのではなく、互いに使用した言葉やイメージを一所の場に臨んで仮に共有するほうが、かえって互いの差異も理解しやすくなるということだった。そして、この「意味のふくみあい」を提供する装置的なるものが、のちの会所や書院や茶室という「語りの場」であり、それを「一座」とみなす認識であり、またそこに用意された「好み」と「趣向」というものだったのである。
自分ひとりぶんの想像力の限界を超え、まだ見ぬ可能性や偶然性を呼び込む「座」や「連」という場は、BPTが発揮される恰好の舞台だったのだ。
■別様の可能性をひらく
いま、BPTモデルがめざす先には何があるのだろうか。
雑誌『ひらく』(2024年1月30日)の「特集 日本とは何か、日本人とは?」に掲載された松岡正剛の『日本の中のデーモンとゴースト』の中に、こんな一節がある。
ある存在やシステムには、その存在やシステムを維持するための自重が生じ、自重は存在やシステムに過剰な負担をもたらし、矛盾や葛藤がたまっていく。そのためのコストがかかり、ストレスがたまる。多くの存在やシステムはシステミック・リスクを抱えることになる(国ならソブリン・リスクをかかえる)。成長しつつある企業ならここで株式を公開して資金を集めたり、M&Aをしたりして組織を太らせることもできるのだが、そういうところにいない企業や存在や組織は往々にしてジリ貧になる。
このようになっていくのは可能性の矛先を「成長する方向」に求めようとするからである。そうではなく、そこには「別様の可能性」があるかもしれないと見直してみてはどうか。変化や変身をしてみてはどうか。これがコンティンジェントな発想だ。すなわち「内なる別様性」を存在やシステムの外にあえてあらわしていくという発想だ。
グローバル・スタンダードをBに定め、利潤や合理性や生産性の追求をTとする現代の一様な世界モデルは、Pで人間を疎外しつづける。ではどのようにBPTを捉えなおしたらよいのだろうか。松岡は近松門左衛門が唱えた「虚実皮膜」や松尾芭蕉の「虚に居て実を行ふべし」という言葉を紹介して、このようにも語っている。
二人とも芸や俳諧を通して驚くべき真相を告げていた。これは、実(リアル)から虚(ヴァーチャル)に移るのではなく、また実(ほんもの)から虚(ほんものらしさ)を生み出そうというのではない。そうではなくて、虚に移っておいてから実を描写するのだという意図の表明なのである。当初において、デーモンやゴーストが舞い散る「虚」を受け入れ、そのうえで「実」を表現しなさいという意味なのである。
一見、逆コースを奨めているようだが、そうではない。すでに歌舞伎の舞台や俳諧の場が世間なのである。その世間は聖徳太子が世間虚仮と言ったように、もとより半端な仮想現実や仮想概念で出来ている。そんな世間虚仮にいて、そこから新たな回答をカッコよくもたらしてみせること、それが「虚に居て実を行ふべし」なのである。
ユートピックな虚を生みだすプロフィール(おもかげ)は、固定された現実と地続きになっているB→Tを変容させ、これまでにはない新たなBやTを創発するのである。
■多様な世界モデルへ向かう
イシス編集学校が描くBPTの基盤には、「生命に学ぶ、歴史を展く、文化に遊ぶ」というスローガンにあるように、生命や人間がどうあるべきかという本来的な問いがある。編集工学研究所のリベラルアーツ・プログラムHyper-Editing Platform [AIDA]シーズン6のゲスト講師の生命誌研究者、中村桂子さんは、たった一つ祖先細胞から生まれていった地球の多様な生きものの40億年の歴史とその共生関係を知り、生命の歴史物語を読みとるプロフィールを巡りながら、生命誌(biohistory)というベースを打ち立てた。そして、自然の一部である私たちの日常を支えるあらたな生命論的世界観をターゲットに掲げ、研究しつづけている。そこには、効率性や利便性をめざす機械論的な現代科学への切実な危機感がある。
科学が、分析・還元・論理・客観を旗印にしているために、そこで行われた生命現象の解明が、まるのままの生きものや人間となにかという日常の問いへの答えにつながっていないもどかしさを感じるのです。(『生命誌とは何か』講談社学術文庫)
中村さんが館長を務めるJT生命誌研究館の季刊誌には、松岡正剛との対談が掲載されている。中村さんはこんなふうに語っていた。
ものごとには必ずうつるというところがある。生きものはまさにそうで、いのちはできあがったもののメカニズムじゃなくて、生まれる、うつろう、あいだがらというような動くところから見ていくととても面白いのです。それが社会から失われたでしょ。
プロセスや関係性や多様性によって支えられている生命。そうした生命や人間を基盤にしたBPTの羅針盤として、イシス編集学校の吉村林頭は6つの編集ディレクションを掲げている。
人や生命がおのずと輝いていくために、BPTはいつもそのつどここに立ち還って循環しつづけ、多様な世界観を描く。
§編集用語辞典
21[BPT]
アイキャッチ画像:穂積晴明
丸洋子
編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。
八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]
公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]
千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。 グノーシスとは「原理的 […]
木漏れ日の揺らめく中を静かに踊る人影がある。虚空へと手を伸ばすその人は、目に見えない何かに促されているようにも見える。踊り終わると、公園のベンチに座る一人の男とふと目が合い、かすかに頷きあう。踊っていた人の姿は、その男に […]












コメント
1~3件/3件
2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。
2026-01-12

午年には馬の写真集を。根室半島の沖合に浮かぶ上陸禁止の無人島には馬だけが生息している。島での役割を終え、段階的に頭数を減らし、やがて絶えることが決定づけられている島の馬を15年にわたり撮り続けてきた美しく静かな一冊。
岡田敦『ユルリ島の馬』(青幻舎)
2026-01-12

比べてみれば堂々たる勇姿。愛媛県八幡浜産「富士柿」は、サイズも日本一だ。手のひらにたっぷり乗る重量級の富士柿は、さっぱりした甘味にとろっとした食感。白身魚と合わせてカルパッチョにすると格別に美味。見方を変えれば世界は無限だ。