昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。




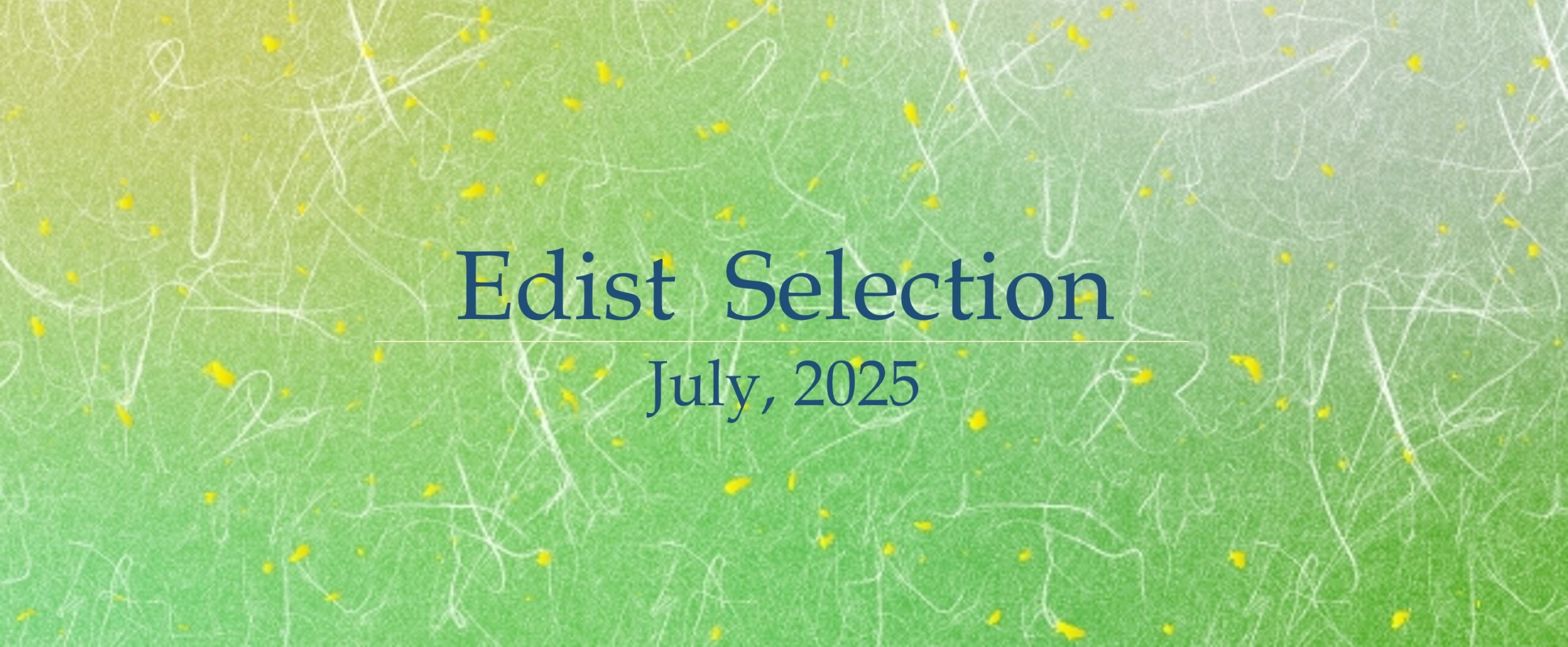
公開されるエディスト記事は、毎月30本以上!エディスト編集部メンバー&ゲスト選者たちが厳選した、注目の”推しキジ” をお届けしています。見逃した方はぜひこちらの記事でキャッチアップを。
では、2025年7月に公開された記事の中から選ばれたオシ記事6選をご紹介します。
今回は、8月18日に松岡正剛校長の自伝『世界のほうがおもしろすぎた』が刊行されたことを記念して、マツコメントに続いて、書籍から校長の言葉をPickしてご案内しました。あわせてお楽しみください。
生成AIは次々に新情報を生み出し、SNSがあっという間に情報を広げていく。
情報の洪水の中を泳ぐ力が、時代に要請されている。しかし、イシスの師範代たちは、泳ぐだけでない。次の流れをつくっていく。師範代を養成する場の秘密を知りたくないだろうか。その秘密の一端を明かしているのが、本記事だ。花伝所のキャンプでは、飛び交うテキストの中で「私」が編集され、様々な情報と繋がる「たくさんの私」が引きだされていく。「私」を卒業し、世界と繋がる「たくさんの私」に出会う。そこが、師範代への扉である。─ 柳瀬 浩之

松岡正剛校長『世界のほうがおもしろすぎた』より
もうひとつ考えたのは、このインタビューでも最初に話したことですが、ぼくには一顧のアイデンティティというものに対してずっと疑問があった。本当は、誰もが自分のなかに、いくつもの自分というものを持っている。かつてプロ野球選手に憧れた自分、ピーター・パンのように空を飛べると思っていた自分、ファイティング原田のように三分間の闘いに挑もうとする自分というようにですね。にもかかわらず、社会のなかでは、ひとつの自分というものに、どんどん限定されていってしまう。ややもすると自分の周りの社会、小さな世間が規定してくるもののほうが早くて、ピーター・パンやファイティング原田であろうとすることを阻んでくる。「そんなの嘘だろう」「無理だろう」というふうに追い詰められてしまう。そんな社会や世間に抵抗したくても、では自分のなかにあるいくつもの自分はどこに、どうやって置いておけばいいのか。これがぼくの積年の疑問であり課題でもあったわけです。(p.262-263)
なぜ「編集用語辞典」としながら辞書的定義がないのでしょう? 答えは、この創文自体にあります。ヨシタケシンスケ展の「かもしれない」に足を止める体験(B)。逡巡のうちに著者と読者の境界は消え、物語が始まります。ラジオの語りから「余白」が浮上し、ソージとルイジにより事象には複数の解釈が潜むと直感する。認知科学や身体性が加わり、BPTは人間本来の知のモデルとして立ち上がる。さらに「ふくみあい」「一座建立」により日本文化に再定位され、虚実論を経て生命誌へと拡張される(複数のP)──こうして読者は別様の可能性に触れ、自らの視界を更新する(T)。つまり、この創文自体がBPTの実演であり、読者変容の物語でもある。だからこそ、この一篇は「編集用語辞典」に相応しいのです。──宮前 鉄也

松岡正剛校長『世界のほうがおもしろすぎた』より
… ぼくがそういうことをまだ試行錯誤していたときに、よく清水博や山口昌男にも聞いてもらったものですよ。二人とも「おもしろいことを考えるね」と言ってくれた。で、たとえば山口さんは「そこにはアイコンというか、トリックスターみたいなヘンなものも出てくるよね」といったヒントをくれるわけです。「そうか、そういうものもあるな」ということで、いったん世界観を定めたり設定したりしたものの脇のほうから出てくるもの、オンとオフ、インとアウトだけではないところでも出入りするものもいっしょに組み立てようというふうになっていくわけです。それをぼくはのちに「面影」とか「プロフィール」というふうに呼んでいくことになるんですね。(p.214)
江戸文化研究者として鮮やかな視点をもち、AIDAボードメンバーであり、
イシス編集学校の学長という「たくさんのわたし」を体現する田中優子さん。
そのもう一つの顔、55[守]師範代として教室に登場する「ゆうこ師範代」の姿も見逃せません。
いつもの鋭さとは異なる、親しみのある語り口とスピーディな指南で、
稽古と遊びが溶けあう濃密な場をつくり出すゆうこ師範代の魅力が伝わってきます。
ぜひその柔らかさと確かな視点に触れてください。── 衣笠 純子

松岡正剛校長『世界のほうがおもしろすぎた』より
そういう経験をしてきた立場からすると、ぼくの編集術を学んだ人たちが何百、何千という単位で社会のなかに出現してきたときに、きっといろんなことを起こしていってくれるんじゃないかと思います。いよいよそういうことが、編集学校のみんなにも問われたり試されたりしていく時期にきているんだろうと思ってますね。(p.269)
【軽井沢別想フロンティア】浅羽米プロジェクト2025 稼働!
突然はじまった多読アレゴリア軽井沢別想フロンティアによる「浅羽米プロジェクト」連載!「浅羽米プロジェクト」とは、11月23日と24日に開催される別典祭に出品する浅羽登志也(モーリス浅羽)が育てるお米の成長記録です。書き手は中原洋子。写真と文で軽井沢の地にすくすくと育つ稲の様子をお届けしています。虫の目のレポートに、土地の季節が感じられる充実の写真が組み合わされて、軽井沢からの風便りのよう。先日第2報も公開されました。
軽井沢別想フロンティアが見守る浅羽米は別典祭で限定販売としてお目見えします。 ── 後藤 由加里

松岡正剛校長『世界のほうがおもしろすぎた』より
…ぼくはだから、そういう日本の「おおもと」にあたるものを、「耐影」というふうに呼んできました。それが何であるかは名指しできないもので、捉えようとしたとたん移ろっていってしまうものである。にもかかわらず、日本はそれをいろんな方法によって繰り返し再現しようとしてきた。だから日本のことを理解するには、この「方法」のほうを見ようとしないかぎり何もわからない。そこにはまた独特なジャパンフィルターのようなものがたくさんあって、それが扇の骨の数とか、屏風の六曲一双とか、日本の和歌の五・七・五・七・七になってきた。つまり方法日本は、多種多層なエディティングフィルターによって形づくられてきた。そういうふうに見ることで、編集という方法と日本という方法を重ねてきたわけです。(p.344)

【2025秋募集★多読アレゴリア】「別典祭」ダイダイ大開催!!!! イシスの新しいお祭り?
イシスの新しいお祭「別典祭」(べってんさい)を開催します! 主催は多読アレゴリアですが、クラブメンバー以外の方、イシスの受講者以外の方も、誰でも参加できます。2025年11月23日(日) & 24日(月・祝)は、ぜひ予定を空けておいてくださいね。
この記事では紹介できませんでしたが、実は多読アレゴリアの秋シーズンにはもう一つのビッグニュースがあります。なんとあの超人気ポッドキャスト番組を制作する「ほんのれん」がアレゴリアのクラブとして参入することが決定しました。その名も「ほんのれんクラブ」です。
詳細はこちら→【特報】ほんのれんクラブ、ついに誕生!【多読アレゴリア・申込受付スタート】:https://edist.ne.jp/just/news_honnoren_club/)。── 金 宗代

松岡正剛校長『世界のほうがおもしろすぎた』より
日本にもかってコーヒーハウスに似たものがありました。それは茶の湯です。茶の湯はわずか数人しか入れないような極小の茶室で行われるものです。草履を脱いで腰の大小(刀)をはずして、小さな躙り口から腰をかがめて茶室の中に入って、亭主のもてなしを受ける。そこでは小さなお菓子をいただき、お茶だけを飲む。でもその茶室のなかではそれまで誰も見たことがないような、楽焼の漆黒の茶碗や織部の歪んだ茶碗なんかが出されて、わずか数カ月後には一万倍もの値段になったりするわけです。これはアダム・スミスのいう「神の見えざる手」でつくられた市場価値ではなく、プロデューサーとしての茶人とそこに呼ばれる客たちのあいだで自由に創発的に生み出されていくもの、クラブ経済なんです。(p.251)
イシス館書棚見回り「書庫邏隊」いよいよ始動―「2025春の陣」その2
松丸本舗に近大アカデミックシアター、角川武蔵野ミュージアムの本棚劇場に、TSURUGA BOOKS & COMMONS ちえなみき。これらは、松岡校長の代表的な仕事の一つである「ブックウェア(書籍空間プロデュース)」の実践例です。
今回の記事では、編集工学研究所と松岡正剛事務所の一部メンバーで構成された「書庫邏隊」(ショコラ隊)が、松岡校長の書物への情熱を受け継ぎながら、選書の腕を競って仕上げた特別な書棚空間が紹介されています。
このセレクションは、編集工学研究所の来客を迎える入口に設けられた本棚空間である「井寸房」の書棚に展開されています。本楼にお越しの際には、入口右手に配されたこの「ブックウェア」の実践を、添えられたリコメンドのメッセージとともに、ぜひ手にとって味わってみてください。── 上杉 公志

松岡正剛校長『世界のほうがおもしろすぎた』より
…だとしたら、明治であって小説であって心理でもあるようなゾーンを本棚のほうに用意して、「こころ』のまわりにそういう領域性をもった本が集まってくるようにするという方法もあるわけです。そうすることによって、本の並びがそのまま文脈になる、本の並びをみるだけで読書がはじまる、そういう本棚づくりをしていくことも可能になるわけです。いままでぼくが試みてきたのはそういう方法です。どこの棚を見ても、一冊の本が次々とべつな一冊の本を呼び込んでいるように見える。そういう本棚づくりを心掛けてきました。(p.232)
以上、2025年7月の記事から、エディスト編集部の”イチオシ” を厳選してお届けしました。みなさんのオシは、見つかりましたか?
次に選ばれるのは、あなたの記事かもしれない!
★無料!編集力チェックはこちら
★未入門の皆様は、メルマガ登録をこちらから
★無料の学校説明会へどうぞ
エディスト編集部
編集的先達:松岡正剛
「あいだのコミュニケーター」松原朋子、「進化するMr.オネスティ」上杉公志、「職人肌のレモンガール」梅澤奈央、「レディ・フォト&スーパーマネジャー」後藤由加里、「国語するイシスの至宝」川野貴志、「天性のメディアスター」金宗代副編集長、「諧謔と変節の必殺仕掛人」吉村堅樹編集長。エディスト編集部七人組の顔ぶれ。
イシス編集学校で予定されている毎月の活動をご案内する短信「イシスDO-SAY(ドウ-セイ)」。 弥生の月がやってきます。今年の3月3日は、皆既月食が見られるといわれています。20時頃からは、赤胴色になった月 […]
イシス編集学校のアドバイザリー・ボード「ISIS co-mission」(イシス・コミッション)に名を連ねる9名のコミッション・メンバーたちが、いつどこで何をするのか、編集的活動、耳寄りニュースなど、予定されている動静を […]
田中優子の酒上夕書斎|第九夕 『日本文化の核心』(2026年2月24日)
学長 田中優子が一冊の本をナビゲートするYouTube LIVE番組「酒上夕書斎(さけのうえのゆうしょさい)」。書物に囲まれた空間で、毎月月末火曜日の夕方に、大好きなワインを片手に自身の読書遍歴を交えながら […]
編集を通して未知の自分になっていく【ISIS co-missionメッセージ 鈴木健】(全文書き起こし)
イシス編集学校アドバイザリーボード ISIS co-missionメンバーより、これから「編集」を学びたいと思っている方へ、ショートメッセージが届きました。なぜ今、編集なのか、イシス編集学校とはなんなのか。イシスチャンネ […]
イシス編集学校で予定されている毎月の活動をご案内する短信「イシスDO-SAY(ドウ-セイ)」。 卒業シーズンに向かう一歩手前の2月です。イシス編集学校では、昨年10月から開講した講座がぞくぞくと修了を迎えま […]








コメント
1~3件/3件
2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。
2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。
2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。