誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)




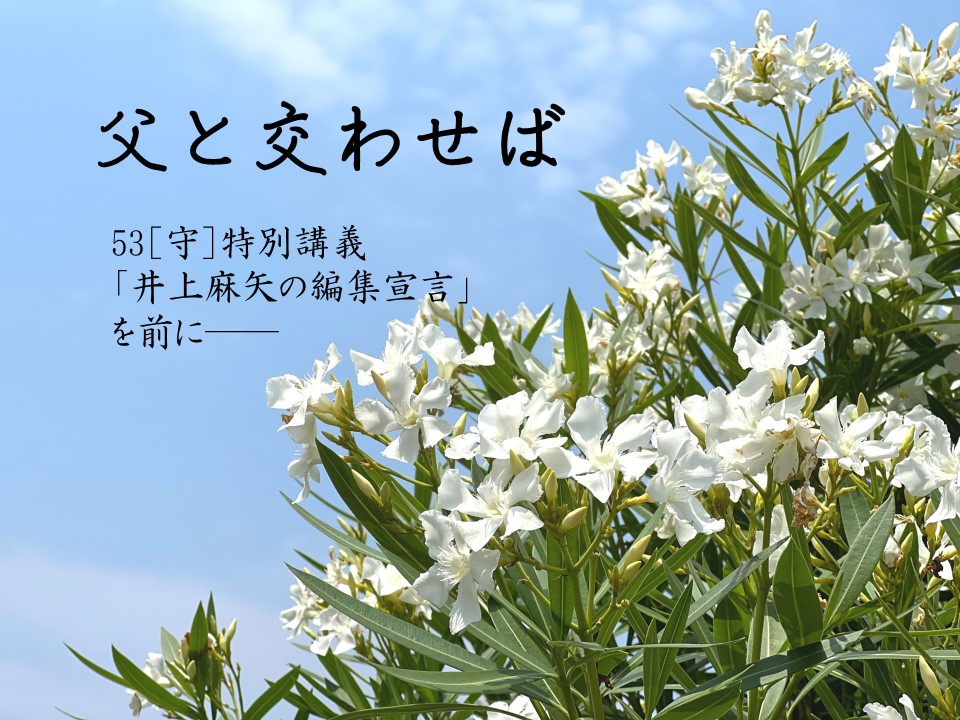
7月14日、豪徳寺・本楼が「編集×演劇」の舞台となる。イシスコミッションのメンバーのひとりで、かつてイシス編集学校の[守]で学んだ井上麻矢さんが、53[守]特別講義を開催するのだ。
井上麻矢さんといえば、父である井上ひさしさんから「こまつ座」を引き継ぎ、10数年奮闘し続けている。その思いとは――。53[守]師範が、井上麻矢さんと井上ひさしさんとの「あいだ」を繋ぎます。
今日も日射しがきつい。「酷暑」という言葉自体が突き刺さる。太陽を見上げて、ある台詞を思い出す。
「あのとき、ヒロシマの上空五百八十メートルのところに、太陽が、ペカーッ、ペカーッ、二つ浮いとったわけじゃ。頭のすぐ上に、太陽が二つ、一秒から二秒のあいだ、並んで出よったけえ、地面の上のものは人間(にんげ)も鳥も虫も魚も石灯籠(どーろ)も、一瞬のうちに溶けてしもうた」
井上ひさし氏の『父と暮せば』は昭和二十三年七月の広島を舞台にした二人芝居だ。出てくるのは図書館員をしている娘・美津江(23)と、父・竹造だ。そして竹造はあの日、亡くなっていて幽霊として登場する。
井上ひさし氏はあとがきで『「しあわせになってはいけない」と自分をいましめる娘と、「この恋を成就させることで、しあわせになりたい」と願う娘とに、真っ二つに分裂して』しまうと書いた。しあわせを願う父は「美津江のこころの中の幻」なのだとも。
けれど、この幻は容赦ない。最初に書いたあの台詞は、竹造が突然、演じてみせた「エプロン劇場」の中の一節だった。子ども達に土地の昔話を聞かせる「夏休み子どもおはなし会」の準備中の美津江の前に出てきた竹造は、その昔話の中に原爆の話を入れてはどうか、と提案する。なぜなら、それが、美津江が恋し始めた木下という、原爆の資料を集めている青年を喜ばせるのでは、と思ったから。
映画『父と暮せば』では原田芳雄演じる父の渾身の演技で、美津江ならずとも「もう、やめて」と目を、耳を覆いたくなる。
美津江は、あの日、死んだ友達を、そして何より家の下敷きになって動けなくなった父を見捨てた自分のことを許すことができない。
竹造はついに怒鳴る「このあほたれが」。容赦ない幻は、容赦なく娘に「おまいはわしによって生かされとる」と言う。昔話を伝えるだけではない、娘が父を見捨てなければならなかったようなむごい多くの別れがあったことを伝えるのがお前の仕事なのだと突きつける。「そいがおまいに分からんようなら、もうおまいのようなあほたれのばかたれにはたよらん」といった父は、誰にたよるかと聞く娘に「わしの孫じゃが、ひ孫じゃが」と答える。
その言葉が美津江の心にしみていく。自分だけではなく子ども達の世代にまで伝えなくてはならないのだと知った時、初めて美津江は木下のことを考える、もう一歩を踏み出せた。この戯曲の最後の台詞、「おとったん、ありがとありました」は限りなく優しく響く。
◆ ◆ ◆
「おそらく私の一生は、ヒロシマとナガサキを書きおえたときに終わるだろう」。戯曲『父と暮せば』の冒頭に、井上ひさし氏は、こう書いた。しかし、ナガサキは書かれなかった。
井上ひさし氏の思いを受け継ぎ、井上麻矢氏が企画したのが『母と暮せば』だ。戦後七十周年の映画として、山田洋次監督がメガホンをとった。映画化の後、麻矢氏が小説化した。
「生き残ったことが罪だ」。両作品に共通するこの思いを軸に、『母と暮せば』は『父と暮せば』と見事に対をなす。『母と暮せば』では幽霊になるのは息子、幽霊となった息子と会話をするのは母だ。息子・浩二は長崎医科大学の学生で、あの日、爆心地の近くで「熱さを感じる間もなく」「一瞬の間に溶けてしまった」。遺品の一つもない状態では諦めもつかない。母・伸子が「浩二はもういない」という現実を受け容れた時、ようやく浩二は幽霊として母の前に出てくることができた。
『母と暮せば』には、もう一人のキーパーソンとして、浩二の婚約者だった町子という娘が出てくる。小学校の先生になった町子もまた浩二のことを諦めきれず、同じ学校の教員・黒田に心を開くことができない。
『父と暮せば』では、幽霊になった父・竹造が、美津江に新たな道へ進む後押しをするが、『母と暮せば』では、生きている母・伸子が、浩二に、町子に、それぞれ新しい道へ進むことを進める。母の言葉が浩二の心にしみて、町子が他の人と結婚することに納得した時、そして町子と黒田の婚約を衝撃を受けながらも町子の幸せを願った時、逆に伸子の口からこの言葉が零れる。「でもどうしてあの娘だけが幸せになるの」。嘘偽りのない、思ってはいけないと知りつつもなお止めることができない思い。辛いことが起きた時、「なぜ自分が、自分だけが辛い目に」と言いたくなる気持ち。
これが大事な人を失った時に「生きているのが申し訳ない」という思いと、対になるもう一つの思いではないだろうか。そう言ってしまった母を逆にいさめる立場になった時、浩二は真に町子の幸福を祈ることができたのだろう。
『父と暮せば』では「幸せになってはいけない」と「幸せになりたい」というように娘が二つに分裂したが、『母と暮せば』では「幸せになってほしい」と「なぜ自分の息子だけが」というように母・伸子が二つに分裂して、その片方が浩二となって表れたように思える。「なぜ自分の息子だけが」という思いを言葉にすることが出来た時、母の気持ちが昇華したのではないだろうか。この対になる言葉をたずさえるかのように、浩二と伸子は一緒に天へと旅立つ。
◆ ◆ ◆
それぞれの映画は見たものの、こまつ座の舞台を見ずに、この文を綴るということに躊躇した。井上ひさし氏・麻矢氏の本領の舞台を見てもいないのに、書いてもよいものだろうか?
しかし井上ひさし氏の戯曲『父と暮せば』の冒頭に、こう書かれている。「あの二個の原子爆弾は、日本人の上に落とされたばかりではなく、人間の存在全体に落とされたものだと考えるからである」。だから「世界五十四億の人間の一人として、あの地獄を知っていながら、『知らないふり』することは、なににもまして罪深いことだと考えるから書くのである」。
原子爆弾が落ちた時・場所、という「地」を広げると、私もまた「知らないふり」はできない。何を言っても軽々しくなりそうで、何かを言うことは難しい。けれど、これだけは言ってもいいのではないかと思う。井上ひさしさん、井上麻矢さん、「知らないふりをしてはならない」というその思いを受け止め、私もまた知らないふりをしない輪に加わります。竹造が「風がおまいのことばを四方八方に散らばしてくれる。よい子たちのこころの中を通り抜けたおまいのことばは風にのって空へのぼり虹になる」といったように、お二人がかける虹の輪が世界にさらに広がっていくことを祈りながら。
文/相部礼子(53[守]師範)
参考資料/
『父と暮せば』井上ひさし/新潮社
『小説 母と暮せば』山田洋次・井上麻矢/集英社
映画『父と暮せば』(監督:黒木和雄/出演:宮沢りえ、原田芳雄、他)
映画『母と暮せば』(監督:山田洋次/出演:吉永小百合、二宮和也、黒木華、他)
特別講義の概要は以下の通り。
●イシス編集学校第53期[守]特別講義「井上麻矢の編集宣言」
●日時:2024年7月14日(日)14:00~17:00
●ご参加方法:zoom開催
●ご参加費:3,500円(税別)
※53[守]受講生は受講料に含まれています。
●申込先:https://shop.eel.co.jp/products/detail/717
※53[守]受講生は教室からお申し込みください。
●お問合せ先:es_event@eel.co.jp
どなたでも受講できます。ふるってご参加ください。たくさんのお申し込みをお待ちしています。
イシス編集学校 [守]チーム
編集学校の原風景であり稽古の原郷となる[守]。初めてイシス編集学校と出会う学衆と歩みつづける学匠、番匠、師範、ときどき師範代のチーム。鯉は竜になるか。
春のプール夏のプール秋のプール冬のプールに星が降るなり(穂村弘) 季節が進むと見える景色も変わる。11月下旬、56[守]の一座建立の場、別院が開いた。18教室で136名の学衆が稽古していることが明らかに […]
番選ボードレール(番ボー)エントリー明けの56[守]第2回創守座には、教室から1名ずつの学衆が参加した。師範代と師範が交わし合う一座だが、その裏側には学衆たちの賑やかな世界が広がっていた。 師範の一倉弘美が俳句で用法3を […]
秋の絵本を「その本を読むのにふさわしい明るさ」で3つに分けると、陽だまり・夕焼け・宵闇になる。 多読アレゴリア「よみかき探究Qクラブ」のラウンジに出された問い「本をわけるあつめる。するとどうなる?」への答えだ。 クラブで […]
教室というのは、不思議な場所だ。 どこか長い旅の入口のような空気がある。 まだ互いの声の高さも、沈黙の距離感も測りきれないまま、 事件を挟めば、少しずつ教室が温かく育っていく。そんな、開講間もないある日のこと。 火種のよ […]
かなりドキッとした。「やっぱり会社にいると結構つまんない。お給料をもらうから行っておこうかなといううちに、だんだんだんだん会社に侵されるからつらい」。数年前のイシス編集学校、松岡正剛校長の言葉をいまもはっきりとはっきり […]







コメント
1~3件/3件
2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。