タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。




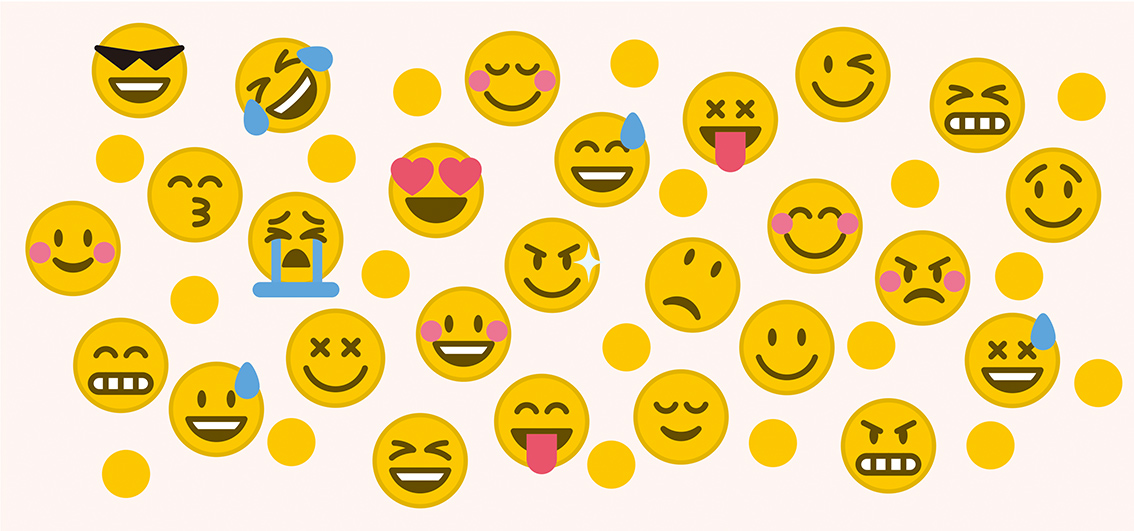
「正直、メチャメチャ悔しいです」(ジャイアン対角線教室 師範代 角山祥道)
「これで悔しくなかったら、ウソですよね」(調音ウラカタ教室 師範代 石輪洋平)
つぎつぎに無念を吐露したのは、師範代だった。アリスとテレス賞講評が届けられた6月5日夜半のことである。歴代トップクラスの指南数に燃えた46[破]でなにが起きたのか。
2週間前、予兆はあった。伝習座にて植田フサ子(評匠)が、今期の知文AT賞の稽古模様に触れたときだった。植田は、今期のひときわ熱血なラリーを讃えながらも、「本に入るのは上手だが、本から出るのがいま一歩」と読み手を意識した編集が不足していたことを師範代にチクリと刺したのだ。
アリスとテレス賞の選評会議に忖度はない。徹頭徹尾、第三者の読み手として作品を吟味する。会議はある日の正午過ぎに始まった。全65作品すべてが印刷され、Zoomに集った11名の選評委員それぞれの手元に積みおかれる。木村久美子(月匠)をはじめとするメンバーは、作品集を上から1枚ずつ俎上に乗せる。一文を読んでは「このエピソードが引用された意図はなにか」「このキーワードに要約される必然性は」など、学衆の読みの射程と表象の手さばきを委員同士で交わしあう。書き手の思いを深読みするほど推察するが、その読みが読者に届けられたかどうか、その判断には透徹したまなざしがある。「この段落にひとことでも、書き手の見方が入っていれば」と、委員が涙をのむ場面もあった。すべての評価づけが完了したときには、ゆうに7時間が経過していた。
会議が終われば、講評執筆が始まる。「推敲過程を見て落涙したのははじめて」と植田は目をうるませ、選評委員は同朋の講評を逐一確認。固有名詞の正誤チェックはもちろん、音引き表記の統一、果ては「廃する」か「排する」か、漢字一字に至るまで辞書を引き議論をしながら、講評という真剣を研ぎ澄ました。不足を突きつけるには、それだけの覚悟がいる。
奇しくも同日、本楼では47[守]伝習座が行われていた。肺がん手術の直後の身体をおして、3種の痛み止めを服用しながも駆けつけた校長松岡正剛は、師範代にメッセージを残した。
「学衆の不足を見つけ、伝えていきなさい。それを恐れてはいけない。学衆の回答をつまらないままにさせておかず、維摩のように引き受けなさい。学衆は変わりたくてここへ来ているのだから」と。
呼応するかのように、イシスのジャイアンは「おまえのキズもおれさまのもの」と共苦の侠気を見せ、師範代石輪洋平は「悔しさに着火して、リベンジします」とひと月後に迫る物語アリスとテレス賞に照準を合わせた。明日6月8日、王冠切れ字教室を先鋒にはじまる汁講は、次回AT賞に向けた決起集会となる。
46[破]アリスとテレス賞 「セイゴオ知文術」大賞作
●アリストテレス賞:大賞 義原星乃(あたりめ乱射教室)
「文字食うて神になった男」/『文字逍遙』
ポッと出の一文:何万本もの針が身体を貫通したかのようにヒリヒリする。
●アリス賞:大賞 李康男(調音ウラカタ教室)
「アゴタとチェギュの缶蹴り遊び」/『悪童日記』
切実の一文 :六歳の頃、名前を変えられ母国語を封印した生活が始まった。チェギュはヤスオに変り、僕は「ぼくら」になった。
●テレス賞:大賞 小倉良之(アジール位相教室)
「世界認識の調律」/『文字逍遙』
さわりの一文 :漢字とは文化史・精神史をその内にはらみ、神話学・民俗学という文脈に読み解かれる方形の宇宙なのだ。
画像:野嶋真帆
※アリスとテレス賞課題本10冊はこちらから
梅澤奈央
編集的先達:平松洋子。ライティングよし、コミュニケーションよし、そして勇み足気味の突破力よし。イシスでも一二を争う負けん気の強さとしつこさで、講座のプロセスをメディア化するという開校以来20年手つかずだった難行を果たす。校長松岡正剛に「イシス初のジャーナリスト」と評された。
イシス編集学校メルマガ「編集ウメ子」配信中。
大澤真幸が語る、いまHyper-Editing Platform [AIDA]が必要とされる理由
Hyper-Editing Platform[AIDA]は、次世代リーダーたちが分野を超えて、新たな社会像を構想していく「知のプラットフォーム」です。編集工学研究所がお送りするリベラルアーツ・プログラムとして、20年にわ […]
【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】もし順天堂大学現役ドクターが本気で「保健体育」の授業をしたら
編集術を使って、医学ゲームをつくる! 「MEdit Lab for ISIS」は2025夏シリーズも開講します。 そして、7月27日(日)には、順天堂大学にて特別授業を開催。 クラブ員はもちろん、どなたでもご参加いただけ […]
【ARCHIVE】人気連載「イシスの推しメン」をまとめ読み!(27人目まで)
イシス編集学校の魅力は「人」にある。校長・松岡正剛がインターネットの片隅に立ち上げたイシス編集学校は、今年で開校23年目。卒業生はのべ3万人、師範代認定者数は580名を超えた。 遊刊エディストの人気企画「イシスの推しメン […]
イシス最奥の[AIDA]こそ、編集工学の最前線?受講した本城慎之介師範代に聞くSeason5。
イシス編集学校には奥がある。最奥には、世界読書奥義伝[離]。そして、編集学校の指導陣が密かに学びつづける[AIDA]だ。 Hyper Editing Platform[AIDA]とは、編集工学研究所がプロデュースする知と […]
【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】編集術を使って、医学ゲームをつくる!?
伝説のワークショップが、多読アレゴリアでも。 2025年 春、多読アレゴリアに新クラブが誕生します。 編集の型を使って、医学ゲームをプランニングする 「MEdit Lab for ISIS」です。 ■MEd […]





コメント
1~3件/3件
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。
2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥
LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。
2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。