タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。




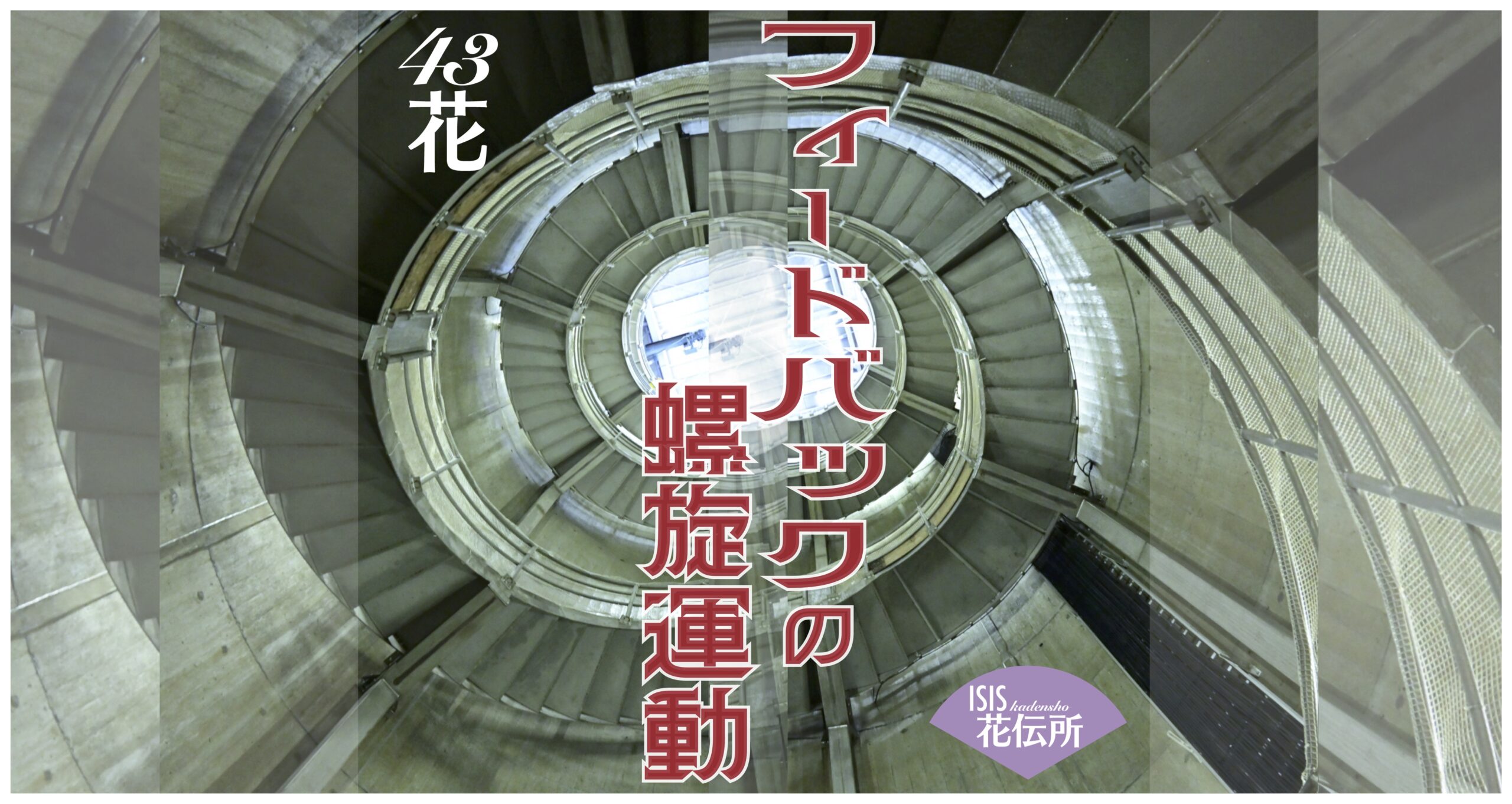
スイッチは押せばいい。誰もがわかっている真理だが、得てして内なるスイッチを探し出すのは難しい。結局、見当違いのところを押し続け、いたずらに時が流れる。
4月20日の43期[花伝所]ガイダンスは、いわば、入伝生たちへの「スイッチを押す機会」の提供であった。古谷奈々、岩野範昭の両花伝師範による講義は、入伝生たちを揺さぶり、隠れたスイッチをあらわにした。あとは気づいて(勇気をもって)押すかどうかだ。
何人かの入伝生たちは、ガイダンスでの「感」を「すぐに解けない問い」に変換し始めた。「答えの出ない状態を一旦、縁側に置いておく」という岩野師範の講義を実践し始めたといえよう。
入伝生の「問い」のひとつを、ここに取り出してみる。
Q.[守][破]のお題にあった「振り返り」と、[花伝所]のいう「フィードバック」の違いは何か。
今まで用いていた言葉をあえて言い換えているときには、アテンションが必要だ。そこには必ず「意図」と「問い」が隠れている。
では、振り返りとフィードバックの違いは何か。こういうときは、5W1Hに置き直してみるとよい。
違いが見えてきただろうか。
松岡正剛校長いわく、「生きているシステム」には3つの特徴がある(入伝生や師範代は、「システム」を教室や場と言い換えてもいいだろう)。
(1)フィードバック・ループがある
(2)バイアスやストレスがかかる
(3)自己組織化がおこり、自己変更もおこっていく、
(校長室方庵◎校長校話「編集工学序説ふう談義(05)」2011年10月5日)
一番目の条件、「フィードバック・ループがある」という点に着目したい。これは、システムの内部に発生した原因や結果は、システムの外部とさまざまなフィードバック関係(相互に影響しあう関係)をもつということだ。端的にいえば、フィードバックは必ず、「外部」(非自己)を必要とする。外部情報の取り込み=情報圏の再編集(更新)が鍵になるからだ。外部を持たないフィードバックは、ただのつぶやきである。
「外部情報の取り込み」は、言い換えるなら「まねる」ということだ。世阿弥のいう「物学(ものまね)」である。
心にて見る所は体(たい)なり。目にて見る所は用(ゆう)なり。
(世阿弥「至花道」、『新編 日本古典文学全集 能楽集』小学館)
真似ようとしたとき、往々にして、「目で捉えたもの」をそのままコピーしてしまう。これでは駄目だと世阿弥はいう。心で「体」を捉えろ、と説く。「体」が月ならば「用」はその光。「体」が花ならば「用」はその匂い。光や匂いといった風情に囚われるのではなく、それを発している大本を捉えよ、と世阿弥は説いたのだ。
「物学」とはつまり、意味の模倣だ。これを「もどき」という。「もどき」とは、本来の何かを継承したいがための模倣である。
自分の中になかった「意味」まで模倣する。ゆえにフィードバックは一筋縄ではいかない。そこには相応の負荷がかかる。何より、フィードバック後には、自己組織化がおこり、自己変更も起こる。
岩野師範はフィードバックを語るにあたって「中村哲」を持ち出した。中村哲は、医師としてアフガンに赴きながらも、同地の現状を目にし(外部情報を取り入れ)、フィードバックをかけることで、井戸掘り、灌漑事業……とロールチェンジを起こしていった。医師というアイデンティティを躊躇なく捨て、「アフガン民衆を救う」というターゲットに対し、次々と「わたし」を着替えていったのである。
フィードバック(feedback)という言葉からも明らかなように、これは後方に溯行することだ。経済学者マルクスのいう「後方への旅」である。戻りながら与件を確認・整理し、外部情報を取り込み、そしてまた戻ってくる。
フィードバックは片道飛行ではない。振り返って終わり、でもない。再編集(更新)してフィードフォワードする。この螺旋のごとき行ったり来たりを「フィードバック・ループ」という。
では、どうやってフィードバック・ループ状態に入ればばいいのか。
怯むことはない。私たちはすでに、[守][破]で「型」を学んできたではないか。「型」とは、そこに出入りするものに感応してフィードバックする回路なのだ。あとは、フィードバックによって起こる自己の変化や更新を楽しめるかどうか。行ったり来たり寄り道しながら、螺旋運動をおこしていきたい。
▲「問・感・応・答・返」もまた、問→感→応→答→返→問→感→応→答→返→問……と螺旋を描くように動き続けている。「問」から「感」への道筋は、複数であり、ノンリニアである。
アイキャッチ/大濱朋子(43[花]花伝師範)
文・作図/角山祥道(43[花]錬成師範)
【第43期[ISIS花伝所]関連記事】
●43[花]習いながら私から出る-花伝所が見た「あやかり編集力」-(179回伝習座)
●『つかふ 使用論ノート』×3×REVIEWS ~43[花]SPECIAL~
●『芸と道』を継ぐ 〜42[花]から43[花]へ
●位置について、カマエ用意─43[花]ガイダンス
●<速報>43[花]入伝式:問答条々「イメージの編集工学」
●43[花]入伝式、千夜多読という面影再編集
角山祥道
編集的先達:藤井聡太。「松岡正剛と同じ土俵に立つ」と宣言。花伝所では常に先頭を走り感門では代表挨拶。師範代登板と同時にエディストで連載を始めた前代未聞のプロライター。ISISをさらに複雑系(うずうず)にする異端児。角山が指南する「俺の編集力チェック(無料)」受付中。https://qe.isis.ne.jp/index/kakuyama
「遊撃」には、あらかじめかちっとした目標を定めず、状況に応じて動いていく、という意味がある。機を逃さず、果敢にうって出る。これぞ「遊撃」だ。 「遊撃ブックウェア」を掲げた感門之盟を経て、44期[花伝所]に飛びこんできた入 […]
褒められるわけでもない。報酬が出るわけでもない。目立つわけでもない。打ち合わせは連日で、当日は朝から現地入り。 だからなのか、だからこそなのか、「感門団」は感門之盟の華であります。江戸に火消しがつきもののように、感門之盟 […]
いったい誰が気づいたか。この男が、感門之盟の途中でお色直しをしていたことを。 司会の2人が、感門テーマの「遊撃ブックウェア」にちなんで、本を纏ったことは当日、明かされたが、青井隼人師範には「つづき」があった。イシスの […]
壇上に登ればスポットが当たる。マイクを握れば注目が集まる。表舞台は、感門之盟の華だ。だが表があれば裏がある。光があれば影もある。壇上の輝きの裏側には、人知れない「汗」があった。 第88回感門之盟(9月6日)は、各講座 […]
アフ感会場で、板垣美玲がショックを口にした。 「今井師範代が来ていたなんて、気づきませんでした」 今井師範代とは、JUST記者の今井サチのことである。果敢に林頭を取り上げたあの今井だ。師範代と学衆の関係だった今井と板 […]







コメント
1~3件/3件
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。
2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥
LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。
2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。