ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。





この夏、作家・元外務省主任分析官の佐藤優さんと編集工学研究所のコラボ講義が目白押しです。
6月30日(月)に編集工学研究所から配信したプレスリリースを、エディスト読者の皆さまにもお届けにあがりました。
1日限りの特別講義、5回にわたって佐藤さんと直接丁々発止するシリーズ講義、知の最先端が集結する半年間のリベラルアーツプログラム。あなたはどれを選びますか?
作家・元外交官の佐藤優氏と、編集工学研究所のコラボレーションプログラムを豪華3本立てで開催します。「インテリジェンス」という情報処理力と、「編集工学」という情報思考力を身につける特別企画です。
株式会社編集工学研究所(東京都世田谷区/代表取締役社長 安藤昭子)は、作家・元外務省主任分析官の佐藤優氏を講師にお招きして、特別プログラムを開催します。「1日限りの特別講義(2025/7/6)」、「全5回のシリーズ講義(2025/7〜10)」、「半年間のリベラルアーツ・プログラム(2025/10〜2026/3)」の3本立てでご紹介します。
情報があふれる時代だからこそ、自らの手で情報を選びとり、思考する力を。近年特に「編集工学」に着目されている佐藤優氏から、情報の渦の中から正しい情報をいかに選びとるか、その上で激動の世界をどう「読む」か、直接学べるまたとない機会です。
編集工学研究所が運営する「イシス編集学校」の特別公開講義に、佐藤優氏が登壇します。7月6日(日)14:00-17:00にオンライン開催です。

激変する世界において、今必要なのは「知を再編集する」力。その力を、「インテリジェンス」と「編集工学」の掛け合わせによって切り開きたい。
編集工学研究所が運営する「イシス編集学校」の特別講義に佐藤優氏が登壇、これからの「知」のあるべき姿を紐解きます。
講義は7月6日(日)14:00-17:00にオンライン開催です。どなたでもご参加いただけます。
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
イシス編集学校第55期[守]特別講義「佐藤優の編集宣言」
編集工学2.0と歴史的現実~正剛イズムをインテリジェンスにどう活かすか?~
●お申込はこちら
●日時:2025年7月6日(日)14:00-17:00
●ご参加方法:オンライン開催 *お申し込みの方にzoomURLをご案内します
●ご参加費:3,500円(税別)
●対象:どなたでも参加いただけます
●ゲスト講師:佐藤優さん(作家・元外務省主任分析官)
●お問合せ先:es_event@eel.co.jp
7月から10月にかけて、5回に渡る佐藤優氏からの講義とディスカッション、オンラインでの課題提出と議論を掛け合わせたプログラム「インテリジェンス編集工学講義」を開催します。

トランプ大統領の再選、ウクライナやガザの戦争、米中の経済対立など、世界では様々な問題が噴出しています。フェイクニュースや有象無象の情報が溢れるなか、いかに世界を読み解き、いかに判断し、いかに行動するのかは、我々にとっても喫緊の課題になっています。
元外務省主任分析官で作家の佐藤優氏のインテリジェンスと松岡正剛の編集工学を融合しながら、世界の最前線に取り組む連続講座「佐藤優のインテリジェンス編集工学講義」が開講します。
「トランプが混乱を生んだのではなく、混乱の結果、トランプが登場した」。そして、ドナルド・トランプの思考にはそのベースとなる理論があると佐藤優氏は語ります。トランプの行動原理を「資本論」「ナショナリズム」「関税論」から紐解き、書物の精読と年表の精査によって知を身体化していきます。
これからの世界を見通すための、インテリジェンスと編集工学の実践的講義は、ここでしか体験することはできません。
5回に渡る佐藤優氏からの講義とディスカッション、オンラインでの課題議論という独自のスタイルによる、新たなシリーズ「インテリジェンス編集工学講義」。ぜひご参加ください。受講/オンライン聴講のいずれかをお選びいただけます。
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
■講義日程
第一回:7/19(土)初回13:30〜16:30 会場開催(編集工学研究所 ブックサロンスペース本楼)
第二回:7/25(金)07:00〜09:00 オンライン講義(zoom)
第三回:8/29(金)07:00〜09:00 オンライン講義(zoom)
第四回:9/26(金)07:00〜09:00 オンライン講義(zoom)
第五回:10/5(日)最終13:30〜16:30 *会場開催(編集工学研究所 ブックサロンスペース本楼)
■講義会場(7/19と10/5の会場開催時)
編集工学研究所 ブックサロンスペース本楼
東京都世田谷区赤堤2丁目15−3
■課題図書
以下をご購入の上、ご参加ください。
(1)フリードリヒ・リスト『経済学の国民的体系』(岩波書店)
(2)松岡正剛監修『情報の歴史21 増補版』(編集工学研究所)
└編集工学研究所のサイトからご購入いただくと、検索できる電子PDF版がセットで届きます。
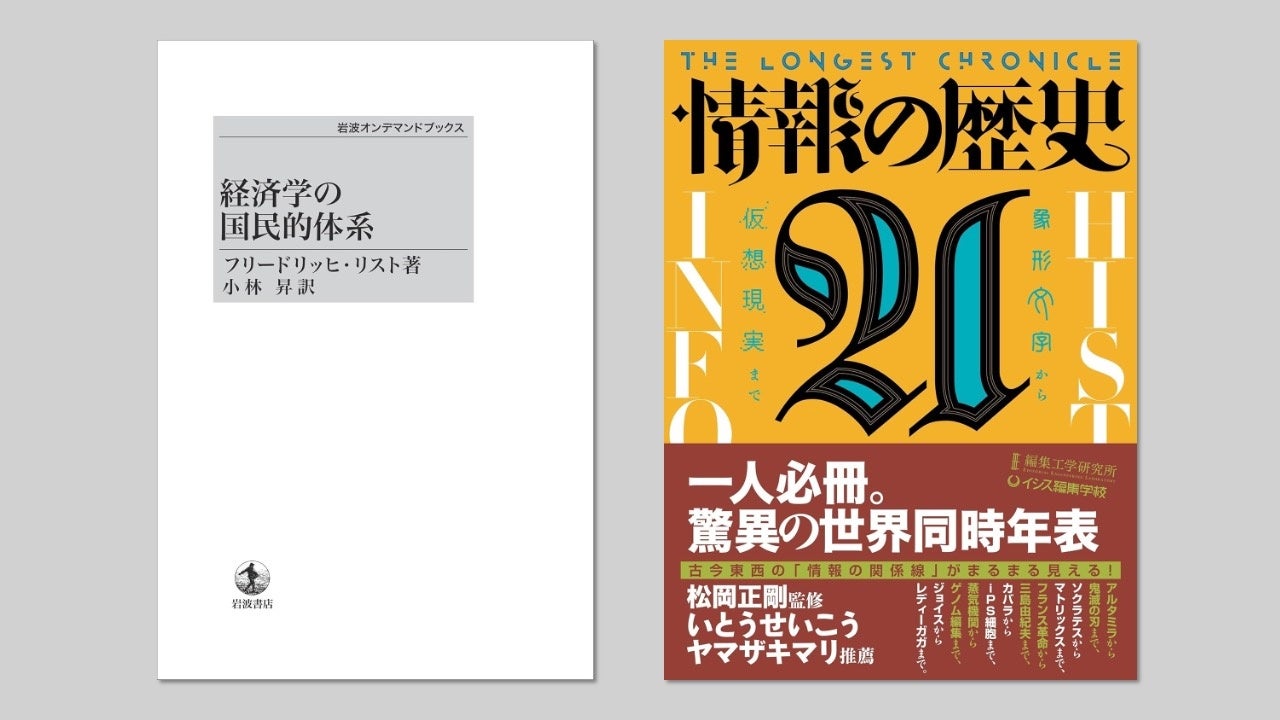
■受講費用
(1)受講生:330,000円(税込)
初回と最終回は編集工学研究所ブックサロンスペース本楼でのリアル会場参加、第二回から第四回はZoomでのオンライン講義になります。
佐藤優氏からの課題講評や、講義中の佐藤優氏とのディスカッション等があります。
(2)オンライン聴講生:165,000円(税込)
全5回とも、オンライン配信の聴講になります。第一回と第五回は本楼会場からの、5台以上のカメラとスイッチングによる臨場感あるLIVE配信です。第二回から第四回まではZOOM画面での配信になります。
*オンライン聴講生は、聴講(オブザーブ)のみです。課題講評や発言はありません。
■募集人数
(1)受講生:28名限定
(2)オンライン聴講生:制限なし
■受講資格
どなたでも受講いただけます。
■お申し込み方法
こちらより、お申し込みください。

Hyper-Editing Platform [AIDA]は、「これから」を担うリーダーたちが集う本気の学び舎です。シーズン6となる2025年は「座と興のAIDA」をテーマに、日本文化の「場の力と創造性」を深掘りします。
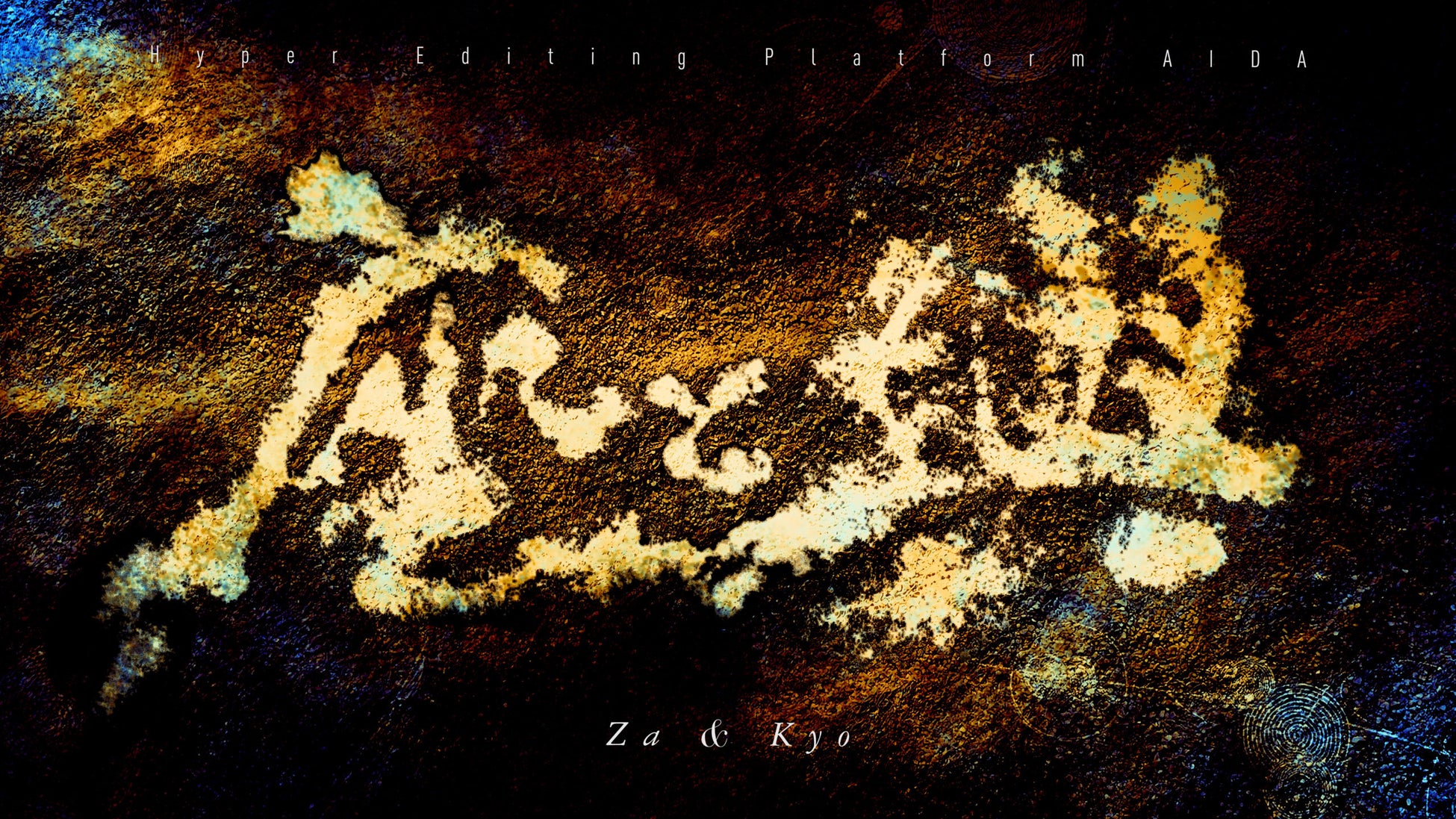
佐藤優氏はHyper-Editing Platform [AIDA]ボードメンバーの一人としてシーズン6も伴走予定です。
ボードメンバーには、佐藤優氏のほか、大澤真幸氏(社会学者)・武邑光裕氏(メディア美学者)・田中優子氏(法政大学名誉教授、江戸文化研究者)・村井純氏(情報工学者)・津田一郎(数理科学者)が名を連ねます。

[AIDA]のボードメンバーである佐藤優さん(作家・元外務省主任分析官)が、「[AIDA]とは何か」を語ったスペシャルインタビュー動画です。
ビジネスに本当の意味で役立つ教養と知識とは? あらゆるモデルが行き詰まっている時代、省みるべきは「未来としての過去」? [AIDA]での学びが唯一無二なのは、なぜか? ぜひご覧ください。
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
「AIDA」という視点で、固定された世界観に切り込み、第一線の知性と混ざり合いながら学ぶプログラムです。自身、日本、そして世界の「これから」を最前線で思考する本気の学び舎は、現在オンライン受講の参加を募集中です。
8月1日(金)20:00〜21:30に、Hyper-Editing Platform [AIDA]シーズン6のオンライン受講説明会を実施します。ぜひご参加ください。
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
■[AIDA]シーズン6 開催日程
第1講 2025年10月11日(土)
第2講 2025年11月8日(土)
第3講 2025年12月6日(土)
第4講 2026年1月17-18日(土・日) *国内合宿
第5講 2026年2月14日(土)
第6講 2026年3月7日(土)
*講義時間は、13:30~19:30(6時間)を予定しています。
*各講の間にオンライン上のラーニングコミュニティ「連」で相互学習に取り組んでいただきます。
■会場
編集工学研究所ブックサロンスペース「本楼」
東京都世田谷区赤堤2丁目15-3
(※)オンライン受講、会場受講のいずれかをお選びいただけます。
■受講料
本楼会場参加 | 1名様につき150万円(税別)
オンライン参加 | 1名様につき60万円(税別)
オンライン参加(合宿現地参加)| 1名様につき85万円(税別) ※こちらはご好評につき満席となりました。
*オンライン参加の方は、第4講は合宿に参加せず記録映像でご視聴いただきます。
お問い合わせは[AIDA]サイトのTOPページ「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。
Season6の詳細&お申し込み資料はこちら。
編集工学研究所では、ニュースレターや各種SNSで最新情報を発信しています。ぜひご登録・フォローください。編集工学研究所ニュースレターはこちらからご登録いただけます。
▼各種SNSもよろしくお願いします。
編集工学研究所 公式X: @EEL_PR
編集工学研究所 youtubeチャンネル: https://www.youtube.com/@EditorialEnginLab
「Hyper-Editing Platform[AIDA]」やその他 編集工学研究所の活動に関する取材を希望される方は、以下へご連絡ください。
株式会社編集工学研究所 広報担当 info@eel.co.jp
株式会社編集工学研究所 info@eel.co.jp
〒156-0044 東京都世田谷区赤堤 2-15-3
Tel: 03-5301-2213 │ Fax: 03-5301-2215
HP:[編集工学研究所] http://eel.co.jp
編集工学研究所 公式X: @EEL_PR
(編集工学研究所ウェブサイトより転載)
山本春奈
編集的先達:レオ・レオーニ。舌足らずな清潔派にして、万能の編集ガール。定評ある卓抜な要約力と観察力、語学力だけではなく、好奇心溢れる眼で小動物のごとくフロアで機敏な動きも見せる。趣味は温泉採掘とパクチーベランダ菜園。愛称は「はるにゃん」。
田中優子×安藤昭子 特別対談「AI時代の編集力」– AIの思考プロセスが可視化された今、人間を支える命綱は「編集力」
ChatGPTの最新モデル「GPT-5」が登場し、いよいよAIとの共生方法が問われるようになってきた。特に意識せずとも、AIを活用した技術にすでに囲まれて暮らしている私たち。こうした時代において、AIがもたらす情報群の中 […]
【変革期のリーダーたちへ】学びに”没入”させる仕組みとは?——Hyper-Editing Platform[AIDA]の「場づくり」の秘密《後編》
〜オンラインなのに“空気”が伝わるのはなぜか?––––「黒膜衆」の編集力〜 既存の枠組みを超えて思考するビジネスリーダーのためのリベラルアーツ・プログラム「Hyper-Editing Platform[AIDA]」(以下 […]
【変革期のリーダーたちへ】既存の思考を”壊す”––Hyper-Editing Platform[AIDA]が示す新たな学び《前編》
〜教えない、導かない。でも変わる——“一座”で学ぶ[AIDA]の挑戦〜 複雑なものを複雑なままに——動的な世界を相手にする力を、物事の「間(あいだ)」に注目することで身につける「Hyper-Editing […]
[AIDA]ボードメンバーからのメッセージ公開。なぜいま「AIDA」が必要か?
編集工学研究所がお送りする、リーダーたちの本気の学び舎、Hyper-Editing Platform[AIDA]。 [AIDA]では毎期、各界の有識者のみなさまに「ボードメンバー」としてご一緒いただきます。 […]
「これから」を担うリーダーが集う本気の学び舎、Hyper-Editing Platform [AIDA]を覗き見たことはありますか? 6月19日(木)に編集工学研究所からプレスリリースを配信しましたので、エディスト読者の […]







コメント
1~3件/3件
2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。
2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。