『性別が、ない!』新井祥
LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。




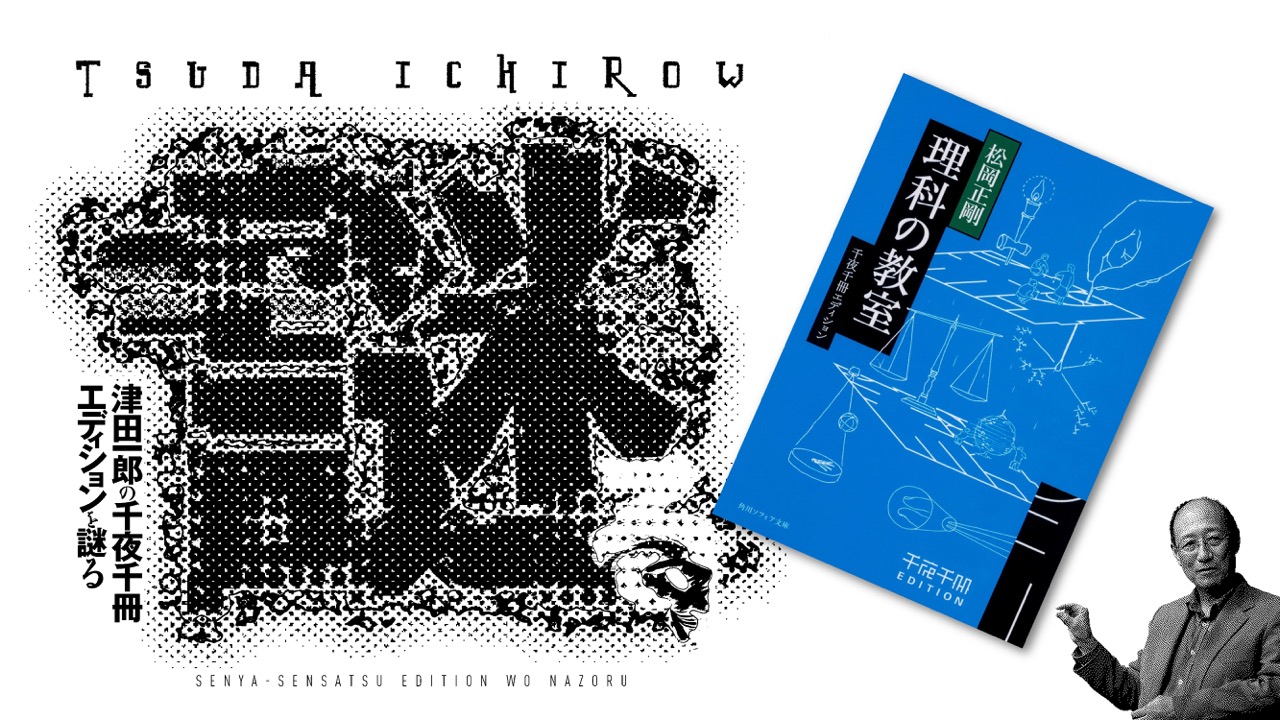
教科書って何だ
松岡さんと私は科学においても似たような志向性を持っていたようだ。それはこの『理科の教室』の目次を見れば一目瞭然だ。さて、今回はP.25を見てハッとしたという話から始めよう。2003年の出来事をありありと思いだしたのである。松岡さんはここで、高校理科の教科書作成にかかわることになったことを告げる。実はこの時、私も東京書籍に呼ばれていて赤羽の本社で松岡さんとバッタリ会ってお互い顔を見合わせたのだった。「僕がおエラい先生にまじって「理科基礎」の教科書の監修者に選ばれたのだ(もう一つ「理科総合」が新設された)」と書いている(第1683夜、『理科の教室』pp.21-37のp.25;p.396)。そう、松岡さんは理科基礎と理科総合の監修者。この“おエラい先生”には当然ながら私は入っていない。私もおエラい先生に交じって、「物理I,II」と「新編物理I」の三冊の監修者になった。2003年と言えば、私は北海道大学理学部数学科の教授になって10年目の年で、数学に軸足を移していたので、まさか物理の教科書にかかわるとは思ってもいなかった。松岡さんと顔を見合わせ、「ほんとにオレたちでいいんだろうか?」とユニゾンになった。「ツダさんは物理出身だからいいけどね、こっちは編集者だからね。いやあ、時代が変わってきたね」と松岡さん。「悪いことじゃないですよ」と私。松岡さんが書いているように、一通り教科書を見回してみると、何とつまらない教科書ばかりであったことか。「これじゃ、だめだね。変えなきゃね。だからオレたちなのかな」と松岡さん。「昔はもっと面白かったんですがね。僕が高校の頃は実教出版の物理の教科書なんか読み物風でよかったし、アメリカではスプートニクショックで高校、大学の教科書を変えようというんで、PSSC物理なんかが作られて、そんなのも見て面白がってました」と私。「そうそうPSSC物理ね。あれは良かった」と松岡さん。こういう話がスプートニクショック、旧ソ連の物理学、特に中央公論社の科学雑誌『自然』に載っていたカピッツァ問題集、さらにはランダウ=リフシッツの物理学教程、そしてファインマン物理学へと続いていった。
さて、それで我々が監修者として参加して教科書がよくなったかと言えば、それが大いに疑問なのである。監修者が全体構成のアイデアを出せればよいのだが、すでに前の改定のときの構想の下で教科書執筆は行われており、いまさら大幅な変更を行うことはできない仕組みになっている。さらに、我々がその時出した全体構想は次に生かされる可能性のある議論のまな板には乗るのだが、その場にはすでにわれわれはいない、という仕組みなのである。これでは思い切った教科書改訂はできるはずもない。そもそもが文科省検定があるのだから、そこを通過するという別の努力が必要になり、それこそ、それは別種のおエラい方々の仕事なのである。それで、松岡さんは「これはもう自分で作るしかない」と思ったに違いない。理科でもなく教科書でもなく、むしろバイブル的なのだが、イシス編集学校 世界読書奥義伝[離]秘伝の『文巻』はその帰結なのではないだろうか。
この教科書作成の縁を思い出したのは、松岡さんが千夜千冊したオストワルドの『化学の学校』のところだ(上掲)。ここで化学の教科書としてどうしても紹介しておきたいのは『実感する化学』(上下二巻)だ。残念ながら、日本の教科書ではなくアメリカ化学会作成の教科書なのだが。原題はChemistry in Contextという。まことにセンスのあるタイトルだ。日本語訳もセンスが良い。この教科書がすごいのは、福島第一原発の事故が起こったら、すぐさまそれを取り上げて原子力エネルギーはもちろんのこと原子力政策についても考えさせる内容になっていることだ。新しい事態が起これば改定する。彼らの根本思想はこういうことだろう:化学を学ぶということは、単に実験室で化学反応を経験するだけではなく(それでは化学が分かったことにはならない)、現実の社会で起こっていることの中に化学がいかに関わっているかを実感することによってである、と。昔、物理学にはよい教科書があった。松岡さんも触れている朝永振一郎の『量子力学 I』とディラックの『量子力学』だ(第67夜、『理科の教室』pp.84-92)。松岡さんの解説のニュアンスとはちょっと違うのだが、少なくとも我々の時代は、日本人学生はディラックを読み、イギリス人学生はトモナガ(日本語の英訳)を読んでいた。それを知って、私はディラックを読んだ後朝永も読んでみたが、これが実に素晴らしかった。物理学に物語を感じるような教科書なのである。対してディラックは鮮やかな形式で量子力学の深みを軽く見せるのに成功している。この深さと重さのバランスが教科書には必要なのである。トモナガとディラックを精読して、本当の量子が分かるのだろうと、その時思ったものだ。
ディラックは記号による簡潔な形式で物理学の法則を表すことで、直観的に捉えにくい物理の本質的な姿を心に描き出そうとつとめた。トモナガは自然から提出された謎を解く道行、すなわち難所を乗り越えるためにあつらえてきた方法や見方の叙述によって、物理学者の世界への向かい方を示している。
同時代を生きた二人は異なるアプローチをとったものの、「物理学者が新しい理論や考えを生み出すために」という共通の眼差しも持っていた。
出典
左図版:Wikimedia Commonsより
右図版:Wikimedia Commonsより
量子と一体化する?
朝永さんの本の中では、松岡さんがすでに千夜千冊(前掲)しているように、『鏡の中の世界』の中の「光子裁判」と最晩年の『物理学とは何だろうか』は教科書の形では書かれていないが、教科書にしてよい本だと思う。前者は量子の本質がミステリー仕立てであかされているし、後者は特に熱力学の考察が秀逸である。朝永さんがこの最後の本の出版直前の物理学会の総合講演(1979年3月)で、発熱をおして「どうしても、物理学会員諸君に伝えておきたい」と言われ登壇されたのには感動した。『物理学とは何だろうか』(1979年5月(上)、1979年11月(下)出版)に書かれた内容の講演だった。それからすぐ1979年7月に亡くなったのだから、まさに物理学会員、物理学会への遺言だったのだろう。
松岡さんは朝永さんの科学には物質の気分というものに対する感知があるようだと述べている。まさに、これは言いえて妙である。我々数学や物理をはじめ自然科学を学ぶものは、研究対象と一体化しないといけない。物理なら分子や原子の中に入り込みまるで自分が原子、分子になったつもりで研究するのだ。むろんこれがいつもうまくいくとは限らないし、そこまで内部観測ができるわけでもない。しかし、朝永さんくらいのハイセンスになると、常にそうやって物理をやっていたんだろうと容易に想像できるのだ。朝永さんはライプチッヒ大学のハイゼンベルクのところに留学した時に、西洋人の科学のやり方についていけないとぼやいた。割り切り方がまねできないと言って悩んだ。松岡さんも、ド・ブロイの物理は俳諧趣味があるが、ボーアやハイゼンベルクの物理にはそのようなものはなく徹底的に説明し切ってしまう、と物理学者の趣向の違いを寺田寅彦が引用した「無常迅速」を引き合いに出して切って見せた(第660夜、『理科の教室』pp47-58)。俳諧趣味のある朝永さんもハイゼンベルクの行列力学をいくら学んでも原子、分子の中に入り量子を“実感する”ことは難しいと感じたのではなかっただろうか。それに加えて、インドからの留学生の冬山での死に対するあまりにもあっさりとした割り切り方に西洋合理主義の冷徹さを感じ取ったようだ。朝永さんが『物理学とは何だろうか』で熱力学を統計力学から理解する努力、とりわけボルツマンの業績を丹念に追いかけているところに松岡さんは震撼した。そして、その理由をいつか書いてみたいと綴った。永久にその機会が失われたのは残念、いや無念というほかない。
ドイツには量子の扉を開けたマックス・プランクの名前を冠した研究所がたくさんある。マックス・プランク物理学研究所は当初ベルリンにあったカイザー・ウィルヘルム研究所が量子の発見者であるマックス・プランクの業績をたたえて改名したものだが、第二次大戦後にベルリンからゲッチンゲン、ミュンヘンへと移っていった。マックス・プランク物理学研究所の初代所長になったハイゼンベルクの愛用のソファーが、ゲッチンゲンのマックス・プランク物理学研究所の“プラントルの部屋”にある。プラントルがハイゼンベルクから譲り受けてその後プラントルが使っていたそうだ。ルートヴィッヒ・プラントルは流体力学のプラントル数で有名な物理学者であり、流体機械の設計者としても有名である。”プラントルの部屋“にはこの設計図がたくさん展示してある。私もゲッチンゲン大学の数学教室に呼ばれたのを機にマックス・プランク物理学研究所でも講演した。この時、このプラントルの部屋を使ってよいということで鍵を渡された。中に入ってみてハイゼンベルクのソファーがあるのでびっくりしたが、しばしそこに座ってハイゼンベルク・プラントルのソファーを構成する原子が発する量子の波と一体化するという至福の時を過ごしたのだった。
写真:2006年7月、ドイツ、ゲッチンゲンのマックス・プランク物理学研究所内のプラントルの部屋。左:ハイゼンベルクのソファー、右:ソファーが入っているプラントル教授室の扉(写真は筆者による)
物理の神髄を拡散させるガモフ
さらなる偶然。それはガモフの『不思議の国のトムキンス』だ。松岡さんは1966年、早稲田の二年か三年のころこれを読んで驚喜した。文学、哲学から物理へと目覚めた衝撃の一冊だったそうだ(第768夜、『理科の教室』pp.93-104)。実は私は1969年秋、高校一年生のときに高校の図書室で偶然この本を見つけて、読み始めたら止まらなくなった。私も物理に目覚めたのだ。おそらく同じ版の本だと思う。私たちの高校は学生運動が盛んで、同級生の何人かを加えた10人くらいが理科教室(!)を占拠したのがきっかけで、授業はすべてストップ。毎日がクラス討論会だった。それでつまらなくなって教室を抜け出した。大好きな理科教室が占拠されたのでしかたなく図書室にこもったのだ。一人で図書室を“占拠”した。授業がないので、一日中閉じこもってこのガモフに夢中になったことを思い出す。これで味を占めて、しばしば図書室を占拠した。このとき、『ガロアの生涯—神々の愛でし人』(L.インフェルト著、日本評論社、1969年)を図書室の書庫で見つけて、これも夢中になって読んだ。ガロアは群論を創始した天才数学者であり、数学における革命児であるとともに政治的にも革命家であった。決闘で亡くなった理想主義者であった。伝統や権威、権力を嫌う姿に時代の雰囲気も手伝って引き込まれたのだった。またある時、興味とは異なるのになぜかスタンダールの『赤と黒』(第337夜、『物語の函』pp314-325)を見つけて読了したことを思い出す。この二人の共通項は1830年のパリ7月革命である。
“知の目印”を求めて
またしても偶然。松岡さんは鉱物フェチであった(第119夜、『理科の教室』pp123-127)。中学生のころに小さなポケット鉱物図鑑を持っていた。これが私と全く同じなのだ。私もポケット鉱物図鑑を持っていた。小学校くらいから持っていたから、年代を考えると同じものではないかと思う。田舎の家だったので、家のいろんなところに変なものが落ちている。実際は仕舞ってあったのかもしれないが私には“落ちている”と見えたのだ。何種類かの鉱物が収めてある箱が落ちているのを発見して興味を持った。それで父親がポケット鉱物図鑑を買ってくれたのだと思う。私は中でも石英と黄鉄鉱が好きだった。うーん、これも松岡さんと同じだ。特に黄鉄鉱は眺めても飽きなかった。松岡さんは少年にとっては心の中に「知の目印」を持つことがとても大切であるという。それが冒険の始まりなのだという。なるほどうまいことをいうもんだと感心して、自分が少年だったころ身近に置いて親しんだ道具を書き出してみた。
「魚とりの網」、これを昆虫採集にも使っていた。捕虫網も買ってもらったが、無意味にでかいと思って好きになれなかった。人間の頭だって入るものを何で虫をとるのに使うのか、子供の私にはさっぱりわからなかった(虫が大好きな人が聞いたらひっくり返るだろう。むろん私だって今ならその理由はよくわかるのだが)。「望遠鏡」、これで月をさんざん眺めた。ウサギの餅つきも確認した。土星の輪も不明瞭ながら見ることができた。「天文図鑑」で、望遠鏡では見えない星がたくさんあることを知った。赤色巨星や白色矮星という言葉もこの図鑑で知った。天文図鑑は何時間見ていても飽きなかった。太陽がこんなに小さく、さらに大きな恒星があることにワクワクしたものだ。宇宙のかなたに思いをはせるに余りある書物だった。「ポケット鉱物図鑑」、これはほんとにボロボロになるまで持ち歩いていたように思う。道端やいろんな家の縁の下に落ちている石と見比べた。近くの山に行って黄鉄鉱を捜し歩いた。それもあって、砂鉄に興味を持った。「U磁石」も持っていて、砂鉄を集めて磁力が作るパターン形成や奇妙な動きにドキドキしたものだ。虫を取って標本を作りピンでとめた昆虫の細密画を描くことに夢中になったこともあった。そのために「顕微鏡」、「ルーペ」、「ピンセット」、「注射器」、「押しピン」は常に持っていた。こう見てくると、かなり松岡さんと重なっていることに気づく。
私が30手前、松岡さんが40手前のころに出会い、全く専門分野が異なるのに意気投合した、その理由がわかったような気がした。「知の目印」が接近していたのだ。最接近といってもよい。それを補強する証拠がある。『理科の教室』のとっぱしにマイケル・ファラデーの『ロウソクの科学』(第859夜、『理科の教室』pp.12-20)を松岡さんは編集した。これはクリスマス講話であり、一般市民向けだが、実に科学の本質を突く話が載っている。私もこの本を中学生の頃に読んで一見複雑に見えて原因の在りかがぼんやりしている現象に鮮やかな一本の糸を通す技に感動したのを思い出す。さらには、「寺田寅彦こそ編集学校の初代名誉校長である」と断言するくらいの寺田物理学への愛着である(第660夜、『理科の学校』pp.47-58)。松岡さんは千夜千冊の出発を寺田の弟子の中谷宇吉郎の「雪」にしたとき(第1夜、『理科の教室』pp.59-63)、数学者すべてが敬愛する大数学者、アンドレ・ヴェイユの妹であるシモーヌ・ヴェイユの「メタクシュ」を中谷が見た雪の中に感じ取った。この「メタクシュ」こそが関係の学問である複雑系科学と編集工学をつなぐ間の概念である。
セイゴオ自ら作った鉱物の標本箱。
石の大きさに合わせてタバコの火で穴を開けて、石をはめ込んで作られた。
図版構成(カオス的編Rec):梅澤光由、稲垣景子
津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る
③『理科の教室』で偶然の一致あるいは縁を謎る
津田一郎
理学博士。カオス研究、複雑系研究、脳のダイナミクスの研究を行う。Noise-induced orderやカオス遍歴の発見と数理解析などで注目される。また、脳の解釈学の提案、非平衡神経回路における動的連想記憶の発見と解析、海馬におけるエピソード記憶形成のカントールコーディング仮説の提案と実証、サルの推論実験、コミュニケーションの脳理論、脳の機能分化を解明するための拘束条件付き自己組織化理論と数理モデルの提案など。2023年、松岡正剛との共著『初めて語られた科学と生命と言語の秘密 』(文春新書)を出版。2024年からISIS co-missionに就任。
津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑨ 『編集力』で負を謎る
アフォーダンスと環世界 アフォーダンスは編集工学の3Aの一つだ。環境が生物に与える行動的意味や価値のことだ。アフォーダンスは知覚者の状態には依存しない。ギブソンの本来の考えとして、アフォーダンスは生物と環境の間にある行為 […]
津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑧ 『編集力』で真似るを謎る
富田のLIFEとエディトリアル 松岡さんは、折に触れ「オリジナリティー」よりも「真似る」ことの重要性を強調してきた。『編集力』でもこのことを強調する箇所が多々ある。そもそも「アナロジー」や「ルイジとソージ」、「擬き」など […]
津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑦ 『編集力』で言語の境界を謎る
生成系AI(LLM) v.s. チョムスキー 今や多くの人が生成系AI(以下、AIと略す)を使って何らかの仕事をする時代になった。編集にも、論文校正にも、ちょっとした疑問点にも、研究にも参考になる視点を与えてくれる。人に […]
津田一郎の『千夜千冊エディション』を謎る⑥ 『編集力』でアブダクションを謎る
推論=心? 『編集力』には編集工学の技法がいっぱい詰まっている。この450ページを超えるエディションを読み込めば、松岡さんの思想と技法が会得できるのではないか。だとすると、これは恐ろしいエディションである。謎ることすら気 […]
イシス編集学校アドバイザリーボード ISIS co-missionメンバーより、これから「編集」を学びたいと思っている方へ、ショートメッセージが届きました。なぜ今、編集なのか、イシス編集学校とはなんなのか。イシスチャンネ […]




コメント
1~3件/3件
2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥
LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。
2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。
2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。