棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。




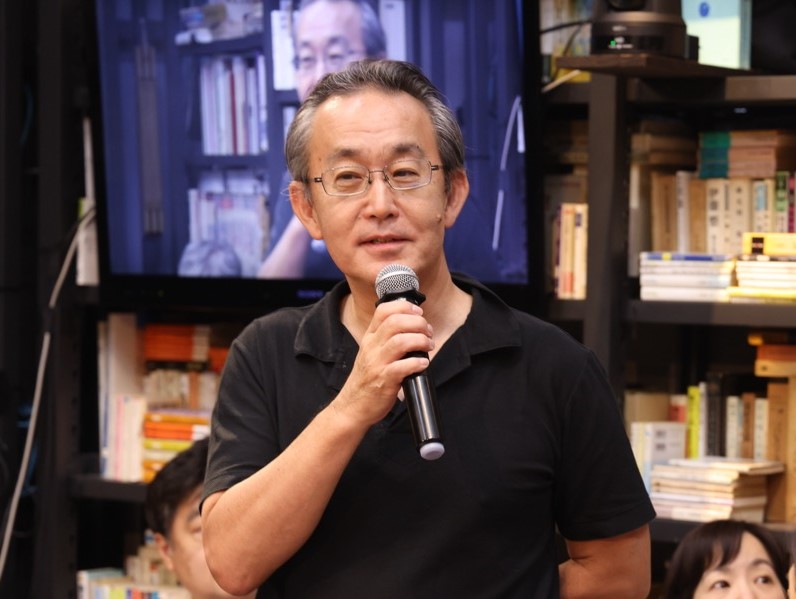
[破]は、松岡正剛の仕事術を“お題”として取り出したとっておきの講座である。だから回答と指南の応酬も一筋縄にはいかない。しかしそのぶん、[破]の師範代を経験すれば、どんなことにも編集的に立ち向かえるようになる――学匠・原田淳子は、普段からそう太鼓判を押している。[破]の師範代たちも、過密な稽古にとことん身を投じながら、おのずと遠くをまなざすようになる。
「いきいきした回答には必ず守の型が潜んでいる」(新坂彩子師範代)「どんどん閾値を超えていく、限界のインフレ状態が面白い」(稲森久純師範代)「学衆の回答にアフォードされる快感を知った」(矢倉芳夫師範代)。講座の折り返し点にあたる第2回伝習座では、日夜回答に向き合う師範代にしか発せられないヴィヴィッドな声が飛び交った。さらにまた、いまここの教室運営のみならず、「講座のその先」をはっきりと見据えた師範代の姿もあった。
「自分の教室から必ず師範代を輩出すること。これが最大の仕事だと、腹をくくりました」
落ち着いた佇まいでそんな“野望”を口にしたのは、「四一・一・二五教室」師範代の束原俊哉である。束原は51[守]師範代のときから「方法の身体化」と「表象の磨き込み」を目標に掲げてきた。Hyper-Editing Platform [AIDA]の座衆でもある束原は、今期[破]の師範代ロールも担うなかで、「編集の社会化」と「社会の編集化」の必要性を切に感じるようになったという。上記の言葉もその想いに根差している。これまでは無理やり師範代輩出を目指さなくてもよいと思っていたそうだが、師範代仲間を増やすことがこの社会をよくすることにつながるという確信から、この2カ月で、束原の中に小さからぬ視座の転換が起こったようだ。
「なにか大きなことを言ってしまったかもしれません」。終盤、はにかみながらそう振りかえった束原だったが、彼の決意は、チーム師範代・渋谷菜穂子に同じ“野望”を抱かせるだけの感化力をもっていた。師範代輩出をアンダーシナリオに置いた編集プロセスは、これを機にチームでの連携も加わって、いっそう愉快・痛快に加速してゆくことだろう。
▼束原師範代と渋谷師範代。最近チームラウンジでやりとりするなかで、なんとふたりとも、まったく同じ建物の異なる階で働いていることが判明したという。さすがに運営側もそこまでは仕組めない。完全なる偶然から生じたチーム編成であった。突破および「その先」に向けての戦略会議は、今後ますます盛んになっていくにちがいない。
写真:後藤由加里
バニー新井
編集的先達:橋本治。通称エディットバニー.ウサギ科.体長180cm程度. 大学生時に入門後、師範代を経てキュートな編集ウサギに成長。少し首を曲げる仕草に人気がある。その後、高校教員をする傍ら、[破]に携わりバニー師範と呼ばれる。いま現在は、イシスの川向う「シン・お笑い大惨寺」、講座師範連携ラウンジ「ISIScore」、Newアレゴリア「ほんのれんクラブ」などなどを行き来する日々。
門を感じて、門に入(い)る。門をくぐって、門をひらく。 イシス編集学校の設立から四半世紀。3月末に開催される感門之盟も、ついに90回目を迎えます。 感門之盟という名は、王羲之の「蘭亭の盟」に肖っています。豪徳寺本楼 […]
準備も本気で本格的に。それがイシス流である。 感門本番まで残すところあと2日、これまで個々に用意を重ねてきた[破][花]の指導陣が、いよいよ本楼に集って全体リハーサルを行った。音響、立ち位置、登降壇順、マイク渡しに席 […]
感門準備の醍醐味は、手を動かし口も動かすことにあり。 8月最後の土日、[守][破][花]指導陣の有志(感門団)で豪徳寺学林堂に集まって、一週間後に控えた感門之盟の下準備に入った。ペットボトル300本に感 […]
「守をちゃんと復習し終えるまで、破へ進むのはやめておこう……」 卒門後、そのように考える慎重な守学衆が毎期何人かいます。けれども、コップに始まりカラオケへ至った学びのプロセスによくよく照らしてみれば、「立 […]
◆感門タイトルは「遊撃ブックウェア」 読書はなかなか流行らない。本から人が離れてゆく。読書はもはや、ごく一部の好事家による非効率でマニアックな趣味にすぎないのだろうか? 読書文化の退行は今 […]




コメント
1~3件/3件
2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。
2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。
2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。