鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。





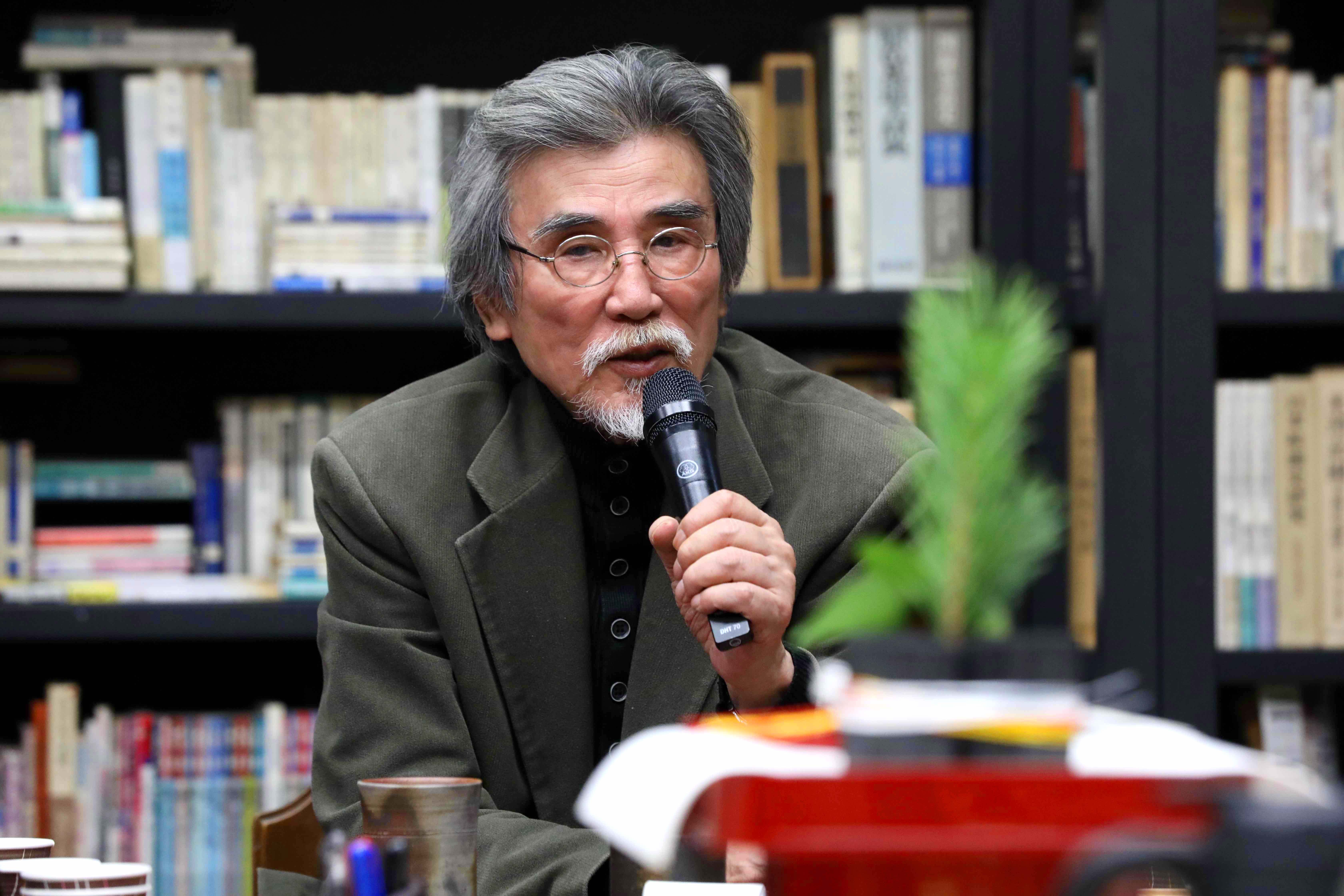
「今年はガンガンやった方がいい」。
編集工学研究所の新年会で同所所長・松岡正剛はそう口を開いた。「今年の後半から来年の頭にかけて、編集工学が時熟する可能性が高い。ぼくも色々とコアコンピタンスを明らかにしていくつもりだ」。
昨年末の千夜千冊エディション『編集力』出版を先駆けに、今年は編集学校・編集工学のメディア露出も増えることになっている。すでに年始から教育新聞での連載もスタートを切った。折しも巷ではメディア・広告業界を中心に「編集」というコンセプトが注目を集めつつある。本年は社会の要請とイシスでの熟成が重なる可能性がありそうだ。
そんな機運が高まる令和2年目の1月6日。松岡は編集ブレイクの前に、やっておくべき五箇条を語った。

年頭メッセージを語る松岡正剛と聴講するスタッフ
しつらいは渡辺文子と和泉佳奈子による。
[1]とにかく徹底する
自らの仕事や実験、表現を追求することはもちろん、他人のどんな可能性についても徹底していくこと。自在・他在を問わず、どんなところでも徹底的にネットワーキングやリンキング、トレーシングを行うことで、創発が起こる。
[2]ハイブリット性を意識する
非一貫、非純粋、非正当。混じり気のある編集クレオールこそ今必要だ。抱える普遍より、放つ普遍を。異質な普遍性が持つ、動的な速度の中に、一気呵成の編集力が潜んでいる。
[3]リアル・ヴァーチャルをつなげる
VR時代のヴァーチャル・リアリティは面白くない。単なるデジタリゼーションではなく、ヴァーチャルでのもてなし・ふるまい・しつらいを今一度熟慮すべし。
[4]観客を用意する
全国の師範、師範代の目、遊刊エディスト、外部のメディアなど、ショーイングを見越して何かに晒される状態を維持すること。出来る限り、読む・書く・借りる・描くを連続的にこなしてみると良い。すると自分の得意手が見えてくる。特に「借りる」が重要。
[5]本の見方を変える
本は全人類史の束だ。なのに今だに何もされていない。恐ろしい読書家の小学生が出てきてもいい。百冊読みがゲーム化されてもいい。本のラッパーが出てきてもいい。本をもっとドラマチックにしなさい。
以上の五箇条を前段として、編集工学はある種の「ゲーム化」へ向かっていくという。今年は東京オリンピック・ムードが際立っているように、ゲーム性のあるものは巻き込み力が高い。もし〇〇立国というものが可能ならば、それは日本中を巻き込めるゲーム性が問われるべきだ。それは編集においても同様だろう。
編集工学的に見れば、ゲームとはスコア(得点・評価)を奪い合うフォーマットだ。それ自体はあくまで敷物のようなものであるが、ルール・ロール・ツールが組み込まれることでシステムとなる。すると自律的に意味や物語を生み出すようになる。「だからこそスポーツも将棋もドラマチックになるんだ」と松岡はゲームの有用性について語った。「単なる整数の得点は面白くない。小数や分数といった微妙なもの。記号や暗号、物語から一茶の句までなんでもスコアとなりうる。大胆なスコアリングを考えてほしい」。
今年の松岡は、角川武蔵野ミュージアムの館長にも就任し、新たな執筆や企画も構想中だという。未だ誰も見てこなかった編集の核心が示されていく年になるだろう。「諸君の一気呵成の編集にも期待します」とスタッフやイシスメンバーの背中を押した。

スタッフ一同、世田谷八幡宮にて
「遊刊エディスト」トップページ
穂積晴明
イシス編集学校方源、編集工学研究所デザイナー、「おっかけ千夜千冊」の千冊小僧。『情報の歴史21』『知の編集工学 増補版』ほか、編集学校のあらゆるものをデザインするが、疲れ目に祟り目でたまに目にカビが生える。
【オツ千vol.55 外伝】ムナーリでペアーノなデザイン探訪
「おっかけ!千夜千冊ファンクラブ」。ちぢめて「オツ千」。今回は『パターンの科学』のオツ千投稿に合わせて、小僧がブルーノ・ムナーリのデザインの秘密を紐解きます。「数学では何の役にも立てませんでした」と傷心する小僧の面目躍 […]
「おっかけ!千夜千冊ファンクラブ」。ちぢめて「オツ千」。千夜坊主こと林頭の吉村と千冊小僧ことデザイナーの穂積。「松岡正剛の千夜千冊」ファンを自認する二人が、千夜のおっかけよろしく脱線、雑談、混乱の伴走するショート・ラジオ […]
ISIS 20周年師範代リレー [第1期 山田仁 てんやわんやの船出]
2000年に産声をあげたネットの学校[イシス編集学校]は、2020年6月1日に20周年を迎えた。手探りで始まった第1期、学衆から師範代が初めて生まれ、新しい講座、イシスから『物語編集力』、15周年では『インタースコア』 […]
セイゴオ、刻まれる!?松岡正剛映像シリーズ「Cut Up Books」配信開始
Jamiroquaiのジェイ・ケイが、デヴィッド・ボウイ「Let’s dance」のパロディで「Lockdown」を歌っている。「マスクをつけてテレビでも見よう」と美声を聞かせるピンヒール姿の中年は、SNSで結構な話題 […]
「集え!編集遊者諸君!」バジラ高橋と行く輪読クエスト《古河探訪篇》
「編集は冒険から始まる」というが、知の冒険には読書が最適だ。イシス編集学校の輪読座はこれをディープに引き受けている。万葉集、空海、折口信夫、西田幾多郎、井筒俊彦などの「レジェンド級」知的モンスターを毎シーズン相手取り、 […]








コメント
1~3件/3件
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。
2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥
LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。