誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)




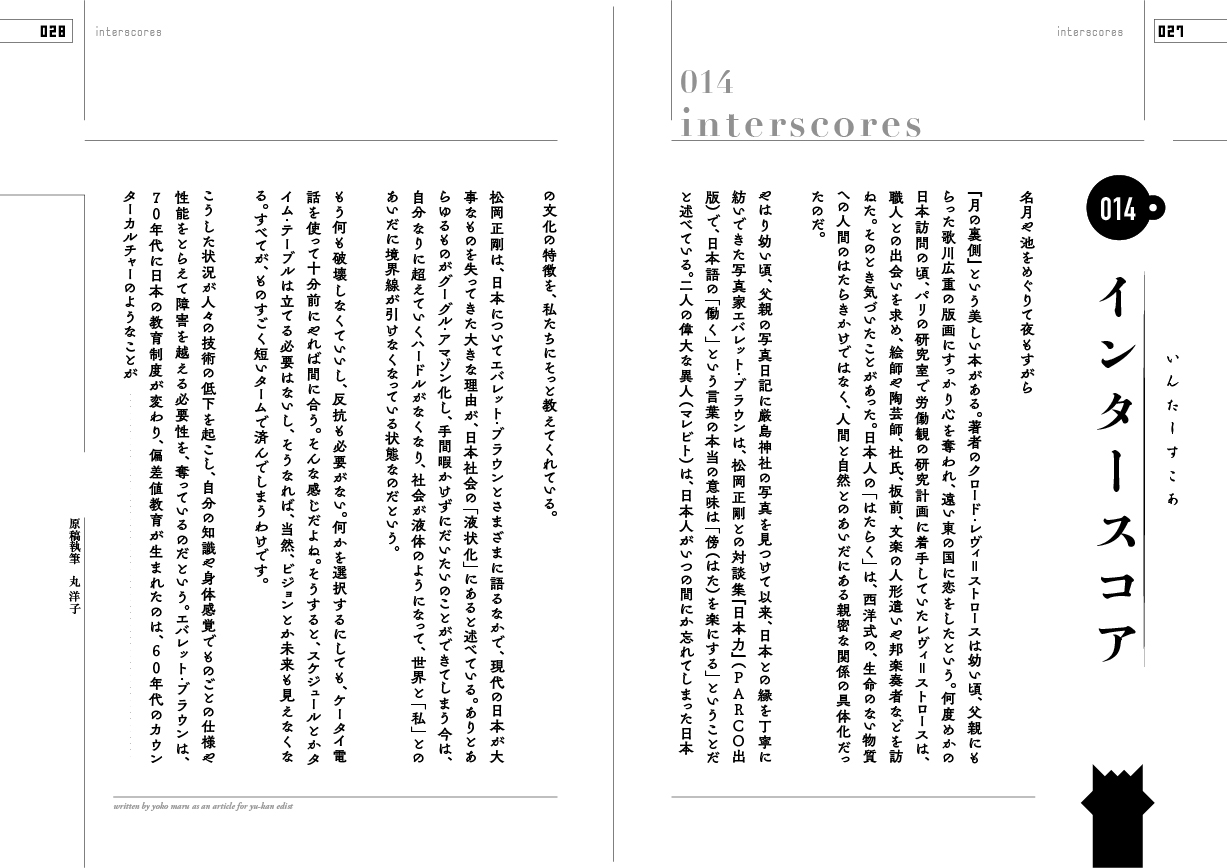
名月や池をめぐりて夜もすがら
『月の裏側』という美しい本がある。著者のクロード・レヴィ=ストロースは幼い頃、父親にもらった歌川広重の版画にすっかり心を奪われ、遠い東の国に恋をしたという。何度めかの日本訪問の頃、パリの研究室で労働観の研究計画に着手していたレヴィ=ストロースは、職人との出会いを求め、絵師や陶芸師、杜氏、板前、文楽の人形遣いや邦楽奏者などを訪ねた。そのとき気づいたことがあった。日本人の「はたらく」は、西洋式の、生命のない物質への人間のはたらきかけではなく、人間と自然とのあいだにある親密な関係の具体化だったのだ。
やはり幼い頃、父親の写真日記に厳島神社の写真を見つけて以来、日本との縁を丁寧に紡いできた写真家エバレット・ブラウンは、松岡正剛との対談集『日本力』(PARCO出版)で、日本語の「働く」という言葉の本当の意味は「傍(はた)を楽にする」ということだと述べている。二人の偉大な異人(マレビト)は、日本人がいつの間にか忘れてしまった日本の文化の特徴を、私たちにそっと教えてくれている。
松岡正剛は、日本についてエバレット・ブラウンとさまざまに語るなかで、現代の日本が大事なものを失ってきた大きな理由が、日本社会の「液状化」にあると述べている。ありとあらゆるものがグーグル・アマゾン化し、手間暇かけずにだいたいのことができてしまう今は、自分なりに超えていくハードルがなくなり、社会が液体のようになって、世界と「私」とのあいだに境界線が引けなくなっている状態なのだという。
もう何も破壊しなくていいし、反抗も必要がない。何かを選択するにしても、ケータイ電話を使って十分前にやれば間に合う。そんな感じだよね。そうすると、スケジュールとかタイム・テーブルは立てる必要はないし、そうなれば、当然、ビジョンとか未来も見えなくなる。すべてが、ものすごく短いタームで済んでしまうわけです。
こうした状況が人々の技術の低下を起こし、自分の知識や身体感覚でものごとの仕様や性能をとらえて障害を越える必要性を、奪っているのだという。エバレット・ブラウンは、70年代に日本の教育制度が変わり、偏差値教育が生まれたのは、60年代のカウンターカルチャーのようなことが二度と起こらないためだったと聞いたことがあると言い、偏差値とは、国民から考える能力を奪うためにあるものではないか、と語る。私たち現代人は、自分なりの価値観や目盛を失いながら、創発的な生活力を衰えさせていっているのである。
■マンガのスコア
情報と情報のあいだに潜むさまざま関係を発見し、自分と世界とのかかわり方を変えていく方法を学ぶ【守】の講座に、「マンガのスコア」というお題がある。お店やマンガに、これまでに存在しない独自の評価単位(スコア)をつくって新しい価値を見いだすお稽古だ。すでに編集が終わっている世界に注意のカーソルを向け、新たな編集をおこしていくことは、スコア化されていない情報を発見することでもある。スコアリングとは、情報に潜む価値に光を当てて明示することだ。このお稽古で、学衆はどんな情報のアウトプットもスコアとして捉えられることを実感する。評価法、判定法、記述法、演算法、分割法などとも言い替えることのできるスコアの意味の広さと深さについて、松岡正剛は『インタースコア』(春秋社)で詳しく述べている。
日記や電話帳、音楽的楽譜、親と子の成長ぐあい、小説や映画の感想文、ダンスやバレエなどのコレオグラフ、ヘアスタイルの変化、家屋や機械の設計図、いたずら書き、野球のスコアブックなどのスポーツゲームの進行記録・・・。これらはみんなスコアだ。
(中略)
情報は“in-form”するものだが、情報がフォームをもっていくというそのすべてのプロセスがスコアであり、スコアリングなのだ。おそらく生体膜によってナトリウムイオンとカリウムイオンを交流させたこと、あるいはRNAがDNAにさせていることが、生命現象としての最初期のスコアリングだったろう。民族や地域や風土によって成立してきたさまざまな言語も、こうしたスコアリングの顛末を示している。そこには声のスコアも文字のスコアも、句読点のスコアもあった。
このように情報のスコアリングはどこにでも、どのようにもおこっているのだが、その記譜や記録もまた、まことにさまざまな多様性をもってきた。歴史のスコアリングが歴史地図になるか歴史年表になるかで、その見た目が大きく異なるように、スコアは記録化のプロセスを受けながら、実に多様多彩なノーテーションに至ったのである。
多様多彩なスコアが、気がつけば世界の価値を規定し、グローバル基準へと収斂されてきている。かつて日本には一尋(ひろ)や一尺といった、身体に基づいたスコアがあったが、今はメートル法のような西洋のスコアを国際標準にしたものが使われているのも、その一例だ。
■インタースコア
イシス編集学校のISISは、interactive system of inter-scores(相互記譜システム/相互記譜的情報編集システム)の略称だ。インタースコアとは、二つ以上のスコアに注目し、これらを「あわせ・かさね・きそい・そろい」にもちこんでみる編集方法のことである。この言葉について、松岡正剛はこう述べている。
インタースコアという用語は新しいが、“インター”はインターナショナル、インターチェンジ、インターミッション、インターカレッジ、インターコンチネンタル、インターディシプリナリー、インターメディエートなどの“インター”と同じで、ようするに「際で交わる」という意味だ。
(中略)
編集学校はその“インター”の感覚をもってスコアをまたぎつつ、相互編集的にスコアリングしていこうというものだ。
――『インタースコア』(春秋社)
インタースコアのもつ驚くべき創発性や相転移は、この書に数多く例示されている。
オシリスとイシスの古代エジプトは、シリウスの伴星の動きとナイル河の氾濫という二つの別々の現象をインタースコアして「時間」を発見したのだし、マックス・プランクはアルザス・ロレーヌの鉄鋼の熔融変化と黒体輻射の変化の関係のインタースコアの記録から「量子」を発見した。ポーランドの難民だったベノワ・マンデルブがフラクタル関数を発見したのは、綿花の市場価格と所得分布の変化をインタースコアしたことによっていた。そこから乱流状態にあるエネルギーの流れは、金融市場のボラティリティ(価格変移の相互値)に似ているということも、しだいに発見されていった。ケインズが利子率の切り下げと社会インフラに対する投資の変化をインタースコアしたことは、金融政策と財政政策を二重に推進するという今日のマクロ経済の基本をつくった。レヴィ=ストロースが婚姻関係と社会構造変化をインタースコアして構造主義を提案したことは、そこから社会における文明観や言語観を研究する人類学の深みを用意した。ぼくはこうしたインタースコアの可能性を、研究や学問の領域だけではなく、どんな場面でも思考できるようにしたかった。
かつて松岡正剛が編集長を務めた雑誌『遊』では、「化学幻想・神道」「方程式・国家論」といった、いっけん関係のない領域を取り合わせた特集が、読者にインタースコアを誘っていた。そして今、イシス編集学校が日常のあらゆる場面へとインタースコアの可能性を広げていく型を伝えている。
■情報の歴史
先日のイベント、「ISIS FESTA『情報の歴史21』を読む」第八弾では、文筆家であり編集者である吉川浩満氏が登壇し、「人間観に関わる諸革命を追う―人類誕生から人工知能まで」と題して語ってくれた。
『情報の歴史21』(編集工学研究所)は、人類がどのように情報を編集してきたかという視点で構成された年表である。吉川氏は講義の中で、認知革命の担い手の一人であるダーウィンに焦点を当てる。年表の「ダーウィン進化論」の見出しを遡っていくと、「ダーウィン、ビーグル号で世界周航」や「ダーウィン、マルサスの『人口論』を読む」という記載があり、ダーウィンの進化論がどのようなインタースコアによって誕生したのかが、リバース・エンジニアリングできるのだという。松岡正剛は吉川氏のレクチャーを受け、情報の歴史は、ほとんどがトークンの交換の歴史であると説いた。トークンとは、たとえば文字や線分、言葉、貝殻といった媒介物のことで、そうしたスコアを媒介して、人は何かと何かを交換することができる。ダーウィンは、あるトークンを使ってマルサスの人口論とインタースコアできたのだという。だから情報の歴史のクロニクルを読むときは、できごととできごととの境界を、ぜひ発見してほしいと語った。
かつてレオナルド・ダ・ヴィンチは『手記』にこう記した。「物体の輪郭はそれの一部分ではなくて、それと接する他の物体のはじまりである。かくのごとく交換的に、何の妨害もなく前者と後者とは互いに輪郭となりあう。」大きな歴史のうねりの中で、いくつものカオスの縁が共振しては、インタースコアによって相転移を起こしているのである。
■日常の中の非日常
宇宙物理学者の佐治晴夫と松岡正剛があらゆる領域を自由に行き来しながら語り合う『二十世紀の忘れもの』(雲母書房)では、ふだん伏せられている脳のカオスの縁に立ち、「あいだ」となるトークンを日々の中で見つける方法について触れている。
松岡:ぼくはエディターが本職ですから話し合っているとだいたいわかるんですが、一般的に、ある人の中には周期的に回っている言語があるんです。ある言語があるカオスを伏せたまま、つねにその周りをずうっと回っているんですね。この話もあの話もその周期の中だけで回っている。本人はいろいろ説明したり、解いたり、自慢したり、あるいは自信を消失したりするつもりになっていますが、そのカオスの「縁」に、ほとんどの問題が出ていましてね。だからブレイク(脱却)がないんですよ。
佐治:なるほど。それは何となくわかります。自分自身のことを考えてみても、私が言っていることをもう一回テープで聴いたりすると、たしかにそれを感じますよね。
だからそういうときに、そこからポンと飛ぶための材料をどこに見つけるかというのが、センスみたいなものですよね。そうなると、いわゆる日常的だったものの中に非日常を見てポンと飛べて、またそれが日常的なものになってということで、わりとつじつまが合うけれど、それが脈絡なくなっていったときに、ちょっと問題になるんじゃないでしょうかね。
松岡:それの解決方法はさっきすでに言われているんですが、実際に170キロを出して運転しているときの自分の視点を、いまの状態にいながら170キロの外側の視点で想定できるかということにかかっていると思います。
体験をバラバラにしないことですね。とくに快感のあった体験をつなげていけるかどうか。バルトークを聞いたことと自転車で土手を走ったことの、その両者の視点を同時にもって、自分を含めた世界を再記述する側にまわれるかどうかだと思うんです。しかもそれをゆっくりやったのでは、おそらくダメだと思う。自分のテンポに合わせて自分のできるときにやろうと思っているかぎりはダメで、むしろ、異常というとちょっとまずいけれど、ちょっとつんのめらないといけませんね。
(中略)
佐治:なるほど。ですから、それには小さいころの教育とか、いろんなことが絡むのかもしれませんけれどね。さきほど自分の内なるものと外なるものとの間に、バーチャルなというか、なにか共通性を感じていくということがあったでしょう。
私がそれに気がついたのは、こういうときなんですよ。それは高村光太郎のひとことでした。「焚火にあたるように太陽の光にあたる」と言っているんですね。やはり、私たちは日光浴とかいうと、ただの日向ぼっこで終わってしまう。太陽に向かうとき、「焚火にあたるように」というあの感覚がないんですよね。やはりその視点を延長線上においておくと、たとえば天文台でいろんな方によく昼間の星ではなくて昼間の月を見せることがあります。青空の中にある月というのは、ほんとうに立体的で夢のように見えるわけですね。何というか、シャボン玉でもないし、とにかく淡くてきわどいね。もう、さわると壊れそうな、ほんとうにきれいな月が見えるわけです。
松岡:「たまらんなあ」というやつですね(笑)
佐治:その月を見たときに、何がイメージできるかということだと思うんですね。たとえば小さい子の頬っぺたをさわってみると、とっても弾力性があって、かわいくて、暖かいものをそこに感じることができるとか。あるいは、よくつくられた和菓子の「求肥」のようなものを思い浮かべることができるとかね。
松岡:まさにそういう体験に出会えると、境界を怖いと思いながらやって来たものと、いま言われたような、“ほたほた”したね、境界を超えるような「いずれアヤメかカキツバタ」みたいなものを、同時に感じられますね。
佐治:それはある意味ではエクスチェンジ(取り交わす)できるんですよね。だから、やっぱり月を見ていて、「ああ、あの月にそっと触れてみたい」という感覚は通常の感覚の中に出てくる。
(中略)
松岡:もうひとつね、さっきの内と外を超える、あるいは両方を入れる、ブラックホールのシュヴァルツシルト半径の両側に立つという、エクササイズというか方法があるんですね。
たとえば、蝶々をつかんだときに、蝶々を逃さないように、しかも殺さないように、手が蝶々の形になることがあるじゃないですか。ハタハタとする蝶をふわりと包むという感覚です。森田童子がそんな歌をつくっているんですが、ぼくはあの体験が非常に大事だと思うんですね。つまり、蝶々なのか手なのかわからないところへ自分がどうやったら入っていけるか、ということです。
(中略)
佐治:誰しもいつもは、やっぱり「自分」と「自分以外」のものを分けていますよね。だからそれがうまい具体に行き来できて、自分が向こうへ行って、向こうのものが自分に入るということができるとすごく楽になるんでしょうね。
五感を研ぎ澄ませば、日常の至るところに境界での出会いがある。そこには、まだ見いだされていないスコアが潜んでいるのだろう。
■石の声を聞く
同書は、『作庭記』という中世の技術書に「石の乞わんに従え」と書かれていることに触れ、「才能」の「才」は物質の中にあり、そのスコアを感じてそれをはたらかせるのが「能」であると説いている。
『日本力』でも、日本の職人が自然とのインタースコアを通してはたらいている実例が、こんなふうに描かれている。
たとえば佐野藤右衛門さんという有名な庭師の方がいますが、病気になって死にそうになったサクラをたくさん復活させた人、サクラの蘇生を手がける人です。その佐野さんは数寄屋づくりにもたくさんかかわっていて、その庭づくりを依頼されることも多い。その場合、さっき言ったように、石がどこに置いてほしいと言ってるのかという声にまず耳を傾けますが、もうひとつは、すでにできあがりつつある床の間の床柱にも聞く。木はもともと、はえていた時に北とか東とか南を持っていますから、もし佐野さんが全部やるとすると、北に植わっていた木であれば北向きに置くわけです。庭だけつくる場合は、つくられている庭床を見て、それに合わせて庭をつくっていく。つまり、庭をつくっているんだけれども、敷地全部のオリエンテーションを頭に入れて、それを感じてつくる。場をとても大事にするんです。
自然や場の声を聞き、「問感応答返」する力が方法を生み、インタースコアを可能にする日本の文化。それが私たちの源だとすれば、グーグルの検索による「分類の知」ではなく、長い年月と手間暇をかけて涵養されてきた「手続きの知」を辿り、ものや言葉や価値観のもとになっているところをゆっくり解きほぐしていくことによって、その面影が見えてくるかもしれない。そこから日本文化のトークンがきっと見つかるのだろう。
§編集用語辞典
14[インタースコア]
丸洋子
編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。
「この場所、けっこうわかりにくいかもしれない」と書かれた看板を手にした可愛らしい男の子のイラストが、展覧会場の入り口に置かれている。眉根を寄せて地図を見ているその男の子を通り過ぎ、中へ進むと「あなたをずっとまっていたのか […]
八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]
公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]
千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。 グノーシスとは「原理的 […]




コメント
1~3件/3件
2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。