ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。





触れられない。集えない。歯止めがかからない。
こんなとき…ベートーヴェンだったらどうするだろう?
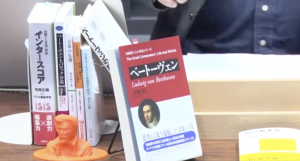
ベートーヴェンと編集工学を重ねるツアー
ここ3年、クリスマスのEditツアーは上杉公志ナビが、得意の音楽談義を交えた編集ワークでもてなしてきた。2020年はオンライン・Editツアーとなる。上杉が選んだテーマはベートーヴェン。生誕250年である。しかし選んだ理由はそれだけではなかった。コロナの影響で第九がホールに流れない年末、「こんなとき彼ならどうする?」との思いが浮かんだのだ。

オンライン参加者との間で多奏に交わす
ベートーヴェンといえば「ジャジャジャ・ジャーン」の交響曲第5番「運命」。
250年にわたり世界中の人に知られるこの曲も、当時には「ない」作り方だった。
音楽的には、和声学でいう「ドッペル・ドミナントの七の根音省略形の下方変位」を突然使うなど、王道を外れまくっていた。また当時は教会で主に用いられ、宗教的なイメージを持つトロンボーンを初めてオーケストラに使った。
これらのチャレンジは、宗教改革をへてフランス革命がウィーン会議に至り都市というものが生まれる時代社会の中で、新しい音楽の可能性をつくることでもあった。
当時の世に「ない」方法を連打した破格の彼が、2020年の世界にいたら何を考えただろうか。それが、上杉の思いだったわけだ。
「ジャジャジャ・ジャーン」は、編集の型でいうステレオタイプ(典型)だ。ツカミ、ぱっと見、流行りものである。では、その違いが何だったのか、音楽の作法としてきちんとプロトタイプ(類型)してみる。奥にある背景・歴史・本来のアーキタイプ(原型)を重ねて見る。すると、生まれる必然や改革の動機が立体化する。
「ステレオタイプは見えやすく、アーキタイプは見えにくいんです」と上杉が補うと、参加者から「日頃接している就活生も自分の可能性を表層的にステレオタイプだけ見ているのかもしれない」など連想が次々動いた。見えないアーキタイプを仮設するだけで、ステレオタイプでかたまったメロディーが重奏ゆたかに響きだす。
かくして、2020年の苦しいクリスマスは、ベートーヴェンの方法に励まされて来たる可能性の音に耳を澄ますジングルベル・ツアーとなった。「方法絵本」を丁寧にめくるような上杉の極上ナビのおかげである。
参加者から名回答もつぎつぎ飛び出した。この「しわ」の大転換に肖りたい。
<お題> ベートーヴェンとサンタクロースをつなげてください。
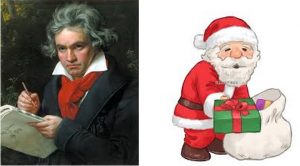
<回答> 眉間皺のベートーヴェン、笑い皺のサンタクロース
佐々木千佳
編集的先達:岡倉天心。「24時間働けますけどなにか?」。無敵の笑顔の秘密は未だ明かされない学林局局長。NEXT ISISでも先頭を日夜走り続けている。子ども編集学校開校は積年の願い。
「では、Thinking dive! 編集稽古をどうぞ」 クイズ番組の名司会さながら、北條玲子師範代による稽古コールが響いています。 イシス編集学校学校説明会、本日は満席で田中晶子花伝所長も動員、ブレイクアウトルームにわ […]
編集が踊っている。 編集ワーク三昧を楽しむイシスの祭り、ISIS FESTA エディットツアー・スペシャルがこの夏も盛況、期間の折り返しにさしかかった。 8月前半は、子ども向け、教育現場の方々 […]
「探究って、あまり楽しくないイメージだったのが、変わった」 200人を超える女子高校生達の瑞々しい感想が届いた。 2019年からこの授業を重ねてきた先生方は、コロナ禍の今年も前倒しで研修会をし、オンライ […]
子どもも大人も、読み・書き・変わる【ツアー@子ども編集学校】
子どもも大人も、学び場を探している。 今回、ISISフェスタでお楽しみいただくプログラム「よみかき編集ワーク」は、学校や図書館をはじめ、地域の文化施設、科学館、書店など、じつにさまざまな場所で行われてきたも […]
オンラインなのに土地にこだわるISISフェスタ「Edit ツアースペシャル」。 編集とはまだ見ぬものを求めることだ。 むかったお題は、Editツアーしてほしい愛媛とは何か? うらうらとした瀬戸内からドキドキする伊丹映画や […]


コメント
1~3件/3件
2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。
2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。