自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。




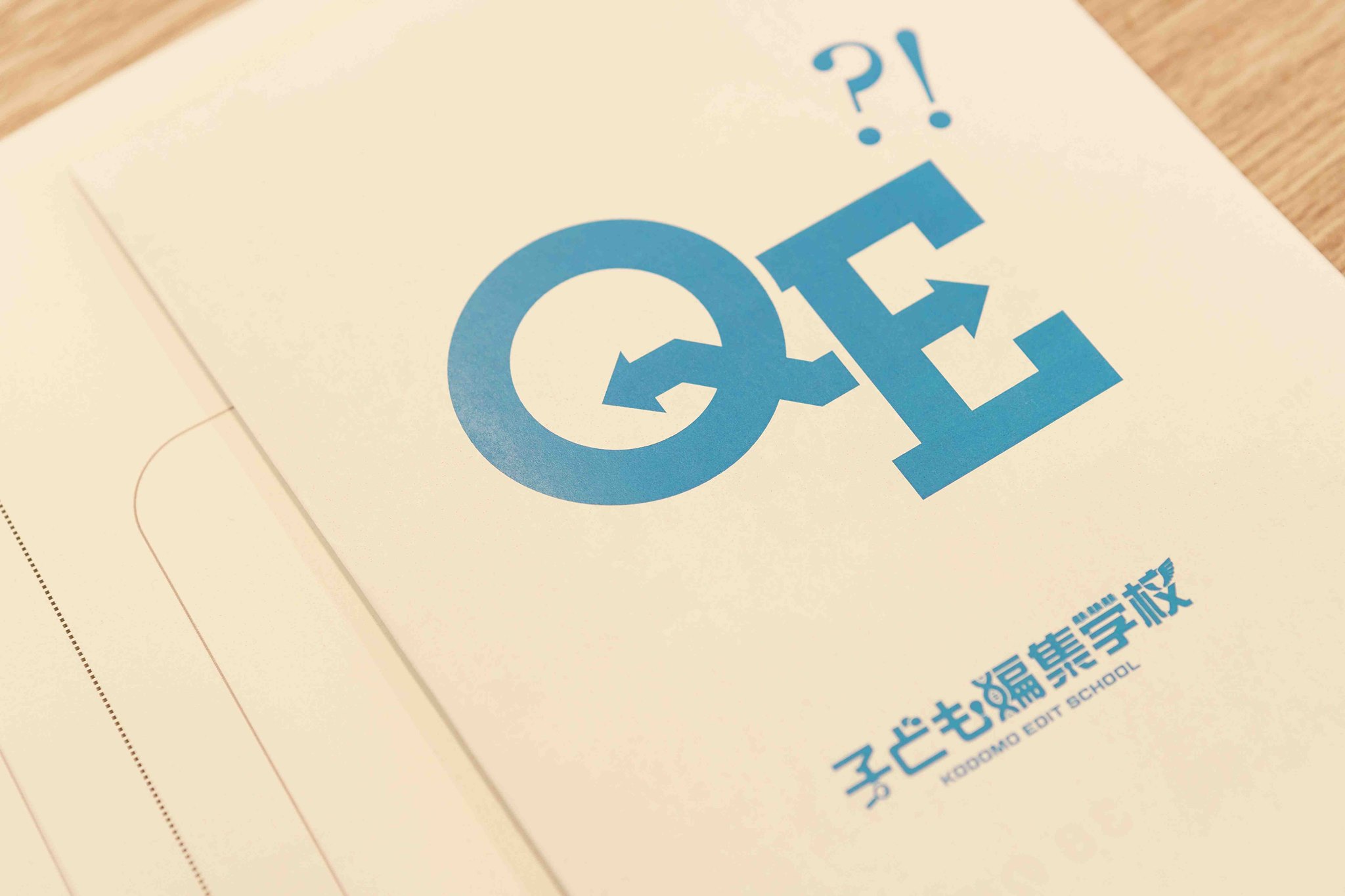
連想と要約。編集の要である。
広げる編集とまとめる編集をどう子どもに伝えればいいだろう。2019年8月24日の本楼おやこ塾「読み書き編集ワーク」が始まった。
A3カラー版の本楼マップを手に、参加者はナビゲーターの豊田香絵師範代とともに本の宇宙を巡る。子どもたちは天井まで伸びるタワーを見上げながら、本の棲み分け方の説明に聞き入っている。
本楼ツアーから帰還した親子に、豊田師範代は問いかける。
「ここにある本には、じつは大きいテーマが一つあるんですが、何だかわかりますか?」
参加者のアタマの中で編集のエンジンがかかった。
「日本でしょうか?」
お父さんの答えに拍手が起こる。
「そうなんです。たくさん本があったので分かりにくかったかもしれませんが、例えば『歌舞伎』や『書道』や『古事記』などに絞ると、『日本』が連想できますね」
本棚を埋め尽くす書物からキーワードを取り出して要約し、「日本」というホットワードを連想する。今日のワークの要諦が仕込まれていたのだ。2万冊の本を通して子どもたちへ編集の扉が開いた瞬間だった。
丸洋子
編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。
「この場所、けっこうわかりにくいかもしれない」と書かれた看板を手にした可愛らしい男の子のイラストが、展覧会場の入り口に置かれている。眉根を寄せて地図を見ているその男の子を通り過ぎ、中へ進むと「あなたをずっとまっていたのか […]
八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]
公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]
千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。 グノーシスとは「原理的 […]
コメント
1~3件/3件
2026-01-13

自らの体内から這い出したコマユバチの幼虫たちが作った繭の塊を抱きしめるシャクトリムシ。科学者は「ゾンビ化されて繭を守るよう操作されている」と解釈するけれど、これこそ「稜威」の極北の姿ではないだろうか。
2026-01-12

午年には馬の写真集を。根室半島の沖合に浮かぶ上陸禁止の無人島には馬だけが生息している。島での役割を終え、段階的に頭数を減らし、やがて絶えることが決定づけられている島の馬を15年にわたり撮り続けてきた美しく静かな一冊。
岡田敦『ユルリ島の馬』(青幻舎)
2026-01-12

比べてみれば堂々たる勇姿。愛媛県八幡浜産「富士柿」は、サイズも日本一だ。手のひらにたっぷり乗る重量級の富士柿は、さっぱりした甘味にとろっとした食感。白身魚と合わせてカルパッチョにすると格別に美味。見方を変えれば世界は無限だ。