誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)




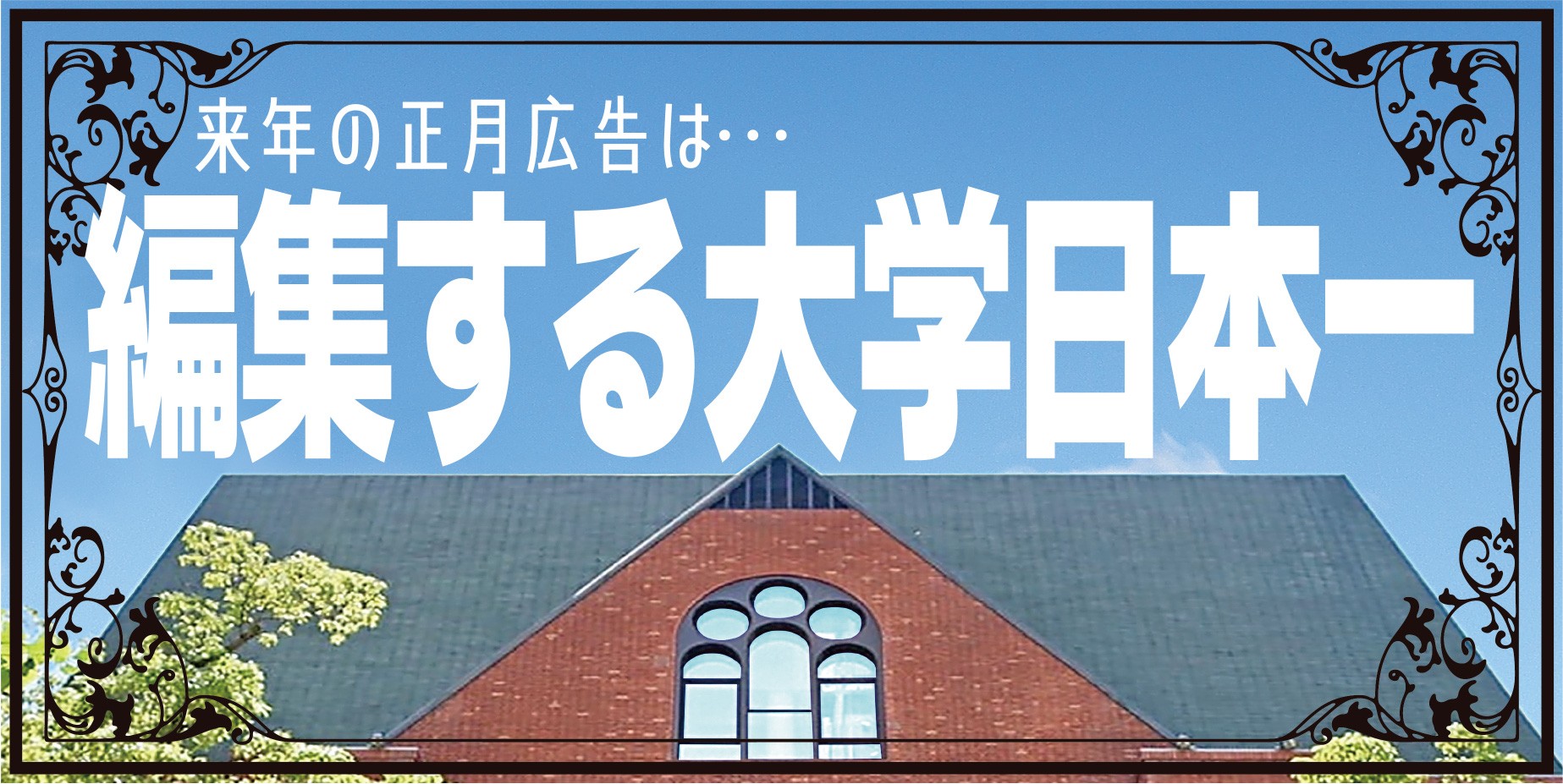
普通の自己紹介では始まらない。なにしろ近畿大学×イシス編集学校のタッグ。挨拶代わりにお題が出る。「部屋にあるとっておきの3つをあげてください」。53[守]開講日恒例の交流会は、一風変わった自己紹介から始まった。少しだけ紹介すると…(左が自己紹介。右はわたしの心の声)。
5月13日に開講した53[守]は近大生21人が受講している。うち15人が会場の近大アカデミックシアターで、2人がZoomで交流会に参加した。始まる30分以上前から席についている学生が数人いる。満員の教室。少しはにかみながら、しかし堂々とした自己紹介。新しく近大番になった西村慧は「アドバイスを聞き、しっかり考えて発表してくれていることに感動した」と話す。
つづいて全員でお題001番「コップは何に使える?」に取り組む。パソコンに打ち込んだり、ノートに手書きしたり。学林局の衣笠純子と、番匠で近大番の景山和浩がテーブルを回ってアドバイスする。初めの5分は1人で考え、次に3~4人のグループで回答を見せ合う。「こんなん考えたんだけど」「それは浮かばなかった」。共読で回答がブラッシュアップされる。回答を見た近大番の中村麻人は「おもしろい回答が多いですね」と感心する。
おもしろい。といえば、近畿大学は「早慶近」「上品な大学ランク外」など、年初の日本を失笑させる新聞広告でおなじみ。今年は強面の職人が寿司を差し出し「あんたも知らん間に、近大を食べてんねんで」と迫った。人を食ったおよそ大学らしくない広告。旧態依然とした大学像に楔を打ち込むようだ。
[守]師範の石黒好美は、かつて伝習座の用法語りで「早慶近」に着目。「早慶」に「近」をプラスするなんて誰が思いつく? これこそ新たな価値を生む「三位一体」だと説明した。常識なんてなんぼのもん。それが近畿大学の矜持なのだ。
53[守]でも、近大生の常識に縛られない突飛な発想が飛び出すに違いない。日常に編集稽古を、一人でも多く卒門へ。そうすれば来年の新聞広告は「編集する大学日本一」になる。そんな夢をみる。
景山和浩
編集的先達:井上ひさし。日刊スポーツ記者。用意と卒意、機をみた絶妙の助言、安定した活動は師範の師範として手本になっている。その柔和な性格から決して怒らない師範とも言われる。
「一人も入ってこないかもしれない」。 ゆうこ師範代がつぶやいた。7月8日、19時半。汁講の開始まで30分を切った頃だった。イシス編集学校の田中優子学長は、55[守]酒上夕魚斎教室の師範代の顔も持つ。教室 […]
「世界と自分についての見方」を劇的に変えよーー54[守]開講
開講メッセージ『いざ、いまこそのインタースコアを!』が、全20教室に届けられた。2024年10月28日正午。これまで松岡正剛校長の筆だったが、今期から田中優子学長からとなった。松岡校長の思いを受け継ぐタイトルは以前のま […]
近大生、いざ番ボー!ー52[守]近大景山組ドキュメント(3)
守護神の如くいつだって[守]稽古の現場に張っているのが52[守]で番匠を務める景山和浩だ。秘めたる涙もろさと機を逃さぬ俊敏さを武器に、近大生の編集稽古ドキュメントを連載し、エディストを席巻しようと目論んでいる。第3回 […]
近大生 うなぎのぼりの回答を!-52[守]景山組ドキュメント(2)
守護神の如くいつだって[守]稽古の現場に張っているのが52[守]で番匠を務める景山和浩だ。秘めたる涙もろさと機を逃さぬ俊敏さを武器に、近大生の編集稽古ドキュメントを連載し、エディストを席巻しようと目論んでいる。第2回は […]
近大生、目指すは「アレ」や-52[守]景山組ドキュメント(1)
守護神の如くいつだって守稽古の現場に張っているのが52[守]で番匠を務める景山和浩だ。秘めたる涙もろさと機を逃さぬ俊敏さを武器に、近大生の編集稽古ドキュメントを連載し、エディスト紙上を席巻しようと目論んでいる。第1回は […]






コメント
1~3件/3件
2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。