昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。




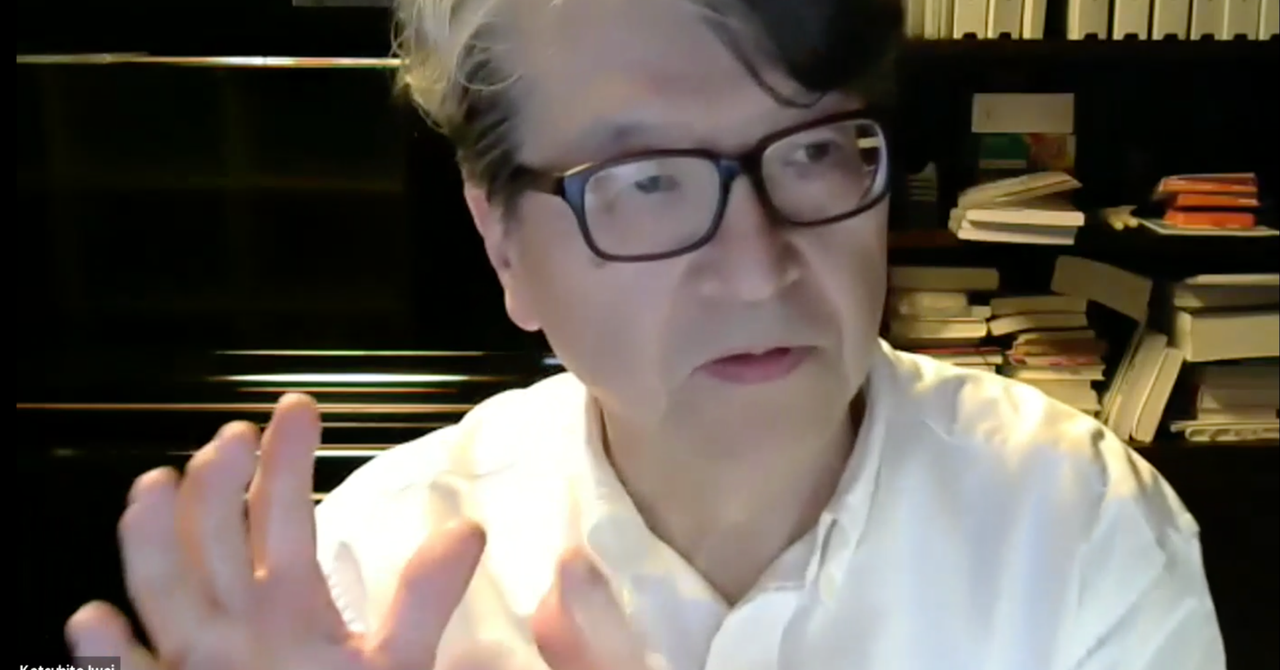
今年度、ハイパーエディティングプラットフォーム[AIDA]Season4が10月から開講する。「生命と文明のAIDA」を考えたSeason1から、Season2では「メディアと市場のAIDA」に向き合い、2022年10月から始まったSeason3のテーマは「日本語としるしのAIDA」だった。過去シーズンのボードメンバーからの声に耳を傾けてみたい。
※内容は取材時のもの
2020年後半から2021年初頭にかけて、編集工学研究所は、自ら主催する“共創のための知のプラットフォーム” Hyper-Editing Platform [AIDA](以下、[AIDA])において、「編集的社会像」というコンセプトを打ち出しながら、「生命と文明のAIDA」をテーマに新しい社会のあり方を描くための議論を行ってきました。本稿では[AIDA]のボードメンバーである経済学者の岩井克人さんに、人間と資本主義の関係を軸とした「編集的社会像」の可能性をうかがいました。
岩井克人(いわい かつひと、1947年〜):経済学者、東京都生まれ。国際基督教大学客員教授、東京財団上席研究員。東京大学経済学部卒業、マサチューセッツ工科大学経済学博士(Ph.D.)。イェール大学助教授、プリンストン大学客員準教授、ペンシルバニア大学客員教授、東京大学経済学部教授などを歴任。研究は法人論、信任論、言語、法、貨幣論など広範囲に及ぶ。2007年4月紫綬褒章を受章。主な著書に『不均衡動学の理論』『ヴェニスの商人の資本論』『二十一世紀の資本主義論』『経済学の宇宙』など多数、『貨幣論』にてサントリー学芸賞、『会社はこれからどうなるのか』にて小林秀雄賞受賞。
―― 岩井さんが経済学をやってこられた動機についてお聞きします。アメリカに行かれて早々に、新古典派経済学と決別するというか、違う道へ進む決意をされたように思います。どういった経緯でそう思えたのでしょうか。
岩井 私が最初にアメリカに渡った時の夢は、まともな経済学者として成功することでした。世界最高峰の研究機関の1つであるマサチューセッツ工科大学(以下、MIT)大学院で、ポール・サミュエルソンやロバート・ソローといったキラ星のような先生たちの下できちんとした仕事をしたいと思っていました。
MITの大学院で私は、新古典派経済学を学びつつ、(新古典派経済学の)根本を見つめ直す研究に取り組んでいました。新古典派経済学の根幹部分を支える基礎的な考え方は、いわゆるアダム・スミスの「見えざる手」です。「市場の価格の調整メカニズム(=見えざる手)が機能していれば、個人の利己心にもとづいた自己利益追求が社会全体の利益を実現する」というものです。ですから、先ほど述べた「共感」などが必要なくなるのです。
新古典派経済学によれば、賃金の硬直性や市場の規制や政府による中央銀行のマクロ政策といった「不純物」を取り除いた、より「純粋」な市場が理想とされます。そうした市場で世界を覆い尽くせば、資本主義は効率性と安定性を同時にもたらしてくれるはずです。まさに資本主義のグローバル化が「見えざる手」の実験でした。しかし実際には、2008年にリーマン・ショックが起こってしまいました。壮大な失敗でした。それ以前にも、1929年の世界大恐慌のような、社会の大きな「不安定」を資本主義は引き起こしています。
私は新古典派経済学の理論化を進める中で、資本主義は「効率性」と「安定性」の二律背反の関係を持った、矛盾に満ちたシステムだということを見い出したのです。資本主義を純粋化すると、世の中の効率性は増しますが、逆に安定性が失われてしまう。不純物があるからこそ、ある程度の安定性を保ってきたと言えます。新古典派経済学に矛盾があることは、当初は自分の間違いかと思い、どのように理解したらよいか分かりませんでした。実は「矛盾」があることそれ自体が真理なのだと、発想を転換するのにかなり時間がかかりました。
その後は、新古典派経済学をひっくり返す仕事をしようと決意し、7年間かけて『不均衡動学』という本を書いたのですが、アメリカの経済学会では受け入れられず、そのまま帰国しました。ですので、経済学の世界では、私は決して成功者ではないのです。しかし、主流派ではなかったことや日本という「戻れる場所」があることは、よい意味で、私の研究生活に非常に大きな影響を及ぼしたと思います。
MITで博士号を取った後の1年間は、カリフォルニア大学バークレー校でポスドク(博士後研究員)をしました。そこで、アンドレア・マスコレルというスペイン人と研究室が一緒になりました。彼はスペイン・カタロニア地方の出身でしたが、独裁者フランコに対抗する政治運動に加担し、スペインにいられなくなっていました。アメリカでは数理経済学の第一人者となって、ハーバード大学の教授にまでなりました。その後、フランコ政権が倒れると彼は大学を辞め、カタロニア再建のためにスペインに戻って文化大臣にまでなりました。私と研究室で一緒だった時はアメリカにいるしかないという立場で、一生懸命論文を書いていました。
一方の私は、彼のようにヨーロッパの政治的な事件に巻き込まれている人間ではなく、つまり、「大人」ではありませんでした。新古典派経済学の矛盾を見出しても、「これを研究して論文を書けば認められる」と、今にして思えば、ひどくナイーブな考えにとらわれていただけでした。
ですから、私は自分の経歴を格好よく書こうと思いません。私がアメリカにいた最初の頃、アジア人と言えばほとんど日本人だけでしたが、徐々に韓国人、中国人、インド人が増えてきました。彼らはアメリカで競争をして、生き抜くという意識が強かった。それに比べて私はのんびりしていました。
―― 競争に勝ち続ける道に行かれずにお仕事されたということは、後の「法人論」や「信任論」のようなお仕事をされることにつながっていったのではないでしょうか。
岩井 ”publish or perish”という、論文を量産しなければ滅びる厳しい競争に乗らず、アメリカから日本に帰ってきました。過度のプレッシャーがない中でじっくりやっていこうと思っていましたので、「法人論」の研究はアメリカの競争社会ではとてもできなかったと思います。
「法人論」研究のきっかけの1つが、「人本主義」を唱えられた伊丹敬之先生(一橋大学 経営学)が主催される企業システム研究会に参加したことです。その研究会で初めて松岡正剛さんとお会いしたのです。
伊丹先生の研究会に参加することで、会社に対する見方が変わりました。伊丹さんは話が上手で、研究会に経営者が来ても、最初はみんな緊張して建前しか喋らないんですが、相手をくすぐりながら、本音を引き出していきます。そして、その本音が面白い。研究会の活動を通して、日本の会社で仕事をしている人たちのリアルな思いを聞くことができたんですね。
私は、欧米型の株主中心の会社は、たくさんの会社のあり方の1つに過ぎないと考えるようになりました。もちろん民間企業ですから、利潤を上げなければいけません。ただし、利潤を上げるという制約はありながらも、従業員の福祉など、直接利潤に結びつかない活動も重要なのではないか。社員の幸福や社会のために貢献する余地を残せる会社。そのような、研究会で聞き及んだ日本の会社のあり方にも、1つの普遍性があるんだと研究を進めていきました。
会社は不思議ですね。本当は「人」ではありませんが、法律上は「人」として扱われる「法人」です。抽象的な存在でしかない法人が、「人」として活動するには、その会社を動かす生身の「人」が必要です。会社を代表して交渉したり、契約書を取り交わしたりするための「人」、それが経営者です。
法人としての会社と労働者やお客や銀行との間には、基本的に契約が存在しています。では、経営者と会社のあいだに、純粋な意味での契約の締結は可能でしょうか? 会社の契約はすべて(最終的には)経営者が結びますので、原理的には、その契約は経営者の「自己契約」です。経営者が自己の利益のみを追求しようとしたら、たとえば巨額のボーナス支給等の契約を会社の名前で自分と結べます。自分にのみ有利な契約書をいくらでも作れてしまう。したがって、会社がまともに運営されるためには、自己の利益を優先せずに、会社の利益のために努めるという「忠実義務」を経営者は必然的に負わなければならなくなります。つまり経営者には「倫理的」であることが要請されるのです。
「効率性」と「安定性」の二律背反を常に抱える資本主義社会がまがりなりにも生きながらえてきたのは、人間の倫理性、あるいは倫理性を持った人間の存在が大きいでしょう。ここで「見えざる手」の思想が覆されます。欧米型の株主中心の会社は、会社の中核に倫理があることを無視、とまでは言わないまでも、どこかで軽視する傾向にあります。しかし、私が法人のあり方について理論化を進める過程で行き当たったのは、経営者と会社との関係以外にも、社会には「医者と患者」などのような信頼によって任す/任されるという関係が無数にあることでした。そのような関係に関する一般理論が「信任論」です。
私はもう一度アメリカに渡りました。実は、妻である小説家の水村美苗(『日本語が滅びるとき』 – 千夜千冊 1699夜)の書いた論文がアメリカの英文学者に読まれ、それがきっかけで彼女はプリンストン大学に呼ばれたんです。彼女と一緒にアメリカに行き、プリンストン大学の客員准教授として日本経済論を教えることになりました。そこで、今お話したような日本の会社のあり方や「法人論」の研究を進めたんです。
私は幸運にも、彼女の書く本の最初の編集者というか、読者です。『日本語が滅びるとき』(筑摩書房)では、日本語と英語の2つの世界はどちらも普遍的であることを表現しています。彼女とは50年以上一緒ですが、彼女の存在や仕事は、私の「法人論」やその後の仕事に大きく影響していると思います。
―― 日本の会社のあり方や日本語の普遍性というお話がありましたが、これからの「編集的社会像」を考える上で、社会への問題意識や、改めて考えるべき視点がありましたら教えていただけないでしょうか。
岩井 最近のコロナ禍で、みなさんもお感じだと思いますが、日本はいつのまにか世界から遅れてしまっていることを気付かされます。たとえば台湾は民主主義国として、日本よりはるか先に行っています。もちろん、私だけではなく、多くの日本人が、日本のさまざまな居心地のよさを感じているとは思いますが。
一方で、松岡さんが言われているように、日本の文化は本当に貴重だと思います。日本は西欧以外で最初に近代化した国です。江戸時代には「日本型近代」の原型の多くが形作られていました。その歴史は世界的にも重要です。さらに日本には古代までさかのぼれる文化的な厚みがあり、それらが資料や書物という物理的な証拠として残っています。こうした独自の文化や歴史を資産として活かさない手はないと思います。
戦前の国語学者である橋本進吉は、万葉集などの古典を解読し、日本語の母音を8つとしました。非常にローカルな研究ですが、それによって古典を現在の人間でも読めるようにした重要なものです。文化の厚みが資料として残っていて、しかも、その後の研究によって現代でも読めるようになっている。それはとても貴重なことです。日本独自の文化や歴史を、今を生きるわれわれは学び直し、丁寧に継承していくべきだと思います。人間は生物的な存在であるとともに、まさに言語をはじめとする抽象的な媒介(物)を共有することで「人間」となった社会的な存在でもあるからです。
取材/撮影/執筆:橋本英人(編集工学研究所)
取材:安藤昭子(編集工学研究所)
撮影:川本聖哉
編集:谷古宇浩司(編集工学研究所)
※2021年5月19日にnoteに公開した記事を転載
エディスト編集部
編集的先達:松岡正剛
「あいだのコミュニケーター」松原朋子、「進化するMr.オネスティ」上杉公志、「職人肌のレモンガール」梅澤奈央、「レディ・フォト&スーパーマネジャー」後藤由加里、「国語するイシスの至宝」川野貴志、「天性のメディアスター」金宗代副編集長、「諧謔と変節の必殺仕掛人」吉村堅樹編集長。エディスト編集部七人組の顔ぶれ。
イシス編集学校のアドバイザリー・ボード「ISIS co-mission」(イシス・コミッション)に名を連ねる9名のコミッション・メンバーたちが、いつどこで何をするのか、編集的活動、耳寄りニュースなど、予定されている動静を […]
田中優子の酒上夕書斎|第九夕 『日本文化の核心』(2026年2月24日)
学長 田中優子が一冊の本をナビゲートするYouTube LIVE番組「酒上夕書斎(さけのうえのゆうしょさい)」。書物に囲まれた空間で、毎月月末火曜日の夕方に、大好きなワインを片手に自身の読書遍歴を交えながら […]
編集を通して未知の自分になっていく【ISIS co-missionメッセージ 鈴木健】(全文書き起こし)
イシス編集学校アドバイザリーボード ISIS co-missionメンバーより、これから「編集」を学びたいと思っている方へ、ショートメッセージが届きました。なぜ今、編集なのか、イシス編集学校とはなんなのか。イシスチャンネ […]
イシス編集学校で予定されている毎月の活動をご案内する短信「イシスDO-SAY(ドウ-セイ)」。 卒業シーズンに向かう一歩手前の2月です。イシス編集学校では、昨年10月から開講した講座がぞくぞくと修了を迎えま […]
「編集」を学べば、情報の本質が見えてくる【ISIS co-missionメッセージ 津田一郎】(全文書き起こし)
イシス編集学校アドバイザリーボード ISIS co-missionメンバーより、これから「編集」を学びたいと思っている方へ、ショートメッセージが届きました。なぜ今、編集なのか、イシス編集学校とはなんなのか。イシスチャンネ […]




コメント
1~3件/3件
2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。
2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。
2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。