タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。




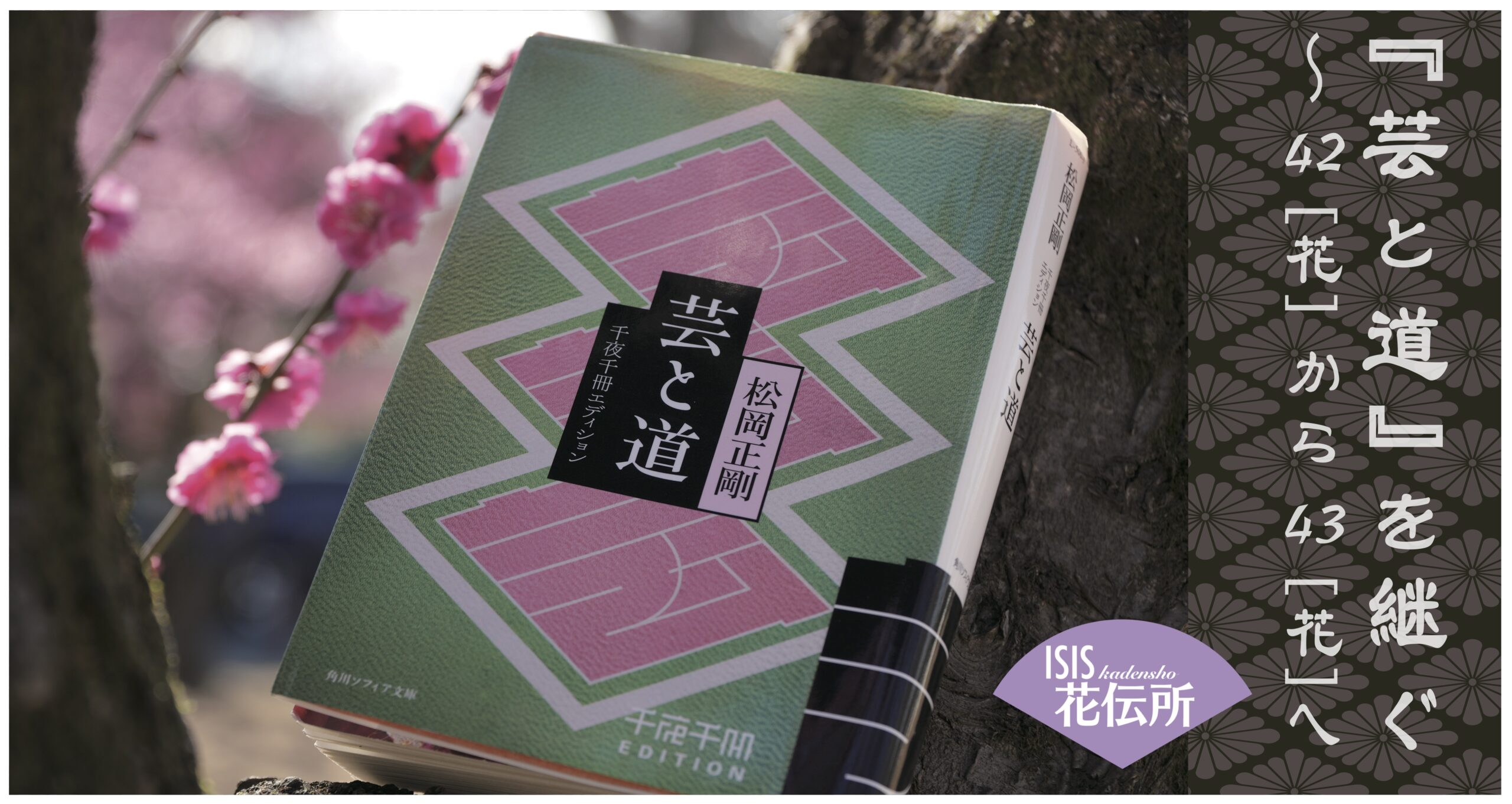
世界は書物で、記憶を想起するための仕掛けが埋め込められている。プラトンは「想起とは頭の中に書かれた絵を見ること」と喝破した。松岡正剛校長は「脳とか意味って、もっともっとおぼつかないものなのだ。だから『つなぎとめておく』ための何かの工夫が必要なのだ」と言明した。
ISIS花伝所では放伝生に託す最後のお題、エディション図解がある。42[花]の千夜千冊エディションは『芸と道』だった。それは師範にとっても託されたものである。その先へ旅を続ける仲間へ、どのように届けるか。当初のターゲットさえ動かす師範の再編集は、インタースコアな語り直しとして第86回感門之盟タブロイドに記されることになる。
しろがね、むらさき、やまぶき、からたち、くれないの道場スレッドが次々に現れる。タブロイドに掲載する創文を相互編集していくためだ。最初に、道場での日々を振り返り放伝生のずっと遠くのターゲットを描きながら、『芸と道』からキーセンテンスが列挙されていった。情報単位の発生、「わける/あつめる」だ。花伝所指導陣が集うラウンジでは語り手の突出へむけ、道場の「いろ」が染みていく。
錬成師範の大濱朋子と渋谷菜穂子が取り出した複数のキーセンテンスから、花伝師範の岩野範昭は生命のうねりを見出す。岩野の「感」はパンクモードを躍動させた。意味が掴みにくい箇所への大濱の指摘に、岩野の思考がリバース・エンジニアリングされる。渋谷の着眼は見出しへもおよび、しろがねの切先をひからせた。
“少数なれど熟したり”の仲間たちに
しろがね道場 花伝師範 岩野範昭
エディターシップはどこからでも発揮できる。『俳優のノート』の山崎努のように、たとえ弱々しくたって、少数意見だってへっちゃらさ。別様の可能性の芽はいつもそこにあるものだ。フラジリティやマイノリティは、編集的自己へ変身できる大事な鍵穴なんだ。ただ鍵は必要。それは未知へ飛び込むカマエという覚悟だよ。やがて感じていた苦みは道行きで香ばしくなる。それが編集道の秘密なんだよ。仲間たち、同志よ。道の先で待ってるぜ。
花伝師範の山本ユキみずから入伝式で届けた世阿弥の「してみてよきにつくべし」を手に、鍵となる引用千夜を取り出す。それは『芸と道』の中でも王道の第1章からだ。師範代になる放伝生へたむける創文には、錬成師範の高田智英子と齋藤成憲も加わる。3者の読みが何層にも重なり、むらさきの色幅が深みを増した。
いざ、ワキ的世界へ!
むらさき道場 花伝師範 山本ユキ
「ワキは自分が鍵をもっていることを最初から知ってはいない」
なにかを察知し、問いを発し、呼び寄せる。ふと、そこに鍵穴があることに気づく。その気づきは偶然ではない。自身を「無用のもの」と思いなし、異界を旅することで、偶然は必然になる。「そこにさしかかることによって、相手に何かをされる契機をもたらすという能力を持つ」からだ。ふいのさしかかりは天空の裂け目のごとく、ワキにしか見えない世界にあらわれる。
最初から鍵となる引用千夜は、543夜 太鼓持あらいの『「間」の極意』一本だった。花伝師範の森本康裕と錬成師範の古谷奈々の真剣が交わされる。森本の創文に古谷が見方と問いを重ね、森本が応じる。言葉は言い換え圧縮され閾値へせまる。冬を越え咲く山吹の黄金色のように、きらめくメッセージが散りばめられた。
式目たずさえ相互編集で「渡」へ向かえ
やまぶき道場 花伝師範 森本康裕
「お座敷で人の心と向き合うことが仕事というものになる。人の心というものはナマである。これに付き合うには芸ばかりではうまくはならない」
技量を極めるだけでは太鼓持ちは務まらない。「間」の取り方が肝になる。師範代も同じである。他者との間にあらわれる「渡」へ向かうことに全力を尽くすのだ。別様の可能性には「他」が必要であり、それが社会にも師範代が必要とされる所以である。花の方法はウチにもソトにも変容をもたらす。
相互編集へ向かう事情も時間も編集したのは、からたちだ。花伝師範の尾島可奈子不在の中、錬成師範の堀田幸義と牛山惠子が創文骨子を組立てる。が、その過程で引用千夜は二分した。千夜は一つに決めなければならないという明記はない。締め切り目前に現れた尾島は、どちらの創文を選ぶでもなく二つを包摂した。
「型」にこころと、いのちを宿して
からたち道場 花伝師範 尾島可奈子
女形は問う。女っぽく見せても、客を魅せられるものなのか。なぞりだけでは芸にならないと。三味線弾きは笑う。何曲もおぼえたとか、たくさん弾けるとかということを誇りなさんなと。「型」に匂いを感じ、それが音色に出るのが津軽三味線だとおもえなきゃ、型はスキルに終わるだろう。そのためには一曲を何度も弾くことだ。「こころ」と「いのち」を宿すべく、弾打し続けるのだ。一途で孤独な「練り」の道は、まだ始まったばかり。
花伝師範の吉井優子と錬成師範の新垣香子は、唯一の道場2人体制だった。振り返れば疼き出す「感」さえも目前心後すれば、未来へ分け入るためのセンサーは100ひらかれる。そのことを吉井と新垣は二人羽織のように互いの意を思い起こし、対話することであらわにする。そして奥に秘めるアツいおもいを人形に託した。
実虚の入れ替わりに本来が見える
くれない道場 花伝師範 吉井優子
「ぼく自身もあらためてふりかえってみると、さていったいその一線をまたいでいろいろの細部が見えてきた臨界値がどこにあったのか定かではないのだが、ある日突然に人形と人形遣いの両方がすべてくっきりと見えてきた」
舞台にたつ人形が「実」ならば、頭巾をかぶる私は「虚」。人形遣いも師範代も、自己にとらわれていたら、虚実は分断されたままだ。虚実がくるり、と入れ替わることが了承されたとたん、世界は一変する。
締めにくるのは、花目付の平野しのぶのコラムだ。花目付といえども一人で創文するのではない。コレクティブ・ブレインの相互編集状態であることは変わらず、妥協を許さぬ刀の交わし合いは第6稿にまでおよんだ。校長が自身の原稿に何度も赤入れするミームは確かに受け継がれている。
▲[守]基本コース入門者だけに公開される“インターメッセージ「松岡校長のAnalogical Way」”より
『芸と道』―すなわち「世阿弥学」。
花目付 平野しのぶ
日本の芸能文化に伏流する奥義は、能楽者・世阿弥がとっくに「伝書」化している。稀代の劇作家でもある世阿弥は、ソリッドな「日本語」でものを考え、場の演出も、作曲も編曲も、作舞までも自ら演じて総合芸術してみせた。芸の上達にはアマチュアの存在が絶必だ。非風こそ他力をもたらし、イメージメントが動きだす。
松岡校長は『芸と道』で、数多の名人の方法と集合知による伝承スタイルに迫り、レパートリーを列挙した。琵琶法師から山崎努まで、その数は千百人余。型の継承と発展の歴史こそ、方法日本を物語る。
編集の骨法は「視点のずらし方」と「問いの立て方」に尽きる。時代をよむ眼も離見の見も、すべては観ることに始まる。仮説的な読み筋さえあれば、稽古と実践によって「道」は開けていく。世阿弥学の真髄たるや、いわんや人生をや、やがて芸と道になってゆく。
42期ISIS花伝所の指導陣が総がかりで編集した『芸と道』のタブロイドページがこれだ。遊刊エディストとの違いも楽しめるだろう。フォントや文字サイズがかわり、色が加わる。紙面という空間で縦横に配置され、記号の意味は奥行きを増す。メディアは乗り換えを焦がれている。
▲第86回感門之盟タブロイドは、54[守]阿久津健師範によるデザイン。見開き左半分には、テーマ「EDIT SPIRAL」にちなんだ指導陣の自己紹介が掲載されている。
これは、プロセスごと一座に埋め込まれた記憶だ。誰かの何かを呼びおこす仕掛けは、世界の至る所に隠されている。
アイキャッチ写真/林朝恵(42[花]花目付)
タブロイドデザイン/阿久津健(54[守]師範)
構成・文/大濱朋子(42[花]錬成師範)
大濱朋子
編集的先達:パウル・クレー。ゴッホに憧れ南の沖縄へ。特別支援学校、工業高校、小中併置校など5つの異校種を渡り歩いた石垣島の美術教師。ZOOMでは、いつも車の中か黒板の前で現れる。離島の風が似合う白墨&鉛筆アーティスト。
たどたどと揺れる火は、点ずる先を探していたのだろうか。内外に吹く風にかき消されぬよう、焚べられる薪を頼りに、今こそ燃えよと寄り合い、やがて気焔を上げる。 2日間のトレーニングキャンプを締めくくるのは、花伝所 […]
まるで吹き矢で射抜くようだった。 「いい加減、学衆の服は脱いでください」 「日常のスーツも脱ぎ捨ててください」 「あなたたちは、『師範代』です」 44[花]キャンプ2日目の朝は、指導陣からの檄 […]
キャンパーの多くが眠りについた頃、東の空には有明月が現れた。キャンプ場には44[花]のF・Kがひとり残っていた。 自分が考えてみたものを出すのって勇気が要りますね。 12月14日 02:44 [芭蕉庵]に、F・Kがろ組の […]
天空に突如生まれる割れ目。そこから、自分のきているTシャツをひっくり返しながら脱ぐように、ジョージ・ガモフのトポロジーの発想で人体を裏返すように、44[花]ラウンジ上に新たな「場」が現れた。[しをり座]と[芭蕉庵]だ。そ […]
[ISIS花伝所]の花伝師範で美術教師。在住する石垣島の歴史や風土、祭祀や芸能、日常に息づく「編集」に気づいた大濱朋子が、日々目にするトポフィリアを“石垣の隙間から”描きだす。 3メートルを超えるサトウキ […]






コメント
1~3件/3件
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。
2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥
LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。
2026-01-20

蛹の胸部にせっかくしつらえられた翅の「抜き型」を邪険にして、リボンのような小さな翅で生まれてくるクロスジフユエダシャクのメス。飛べない翅の内側には、きっと、思いもよらない「無用の用」が伏せられている。