発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。




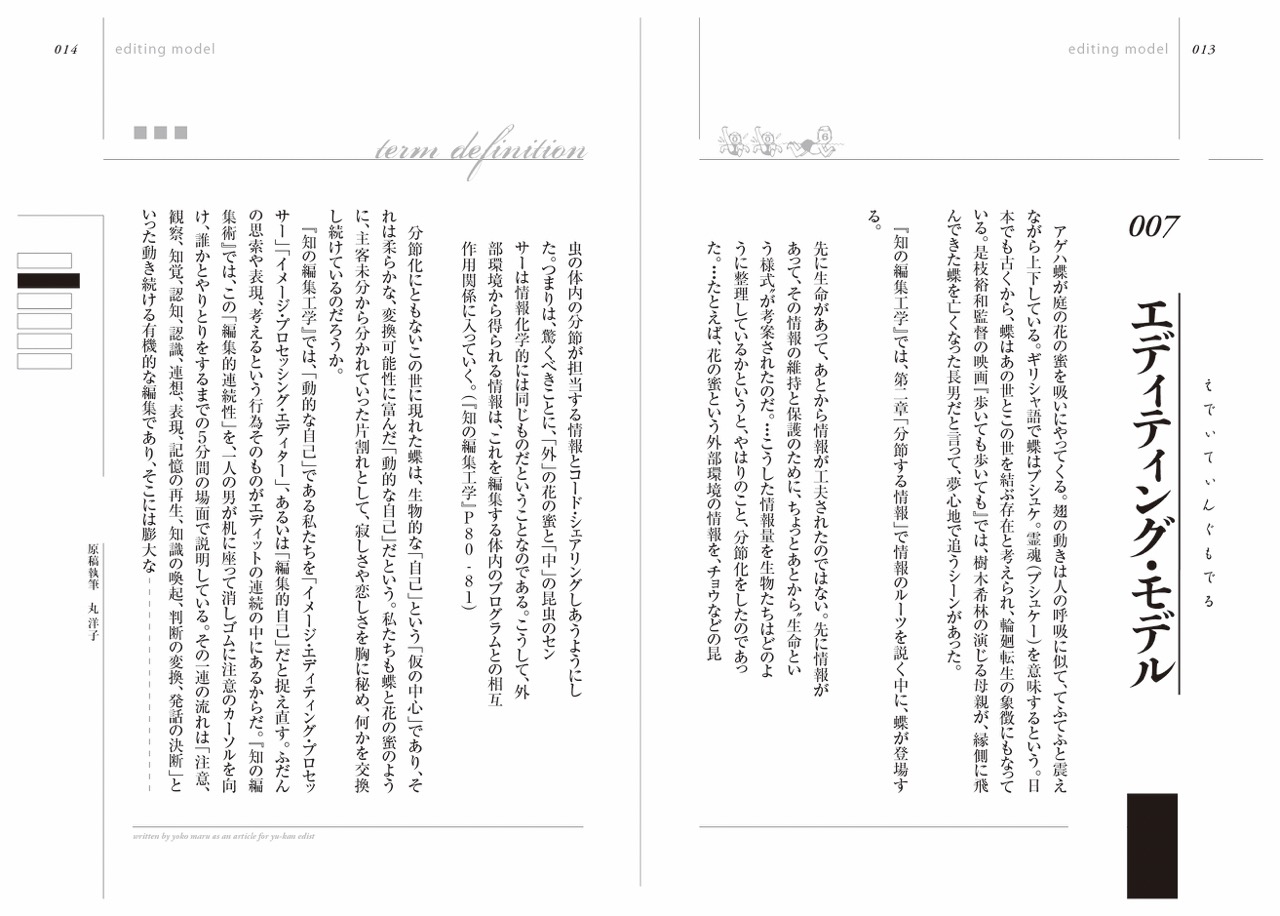
アゲハ蝶が庭の花の蜜を吸いにやってくる。翅の動きは人の呼吸に似て、てふてふと震えながら上下している。ギリシャ語で蝶はプシュケ。霊魂(プシュケー)を意味するという。日本でも古くからあの世とこの世を結ぶと考えられてきた蝶は、輪廻転生の象徴でもある。是枝裕和監督の映画『歩いても歩いても』では、樹木希林の演じる母親が、縁側に飛んできた蝶を亡くなった長男だと言って、夢心地で追うシーンがあった。
『知の編集工学』では、第二章「分節する情報」で情報のルーツを説く中に、蝶が登場する。
先に生命があって、あとから情報が工夫されたのではない。先に情報があって、その情報の維持と保護のために、ちょっとあとから″生命という様式″が考案されたのだ。…こうした情報量を生物たちはどのように整理しているかというと、やはりのこと、分節化をしたのであった。…たとえば、花の蜜という外部環境の情報を、チョウなどの昆虫の体内の分節が担当する情報とコード・シェアリングしあうようにした。つまりは、驚くべきことに、「外」の花の蜜と「中」の昆虫のセンサーは情報化学的には同じものだということなのである。こうして、外部環境から得られる情報は、これを編集する体内のプログラムとの相互作用関係に入っていく。ー『知の編集工学』P80-81
分節化にともないこの世に現れた蝶は、生物的な「自己」という「仮の中心」であり、それは柔らかな、変換可能性に富んだ「動的な自己」だという。私たちも蝶と花の蜜のように、主客未分から分かれていった片割れとして、寂しさや恋しさを胸に秘めつつ、何かを交換し続けているのだろうか。
■連結する編集力
『知の編集工学』では、「動的な自己」である私たちを「イメージ・エディティング・プロセッサー」「イメージ・プロセッシング・エディター」、あるいは「編集的自己」だと捉え直す。ふだんの思索や表現、考えるという行為そのものがエディットの連続の中にあるからだ。『知の編集術』では、この「編集的連続性」を、一人の男が机に座って消しゴムに注意のカーソルを向け、誰かとやりとりをするまでの5分間の場面で説明している。その一連の流れは「注意、観察、知覚、認知、認識、連想、表現、記憶の再生、知識の喚起、判断の変換、発話の決断」といった動き続ける有機的な編集であり、そこには膨大なイメージや意味の連鎖が起きている。編集的連続性について、『多読術』にはこのように書かれている。
私たちが記憶やコミュニケーションや表現をすることができるのは、記憶能力やコミュニケーション能力や表現能力のそれぞれによっているのではなくて、それらを連結させている編集構造によっているというふうになっていくわけですね。これは、記憶力や表現力よりも、編集力がいろいろな記憶や表現の基本力になっているだろうということです。そして、この連結する編集力のなかで動いているのが、エディティング・モデルなんですね。ー『多読術』P101
■意味の交換のためのエディティング・モデル
例えば同じ映画を観ても、記憶している個所や内容は異なり、そのあらましを語れば情報圧縮の偏りがあるように、連結する編集の方法には一人ひとりのクセがある。これまでの人生で、さまざまな情報の意味をどのように記憶してきたのか、それをどのように想起するのか、このinputとoutputのあいだにエディティング・モデルが潜んでいる。『知の編集工学』には、「そもそも記憶の再生というのは、外からやってきた情報が自分に似たカテゴリーやプロトタイプをさがしだすということなのである」と記されている。これは私たちのコミュニケーションで起きていることにも重なっていく。
私たちはそうやってとりかわされる情報のやりとりのプロセスで、たがいに似ていそうだとおもわれる″情報の贈り物″を適当にあてはめあっているのである。すなわち、レパートリーから抜き出したエディティング・モデルをつきあわせているはずなのだ。これは<編集的相互作用>というものである。なぜ、そんなことになるかというと、そこでおこなわれているのはたんなる情報交換やメッセージ交換ではなく、意味の交換であるからだ。ー『知の編集工学』P126 – 127
コミュニケーションで意味の交換のプロセスを司るエディティング・モデルを、松岡校長は、『多読術』ではこのように説いている。
エディティング・モデルというのは、その情報編集をしているときにやりとりしているモジュールのことで、それを使ってわれわれは「意味」というものを探ったり、保持しています。つまり、コミュニケーションのなかで「意味の交換」を成立させているもの、それがエディティング・モデルです。この用語はぼくが作ったもので、当時の通信理論にもとづいた情報コミュニケーション・モデルとは別のモデルを提案するためのものでした。ー『多読術』P96
私たちは編集された情報を自分のモデルの中で言い替えながら捉え直し、自身の中にある似ているものをよすがに「わかる」へと近づく。この編集的相互作用による意味の交換や意味の変容で発揮されるのが、似ている構造の断片やエディティング・モデルになりそうなものを探り合いながら対角線で結んでインタースコアする編集力だ。
■コンパイルとエディット
[守]の講座には、一つの言葉を「コンパイル」と「エディット」という二つの編集方法で書き分けて説明するお題がある。コンパイルは辞書のように言葉を相互規定して定義する、世の中のルールや法律などを支えているロジカルで普遍性を目指す編集である。これに対し、エディットでは、言葉に潜むイメージの種子をふくらませ、アナロジカルに解釈を動かしていく。コンパイルでは学衆の回答はどれも似ているが、エディットでは一人ひとりの個性が生き生きと浮かび上がる。情報の地と図で言えば、情報を絞り込むのがコンパイルで、地を広げていくのがエディット。この二つは相互に補完しあい、作用しあう。
私たちはすでにコンパイルされた情報の地の上に投げ出された存在だ。その制約を受けているからこそ、既存の編集をリバースする型を使って地と図に解きほぐし、情報を動かし、異質なものどうしに関係性を発見して再編集していくことができる。まだ見ぬ片割れの欠けたピースを見出し、繋ぎ合わせて新しいかたちを生み出す。そうやって価値や意味を創発し、これまでの自分や世界モデルを問い直していけるのがエディットである。編集稽古では、師範代とのやり取りを通して自分のエディティング・モデルを発見していく。それは、世界とのかかわり方や意味づけや生き方がおのずと浮き彫りになり、それらを自在に動かせるようになっていくプロセスでもある。エディティングし続ける編集的自己は、花と交わる蝶のように「私があるということ」と不可分なのである。
§編集用語辞典
07[エディティング・モデル]
丸洋子
編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。
八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]
公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]
千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。 グノーシスとは「原理的 […]
木漏れ日の揺らめく中を静かに踊る人影がある。虚空へと手を伸ばすその人は、目に見えない何かに促されているようにも見える。踊り終わると、公園のベンチに座る一人の男とふと目が合い、かすかに頷きあう。踊っていた人の姿は、その男に […]








コメント
1~3件/3件
2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。
2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。
家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。
せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。
添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!
イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。
エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。
2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。
山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)
この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。
お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。
深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。