桃の節句に、桜の葉が好きなモモスズメ。飼育していると、毎日、たくさんの糞をするが、それを捨てるのはもったいない。こまめに集めて珈琲フィルターでドリップすれば、桜餅のかほりを放つ芳しき糞茶のできあがり。




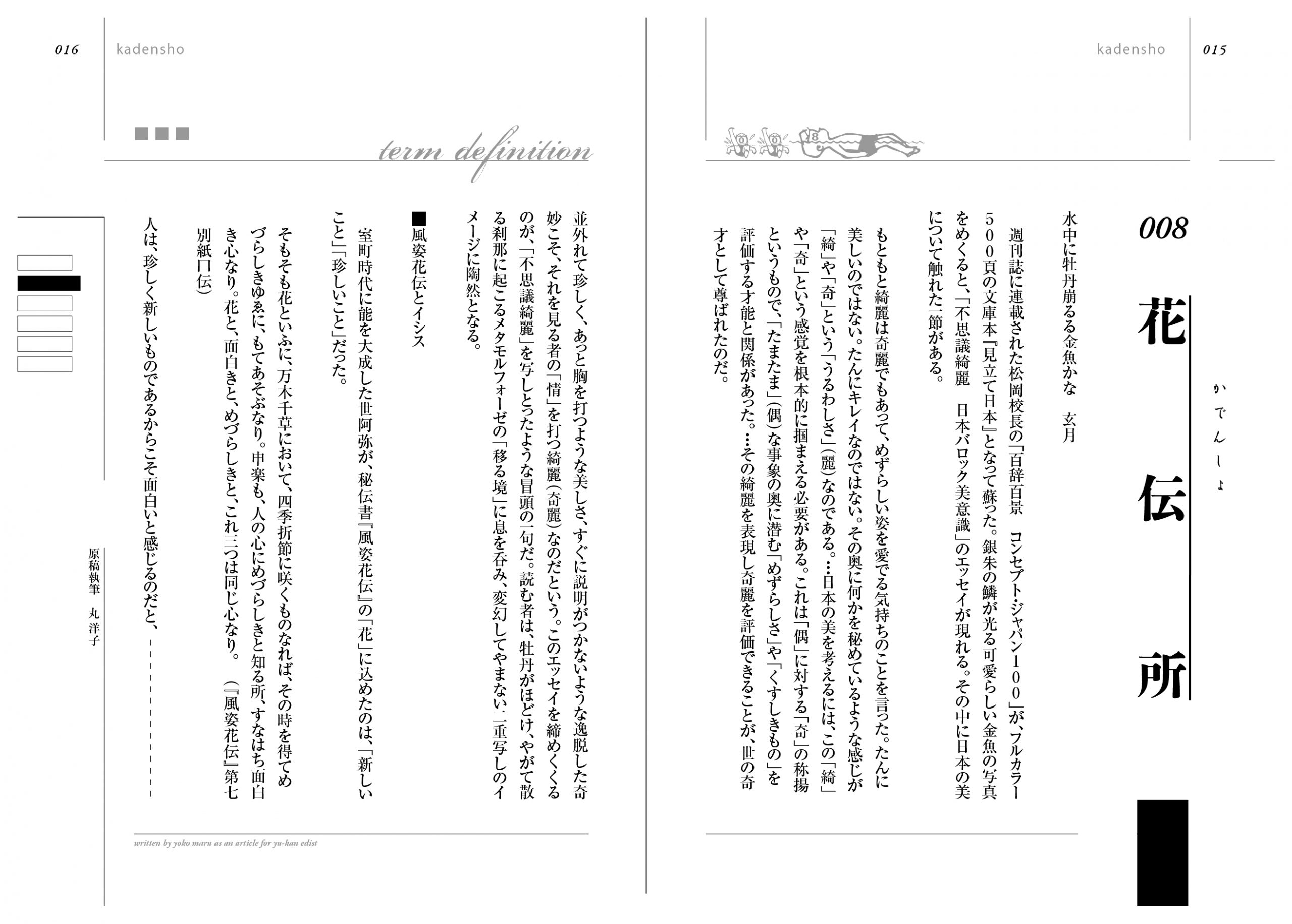
水中に牡丹崩るる金魚かな 玄月
週刊誌に連載された松岡校長の「百辞百景 コンセプト・ジャパン100」が、フルカラー500頁の文庫本『見立て日本』となって蘇った。銀朱の鱗が光る可愛らしい金魚の写真をめくると、「不思議綺麗 日本バロック美意識」のエッセイが現れる。その中に日本の美について触れた一節がある。
もともと綺麗は奇麗でもあって、めずらしい姿を愛でる気持ちのことを言った。たんに美しいのではない。たんにキレイなのではない。その奥に何かを秘めているような感じが「綺」や「奇」という「うるわしさ」(麗)なのである。・・・日本の美を考えるには、この「綺」や「奇」という感覚を根本的に掴まえる必要がある。これは「偶」に対する「奇」の称揚というもので、「たまたま」(偶)な事象の奥に潜む「めずらしさ」や「くすしきもの」を評価する才能と関係があった。・・・その綺麗を表現し奇麗を評価できることが、世の奇才として尊ばれたのだ。
並外れて珍しく、あっと胸を打つような美しさ、すぐに説明がつかないような逸脱した奇妙こそ、それを見る者の「情」を打つ綺麗(奇麗)なのだという。このエッセイを締めくくるのが、「不思議綺麗」を写しとったような冒頭の一句だ。読む者は、牡丹がほどけ、やがて散る刹那に起こるメタモルフォーゼの「移る境」に息を呑み、変幻してやまない二重写しのイメージに陶然となる。
■風姿花伝とイシス
室町時代に能を大成した世阿弥が、秘伝書『風姿花伝』の「花」に込めたのは、「新しいこと」「珍しいこと」だった。
そもそも花といふに、万木千草において、四季折節に咲くものなれば、その時を得てめづらしきゆゑに、もてあそぶなり。申楽も、人の心にめづらしきと知る所、すなはち面白き心なり。花と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり。 (『風姿花伝』第七 別紙口伝)
人は、珍しく新しいものであるからこそ面白いと感じるのだと、花と芸能をインタースコアした世阿弥。生成変化のないところに「花」は咲かない。身に迫る危機意識のさなか、後継者のために書き綴った花伝書には、つねに新しく珍しいものをつくり出し、それを人の望む「時」を捉えて取り出す革新の知が注ぎ込まれていた。校長が世阿弥の切実ごと、芸能と学習の方法をアルス・コンビナトリアして『風姿花伝』に肖って名づけたのが、イシス花伝所だ。編集の型を身に着け、新しい見方を見出し、新たな自分と世界を創造するための編集稽古。その指南役を育てる苗代で伝授することは、校長が千夜千冊第1508夜 西平直『世阿弥の稽古哲学』の冒頭に綴った世阿弥の方法と重なる。
世阿弥は「型」と「稽古」を重んじた。二曲三体を指定して、我見と離見を組み合わせた。「時分の花」と「離見の見」によって芸能のあれこれを深々と指南した。そこに無文と有文とが区別され、一調・二機・三声が生じ、驚くべき「却来」という方法が萌芽した。
意外なことに能の舞と歌(二曲)には「型」がないという。曲は習うことができない位相であり、実体のない音楽性、「心」だからだ。型のある「節」をひたすらまねる稽古を極めた先に、おのずから匂い出すのが曲なのである。これが型を生かした学習のヒントになるのだと、校長は語る。
世阿弥は「花」のことをしばしば「まこと」とも言った。校長の『日本文化の核心』には、「真なるもの」を映し出すのが「花」だったのだと説くくだりがある。
真なるものは容易にはつかめません。接近すらむつかしいこともある。そこで世阿弥は「真(まこと)」が外にあらわしているだろう「体(たい)に注目し、そこを「まねび」なさいと言うのです。・・・稽古とは「古(いにしえ)を稽(かんがえ)る」ということです。「古」は真を孕んでいるかもしれない。それは「もともと」です。その「もともと」の「古」に風体をもって接近するために、ひたすら稽古をする。それにはどうしても「物学(ものまね)」が必要です。古の「もの」に学ぶことが必要です。日本における「もの」は「物」であって「霊」です。
世阿弥は「まねび」を稽古することをもって「まこと」に近づいていくことを「まなび」としたのだという。
校長の『擬』には、日本の芸能はモドキを媒介にして、姿やかたちを持たないおおもとの面影のよすがを偲ぶとあり、モドキが、面影を手繰るために欠かせない方法になっていったとも書かれている。
■寺子屋とイシス
花伝所に入伝した学衆は、道場での7週間の濃密な型の学びと真似びのなかで師範代へと相転移する。イシスをネット社会の「別世」だと唱える田中優子先生は、校長との対談集『日本問答』のあとがきで、この学校を江戸時代の寺子屋になぞらえ、師範代というロールの特異性に光を当てている。
ところで、松岡正剛のプロデュースする「イシス編集学校」では最初に、ものやことを、複数の用途や意味で認識する訓練から入る。私がこの対談で明らかにしたかったことのひとつは、学校で何を教えるか、であった。もはや知識を伝達するという意味の教育では、何もかもが間に合わなくなっている。編集学校は私から見ると「多方向からの認識力」「敏捷な組み合わせ能力」「書くこと(編集と論理)への集中力」「速い読書による語彙(観念)の発掘力」を通して、自らの言葉(思想形成)をできるだけ豊かに創造する能力の獲得をめざしていると見える。それを多くの講師による個人指導でおこなっている。エライ先生が個々人につくのではなく、かつて生徒だった者が訓練を受けて指導に当たるので、きめ細かな個人指導が可能になる。それができるのは、指導方法が松岡メソッドとして確立しているからである。すなわち、インターネット上の先端的寺子屋教育だ。
■花をかたちづくる5つのМ
学衆一人ひとりの気づきを促しながら、自由な編集状態へと導く「先端的寺子屋教育」を可能にする花伝所での学びとは、どんなものなのだろうか。紐解けば五枚のMという型の花びらがほどけていく。
М1【Model】 モデルをつかむ
学ぶ側と教える側のエディティング・モデルの交換の極意
М2【Mode】 モードを立てる
指南の言葉やハコビのバリエーション
М3【Metric】 メトリックを選ぶ
回答の理解の分岐点と可能性を測る多様な軸や視点
М4【Making】ゲームメイクする
「花は心、種は態(わざ)なるべし」――錬成場での演習
М5【Management】場をマネージする
教室というシステムを運営するためのさまざまな場面編集
花伝所の道場では、回答に注意のカーソルを向けて方法的に評価し、学衆が気づかない思考のクセ、不足や可能性を多様なメトリックで掘り起こす指南の鍛錬が続く。その試行錯誤のプロセスで、入伝生は回答の拠って立つ「地」を丹念に辿りながら受容するプロセスを学び、「他者のまなざしを、わがものとする」「離見の見」を学ぶ。学衆や場の視点を借りて、自分の見方(我見)を離れるのである。自分の中に位置づけられていた世界は、そのつどぐるりと反転して、世界の中へと自分が位置づけられる。
『世阿弥の稽古哲学』によれば、「離見の見」とは、「即座(その時その場)」の立脚点から離れ、別の視点に身を置き、そこから見返すことによって、「即座」を今までとは違った仕方で体験する一連のダイナミズムであるという。そしてこの「違った仕方で体験する」が、後日と当日の二重性であり、改めて現実を新鮮に体験することだという。我見が揺らぎ、現実が異化し、隠れていたアナザーワールドがふっと顕れ、ここと重なる瞬間――それは複式夢幻能とも、不思議綺麗の奥にある「綺(奇)」が見せる異質性やthereや存在の神秘を感じる刹那とも、どこかで繋がっているのかもしれない。
学衆の回答に潜む方法に寄り添って生まれるエディティング・モデルの交換は、関係の変化を起こし、教室という場も動かし続ける。師範代には徹底した用意と、それを半ば捨てる卒意が求められる。花伝所では、さしかかる偶然や機を活かす即興的な身体と、リアルタイムの編集の大切さを学ぶ。差異やズレ、行き詰りも再編集の契機となる。師範代が、仮説した図を別様の可能性の潜む地へと戻してはつくり直していくなかで、自己の境界も、関係の境界も変化する。皮膚に包まれた固定した近代的自己はメタモルフォーゼし続け、「移る境」の刹那ごとに拡張し、学衆と師範代の唯一無二の「その人らしさ」が共振しながら有機的に繋がってゆく。やがて教室という座にはかぐわしい花の匂いが立ち、創発と秩序がおのずから生じる。
■編集的自由へ
「型を守って型に就き、型を破って型を出て、型を離れて型を生む」という言葉がある。まず徹底して身体に型を通す。型を守っているうちに、方法を自在にさまざまな場に合わせて生かし、主体的に編集できるようになれば、型はおのずと内側から破れる。型が破れたあいだに生じるのは自己モドキらしきものだ。そこからなすべきことが顕れて、型を生む。あいだにこそ、意味が生まれ続ける。私たちはもともと、自分だけでは完結できないあいだ含みの自己であり、他者含みの自己である。その忘れていた本来が、能の呪能的な声が呼び覚ます、遠くて懐かしい何かのように蘇る。そのとき、自他の分離した近代的自己の鎖は解き放たれ、個が全体を共有し、生命の更新と編集的自由へと向かうことができる。ハイコンテキストで暗示的な相互編集は、息遣いとともに加速していく。そのおおもとにあるのが、日本という方法が培ってきた古くて新しいコーチング・メソッドを実践する花伝所なのである。
§編集用語辞典
08[花伝所]
丸洋子
編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。
「この場所、けっこうわかりにくいかもしれない」と書かれた看板を手にした可愛らしい男の子のイラストが、展覧会場の入り口に置かれている。眉根を寄せて地図を見ているその男の子を通り過ぎ、中へ進むと「あなたをずっとまっていたのか […]
八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]
公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]
千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。 グノーシスとは「原理的 […]







コメント
1~3件/3件
2026-03-03

桃の節句に、桜の葉が好きなモモスズメ。飼育していると、毎日、たくさんの糞をするが、それを捨てるのはもったいない。こまめに集めて珈琲フィルターでドリップすれば、桜餅のかほりを放つ芳しき糞茶のできあがり。
2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。
2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。