昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。




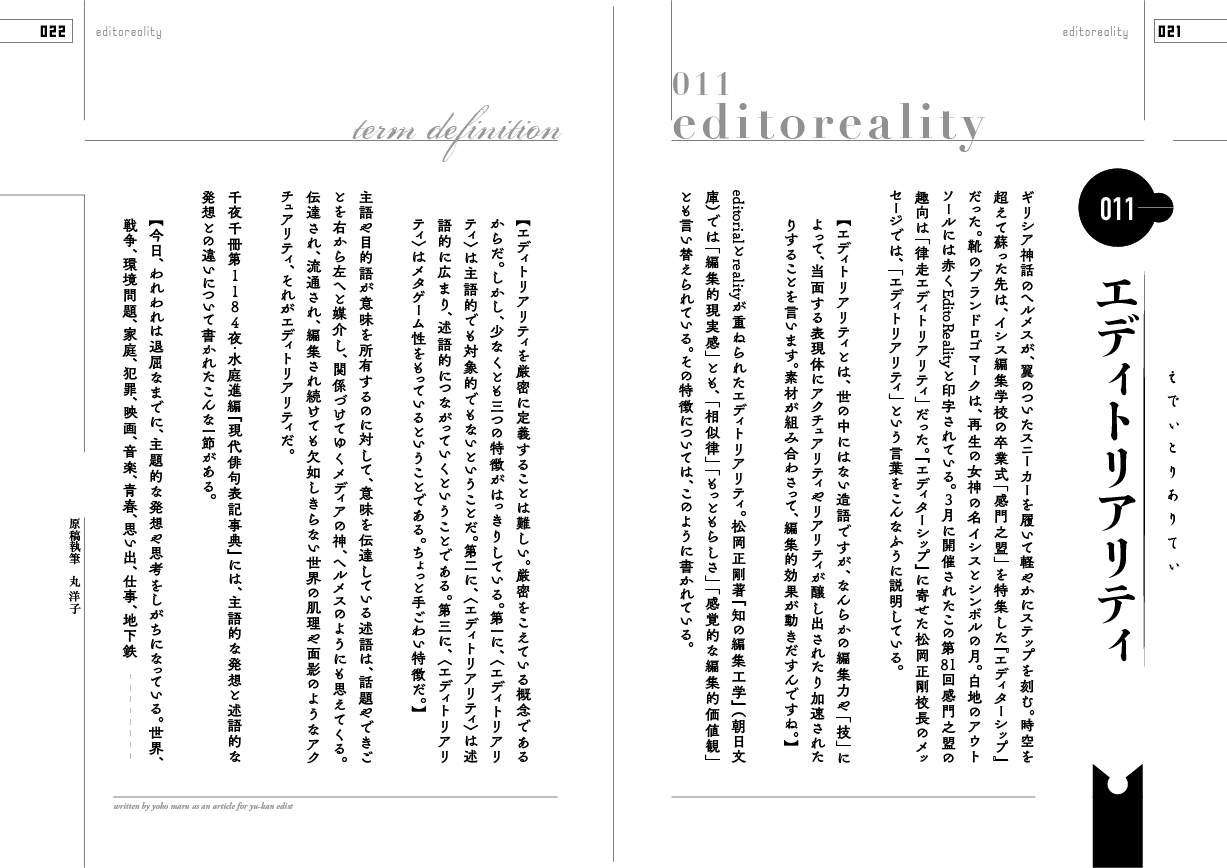
ギリシア神話のヘルメスが、翼のついたスニーカーを履いて軽やかにステップを刻む。時空を超えて蘇った先は、イシス編集学校の修了式「感門之盟」を特集した『エディターシップ』だった。靴のブランドロゴマークは、再生の女神の名イシスとシンボルの月。白地のアウトソールには赤くEditoRealityと印字されている。3月に開催されたこの第81回感門之盟の趣向は「律走エディトリアリティ」だった。『エディターシップ』に寄せた松岡正剛校長のメッセージでは、「エディトリアリティ」という言葉をこんなふうに説明している。
エディトリアリティとは、世の中にはない造語ですが、なんらかの編集力や「技」によって、当面する表現体にアクチュアリティやリアリティが醸し出されたり加速されたりすることを言います。素材が組み合わさって、編集的効果が動きだすんですね。
editorialとrealityが重ねられたエディトリアリティ。松岡正剛著『知の編集工学』(朝日文庫)では「編集的現実感」とも、「相似律」「もっともらしさ」「感覚的な編集的価値観」とも言い替えられている。その特徴については、このように書かれている。
<エディトリアリティを厳密に定義することは難しい。厳密をこえている概念であるからだ。しかし、少なくとも三つの特徴がはっきりしている。第一に、<エディトリアリティ>は主語的でも対象的でもないということだ。第二に、<エディトリアリティ>は述語的に広まり、述語的につながっていくということである。第三に、<エディトリアリティ>はメタゲーム性をもっているということである。ちょっと手ごわい特徴だ。
主語や目的語が意味を所有するのに対して、意味を伝達している述語は、話題やできごとを右から左へと媒介し、関係づけてゆくメディアの神、ヘルメスのようにも思えてくる。伝達され、流通され、編集され続けても欠如しきらない世界の肌理や面影のようなアクチュアリティ、それがエディトリアリティだ。
■述語的につながる
千夜千冊第1184夜・水庭進編『現代俳句表記事典』には、主語的な発想と述語的な発想との違いについて書かれたこんな一節がある。
今日、われわれは退屈なまでに、主題的な発想や思考をしがちになっている。世界、戦争、環境問題、家庭、犯罪、映画、音楽、青春、思い出、仕事、地下鉄、病気、大リーグ、テレビ番組、いじめ、高齢化、みのもんた ・・・。まあ、それもいいけれど、このような主題から始めるかぎりはすぐに限界がくる。それよりも、述語的にものごとがつながったり響きあったりするほうが、ずっと新鮮になる。述語的というのは、主語がなんであれそこに展開されていった述語部分の表現のことをいう。 ・・・「咳けばモネの睡蓮とろとろと」「とろとろとうつつにありし春の風邪」あたりが並んでくると、「とろとろ」も俄然動いてくる。「ぽきぽきと洋傘たたみ卒業す」「終戦日骨ぽきぽきと背を伸ばす」には、述語によってこそ共通する何かの結節がある。
『知の編集工学』では、こうした述語が発揮するエディトリアリティを、このように述べている。
私たちは主語を強調したことで思索の主体を獲得したように見えて、かえってそこでは編集能力を失い、むしろ述語的になっているときにすぐれて編集的なはたらきをしているはずなのである。
そしてその理由を、西田哲学を紐解きながらこう語る。
西田幾多郎は「無」を媒介にした述語論理が成立しうるという論述をしたうえで、こう書いた。「判断というものは、じつは主語を述語が包摂することなのだ」。これは「特殊」としての主語にたいして、述語が「一般」であることを強調したものである。そのため、人間の知識は、この「一般」の無限の層の重ね合わせとして理解されるしかないのだととらえられた。いいかえれば、人間は自分自身の底辺にある「述語面」で、あらゆる意味と意味のつながりを連絡づけているということだった。
「何が」ではなく「どのように」で繋げていく述語的なネットワークからは、果てしない広がりが見えてくる。
■世界との現実的なかかわりとしてのエディトリアリティ
ものごとの関係を発見していく「とろとろ」や「ぽきぽき」のようなオノマトペイアは、対象へと限りなく五感と心を寄せるなかから生まれてくる、主観と客観の間のエディトリアリティである。
松岡正剛の千夜千冊第1536夜『あいだ』でも取り上げられている精神科医の木村敏は、著書『自分ということ』の中で、主語と述語について、「もの」と「こと」の違いで分かりやすく説いている。「この花は美しい」というとき、「この花」は「もの」であるのに対し、「美しい」という述語は、美しいという「こと」で、「もののありさまというか、様子というか、あるいはそれに伴う気分というか、あるいはそれに対するわれわれの評価というか、そういうものを表わしている」のだという。
「美というもの」は実践を離れた美学的考察の対象となりうるにすぎないけれども、「花が美しいということ」は私たちを家からさそい出して一日の遊山という行動を起こさせる。
「もの」は中立的で客観的な対象だが、「こと」はそれに対する実践的関与を促すはたらきをもっているのである。
■共通感覚とエディトリアリティ
『知の編集工学』では、意味のつながりを連絡づける述語を、五感を結び、関係づける共通感覚という視点からも捉え直している。例えば民族や文化を越えて、「速い」というイメージには「薄い・明るい・広い」が連想され、「重い」というイメージには「下・暗い・近い」、あるいは「静かな」には「水平的な」、「騒がしい」には「曲がっている」が、密接に関係しあっているのだという。このような共通しあう感覚的なものが、エディトリアリティだ。
木村敏は著書『あいだ』で、共通感覚は「それ自体は対象化し言語化することの困難な『生の原理』でありながら、われわれがいろんな出来事を対象化したり言語化したりするときには、いつもそれに影のように伴って、それにさまざまなニュアンスを添えたり、言葉の比喩的使用という形でわれわれの言語生活を豊かなものにしてくれる」と述べている。アリストテレスも共通感覚の一様態として考えている想像力や構想力(ファンタジア)は、この共通感覚の機能と深く関係しているという。個人の感覚でありながら、世界との実践的、能動的なかかわりによって生まれる深い感覚を意味する共通感覚では、例えば視覚的な白さを「しらじらしい」、「しらける」、「潔白」、「白い目」といったメタファーとして使ったり、味覚的な甘さを「甘い情景」、「芸の甘さ」、「甘言」、「甘え」などへと意味を転移したりすることが可能となる。「甘いこと」や「白いこと」には、世界の受け取り方やかかわり方が含まれているからである。
■エディトリアリティを創造する
さらにこの書では、イタリアの思想家ジャンバッティスタ・ヴィーコの鍵概念の一つである「共通感覚」が紹介されている。ヴィーコによれば、共通感覚は「ある事柄に実際にかかわる場合の要点」であり、どの程度「真らしい」かを導く感覚だという。千夜千冊第874夜ジャンバッティスタ・ヴィーコ『新しい学』には、こう書かれている。
デカルトの『方法序説』は「理性を正しく導き、諸科学において真理を求めるための方法」を定義した。この方法は ・・・真理と虚偽を最初から分けて学問に臨む方法だった。しかしヴィーコはこれに正面から反抗し、むしろ真理は共通感覚から出所すべきものだと断言したのである。自然や世界には先験的に真理なるものなどはなく、「真理はつくられたものに等しいはずだ」というのがヴィーコの思想だった。
どんな知も変化しつづけているこの世界に、真理はない。私たちは、すでに編集された現実感を真理のごとく受け取って、仮留めのワールド・モデルの中を生きているのである。「現実は甘くない」「リアリティがある」といったときの「現実」や「リアリティ」は、社会が編集した現実感(エディトリアリティ)を指す。そうであるなら、私たちは一方的に受け取っているエディトリアリティだけでなく、私たちがそうありたい、そうなりたいエディトリアリティという自己や世界に向かって、編集を起動できるはずだ。そのような「実践の要点」であるエディトリアリティを発見するためには、何が必要なのだろうか。それは「異なったもののあいだの共通性」を見つけ出すことによって、相互に離れたところにある異なったものごとをひとつに結合する能力だと、ヴィーコは説く。そしてこれを「インゲニウム」と呼び、記憶能力と仮説能力と並んで、知識や思考を動かし、新しいことを発見するための知的能力だとした。編集学校の守や破の稽古では、このインゲニウムを引き出し、新しい価値へと向かうエディトリアリティの感覚を鍛える。
■主体と客体
千夜千冊『あいだ』では、木村敏の仮説が紹介されている。
木村さんには、木村さんの「あいだ」論で前提にしているとても大事な仮説がある。それは次のような仮説だ。「この地球上には、生命一般の根拠とでもいうべきものがあるはずであって、われわれ一人ひとりが生きているということは、われわれという存在が行為的にも感覚的にも、この生命一般の根拠とのつながりを維持しているということにほかならない。」
木村敏は著書『からだ・こころ・生命』の中で、こんなふうに語っている。たとえば子どもの怪我を目撃した母親が自分自身に激しい痛みを感じるとか、親しい人たちのあいだでは喜びや悲しみが伝染するとか、恋人どうしが一心同体のふるまいを示すとか、そういったきわめて私的な間主観性があるが、じつは、この間主観性はあらゆる人間関係のなかでいつも見られるものなのだ。
もしわたしたちが各自の身体の個別性に目を奪われ、わたしたちの日常を支配している個の自己同一性の論理に引きずられて、事実を見誤りさえしなければ、わたしたちの一見個別的な主観的経験や主体的行動の背後にも、この私的間主観性がつねに働いていて、それがわたしたちの意識や行動に一種の『奥行き』を与えていることに気づくはずです。
私的な間主観性は「個体間の生命的連帯感の根底」としていたるところで働いていて、私たちの共生関係を支えているのである。
『知の編集工学』では、「いったい主体と客体とをきっぱり分けるという方法が、歴史的にはごくごく新しいものであり、しかも近代的な社会力学の必要に応じて生まれてきたものだった」と説き、subjectとobjectの意味の変遷を辿っている。エディトリアリティは、「この主体と対象が分かれる以前の中世的な感覚である言葉の状態を取り戻すための未然性に富んだ概念でもあった」のだ。
■分断された「もの」から「こと」へ
「律走エディトリアリティ」と題した感門之盟のオープニングでの松岡校長のメッセージが、エディストの速報で伝えられた。そこには「エディトリアリティとは、本来の生命や生物や幼児が持っているものが、社会化されることで分断され、その分断を受け入れ、さらに分断されたものを取り戻す、その過程なのである」と記されている。
生命一般の根拠である情報を分節化し、分有して生まれた私たちは、矛盾やあてどなさを抱えつつエディティング・モデルの交換をし、借り物の物語を紡いではほどいて編集しつづける。主語によって分断され、社会化によって失われていった情報の「意味」や「文化」を、私たちはエディトリアリティによってひそかに交換しつづけ、発掘しては取り戻し、創造しているのである。
参考文献:
木村敏著『自分ということ』(ちくま学芸文庫)
『あいだ』(ちくま学芸文庫)
『からだ・こころ・生命(講談社学術文庫)
§編集用語辞典
11[エディトリアリティ]
丸洋子
編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。
「この場所、けっこうわかりにくいかもしれない」と書かれた看板を手にした可愛らしい男の子のイラストが、展覧会場の入り口に置かれている。眉根を寄せて地図を見ているその男の子を通り過ぎ、中へ進むと「あなたをずっとまっていたのか […]
八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]
公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]
千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。 グノーシスとは「原理的 […]











コメント
1~3件/3件
2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。
2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。
2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。