誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)




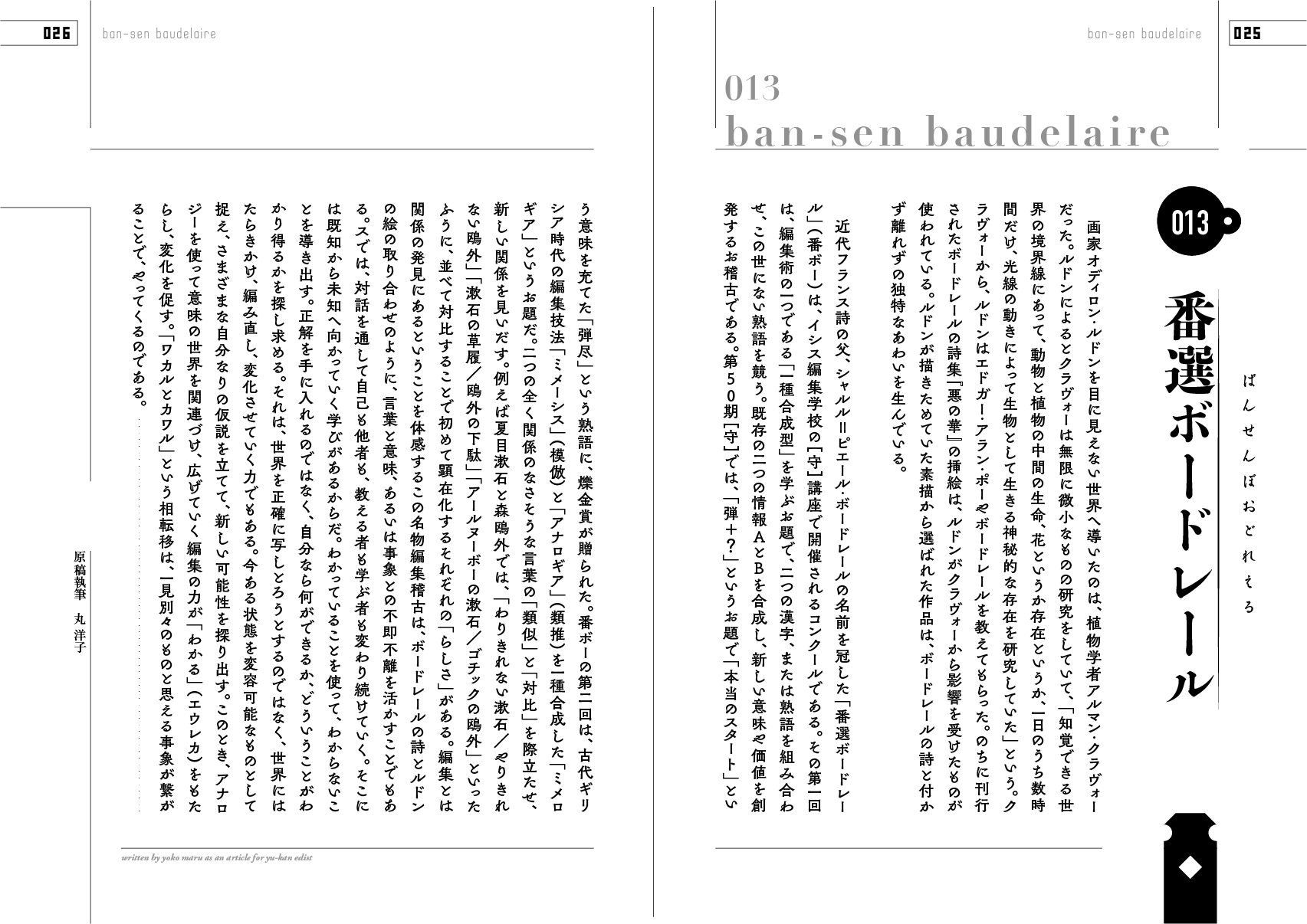
画家オディロン・ルドンを目に見えない世界へ導いたのは、植物学者アルマン・クラヴォーだった。ルドンによるとクラヴォーは無限に微小なものの研究をしていて、「知覚できる世界の境界線にあって、動物と植物の中間の生命、花というか存在というか、一日のうち数時間だけ、光線の動きによって生物として生きる神秘的な存在を研究していた」という。クラヴォーから、ルドンはエドガー・アラン・ポーやボードレールを教えてもらった。のちに刊行されたボードレールの詩集『悪の華』の挿絵は、ルドンがクラヴォーに影響を受けたものが使われている。ルドンが描きためていた素描から選ばれた作品は、ボードレールの詩と付かず離れずの独特なあわいを生んでいる。
近代フランス詩の父、シャルル=ピエール・ボードレールの名前を冠した「番選ボードレール」(番ボー)は、イシス編集学校の[守]講座で開催されるコンクールである。その第一回は、編集術の一つである「一種合成型」を学ぶお題で、二つの漢字、または熟語を組み合わせ、この世にない熟語を競う。既存の二つの情報AとBを合成し、新しい意味や価値を創発するお稽古である。第50期[守]では、「弾+?」というお題で「本当のスタート」という意味を充てた「弾尽」という熟語に、爍金賞が贈られた。番ボーの第二回は、古代ギリシア時代の編集技法「ミメーシス」(模倣)と「アナロギア」(類推)を一種合成した「ミメロギア」というお題だ。二つの全く関係のなさそうな言葉の「類似」と「対比」を際立たせ、新しい関係を見いだす。例えば夏目漱石と森鴎外では、「わりきれない漱石/やりきれない鴎外」「漱石の草履/鴎外の下駄」「アールヌーボーの漱石/ゴチックの鴎外」といったふうに、並べて対比することで初めて顕在化するそれぞれの「らしさ」がある。編集とは関係の発見にあるということを体感するこの名物編集稽古は、ボードレールの詩とルドンの絵の取り合わせのように、言葉と意味、あるいは事象との不即不離を活かすことでもある。
■番(つがい)
三十八番ある[守]の編集稽古の中から、これぞという一番を選び出した番選ボードレール。コンクールの名称にある「番」には、「つがい」の意味も重ねられている。松岡正剛著『見立て日本』(角川文庫)によれば、「つがい」とは「二つのものが組み合わさっていて、それらが代わる替わるになっていくこと」「何かが一対になって組み合わさっていること、またそうした一対を組み合わせるための仕組みや仕掛け」を指す。「継ぎ合う」から「つがう」という動詞が生まれ、それが「つがい」になったのだという。
松岡正剛は『日本流』(ちくま学芸文庫)の中で、「多様が一途によってつながっている」日本文化の面白さに、この一対の感覚を挙げている。
一対というのは、「紺と金」とか「神と仏」とか「雅びと鄙び」というような、そういう対照的な一対で、かつ相互に関係しあう一対のイメージのことです。すでに三浦梅園が発見していた方法でした。・・・日本では、こういう一対の色彩感覚が確立すると、これに対して別のジャンルに別の一対の色彩感覚が生まれるのです。いったん別のジャンルへの転移がおこると、また次がある。・・・これを「本歌」に対するに、その派生と転移、さらにはそれらの「見立て」、その見立てに対する再度の「付合」や「見立て付」というふうにみなすことができます。連歌や連句がめっぽう得意としたことでした。その移行のたびに一対の感覚が次々に飛び火する。これが日本流というものなのです。
一対は、連歌の発句を起源とした俳句にも見ることができる。松岡正剛著『フラジャイル』(ちくま学芸文庫)では、永田耕衣の「てのひらというばけものや天の川」という俳句を例に、「や」の一字がつくる「あはひ」について触れている。てのひらという極小の断片と天の川という巨大な実体。一見関係のないこの二つを一対にする「や」という切れ字から生まれる言葉のしじまに、読む者はじっと耳を澄ませ、イメージの横溢とともに時間と空間が豊かに揺蕩っていくダイナミズムに身を委ねて句を味わう。そのとき、手元の小さなてのひらと、遥かな夜空に広がる天の川との面影が、行きつ戻りつするのである。
■アワセ
日本の遊びの原型には、こうした取り合わせのような「アワセ」という方法がある。物合わせや歌合わせが発展するプロセスで、ツール(道具性)、ロール(役割性)、ルール(競技性)も多様に複雑になり、日本の文化を育んでいったのだという。『日本流』では、こうしたシステムを日本独特の「仕組」と「趣向」という一対で捉え直している。仕組は序破急のことで、全体の「筋」であり、趣向はいろいろな「事」で構成されている部分だ。この二つは全体と部分でありながら一対であり、部分は全体の構成要素というよりも、いわば「全体を変えようとしている部分」というようなもので、「超部分」なのだという。画一性や均質性ではなく、そのつど状況や場や相手に合わせて、その持ち前をあますところなく発揮する多様性である。このことを松岡正剛は、『日本数寄』(ちくま学芸文庫)では「端」と「縁」という言葉に託してこのように語っている。
そこに何かが端然と始まること、それが「端」だった。・・・そもそも編集とは、この「端」に着目し、そこに先端の気配を求めつつ、これをさまざまな他端につなげていくことをいう。編集はたんなる調整や修正ではなく、たんなる自己表現でもない。素材や状況はそこに伏せている。現前にある。花鳥風月を友とするとはそのことだ。その現前の素材や状況に応じてその一端の特徴をとらえ、そこから事態や現象を先方に合わせて新たな関係を発見していくこと、それが編集なのである。そこに端座するものから始まる進捗や出会いや包摂を大事にし、「このまま」から「そのまま」への景色の展出をはかるのが編集なのだ。したがって編集は、「端」とともに「縁」を重視する。「縁」は縁(ふち)やら渕(ふち)やらが相互にめくれあがり、つながっていくことをいう。相互の縁起をつなげ、縁談をもちかけること、それも編集だった。日本の和歌の世界が歌枕や枕詞をはじめとする縁語に満ちているのも、そのためだ。もともと海外から社会文化のコード(要素)を輸入して、これを和漢折衷ないしは和漢並立などの新たなモード(様子)に編集するのが得意な日本文化である。・・・そこには厳密な論理の整合性の継承よりも、むしろ言葉の律動や意味の共鳴こそが継承された。アワセやカサネやツラネの文化はここから生じていった。このとき「端」や「縁」が動き出す。これは事象や現象の共通する特徴をとらえることであり、そこに立ち会う者の心の機微をとらえるということである。
番ボーは、日本の文化を育んだアワセに肖り、言葉の縁起と端緒を巡る旅路でもある。
『花鳥風月の科学』(中公文庫)で、松岡正剛は「畢竟、花鳥風月とは『片方』を求めて『境』を感じる世界です」と語っている。同書によれば、古代初期には「間」はあわいを指す言葉ではなく、「真」(究極的な真なるもの)という字があてられていたという。この「真」というコンセプトは、一と一が両側から寄ってきてつくりあげる合一としての「二」を象徴していた。二である真を成立させている「一」は、「片」と呼ばれていた。「真」はその内側に二つの片方を含んでいたのだ。
それなら、その片方と片方を取り出してみたらどうなるか。その取り出した片方と片方を暫定的に置いておいた状態、それこそが「間」なのです。
片方は、「真」や「間」の半分である。先ほど『日本流』に登場した三浦梅園の千夜千冊(第933夜『玄語』)で、松岡正剛は自身の編集工学の発想や着想には、半分の「半」や「対」(つい)という考え方がいつも動いていたと述べている。
対というのは、半と半とが互いに相並んだ状態で、何かと何かで一組になっている状態のことです。この一組、あるいは一対は、私の見方ではそれ自体で「一つ」なんですね。・・・ということは、半と半で「一」になるわけで、一対にはいつも半と半とがあるということです。いいかえれば、どんな一つのことを見ても、そこには何かの半と半とがやってきていると見るとおもしろいということです。・・・その半端をきちんと見極めて、これを別の半端とつなげていったっていいんです。編集というのはそういうことを無視しない。・・・そうすると、たとえば物理学と民族学のようなまったく異質なものが、それが断片で半端であるがゆえに、ちょっとずつ繋がってくる。関係しあってくるんですね。
一つのものが果てしない相互依存の関係にある世界の一端を、そのときどきの仮の一対で合わせて繋げれば、別様の可能性が拓かれていくのである。
■ウツロイ
松岡正剛著『日本という方法』(NHKブックス)は、対比や対立があってもその一軸だけを選択せずに、両方あるいはいくつかの特色を残そうとする傾向をもつ日本という方法を、「面影」と「うつろい」という見方で解き明かす。面影は何かの「思い」をもつことがきっかけになって浮かぶプロフールの動向である。うつろいは、有為転変をあらわす言葉だ。
うつろいという言葉には、内部が空洞になっているウツ(空)という語根が入っている。ウツは、さなぎのように何かの情報を宿す生成力をもった言葉だという。そのため、ウツは「空」や「虚」とも、「全」とも書く。ウツには反対の意味を吹き出せる力があったのだ。
空っぽの何もないところからウツツ(現)というアクチュアリティが生まれるウツロイ。うつろいは、実在するものがたんに移行したり移転したりするだけでなく、見えないものと見えてくるものをつないでいる言葉でもある。一対の「あはひ」であるウツロイに面影が動き、人の想像力に、もう片方の気配が宿る。寂しいという負の感情こそが「サビ」という新しい価値を生むような、リバース・モードがはたらく力がそこにはあるのだという。
■コレスポンダンス
負のものが正になり、見える世界と見えない世界が照応するアワセとウツロイ。千夜千冊第773夜『悪の華』には、次のような一節がある。
そんな「想像としての苦み」を通して(ボードレールが)何をしようとしたかといえば、「照応」という一事が万事であった。万物反応・万物照応(correspondances)である。コレスポンダンス。この一語にはボードレールの想像力のすべてが殺到している。
ボードレールは、想像力が森羅万象を解体すれば、新たな世界像は言葉によってコレスポンダントに現出しうることを確信した。コレポンをボードレールがつくるのではなくて、ボードレールがコレポンに入ってしまうこと、それがコレスポンダンスだった。万物が照応するのではなく、照応することが万物なのだ。
一つの香水瓶の中に時空を超えた万物が滲み込んでいると詠ったボードレール。
ボードレールの照応は、方法の中での照応であり、言葉の化学反応のなかでの照応だという。照応力は互いに反応し、極小のてのひらと巨大な天の川も、ミクロコスモスとマクロコスモスも、対立する神と悪魔も、陰と陽も、相互に照らし合い、繋がり合う。
既成概念に縛られない独自の審美眼を持つボードレールは、美術批評家としての誉れも高い。番ボーは、ヨーロッパの美術批評の草分けと、好みや数寄で作品を評価する編集学校の目利き、同朋衆とのアワセでもある。
『悪の華』の草稿は、判読不能なほどの推敲につぐ推敲の跡が遺されていたという。まるで番ボーのお稽古のプロセスそのもののようだ。
§編集用語辞典
13[番選ボードレール]
丸洋子
編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。
「この場所、けっこうわかりにくいかもしれない」と書かれた看板を手にした可愛らしい男の子のイラストが、展覧会場の入り口に置かれている。眉根を寄せて地図を見ているその男の子を通り過ぎ、中へ進むと「あなたをずっとまっていたのか […]
八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]
公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]
千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。 グノーシスとは「原理的 […]




コメント
1~3件/3件
2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。