誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)




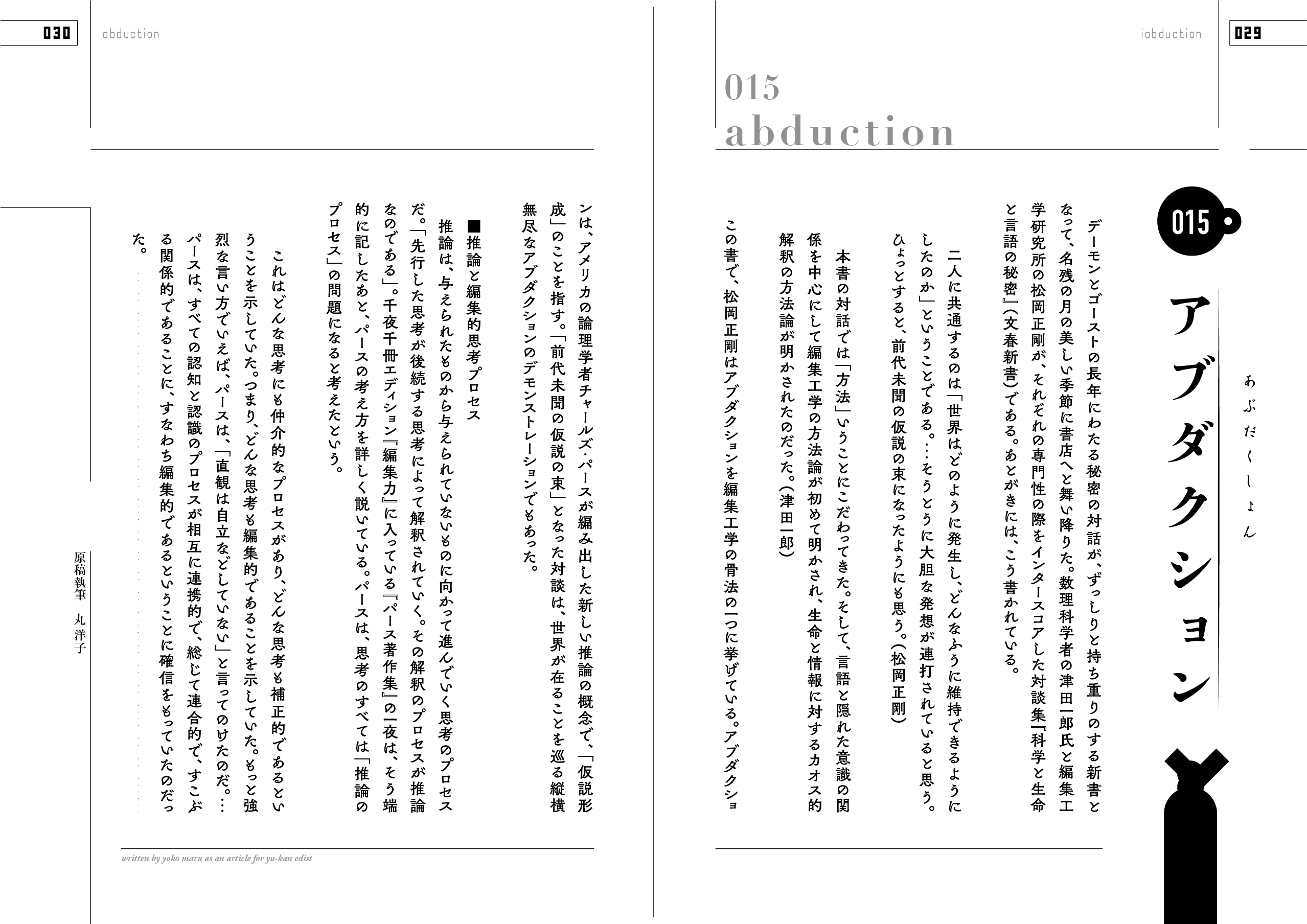
デーモンとゴーストの長年にわたる秘密の対話が、ずっしりと持ち重りのする新書となって、名残の月の美しい季節に書店へと舞い降りた。数理科学者の津田一郎氏と編集工学研究所の松岡正剛が、それぞれの専門性の際をインタースコアした対談集『科学と生命と言語の秘密』(文春新書)である。あとがきには、こう書かれている。
二人に共通するのは「世界はどのように発生し、どんなふうに維持できるようにしたのか」ということである。・・・そうとうに大胆な発想が連打されていると思う。ひょっとすると、前代未聞の仮説の束になったようにも思う。(松岡正剛)
本書の対話では「方法」いうことにこだわってきた。そして、言語と隠れた意識の関係を中心にして編集工学の方法論が初めて明かされ、生命と情報に対するカオス的解釈の方法論が明かされたのだった。(津田一郎)
この書で、松岡正剛はアブダクションを編集工学の骨法の一つに挙げている。アブダクションは、アメリカの論理学者チャールズ・パースが編み出した新しい推論の概念で、「仮説形成」のことを指す。「前代未聞の仮説の束」となった対談は、世界が在ることを巡る縦横無尽なアブダクションのデモンストレーションでもあった。
■推論と編集的思考プロセス
推論は、与えられたものから与えられていないものに向かって進んでいく思考のプロセスだ。「先行した思考が後続する思考によって解釈されていく。その解釈のプロセスが推論なのである」。千夜千冊エディション『編集力』に入っている『パース著作集』の一夜は、そう端的に記したあと、パースの考え方を詳しく説いている。パースは、思考のすべては「推論のプロセス」の問題になると考えたという。
これはどんな思考にも仲介的なプロセスがあり、どんな思考も補正的であるということを示していた。つまり、どんな思考も編集的であることを示していた。もっと強烈な言い方でいえば、パースは、「直観は自立などしていない」と言ってのけたのだ。・・・パースは、すべての認知と認識のプロセスが相互に連携的で、総じて連合的で、すこぶる関係的であることに、すなわち編集的であるということに確信をもっていたのだった。
脳の中は、知識やイメージが複雑なリンクを張り巡らせている。パースはどんな経験や思考も瞬間的な事柄ではなく、時間を要する事象であり、ひとつの連続的なプロセスとして生じていると考えた。そして時間がかかっているぶん、そのプロセスには必ず推論が起こっているはずだとみなしたのだ。パースは、自意識や心でさえも複雑な推論プロセスだと捉えた最初の哲学者だったという。
■三つの推論
推論といえば、帰納法と演繹法がよく知られている。アブダクションは、この二つの推論の奥にひそむ仮説的思考のしくみをめぐる大胆な推論の方法だという。
安藤昭子著『才能をひらく編集工学』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)では、帰納法と演繹法という二つの推論とアブダクションとを比較して、わかりやすく解説している。
パースは、帰納も演繹もそれ自体ではなんら新しい観念を生み出すことができないと言い、科学の諸観念はすべてアブダクションによってもたらされると喝破しました。「演繹」は、一般的で普遍的な事実を前提として、そこから結論を導き出す推論です。以下の三段論法の例がよく知られていますね。
[大前提]すべての人間は死すべきものである
[小前提]ソクラテスは人間である
[結論] ゆえにソクラテスは死すべきものである
・・・演繹は、「ある仮説や理論が与えられてあるものとする」という前提からはじまり、前提の中にすでに含まれている以上のことを結論として導き出すことはできません。
・・・帰納は、さまざまな事実や事例から導き出される傾向を一般化して結論につなげる推論です。「このクマは鮭を食べている。あのクマも鮭を食べている」と観察していき、「クマは鮭を食べるもの」という仮説を導くものです。最近のAIで進化が目覚ましいディープラーニング(機械学習)は、帰納法的なアプローチが成功している例といえるでしょう。
観察データにもとづいて一般化を行う推論が帰納だとすると、アブダクションは観察データを説明するための仮説を形成する推論です。「あの見知らぬ動物は鮭を食べている。もしかして、あの動物はクマの仲間では?」と、新たなアイデアを導くものです。帰納は「正当化のための文脈」(the context of justification)で機能しますが、アブダクションは「発見の文脈」(the context of discovery)でこそその力を発揮します。・・・観察された現象や経験値にあるものを、いかに結びつけ、想像力を働かせ、まだ見ぬものを想定できるか。アブダクションは、こうした「飛躍」(leap, jump)がおこる推論です。その裏では、ダイナミックに対角線を引き関係を発見していくアナロジカル・シンキングが動かないとなりません。
なるほど演繹は、大前提の仮説(新しい仮説ではないにせよ)からスタートし、帰納も、複数の事実どうしのあいだで「似ているもの」を発見する仮説によって、一般化した結論を導いている。アブダクションが仮説を形成する推論だとすれば、いっけんロジカルな演繹や帰納の奥で、アブダクションはゴーストやデーモンのように暗躍していたのだ。パースは、「想像力を働かせ」、「ダイナミックに対角線を引き関係を発見していくアナロジカル・シンキング」が発揮できるような仮説領域というステージ(アブダクティブ・ステージ)があるのではないかと考えたのだと、松岡正剛は『編集力』に入っている別の一夜で述べている。そのステージの楽屋では、相似や類似を見つけて関係づけ、新たな見方を創造していく編集力が生き生きとはたらいているのだという。(第1642夜『類似と思考』鈴木宏明)
『編集力』に入っている米盛裕二『アブダクション』の一夜によれば、パースが思考のプロセスに注意のカーソルを注ぎ見出したアブダクションは、帰納法から生まれてきた推論だという。
もともとアブダクションは帰納法の途中から発展してきました。事例をどこまでも集めるだけではキリがないとき、いったん仮説を設定して、その仮説の地平からあたかも戻ってくるように推論を仕上げるという方法です。
では二つの推論の違いは、どこにあるのだろうか。
どこが帰納法とアブダクションとで大きく異なるのかといえば、次の点にあります。ひとつにはアブダクションは「われわれが直接に観察したこととは違う種類の何ものか」を推論できるということです。残念ながら帰納法には「違う種類のもの」は入りません。似たものばかりが集まってくる。けれどもアブダクションは「違うもの」を引き込むことができる。ここがとても重要なところです。
もうひとつには、アブダクションは「われわれにとってしばしば直接には観察不可能な何ものか」を仮説できるという特色があります。いまだに例示されたことのない仮説的な命題や事例を想定することができるのです。これは哲学や社会学がこれまで前提にしてきた概念で言うと、いわば「ないもの」さえ推論のプロセスにもちこむことができるということで、きわめて大胆な特色になります。ぼくが気に入っているのは、ここなんですね。
このような驚くべき特徴は、アブダクションには例外性や意外性をとりこめる「飛躍」(leap)があるということを示します。
人類史において科学の大きな転換点を創ったニュートンは、木陰に座り、リンゴが地面に落ちるのを見て問いを立て、目には見えない力の存在をアブダクションした。そして、月が地球を回る不思議と繋げたのだった。
■注意のカーソルで、問いを立てる
『才能をひらく編集工学』ではニュートンを例に挙げ、アブダクションが動き出すエンジンは「驚く」ことにあると説いている。
たとえばニュートンは、「なぜいつも林檎は真下に落ちるのか?」という疑問から、「万有引力の法則」を導きました。
落ちる林檎を「驚くべき事実C」と認識したところから、ニュートンの探究は始まります。「引力」という〈説明仮説H〉を持ち込めば、林檎が落ちるのも、樹の葉が落ちるのも、すべて説明がつく。そしてニュートンは、地上の物体間においてだけでなく、同じ「引力」が天体間にも働いていると考えて、地上と天上の運動を統一的に説明しうる万有引力の原理を確立しました。
地上界と天上界の物体の運動はまったく違う性質のものと考えられていた当時においては、はなはだクレイジーな仮説に映ったことと思いますが、この発見が後の科学を大きく進展させたことは周知の通りです。強力なアナロジーの力がもたらした、創造的飛躍(leap)を伴うパラダイム・シフトでした。
パースは、推論では感覚や知覚が「注意」(attention)によって編成され、再編成されていくことを重視したという。当たり前だと見過ごしたり、断定したりすることなく、新鮮な驚きをもってものごとを捉えなおすことが、私たちに問いと探究を引き起こし、新たな仮説の余地を生む。注意のカーソルで、対象へエンパシーとともに寄り添い、細やかな観察をする。そこから推論と洞察や発見が徐々に導かれ、私たちの世界に豊かな意味や価値がもたらされていく。『パース著作集』の一夜には、こう書かれている。
「感情(フィーリング)、他者についての感覚、そしてこれらに媒介すること。この三つのほかに意識の形式はない」。いったいこのメッセージに何を加える必要があるだろう。これで十分なのだ。「知覚者によって知覚されていないことがある。それは知覚者が何を知覚しているかということである」。まさに、この通りだ。この問題以外に、脳科学者や認知科学が考えることがあるのだろうか。「思惟と論理は不可分の関係にある。なぜなら人間の思惟は類似を通して前に進んでいるからだ」。そうなのだ、われわれはアナロジカル・シンキングをしている動物であって、どんなときもつねにメタファーをさがしている存在者なのである。
松岡正剛は『アブダクション』の一夜で、編集的な思索には「アブダクション→演繹→帰納」の順に進めることが大切だと説く。
ここに与えられた問題があるとします。・・・このとき、最初から問題の中に含まれる「驚くべき事実C」にできるかぎり早く注目してしまうことを奨めたい。いいかえれば、その問題に含まれる意外性や例外性をできるだけ早めに発見して、つまりは早々に「ゆきづまり」を想定して、それがどんなに非常識に見えようとも、その意外性や例外性を議論できる仮説ステージを早期につくってみることです。つまりアブダクションを最初におこしてしまうのです。
ふつう、問題にとりかかってしばらくは、その問題の中心部にあることばかりを追いかけるでしょう。それはもちろん必要なのですが、同時にそこにまじっている異質性にも注目する必要があるのです。これは九鬼周造が「いき」とか「偶然性」と呼んだものにもあたります。
それには、与えられた問題をさまざまな角度で検討して、この仮説から観察可能な予測がどのくらいあるのかを演繹的に導き出しておくようにします。これでとりあえずの問題の方向が見えてきたら、その問題が社会や企業や人間の認知過程でどのくらい確かめられるものになるのかを、帰納的に調べます。・・・当初のアブダクションと最後の帰納とのあいだで、適宜、演繹的な実証説明をすればいいのです。
ニュートンがアブダクションした万有引力の法則や三つの法則は、コペルニクスやガリレオやケプラーといった先人たちのゆきづまりを、一気に打開した。
「驚くべき事実C」や異質性がアブダクションを引き起こすとすれば、その背後にあるものとは、何だろうか。
■共通感覚と暗黙知
私たちの推論を支えているアナロジカルやメタフォリカルな思考は、脳の複雑なリンクから生まれる。そこで活躍しているのが、私たちの五感を貫いてそれらを統合する、未分節で根源的で述語的な感覚――共通感覚だ。それはたとえば「ばらの甘い香」「世間知らずの甘い考え」といったようなメタファーにも表れている。『編集力』に入っている中村雄二郎『共通感覚論』の一夜によれば、共通感覚は「五感をバラバラにしないで、つねにそのいずれかを複合的に組み合わせて発揮してきた知覚」であり、「心身相関の場所」であり、「他のすべての人々のことを顧慮し、他者の立場に自己をおく立場のこと」をいう。それは、きわめてパーソナルで身体的な受け取り方や見方を主体的に表現しながら、世界や他者と出会う方法である。普遍的な正誤の価値判断ではなく、そのつどその場や文脈にふさわしいもっともらしさ(plausibility)を発揮する感覚でもある。こうした能動的、実践的なかかわりである共通感覚――主体と対象が分かれる以前の言葉の状態を取り戻すための未然性に富んだ概念であるエディトリアリティが、我見を超えた別の視点から私たちの注意のカーソルを促し、目に見えない連携や統合を通して「驚くべき事実C」の発見やアブダクションを突き動かしているのかもしれない。
アブダクションは新しい発見を生む推論だが、この「発見」のメカニズムに「暗黙知」という、言語による明示化の限界を超えた方法知の存在を掲げたのが、マイケル・ポランニーである。『編集力』の『暗黙知の次元』の一夜によれば、ポランニーは生涯をかけて「発見とは何か」ということを研究したという。
ポランニーの言う暗黙知とは科学的な発見や創造的な仕事の作用の出入りした知のことなのである。思索や仕事や制作のある時点で創発されてきた知が暗黙知なのだ。
「発見」は、「知ること」(知識)と「在ること」(存在)のあいだがつながったときにおこる。パースがあらゆる認知と認識のプロセスが相互に連携的、連合的、関係的であると確信していたように、ポランニーは発見のプロセスを研究するにつれ、「知ること」と「在ること」のあいだには「見えない連携」のようなものがはたらいていて、私たちの想像力や創造力も、それを発見しようとしているのではないかと考えたという。私たちは言語というアーティキュレーションによって世界を分節化することで、ものごとが分かり、知識として蓄える。この分節化によってとりこぼされた、言語的分節の奥にある潜在的な知が暗黙知であり、私たちの言語的分節を支えているのだという。『共通感覚論』の著者である中村雄二郎による『述語集』には、暗黙知においては私たちの身体が関与し、そこに「棲み込み」(dwelling in)が起こるとある。諸部分からなる事物の全体的な意味を理解するために、外側から眺めるのではなく、事物の中に潜入するのである。『暗黙知』の一夜を取り上げた先日の「おっかけ!千夜千冊ファンクラブ(オツ千)」では、吉村堅樹林頭が、この自己の内面からの捉えなおしによる統合と共通感覚との関連性を説いている。
『編集力』によれば、暗黙知によって「知ること」と「在ること」を繋げる発見に必要なのは、「推測するためのアート(技芸)感覚」、「未知のものを見るスキル(技能)」、「それが妥当である(レリバンス)と判断する標準性」の三つである。オツ千では、穂積晴明方源がこの三つを編集学校で大切にしている3A(アナロジー、アブダクション、アフォーダンス)と照合させて語っている。
ポランニーは、知を新たな更新に導くものは、その知識にひそむ方法知であり、その方法知がアート、スキル、レリバンスで組み立てられていると見たのだという。
ポランニーは技能のなかにこそ、のちの創発を喚起する方法が芽生えていると見通したのである。一般には、技能は対象に向かって行使され、その技能を借りて発見に到達するとおもわれているのだが、そうではなく、その技能を行使しているプロセスが次の発見をよびこみ、発見を呼び覚ます秘密をもっていたのである。
あらかじめ未知の対象がそこに設定されていなかったからといって、その設定のために使われた方法によって、設定されていなかった新たな知を生み出すということがありうるということだ。・・・方法をめぐる編集的プロセスのすべてに、大小無数の暗黙知が分節されていると言いたいくらいなのである。
言語や知識の奥にある「在ること」へと至るための新たな発見(もっともらしさ)の秘密は、方法や型を通した手続きのなかにあったのだ。
■編集稽古とアブダクション
パースは、「注意」(attention)こそが、後続する思考に大きな影響を及ぼしていると考え、推論の中身は、注意のカーソルの動向が示す多焦点によって姿をあらわす「解釈思想」だと捉えた。この解釈のプロセスを、編集学校では「編集十二段活用」や「編集八段錦」や「BPT」(ベース・プロフィール・ターゲット)といった型で取り出し、「意味のふくみあいの世界」の可能性を広げていく。編集学校では、ほかにも脳の思考プロセスを、型を使ってハイパーリンク状態にして、新しい発見的視点や価値へとつなげるお稽古をする。たとえば「コップは何に使える?」というお題では、情報の地と図に着目し、解釈の視点を切り替えていく。「部屋にないもの」では、ここにないものにも注意のカーソルを注ぐ。「豆腐で役者を分ける」では、仮説によって情報の「らしさ」(plausibility)を取り出す。さらには情報を関係づける編集思考素の型など、【守】で学ぶ用法1から4まで、アブダクティブ・アプローチの鍛錬がひしめいている。そうやって自分の推論的思考の方法を意識的に活用していくことで、エディティング・モデルの交換やインタースコアによって自己と他者を編集する方法をコミュニケーションの場で起こしていく力が、身につくのである。
編集学校のお稽古では、学衆はお題に向き合うときに仮説を立てて回答する。それまでに見たことがない、正解のないお題だからである。師範代は学衆の回答を受容し、方法を取り出し、教室という生きた場の動きを内側から捉えて、仮説をそのつど立て直す。そのプロセスでおのずと自己変容を起こしながら、場の生成に関わり合う。「問感応答返」をとおしたエディティング・モデルの交換とは、自己と場所がともに変化しつづけるような主体的なコミットでもある。
■アブダクションと言語の発生
パースは、人間には適切な問題意識と仮説を選び出す生得的本能があると考えていたという。最近話題になっている今井むつみ・秋田喜美著『言語の本質』(中公新書)では、人が言葉を持つようになった謎を解き明かす鍵の一つにアブダクションを挙げている。筆者は乳児が言葉を覚えていくプロセスをさまざまな実験を通して研究した結果を踏まえ、人間が仮説を形成し、それを自己修正していく驚くべき力に注目している。
アブダクション推論によって、人間は言語というコミュニケーションと思考の道具を得ることができ、科学、芸術などさまざまな文明を進化させてきたと言えるかもしれない。・・・人間はあることを知ると、その知識を過剰に一般化する。ことばを覚えると、ごく自然に換喩・隠喩を駆使して、意味を拡張する。ある現象を観察すると、そこからパターンを抽出し、未来を予測する。それだけではなく、すでに起こったことに遡及し、因果の説明を求める。これらはみなアブダクション推論である。人間にとってアブダクション推論はもっとも自然な思考なのであり、生存に欠かせない武器である。
アブダクションは、生命に根ざした実践であり、言葉や文明の発明の母であり、絶え間ない仮説形成と自己修正は、世界と出会いつづけるための主体的なかかわり方――エディトリアリティの実践である。
■大澤真幸氏の特別講義
今年の7月に、社会学者の大澤真幸氏が「真理の不能:編集力はなぜ必要か」と題した特別講義を本楼でおこなった。アブダクションを編集の精髄として取り上げたその講義の詳しい内容が、エディスト記事に紹介されている。世界は、ほかならぬこの私に向けて呼びかけているのか? たとえその疑いが拭い去れないにしても、それでもとりあえずその呼びかけを仮説して信じる――つまりアブダクションは、世界からの呼びかけを見出す切実な方法でもあるという。呼びかけを見出すとは、『暗黙知』の一夜で語られていた「『知ること』と『在ること』とのあいだが何らかの方法でスパークするようにつながった」ことでもあるのかもしれない。
現代に生きる個人にとって、「私」と「世界」はどこか分断されていて、自分が世界にコミットしているという生き生きとした実感は持ちにくい。大澤氏によれば、編集とは「世界からの呼びかけをどのように見つけるかという技術」である。その背景には、「世界は我々のためにあるのか」という強烈な疑いがあることを知っておくことが、大切だという。世界から何が問われているのか、それが見つかれば、人はそれに応答することで、情報を動かし、主体的にコミットできる。私たちは、これまで世界を編集してきた過去の人々から呼びかけられている。先人の声に耳を澄ませ、寄り添い、棲み込み、考え方や生き方を辿り、新しい仮説を創造して、現在も過去の意味もエディットしなおす。編集工学研究所のモットーの一つ、「歴史を展く」ことが、その応答である。すでに編集されている社会や、これまでの自分の見方をアブダクティブに再編集し続けるプロセスが、世界と自己とをつなげていくために必要なのだ。
■主客の入れ替え
先月出版された松岡正剛著『増補版 知の編集術』(朝日文庫)に、大澤真幸氏は編集工学が大切にしている3Aをもとに解説を寄せている。編集工学においては、情報を関係づける技法の基本であるアナロジーは、それが意味をもつような全体的な領域である「世界」を定めたあと、別様の可能性が立ち現れるという。世界定めの壁は外に開かれ、何かを迎え入れられるような隙間(アフォーダンス)がたくさん開いている。そしてあちらの世界からやってきた情報(客人)との「主客の入れ替え」が起こるのだ。客人こそが主人になるのである。この反転がアブダクションなのだという。デーモンやゴーストやマレビトは、自分の中にアブダクティブな深い軒を用意したときにやってきて、そのつど「知ること」から「在ること」へと私たちを導いてくれるのかもしれない。
§編集用語辞典
15[アブダクション]
丸洋子
編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。
「この場所、けっこうわかりにくいかもしれない」と書かれた看板を手にした可愛らしい男の子のイラストが、展覧会場の入り口に置かれている。眉根を寄せて地図を見ているその男の子を通り過ぎ、中へ進むと「あなたをずっとまっていたのか […]
八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]
公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]
千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。 グノーシスとは「原理的 […]








コメント
1~3件/3件
2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。