ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。




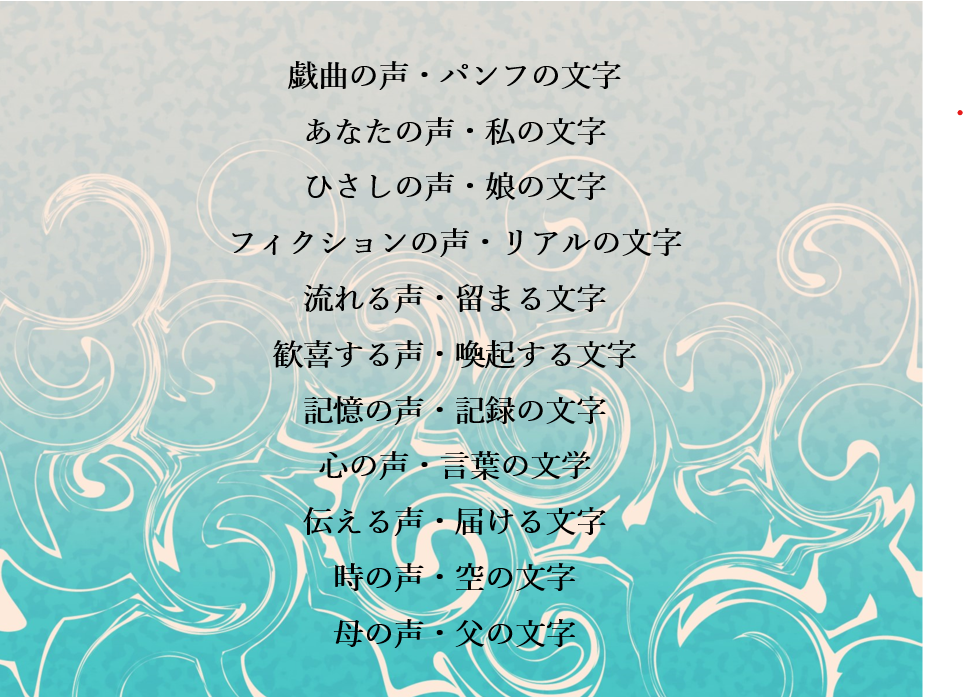
井上麻矢さんを招いての特別講義には、53[守]の学衆を中心に100名近くがZoomで参加していた。
開始早々、師範の石黒好美がチャットで檄をとばした。「私たちにとってはチャット欄が稽古場です!前に進んでいきましょ~」
その檄が実体となったのは、「井上ひさし生誕77フェスティバル」に寄せられたコメントを、麻矢さんが紹介した時だった。~台本を開いて、一つひとつの言葉をそこから聴くのです。(演出家・栗山民也)~
「いま 声・文字 の話だ!」石黒がチャットに書き込む。
「おお、ミメロギア!」師範の角山祥道が続く。
特別講義の7月14日は、025番「即答・ミメロギア」の出題日。お題に「声・文字」があったのだ。
「戯曲の声・パンフの文字」角山が即答する。
「あなたの声・私の文字」師範の紀平尚子が続く。
「ひさしの声・娘の文字」(紀平師範)
「フィクションの声・リアルの文字」(上原悦子師範代)
「流れる声・留まる文字」(本城慎之介師範代)
「歓喜する声・喚起する文字」(角山師範)
「記憶の声・記録の文字」(コードブレイカー教室 Tさん)
「心の声・言葉の文学」(ナイーヴ朋楽教室 Nさん)
「伝える声・届ける文字」(橘まゆみ師範代)
「時の声・空の文字」(花伝所 Kさん)
「母の声・父の文字」(花伝所 Kさん)
講義の言葉とリンクしながら、声と文字のシソーラスが広がる。師範、師範代、学衆に、花伝所のメンバーも加わり、10分あまりで11のミメロギアが生まれた。
「何をする時にもシソーラスを徹底的にあつめて、物語を作り出す。それをパッケージにまとめて、そこから拡げる。その過程を楽しむ」麻矢さんの仕事の極意は、ミメロギアの極意でもあった。
19年前の12[守]胸中サンズイ教室でつくったミメロギアを、麻矢さんは記憶していた。「魂のエアロビ・命のコンビニ。珍しく師範代に褒められた回答だったのです」。
025番出題から3日め。53[守]のあちこちから、忘れられないミメロギアの胎動が聞こえている。
(文:石井梨香)
イシス編集学校 [守]チーム
編集学校の原風景であり稽古の原郷となる[守]。初めてイシス編集学校と出会う学衆と歩みつづける学匠、番匠、師範、ときどき師範代のチーム。鯉は竜になるか。
世間では事業継承の問題が深刻化しているが、イシス編集学校では松岡校長の意伝子(ミーム)を受け継ぐ師範代になるものが後を絶たない。56[守]では、初の”親子”師範代、スクっと芍薬教室の原田遥夏師範代が誕生した。まもなく卒門 […]
春のプール夏のプール秋のプール冬のプールに星が降るなり(穂村弘) 季節が進むと見える景色も変わる。11月下旬、56[守]の一座建立の場、別院が開いた。18教室で136名の学衆が稽古していることが明らかに […]
番選ボードレール(番ボー)エントリー明けの56[守]第2回創守座には、教室から1名ずつの学衆が参加した。師範代と師範が交わし合う一座だが、その裏側には学衆たちの賑やかな世界が広がっていた。 師範の一倉弘美が俳句で用法3を […]
秋の絵本を「その本を読むのにふさわしい明るさ」で3つに分けると、陽だまり・夕焼け・宵闇になる。 多読アレゴリア「よみかき探究Qクラブ」のラウンジに出された問い「本をわけるあつめる。するとどうなる?」への答えだ。 クラブで […]
教室というのは、不思議な場所だ。 どこか長い旅の入口のような空気がある。 まだ互いの声の高さも、沈黙の距離感も測りきれないまま、 事件を挟めば、少しずつ教室が温かく育っていく。そんな、開講間もないある日のこと。 火種のよ […]



コメント
1~3件/3件
2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。
2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。