昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。




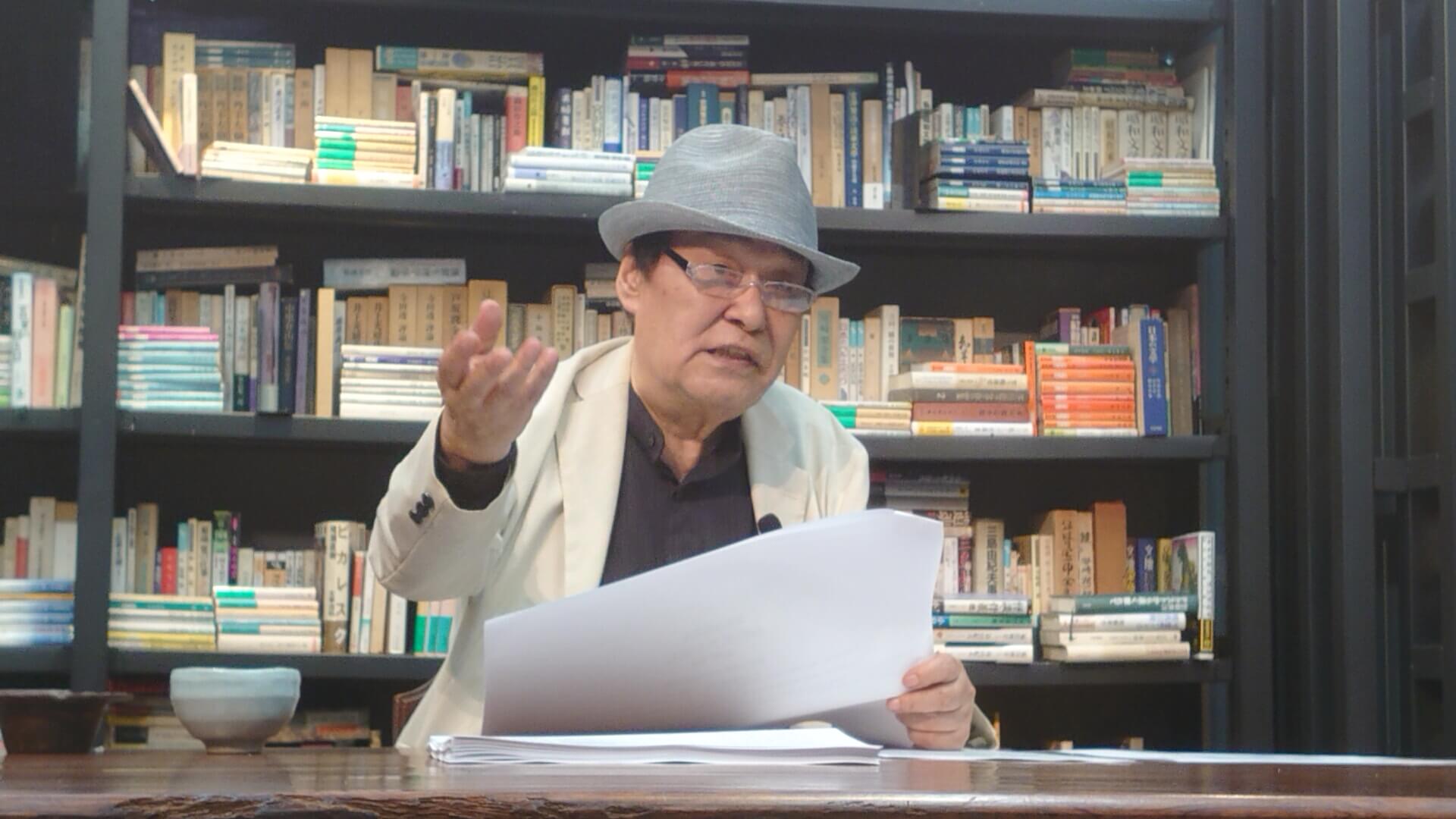
「事件がない」という事件
我々はともすると事件やスキャンダルに目が向かいがちだ。しかし本当に注視すべきは、事件なき平時の編集なのである。
6月27日の午後、輪読座第三輪では柳田国男の農業政策や日本語問題を輪読していた。同じ頃、とあるウェブサイトのトップニュースに目を向けると、秋田で真夏日記録、ワクチン接種後のコロナ陽性判明、賠償金着服疑いで弁護士逮捕、自転車レース事故といった有事ばかりが並ぶ。
しかし、110年前の1911年に柳田国男が注目したのは、事件やスキャンダルではなかった。その対象は、山梨県の道志村。現代ではもちろん、当時ですらおそらくメディアで取りあげられないであろう、事件とは無縁の「普通の村」だった。
常民は平時に有事を編集する
道志村調査の前年にあたる1910年、柳田は郷土会の幹事となった。後援者には、郷土としての日本に興味をもち、地方学(ぢかたがく)や農政学を独自に編集した新渡戸稲造がいる。
郷土会では、「文化の中央偏重抑止」「西欧科学の盲目的摂取の批判」「実地調査に基づく土着の価値発見」を重視した。都市部や西欧ではなく、各地の村で培われている方法を重視する柳田の思想が、端的にあらわれている。大きなニュースがないということは、平時から有事を想定した編集がなされているということでもある。それゆえに、柳田は災害や戦乱からは無縁の自立した「普通の村」の常民の方法に着目したのだった。
「柳田のこうした見方の原型には、幼少期の飢饉体験があり、柳田農政・民俗学の基礎になっている」とバジラは仮説する。
柳田が『蝸牛考』を著したわけ
こうした柳田の一貫した姿勢は、標準語を求める国語学への批判にもあらわれている。
柳田にとって「標準語を決めるのは『聴く者』や『使ふ当人』」であった。生まれ育った村で使われ親の語ることばが、本来の標準語だと考えた。各地で様々な言葉が用いられる「たくさんの標準語状態」が、柳田のエディトリアリティであったのだろう。
柳田の著書の一つに『蝸牛考』がある。全国に生息する「カタツムリ」の呼び方を調べ、その分布が日本では円周型になっているという「方言周圏論」を打ち出した論書である。
「方言周圏論」とは、地理的に見て方言が同心円上に分布されていて、文化的中心地付近ほど新しい言い方が広まっており、離れるほど古い言い方が残っているという考えを指す。例えば、当時の文化的中心地出会った近畿地方では「デデムシ」という新しい言い方が、中部や中国地方では「マイマイ」、東北北部や九州西部までいくと「ナメクジ」という分布になっているという。
この多様な言葉のあり方こそ、柳田の考える本来の標準語のあり方だったのだろう。もしかしたら柳田は、ダイバーシティへの理解や予測不可能な時代と呼ばれる21世紀の課題を、とっくに先取りしていたのではないだろうか。
こうした柳田の思想は、次の言葉に凝縮されている。
方言の消失は思考の多様性の消失、ことばの画一化は日本文化・世界観の消失
(バジラ高橋による図象より)
21世紀にもし柳田が生きていたら?
事件や有事に目が向かってしまうのは、20世紀も21世紀も変わらない。
しかし、21世紀はグローバル資本主義や標準化のもと、柳田のいう常民や方言の方法がますます追いやられているのではないか。
「もし柳田が生きていたら、どのように行動するだろう?」
柳田という方法は、不透明で先が見えないコロナ時代の今、再編集される時を待っている。

上杉公志
編集的先達:パウル・ヒンデミット。前衛音楽の作編曲家で、感門のBGMも手がける。誠実が服をきたような人柄でMr.Honestyと呼ばれる。イシスを代表する細マッチョでトライアスロン出場を目指す。エディスト編集部メンバー。
11/23(日)16~17時:イシスでパリコレ?! 着物ファッションショーを初披露【別典祭】
本の市場、本の劇場、本の祭典、開幕! 豪徳寺・ISIS館本楼にて11月23日、24日、本の風が起こる<別典祭>(べってんさい)。 松岡正剛、曰く「本は歴史であって盗賊だ。本は友人で、宿敵で、恋人である。本は逆上にも共感に […]
第89回感門之盟「遊撃ブックウェア」(2025年9月20日)が終了した。当日に公開された関連記事の総覧をお送りする。 イシス校舎裏の記者修行【89感門】 文:白川雅敏 本を纏う司会2名の晴れ姿 […]
「松岡校長のブックウェア空間を感じて欲しい」鈴木康代[守]学匠メッセージ【89感門】
読書することは編集すること 「読書」については、なかなか続けられない、習慣化が難しい、集中できずにSNSなどの気軽な情報に流されてしまう――そうした声が少なくない。 確かに読書の対象である「本 […]
第88回感門之盟「遊撃ブックウェア」(2025年9月6日)が終了した。当日に公開された関連記事の総覧をお送りする。 なお、今回から、各講座の師範陣及びJUSTライターによる「感門エディストチーム」が始動。多 […]
「松岡正剛の方法にあやかる」とは?ーー55[守]師範陣が実践する「創守座」の場づくり
「ルール」とは一律の縛りではなく、多様な姿をもつものである。イシス編集学校の校長・松岡正剛は、ラグビーにおけるオフサイドの編集性を高く評価していた一方で、「臭いものに蓋」式の昨今のコンプライアンスのあり方を「つまらない」 […]


コメント
1~3件/3件
2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。
2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。
2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。