鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。




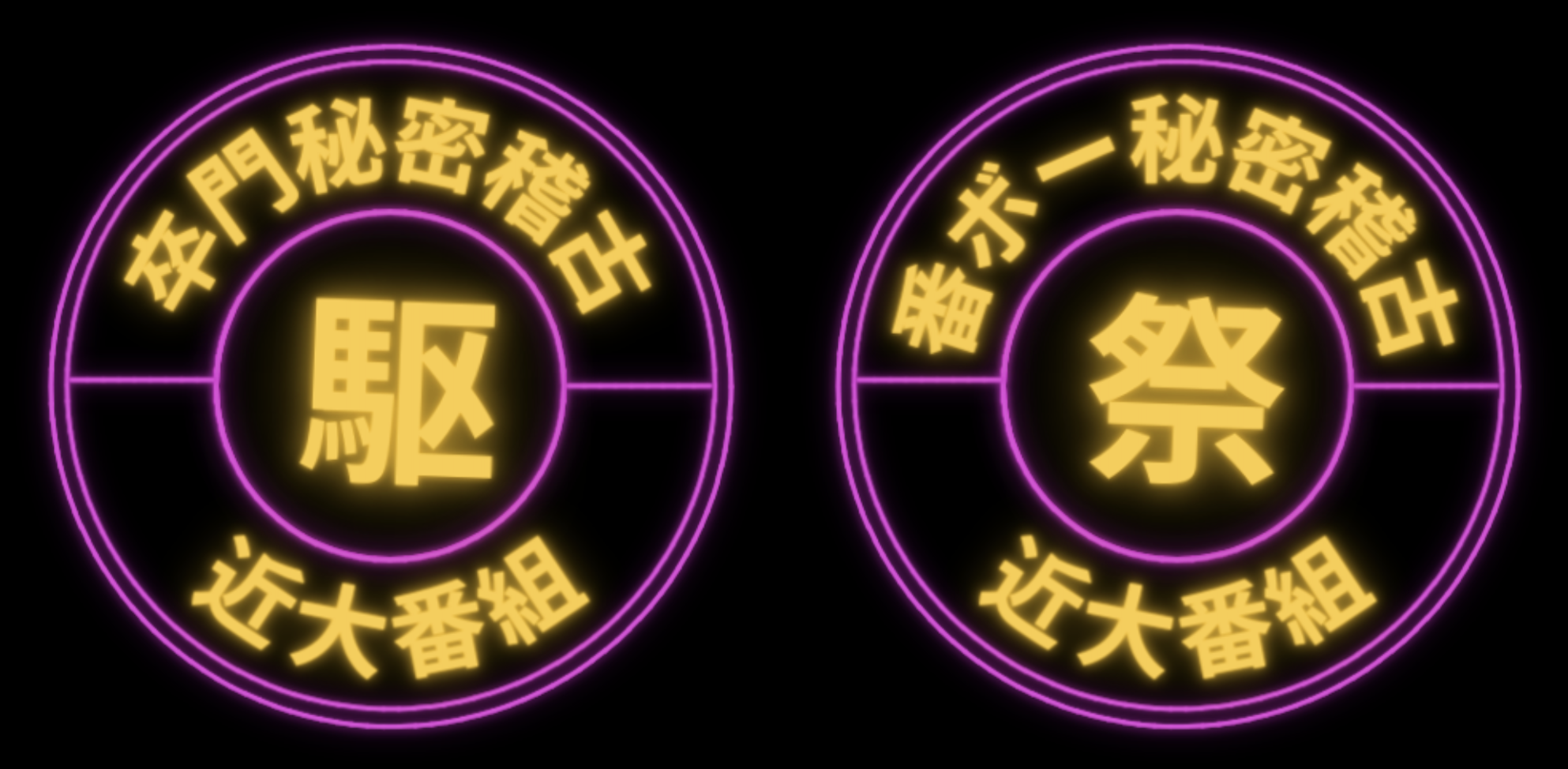
「坊主」とは、髪を剃った僧侶を指す。放っておいても生えてくる髪の毛は、消そうとしても消せない煩悩の象徴。剃髪することで、煩悩を打ち消す第一歩と言われる。
一方で、「ボウズ」とは、釣り人のスラングであり、皮肉な言葉。
目的の魚が1匹も釣れずに終わることを指す。由来は、髪の毛を魚に見立て、「毛がない」、つまり、1匹も「魚がいない」というわけだ。
11月、12月に「祭りだ!番ボー秘密稽古」と銘打った近大生交流会を開催し、2月7日は、第3弾「駆け込め!卒門秘密稽古」を予定。2月11日の卒門に向けて、稽古の困りごとの相談や難しいと感じるお題に近大番と一緒に取り組むもの。稽古のフォローアップの機会だ。
⬛︎19:00 準備は万全
稲森久純・阿曽祐子・景山和浩の近大番に、学林局・衣笠純子の4人は、開始時刻の30分前に集まった。本日のプログラムの流れを確認し、19:30を待ち望んだ。
⬛︎19:40 竿はピクリともせず
ZOOMの画面に映るのは指導陣4人だけ。衣笠純子の柔らかく包み込むような温かい声で、大人のトークタイムだね〜のセリフが印象的。ここで編集とは何たるものか思い出してほしい。
編集は遊びから生まれる。
編集は対話から生まれる。
編集は不足から生まれる。
編集学校の校訓、コンセプト。松岡正剛の『知の編集術』(講談社現代新書)の序文に記される3つのテーゼだ。
この不足を「機」と捉え、指導陣4人は対話から、遊び倒した。
⬛︎19:45 風向きと潮目が変わる
「集客の最適解とは、何なのか」から話題がスタートした。
本の帯を見て本を買うよね。佐藤優氏の帯をよく見るよね。今の100分de名著のローティって校長の千夜千冊につながるね。魚が集まりたくさん釣れることってなんて言ったけ? 入れ食いの反対の言葉は? なぜ稲森番は釣りをするの? そもそも釣りってなんなの? 狩猟採取が目的? 娯楽が目的?
[守]のお題「030番:連想シソーラス」のように集客から釣りまで連想が広がる。
そう!稲森は、生粋の釣り好き。50守師範代として登板の際、教室名も「釣果そうか!教室」。自身が制作した教室名フライヤーも、魚で埋め尽くす。
*釣ってきた魚たちを稲森は魚拓としている
釣りは、魚が釣れすぎると面白くない。釣れないから面白い。潮の流れ、気温、風向き、糸の細さなど、何が問題で釣れないのか。問いをたて、3A(アナロジー・アブダクション・アフォーダンス)を全力で働かせ、仮説と検証を繰り返す。「021番:秘密基地でBPT」の「T:ターゲット」である「釣りたい魚」も歳を重ねるごとに変化する。小さい魚なら5センチのタナゴ。大きい魚だと100センチを超えるアジを狙う。3A全開の仮説と検証のサイクル。年齢とともに変化するBPT。これらがあるからこそ、釣りはやめられない。
⬛︎20:15 依然、ピクリともせず
卒論前? 時間帯? 内容? 今日のイベント知られてない? と問いを立てる。3Aを全力で働かせ、稽古する動機を追求する。
そもそも、なぜ、編集学校で稽古をするのか。
4人が出した結論は2つ。
・ただの社会人、ただの学生でありたくない。
・ただ、ただ、お稽古が楽しい。
上段は、現状に満足できず、自己研鑽的な要素と知への探求と好奇心。下段は、バライティに富んだお題への回答、師範代との回答→指南のキャッチボールの楽しさ。
大切なのは、1つで成立せず、両輪があってこそ。
一方、なぜ釣りをするのか。
・ただの魚ではなく、大きな魚や珍しい魚を釣りたい。
・ただ、ただ、竿を出すのが楽しい。
釣り人は、自分が釣りたい魚を求めて、あくせくする。魚を釣るために無心に自然環境と対峙する。一本の釣り竿から垂らす糸で水の中と交信する。
知への探究、その先のまだ見ぬ自分を求めて。
まだ見ぬ夢の巨魚・珍魚を求めて。
編集学校も釣りもロマンである。
⬛︎20:30 思いもよらぬ釣果
次期の近大番の編集について、今期を振り返りながら、検討がスタート。
これまでの議論を踏まえて、学生にどのように伝えるか。
・ただの社会人、ただの学生でありたくない。
・ただ、ただ、お稽古が楽しい。
この考えを軸に、学生とのコミュニケーションツールの話、キックオフ説明会の内容、期中のイベント構成と来期の内容が決まった。そして、ワクワクする新企画のアイデアも生まれた。ツルツルてんのボウズも悪くない。釣り上げたものが企画会議と思わぬ結果となり、これにて竿納め。
【記事・写真 稲森久純】
イシス編集学校 [守]チーム
編集学校の原風景であり稽古の原郷となる[守]。初めてイシス編集学校と出会う学衆と歩みつづける学匠、番匠、師範、ときどき師範代のチーム。鯉は竜になるか。
春のプール夏のプール秋のプール冬のプールに星が降るなり(穂村弘) 季節が進むと見える景色も変わる。11月下旬、56[守]の一座建立の場、別院が開いた。18教室で136名の学衆が稽古していることが明らかに […]
番選ボードレール(番ボー)エントリー明けの56[守]第2回創守座には、教室から1名ずつの学衆が参加した。師範代と師範が交わし合う一座だが、その裏側には学衆たちの賑やかな世界が広がっていた。 師範の一倉弘美が俳句で用法3を […]
秋の絵本を「その本を読むのにふさわしい明るさ」で3つに分けると、陽だまり・夕焼け・宵闇になる。 多読アレゴリア「よみかき探究Qクラブ」のラウンジに出された問い「本をわけるあつめる。するとどうなる?」への答えだ。 クラブで […]
教室というのは、不思議な場所だ。 どこか長い旅の入口のような空気がある。 まだ互いの声の高さも、沈黙の距離感も測りきれないまま、 事件を挟めば、少しずつ教室が温かく育っていく。そんな、開講間もないある日のこと。 火種のよ […]
かなりドキッとした。「やっぱり会社にいると結構つまんない。お給料をもらうから行っておこうかなといううちに、だんだんだんだん会社に侵されるからつらい」。数年前のイシス編集学校、松岡正剛校長の言葉をいまもはっきりとはっきり […]






コメント
1~3件/3件
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。
2026-01-22

『性別が、ない!』新井祥
LGBTQなどという言葉が世間を席巻するはるか以前、このマンガによって蒙を啓かれた人も多いのでは?第一巻が刊行されたのが2005年のことで、この種のテーマを扱った作品としてはかなり早かった。基本的に権利主張などのトーンはほぼなく、セクシャルマイノリティーの日常を面白おかしく綴っている。それでいて深く考えさせられる名著。