草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。
「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。





「いつもいっしょでした/たいがいは夜/読んでないときでさえ」
北国の田舎町に暮らす17歳の高校生・実ッコこと田家実地子(たい・みちこ)[※01] は、図書館からロジェ・マルタン・デュ・ガール『チボー家の人々』(白水社、1966年)[※02] を借りて読みはじめます。この『チボー家』こそがタイトルの「黄色い本」[※03] で、卒業式の日に本を返却するまでのめくるめく読中劇というのが話の大ざっぱなあらましです。
いまは白水Uブックス(全13巻)が定番となっていますが、高野文子さんが文学少女だった時代の『チボー家』といえば、黄色い装丁の全五巻本でした。
真夜中まで布団にくるまって、実ッコは読み耽っています。本を読んでないときでさえ、ふとした拍子に気に入ったフレーズを呟くほどに、だんだん耽読、どんどん溺読、ずんずん貪読。そのうちしだいに、主人公のジャック・チボーと会話まで交わし、小説の中の革命仲間たちとレジスタンス集会へも参加することになりました。
こんなふうにして、現実と本の世界がぐるぐる混ざり合っていくという、たった72ページの小さな作品ですが、「黄色い本」は本を読むことの幸福と、本を閉じることの哀切、そして本との対話をドラマチックかつヴィヴィッドに描き切っています。あふれんばかりの活字を描いたコマだけで構成した一頁目からして圧巻です[※04]。


左:『ユリイカ2002年7月号 特集=高野文子』(青土社)
右:『高野文子「私」のバラけ方』(カタリココ文庫)
『ユリイカ』や『カタリココ文庫』[※05] の高野文子特集を読んで知ったのですが、高野さんは生涯最後の一作のつもりでこの作品に取り組んだのだそうです。「そもそも漫画家という職業に就こうと思ったきっかけは何だっけ」と自分の根っこを問いなおし、漫画家になる以前の「精神の17歳」まで戻ることを決意したのでした。まるで、実ッコやジャックがそうしたように。
高野さんが漫画に目覚めたのは、17歳のとき。萩尾望都の「モードリン」や「11月のギムナジウム」に一目惚れしてからのことです。漫画家になりたいというより、「萩尾望都になりたい!」と夢みていました。
でも、それならばなぜ。それならばなぜ、「黄色い本」なのでしょう。なぜ、「11月」のエリークやトーマではなく、ジャック・チボーなのでしょうか。

『ドミトリーともきんす』(中央公論新社)
じつに14年ぶりの新作「ドミトリーともきんす」(2014)で、高野さんは文学から科学へと、まさしく主題のコペルニクス的転回[※06] を果たしたわけですが、それまでは「自分のことを掘り下げていくと何かわかるかもしれない」とワタクシ小説的理想をギュウッと握りしめていたと告白しています。そして、その極北まで突き進んだのが「黄色い本」でした。「これ以上自分のなかを覗くのは危険」という水域までふかく潜りこみ、ついにここで終止符を打とうと決めたのでした。
高野さんが萩尾望都に出会うより前の、もっともっと何者でもないピュアな”17歳の文チャン”と再会することを願ったのは、もしかしたらそのせいかもしれません。これは高野さんご本人の言葉ですが、「黄色い本」は「高野文子の正義」であり、描き続けるために「頑張れる勇気」なのです[※07]。
高野文子も「黄色い本」も、かわいらしい見た目とは裏腹に、薄紙一頁ペラッとめくり上げると中は刃物のように鋭く尖っています[※08]。一コマ一コマが切々で、ギリギリです。一言でいえばつまり、「絶対安全剃刀」ということになるのですが、それについて詳しくは千夜千冊108夜を読んでください。
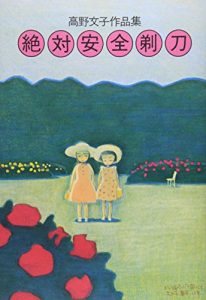
『絶対安全剃刀―高野文子作品集』(白泉社)
ところでさっき、「精神の17歳」というちょっと変わった言い回しを使いましたね。じつはこの不思議なコトバに出会ったのが『17歳のための世界と日本の見方』[※09] でした。もちろん、”セイゴオMという名の先生”に最初に出会ったのもこの本です。
「世界と日本」という字面にいざなわれ、今はなき紀伊國屋書店新宿南店(2016年7月閉店)の現代哲学コーナーの棚に仕掛けられた、檸檬色の書物をドキドキしながら引き抜いたときのことを今でもよく覚えています。ときは2007年の春。しかも、意外な読機のキューピッド(クピド)が、過烈な熟読をもたらしてくれたのです。
いくぶん時計の針を逆回転して、2007年の正月。ぼくはモロッコのティネリールという田舎町にいました。そこはサハラ砂漠に向かうための中継地点のような場所です。よちよちと危なっかしい一人旅の帰路、バスの出発時刻まで山ほど時間があったので、街のハマムでひとっ風呂浴び、暇つぶしにカフェで甘すぎるミントティーをちょびちょび啜っていました。
そのときです。例のキューピッドは不意に現れました。たしか、アルジャジーラの放送だったと思います。ギョッとする映像が目に飛び込んできました。
お店のブラウン管の小さなテレビに、サダム・フセインの絞首刑を執行する一部始終が無修正で放映されていたのです。実際にフセインが処刑されたのは2006年12月30日のことなので、ぼくが見たときには処刑から数日が経過していたことになります。死刑確定(12月26日)からわずか4日後に執行されたことも、のちのち知りました。ちなみに、この数年後にモロッコを除く北アフリカで「アラブの春」が巻き起こります。
たしかにドゥジャイル村やクルド人に対する虐殺は許されるべきではないけれど、これは何かの「まちがい」ではないか。怒りとも似た直感が、雪のアルハンブラ宮殿、ムスリムの友人、グナワのリズム、迷宮都市フェズなどのイスラミック・メモワールとごちゃまぜの砂嵐となって、どどどっと押し寄せてくるのでした。どっどど、どどうど、どどうど、どどう。
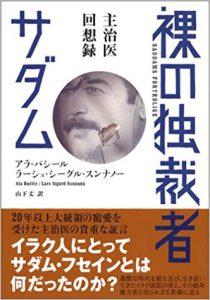
『裸の独裁者サダム―主治医回想録』(日本放送出版協会)
『17歳』は世界宗教の発生からバロック時代までを超高速・超濃密に駆けめぐります。が、とにかくぼくは「精神の17歳」「宗教編集」「バロックの織部」という”言葉づかい”に目を奪われ、これが”編集力”なのかとブッ魂消(たまげ)ました。今すぐにでも松岡正剛に会いたい。会わなくてはいけないというわけの分からない使命感さえ芽生えていたほどでした。
「世界と日本」を同時に見るには、「編集的に見る」という見方がどうしても欠かせません、とセイゴオ先生は言います。あらためて「編集」とは、二つ以上の物事や人間や世界観をさまざまな角度や意味あいから見て、そこから新しい関係を発見することです。そのとき、「異質」を排除しないということが大切です。そもそも歴史とは「異質との出会い」の連続なのです。
セイゴオ先生が「精神の17歳」を強調しているのは、「異質との出会い」に敏感でナイーヴなあの感性を取りもどしてほしいというメッセージなのかもしれません。
表紙に黄色のバツ印をあしらった意匠の姉妹本『誰も知らない世界と日本のまちがい』[※10] が刊行されるとそれもすぐさま貪り読みました。
こちらはエリザベス女王以降の近代史と、中東戦争にいたる現代史をとりあげています。サダム・フセインを名指しして、彼が処刑された意味を理解するには、せめてオスマン帝国にまで遡らなければならないと示唆するあたりは、さすがに釘付けになって、実ッコが『チボー』を読むみたいに必死で活字を追いかけました。
第一次世界大戦でドイツと組んで敗退し、オスマントルコがずたずたに分割されてしまったことが、その後の中東問題やアラブ世界を考えるうえで大事な「負の青写真」になったというわけです。たとえば池上彰さんが1979年のソ連のアフガン侵攻をアラブ世界のターニングポイントだと見ている歴史観と比べてみても、これはかなり”抉った見方”だと思われます。
言い換えれば、中東のアラブ国家独立を約束したフサイン・マクマホン協定、パレスチナにおけるユダヤ人居住地を明記したバルフォア宣言、そしてオスマントルコ分割の密約であるサイクス=ピコ協定という「イギリスの三枚舌」が「まちがい」の根っこであると喝破しているのです。
このあたりは、いずれ重信メイさんの『「アラブの春」の正体』や『裸の独裁者サダム』などを取っ掛かりにして、歴史をさかのぼりながら、アラブの声にじっくり耳を傾けたいと思います。このことは、天使なのか、悪魔なのか、髭を生やしたキューピッドからの宿題だと思っています。

『「アラブの春」の正体 欧米とメディアに踊らされた民主化革命』(KADOKAWA)
さて、『まちがい』の”言葉づかい”ということでいうと、最終章の「苗代という方法」には今なおゾッコンです。これはダイレクトに直播きするのではなく、いったん幼若な苗にして、それから本番で植え替えるという、稲作に見立てた方法の提案です。日本の稲作は、「苗代」という仮の場所に種をまいて、小さく育ててからその苗を田んぼに移し替え、それから本格的に育てていきます。いわば間接話法であり、部分の重視です。
苗代は、梅雨を挟んで、どのように苗を丈夫に育てたらいいのかということを工夫した知恵から生まれた方法です。そこに何かがやってきたり、着いたり、宿ったり、育ったりする、とても小さな「座」や「棒」や「冊」のようなもの、「依代」(よりしろ)や「憑座」(よりまし)や「物実」(ものざね)といった日本独特の考えかたのルーツになりました。
2000年にインターネット上の一隅に生まれたイシス編集学校と千夜千冊は、セイゴオ先生の「苗代という方法」の実践(プラクシス)だと言っていいでしょう。そしていよいよ今年、20周年を迎えました。千夜は角川ソフィア文庫のエディションに”編装”し、イシスでは多読ジムの”bookin`on”が鳴り響いています。そろそろ苗を田んぼに移し替える時機が到来しているのかもしれません。
ちなみにぼくは2009年に[守]講座の門を叩き、突破後に7[離]を経て、今は「代将」というニューロールを担当しています。ちなみにちなみに、7[離]はハイパーテキスト文巻にはじめて本格的にイスラームが記述された季でもありました。代将と苗代が同じ”代”の一文字を背負っていることも、ぼくにとって、かなりイミシンです。

誰にでもその人だけのかけがえのない「黄色い本」があるのだとぼくは思っています。『17歳』と『まちがい』の黄色姉妹のイッツイさんはまぎれもなく、ぼくにとっての「黄色い本」となりました。二冊のジャケットカラーに黄色を選んでくれたMIKAN-DESIGN(ミカンデザイン)の美柑和俊さん、ありがとうございます。
ではあらためて、「黄色い本」っていったい何ですか。実ッコのトーチャン [※11] に聞くが一番です。
「実ッコ その本買うか?」
「ええ?」
「注文せば良いんだ/五冊買いますすけ/取り寄せてください/言うて」
「いいよう/もう読み終わるもん/ほら」
「好きな本を/一生持ってるのも/いいもんだと」
「実ッコ 本はな/ためになるぞ 本はな/いっぺえ読め」
はい、実ッコのトーチャン、そうします。ぼくもまだまだこれから、いっぺえいっぺえ読みまくりたいと思います。
※01 田家(たい)
主人公・田家実地子(たい・みちこ)の苗字は高野文子の出身地の「新潟県旧新津市田家」にちなむ。街の男の八割が国鉄勤めという国鉄の街。汽車が路線橋の下を通ったあとは息を止めないと駄目ってくらいに煙が満ちる。父も国鉄のサラリーマンで、汽車の修理が仕事だった。田んぼの埋立地に建てられた市営住宅に暮らし、工場には銭湯があった。晩ご飯のおかずも、学用品も会社の物資部で買う。まわりは農家の子が多かったが、学校でもみんな貧乏、みんな同じ。母や叔母は編み機で内職をする。高野は「日本の共産圏」だと述懐している。
※02 チボー家の人々
1920年から19年もの歳月を費やして完成したデュ・ガールの大作。物語の「舞台は第一次世界大戦前後のフランス。時代が大きく変動する不安と動揺の時に身をおいた若者たちが、鋭い感受性ゆえに悩み傷つき、そして苦悩の末にそれぞれの決断をしていく」(『チボー家のジャック(新装版)』解説)。キーワードは「青春」と「労働者階級(プロレタリアート)」と「革命」。
※03 黄色い本
デビュー本『絶対安全剃刀』(白泉社)、『おともだち』(綺譚社→筑摩書房)、『棒がいっぽん』(マガジンハウス)に続く高野文子の4冊目の作品集であり、8年ぶりの単行本。高野作品で「あとがき」が付されているのは、本作と次作「ドミトリーともきんす」のみ。本作が縁となり、2003年12月、原作の五分の一ほどのコンパクトサイズになって、白水社から往来の黄色いカバーの『チボー家』抄訳版が高野文子装丁で新装復刊(白水社)された。
※04 読書マンガ
読書体験を表現するための様々な試みがおこなわれている。ときどき左ページ左下のコマに小さな栞型のコマがついているところがあるのだが、これには小説の段落のような役割をになわせようとしている。
高野は新潟の少女時代に1年くらいかけて『チボー家』を読んだという。当時、同世代の文学少女たちにとって図書館の定番だったらしい。父の画集と植物図鑑以外、家にほとんど本はなかったため、高野にとって本といったら学校の図書館だった。
『黄色い本』の制作にあたり、当時の日記などをたよりに読書の記憶をなんとかたぐりよせ、つなぎ合わせた。担当編集者を三年待たせながらも作品を描き終えた後、資料にした中学時代からの日記も本も「思い出すこともすっからかんになって」すべて捨ててしまった。
※05 「私」のバラけ方
少女の文チャンは、絵を描いたり、人形遊びやままごとなど、一人遊びの方が好きだったが、「ひとりぼっちは治さなきゃいけない」と思って育った。昭和30年代の新潟の農村というトポスに対して、幼ごころに「孤立は生存にかかわる」と感じていたからだ。”フツー”を装うのは別に嫌いではないようだが、本を読むときと漫画を描くときだけ、「バラける」ことができると述べている。
『棒がいっぽん』収録の「奥村さんのお茄子」(1994)を描いた時、人形遊びの感覚で小さくなっちゃえば楽ちん、小さくすれば小さくするほどうまくいく、と気がつく。建物のサイズはそのままで、動く自分を身長15センチくらいに小さくして、机の上をとことこ歩いた入りする。それまでとは違うバラけ方をものにした。自伝的要素が強い「黄色い本」ではバラけたままもどれなくなったら、という不安もあった。
※06 コペルニクス的転回
「私がね、私がね」という語り方はやめようと思った。「血中文学濃度が上がりすぎちゃった」この体をどうにかしたいと、「ドミトリーともきんす」で大転換を決心。あとがきにはこう書いている。
「まずは、絵を、気持ちを込めずに描くけいこをしました。変に聞こえるかもしれませんが、涼しい風が吹くわけは、ここにありそうなのです。
わたしが漫画を描くときには、まず、自分の気持ちが一番にありました。今回は、それを見えないところに仕舞いました。自分のことから離れて描く、そういう描き方をしてみようと思いました。
道具は、製図ペンを使いました。頭からしっぽまで、同じ太さが引けるペンは、じつに静かな絵が描けます」。
※07 高野文子の方法
高野文子はほとんど一作ごとに画風を変え、つねに新しい表現方法を模索している。一度使った方法はその一作で惜しげもなく捨てる、徹底した方法の人である。だが、本人はテーマ主義を自称している。まず「最初に思いつくのはテーマ」だからだ。その後、編集者に〆切を決めてもらい、制作に入る。
制作のダンドリにはルールがある。ノートを用意し、描けそうなコマからつくっていく。これは使えるなと思ったら、四角くハサミで切って、セロテープで床に貼っていく。だいたい6コマで1ページぶんになる。4ページぶんくらい床に並べて、コマとコマを交換することもある。これをもう絶対に動かさないぞというところまで徹底的にやり、背景まで鉛筆で描きこむ。ここまでの下書きに二年かかった。その下書きの鉛筆線をトレースする形で、やっとペン入れの段階に入る。ただし、推敲の手を止めることはない。これら全工程を1畳半の風呂場の脱衣所に小さな机と手製のトレス台を置いて行う。トーン61番(薄ねず)にするか、74番(濃いねず)にするかで苦悩し、実ッコの家の光と影の演出する。人の顔より畳を描くことに賭ける。感情をこめて描くことを極端に嫌い、絵に自分が出てこない方法を模索する。
※08 癒し系の拒否
絵本『しきぶとんさん かけぶとんさん まくらさん』や『るきさん』などの絵柄を見て「癒し系」だと思われることを、本人は「誤解だ!」とキッパリ否定している。居合いが趣味で江戸末期の真剣も所持している。「腹式呼吸」「点を凝視しない」「周辺を半眼で見る」を漫画でも実践し、手や目ではなく全身の筋肉で描くことを心がけている。ペン入れは初発刀なのだ。
※09 17歳のための世界と日本の見方 セイゴオ先生の人間文化講義
本書はデジタオブックレット『帝塚山講義(一)~(五)』(松岡正剛編集セカイ読本・低速、degitao、2003~2004)を増補改訂し、新たに戯画イラストレーションを著者が加えたもの。松岡正剛編集セカイ読本シリーズは、デジタオブックス井口尊仁によるオンデマンド出版の実験的プロジェクトの一環として、「知の速度」に応じて選べる低速・中速・高速の3つのシリーズを刊行。井口は米国カリフォルニア州在住のIT起業家で、音声+AIでビジネス・ミーティングを即時ビジュアライズするサービス「トランスペアレント」を開発している。
元号令和の発案者と目されている中西進さんの招きを受けて、セイゴオ先生は1998年から2004年にかけて帝塚山学院大学人間文化学部の教授に。『17歳』は、その帝塚山の一年生向けの講義「人間と文化」がもとになっている。講義では、次の5つの編集方針を立てた。(1)「世界と日本をめぐる人間文化」という視点で話す。(2)大事なことは、あえて風変わりなことでも話す。(3)教科書に載っていないことを話す。(4)文明と文化のディテールも話す。(5)少年時代や青年時代の体験から話し始める。その体験は、第一章の「聞こえない風鈴ー文化感覚距離」「七メートルの境界線」に眩しく綴られている。
※10 誰も知らない 世界と日本のまちがい 自由と国家と資本主義
とびっきり痛烈なのは「近代史のまちがい」をあえて「イギリスのまちがい」だと見立てていること。もちろん、イギリスが犯罪者だというのではない。議会も株式会社もジャーナリズムも小説も産業技術も、近代社会がその恩恵によくしているモデルの多くが、イギリスの発明だ。ところが、これらを世界に撒き散らさないと覇権を握れなくなったために、イギリスは植民地を経営し、奴隷を発明し、三角貿易を定着させた。さらにそのイギリスからの移民によって自立したアメリカが覇権を継承すると、世界中が同一のルル三条(ルール・ロール・ツール)を使うようになっていった。グローバリズムの過ぎたる悪禍に便乗した日韓併合や満州国の建国もそういう勇み足だった。これが「まちがい」なのだ。
2015年、大幅な加筆と修正により『国家と「私」の行方』(東巻・西巻)に改訂。東巻では資本主義の近代的出発点の問題と日本や東アジアの抱えた矛盾を、西巻では今日まで続く中東問題に潜む欧米の欺瞞や、ポピュリズム政治とネット社会の矛盾を突く。
※11 実ッ子のトーチャン
父は美術全般が好きでとりわけ生け花の龍生派に傾倒。四畳半と六畳間の小さな家だったが、1950年代のモダニズム風の花器がたくさんあった。工場から帰って夕飯の後に農家のお嫁さんたちを集めて生け花を教えた。そんな父も母も、食えない「芸術系には決してさせまい」と思っていた。自宅ではだいたい月に一度、組合の寄合があり、その様子は『棒がいっぽん』(マガジンハウス)収録「美しい町」に描かれている。「美しい町」のノブオさん、「黄色い本」の実ッコのトーチャンのモデルも実父。
※12 おまけ
高野文子は今でもマンガを描くのは「あぶくのようなこと」だと考え、いつも看護婦に復職することを考えている。昭和のくらし博物館の近所に暮らし、フツーを装うために地域のお掃除サークルに入って草刈りをしている。夫はフリー編集者の秋山協一郎。『おともだち』を刊行した綺譚社の代表でもあり、高野と並んでニューウェーブの旗手と騒がれた大友克洋の『GOOD WEATHER』(1981年)や『BOOGIE WOOGIE WALZ』(1982年)も綺譚社刊。早稲田大学の文芸サークルワセミス出身で、秋山狂介名義で大藪春彦の評論・研究もおこなう。
続きは、堀江純一の「マンガのスコア」高野文子号をお楽しみに。
●3冊の本:
『黄色い本 ジャック・チボーという名の友人』高野文子/講談社
『17歳のための世界と日本の見方 セイゴオ先生の人間文化講義』松岡正剛/春秋社
『誰も知らない世界と日本のまちがい―自由と国家と資本主義』春秋社/松岡正剛
●3冊の関係性(編集思考素):一種合成型
金 宗 代 QUIM JONG DAE
編集的先達:宮崎滔天
最年少《典離》以来、幻のNARASIA3、近大DONDEN、多読ジム、KADOKAWAエディットタウンと数々のプロジェクトを牽引。先鋭的な編集センスをもつエディスト副編集長。
photo: yukari goto
佐藤優さんから緊急出題!!! 7/6公開◆イシス編集学校[守]特別講義「佐藤優の編集宣言」
佐藤優さんから緊急出題!!! 「佐藤優の編集宣言」参加者のために佐藤優さんから事前お題が出題されました(回答は必須ではありません)。回答フォームはこちらです→https://forms.gle/arp7R4psgbD […]
多読スペシャル第6弾「杉浦康平を読む」が締切直前です! 編集学校で「杉浦康平を読む」。こんな機会、めったにありません! 迷われている方はぜひお早めに。 ※花伝寄合と離想郷では冊師四人のお薦めメッセージも配信 […]
「脱編集」という方法 宇川直宏”番神”【ISIS co-missionハイライト】
2025年3月20日、ISIS co-missionミーティングが開催された。ISIS co-mission(2024年4月設立)はイシス編集学校のアドバイザリーボードであり、メンバーは田中優子学長(法政大学名誉教授、江 […]
【続報】多読スペシャル第6弾「杉浦康平を読む」3つの”チラ見せ”
募集開始(2025/5/13)のご案内を出すやいなや、「待ってました!」とばかりにたくさんの応募が寄せられた。と同時に、「どんなプログラムなのか」「もっと知りたい」というリクエストもぞくぞく届いている。 通常、<多読スペ […]
【6/20開催】鈴木寛、登壇!!! 東大生も学んだこれからの時代を読み通す方法【『情報の歴史21』を読む ISIS FESTA SP】
知の最前線で活躍するプロフェッショナルたちは、『情報の歴史21』をどう読んでいるのか?人類誕生から人工知能まで、人間観をゆさぶった認知革命の歴史を『情歴21』と共に駆け抜ける!ゲストは鈴木寛さんです! 「『 […]







コメント
1~3件/3件
2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。
「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。
2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二
セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!
目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!
2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。
配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。
昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。