発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。




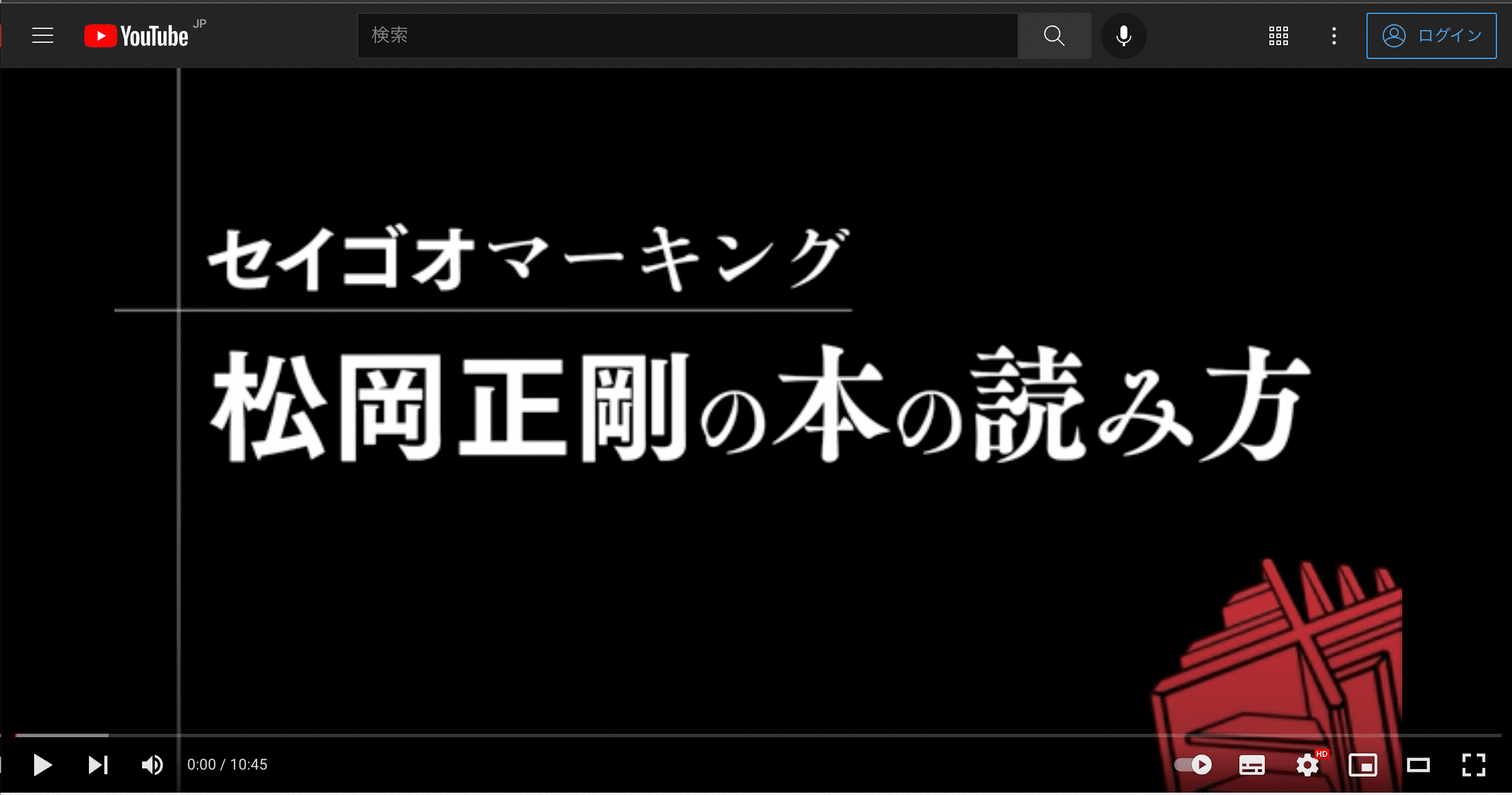
■「想像上の生き物」としての書物
読んだそばから、逃げていく。掴んだつもりが、もういない。読書という行為は、気まぐれな猫の相手に似ている。「稽古をしていると、何かチカっと光るのですが、すぐに消えてしまいます」(レディ・ガラ教室学衆S)
47[破]は、文体編集術を総動員する「セイゴオ知文術」の稽古に呻吟している。これは自分が読んだ1冊の本を、別の誰かに紹介する800字の文章を書くというお題だが、これがなかなか難しい。それは松岡正剛にとってもそうなのだ。千夜千冊の原点とも言える伝説のブックガイド『遊読365冊』の付記で、松岡は「読書という面妖な行為」とそのわだかまりを綴っていた。
いったい何の本をどう読んだのか、その一冊の感想は言えるだろうものの、読んでいるときのプロセスがうまく取り出せない。納得のぐあい、はずれた感じ、ぐいぐいとひっぱられた快感、胸の高まりや詰まり方、困った印象、あとから引用したいと思ったところ、これらはその本を読んでいるときは実感していたはずだろうことなのに、いざ読みおえるとさっぱり取り出しにくい。取り出そうとすると、縮退してしまうか、散逸してしまう。そこをむりやり再現しようとすると、結局は元のテキストに戻ってしまう。
松岡正剛『遊読365冊』p.218-219(2018年付記)
本を読み、語るなど、無謀な行為なのか。その突破口は、本という生き物の向き合い方にある。師範北原ひでおは、『遊読365冊』から1981年発刊当時の前書きを引用した。
「書物というものを、何かがぎっしり詰まっている言語建築のように考えるのはよくない。そういうイメージは図書館にこそあてはまる」読書とは、何十年も変わらぬ書棚から煤けた本を取り出し、それを一文字違わずノートに転記する受験勉強のようなものではない。
松岡は主張する。「書物は、隙間だらけ、気温によってどうにでも動き回る『想像上の庭に棲む動物』のように思っていたほうがいい」
■読書という現象を再現するための
セイゴオ式マーキング
読書体験が語りにくいのは、それが揺らぐ行為だからである。映画館でポップコーン片手に予告編を待つわたしと、放心してエンドロールを眺めるわたしは違う。体験以前と以後では自分が変化してしまうのだ。
松岡はこの動的な体験を、なんとか再生可能にしようと試みた、それが本を汚しながら読む「セイゴオマーキング」である。師範代小桝裕己は松岡の動画を持ち込み、セイゴオ知文術で『イヴの七人の娘たち』に『万物理論』に格闘する学衆への手がかりとした。
人名はパーレンで括り、キーワードは記号化し、キーフレーズは枠囲みにする。松岡はなぜ読書のたびにマーキングをするのか。映像の最後に語られるのは、オムレツを作る料理人の話だ。
卵を割ったり溶いたりする決まった手続きが味を保証するように、松岡は、本を読むときもその「手続き」を踏むことで読書体験をたしかなものにしていくという。
▲2度目の肺がん手術のまえ、駒沢公園のベンチで読んだという1770夜『小枝とフォーマット』(ミシェル・セール)。赤と青のVコーンによるマーキングのページは、千夜に写真が掲載されている。遊刊エディストでも「伴読リレー」という名で千夜もセイゴオ知文術されている。該当千夜は、林頭吉村堅樹によるこの記事。【多読ジム】GWはセールだよ!千夜リレー伴読★1770夜『小枝とフォーマット』
■凡庸な作文に陥る
読み書き3大敗因
セイゴオ知文術は特別な稽古だ。通常のお題とは異なり、すべてのエントリー作品を選評委員が吟味。そのうえで「賞」が贈られる。著作のモードやスタイルを活かす「モード文体術」がすぐれた作品には、アリス賞。知識情報を的確に扱う「知文術」が光れば、テレス賞。最優秀賞はその両者を兼ね備えた「アリストテレス大賞」である。
37[破]で10冊の課題本が設定されてから、はや4年。なぜか大賞作品が生まれない課題本があることに、46[破]師範代石輪洋平は気づいた。「なぜ、『オリガ・モリソヴナの反語法』はアリストテレス大賞が取れないのでしょう」 汁講で問われた[破]学匠原田淳子は仮説を立てた。凡庸な作文にとどまってしまう要因は3つある。
1)要約を諦めてしまう
2)登場人物のわかりやすい魅力に溺れてしまう
3)本の重みを引き受けない
『オリガ〜』を例に言えばこうだ。
その1。この小説は、3つの時代を行き来するという複雑な物語構造をもつ。それゆえはなから要約を放棄する学衆も多い。構造の読み解きのためには、メモを取りながら読むべし。ミステリーであっても堂々とネタバレする。肝心要を伏せては本の紹介ができないからだ。
その2。本に書いてあるままの「ド派手なファッション」や「どぎつい罵詈雑言」などのわかりやすい魅力だけを取り上げないこと。うわべだけを撫でない。なぜその振る舞いに至るのか、登場人物が奥底にもつ信念や矜持まで踏み込むべし。
その3。「フィクションでしか書けなかった」という重い真実を受け止めよ。「この話はフィクションです」という断りをナイーブに信じないこと。作中のソビエト学校の様子は著者米原万里の実体験に拠るし、罪なく強制収容所に入れられたオリガ・モリソヴナも実在する。なぜこの物語がこの形式で書かれているのか、その背景を推し量るべし。
伝習座で3つの敗因を聞いた評匠高柳康代は、「裏を返せば、これが勝因になる」と応じた。要約を諦めない、登場人物の真のWhyを探る、本というメディア・メソッドごと引き受ける。この3つの突破口はどの課題本にも共通するはずだ。47[破]はマーキング術、知文術、モード文体術などセイゴオメソッドを矢として束ね、本というユニコーンの疾駆や鳳凰の飛翔を追いかける。
▼6分で知る!松岡正剛のマーキング読書法。撮影は往時の松丸本舗。
▼セイゴオ知文術に際して読みたい千夜
●『文体練習』レーモン・クノー(138夜)
●『本を書く』アニー・ディラード(717夜)
●『漢字の世界』白川静(987夜)
●セイゴオほんほん35 「読書は格闘技である」2020年12月29日(火)
書評サイトだと見られている向きもあるようだが、そうではない。[…]千夜の読書はまずはコンデンセーションなのである。
▼セイゴオ知文術 アリスとテレス賞関連記事
●スラスラ書くな、モヤモヤ足掻け◆作文・創文・知文のヒント【46[破]課題本一覧】
⇒今期は『稲垣足穂さん』に代わり、『フラジャイル』(松岡正剛著)が課題本入り。
●松岡正剛ライティング術!文章のクオリティを格上げする「ポッと出」とは【46破 知文AT】
●講評は果たし状 悔し涙の師範代 【46[破]知文AT賞 結果発表】
梅澤奈央
編集的先達:平松洋子。ライティングよし、コミュニケーションよし、そして勇み足気味の突破力よし。イシスでも一二を争う負けん気の強さとしつこさで、講座のプロセスをメディア化するという開校以来20年手つかずだった難行を果たす。校長松岡正剛に「イシス初のジャーナリスト」と評された。
イシス編集学校メルマガ「編集ウメ子」配信中。
大澤真幸が語る、いまHyper-Editing Platform [AIDA]が必要とされる理由
Hyper-Editing Platform[AIDA]は、次世代リーダーたちが分野を超えて、新たな社会像を構想していく「知のプラットフォーム」です。編集工学研究所がお送りするリベラルアーツ・プログラムとして、20年にわ […]
【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】もし順天堂大学現役ドクターが本気で「保健体育」の授業をしたら
編集術を使って、医学ゲームをつくる! 「MEdit Lab for ISIS」は2025夏シリーズも開講します。 そして、7月27日(日)には、順天堂大学にて特別授業を開催。 クラブ員はもちろん、どなたでもご参加いただけ […]
【ARCHIVE】人気連載「イシスの推しメン」をまとめ読み!(27人目まで)
イシス編集学校の魅力は「人」にある。校長・松岡正剛がインターネットの片隅に立ち上げたイシス編集学校は、今年で開校23年目。卒業生はのべ3万人、師範代認定者数は580名を超えた。 遊刊エディストの人気企画「イシスの推しメン […]
イシス最奥の[AIDA]こそ、編集工学の最前線?受講した本城慎之介師範代に聞くSeason5。
イシス編集学校には奥がある。最奥には、世界読書奥義伝[離]。そして、編集学校の指導陣が密かに学びつづける[AIDA]だ。 Hyper Editing Platform[AIDA]とは、編集工学研究所がプロデュースする知と […]
【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】編集術を使って、医学ゲームをつくる!?
伝説のワークショップが、多読アレゴリアでも。 2025年 春、多読アレゴリアに新クラブが誕生します。 編集の型を使って、医学ゲームをプランニングする 「MEdit Lab for ISIS」です。 ■MEd […]












コメント
1~3件/3件
2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。
2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。
家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。
せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。
添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!
イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。
エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。
2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。
山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)
この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。
お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。
深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。