昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。




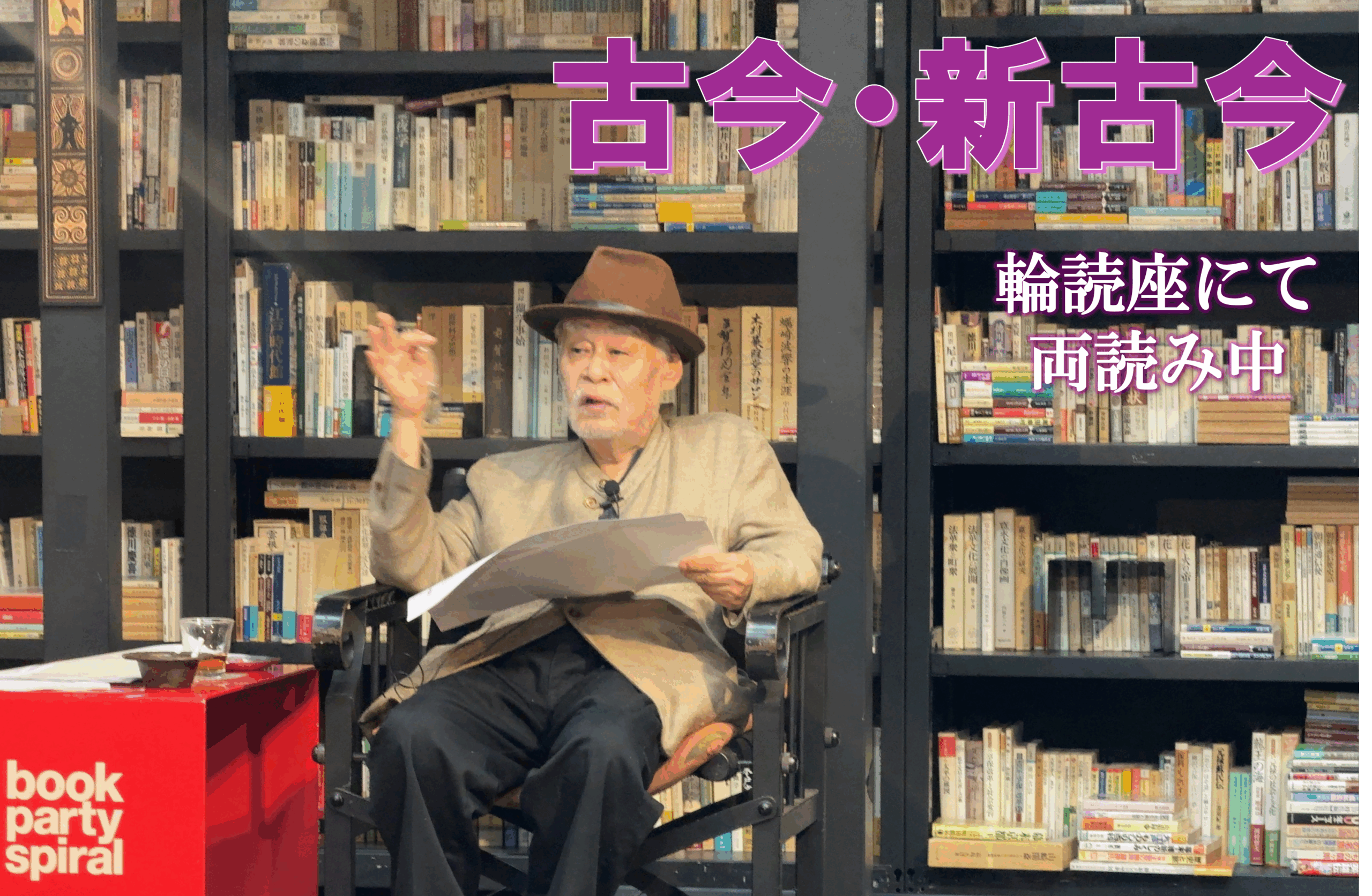
『古今和歌集』『新古今和歌集』の解説に、Adoやボーカロイドは一見結び付かない。しかし輪読師バジラ高橋がナビゲートする「輪読座」では、和歌の理解というよりは、仮名文字の成り立ちや音韻の変化にまで踏み込み、現代の音楽表現と絡めてバジラ節で考察していく。古代や中世を語りながらも、令和のトレンドを軽やかにカサネアワセてくるのが輪読師バジラ高橋の方法なのだ。
◆「読み人知らず」と「ボーカロイド」に通じる匿名性
独自の見方を図象化してみるというお題は輪読座名物だ。第2輪で宿題共有してくれたO座衆の図象を紹介したい。第1輪の解説の中で空海がもたらした日本語音韻とボーカロイドの音韻の整理の話に関心を持ったというO座衆。図象内左側には『万葉集』『古今和歌集』が編纂された時代と空海の生きた時代、古今和歌集の中で生没年のわかる歌人をピックアップした。右側にはボーカロイドについての見方を展開する
前回の解説の中で、五十音図と空海の関係性についての話も出ていたが五十音図ができたのは空海が亡くなってだいぶ経ってからである。では最初の五十音図ができたのがいつなのかというと『孔雀経音義』だった。古今和歌集の歌人たちは、空海の人生半分ぐらい後に生まれた人なので、空海の子供や孫世代になる。空海が持ち込んだものが世の中に伝わりはじめて五十音図になっていく。そういう中で古今の歌が詠まれたということなのではないか。

右側はボーカロイドと古今和歌集の相似性について考えたこと。古今はそれまで意味的な文字で表現されていたものから音声的な文字表現に変ることで書いた人が意図した音声表現になった。ボーカロイドは音素を分解したものを組み合わせ歌声にしてリアルな音声表現ができるようになった。まだまだ機械っぽいと思っていたがNHKスペシャルの「新ジャポニズム」を見ていると、機械っぽさゆえに世界中の人に受け入れられているという。自分がどんな感情のときでも、それにあった歌声に聞こえるらしい。記号的な音声だからこそ受け入れられた。『古今和歌集』に戻ると、前回、「読人知らず」歌が4割ぐらいあって多いと思った。天皇が詠んだ歌、という情報があるとそれが先入観になるが、「読人知らず」は匿名的な表現になる。ボーカロイドの匿名的な声と古今の匿名的な歌が相似性がある。古今の音声記号的な文字表現とボーカロイドの記号的音声歌唱も似ている。結果、古今もボーカロイドも自分にかさねあわせるものとして広くうけいれられたのかと思った。

◆平仮名の成立として伝わる2つの文書
第2輪の図象解説では「平仮名の成立」として2つの文書についての解説もなされた。
1つ目は貞観9年(867年)「有年申文」だ。現存する最古の草書体の仮名、かつ仮名を使用した公文書として知られている。平安時代の貴族である藤原有年が讃岐国司を解任された理由を記載した文書で、漢文の中に平仮名が交ぜられている。
全文:
改姓人夾名勘録進上
許礼波奈世无尓加
官尓末之多末波无
見太末ふ波可利止奈毛お毛ふ
抑刑大史乃多末比天
定以出賜 いとよ可良無 有年申
訓読:
(改姓人夾名勘録進上)
これは何(な)為(せ)むにか
官(つかさ)に申(ま)し賜(たま)はむ
見(み)賜(たま)ふばかりとなも思(おも)ふ
抑(そもそも)刑(ぎや)大(たい)史(し)宣(のたま)ひて
(定以出賜) いと良(よ)からむ (有年申)
2つ目は、平安時代の草仮名の代表的遺品『秋萩帖』である。和歌48首と王羲之の尺牘(せきとく)臨書11通が書写されている。伝称筆者は小野道風や藤原行成と伝えられる。書写年代は不明だが10世紀ないしは11世紀ころ。色とりどりの濃淡に染めた色替わりの楮紙を継いでおり、第一紙は、薄い縹色に染めた麻紙に一首4行書きの和歌2首(秋歌)を書す。巻頭の和歌は「あきはぎのしたばいろ(“ろ”脱か)づくいまよりぞひとりあるひとのいねがてにする」で、これが「秋萩帖」の呼称の由来になっている。この和歌は日本語の1音節を漢字1文字にあて、古今和歌集巻四・秋歌の220番歌「秋萩の下葉色づく今よりやひとりある人の寝ねがてにする」(よみ人しらず)と同歌とみられるが、第3句が「いまよりぞ」となる点に小異がある草書体で書写されている。
原文の漢字表記:
安幾破起乃
之多者以都久
以末餘理處
悲東理安留悲東乃
以禰可轉仁数流
音読:
あきはぎの したばいろづく いまよりぞ
ひとりあるひとの いねがてにする
ーーー
輪読中に知っている短歌が出てくると「あ、これは知っている!」と耳が反応する古今和漢集・新古今和歌集両読み。かさねて日本語がどのように変遷してきたのかにも触れられる。第2輪の終盤にはY座衆から「古今和歌集は今でいうとインスタグラムのようにも感じた。いいなと思ったものを写真をとるように歌にしている」という発言も飛び出した。古今はボーカロイドであり、インスタグラム。『古今和歌集』と令和日本に通底する見方に触れる機会は希少である。
輪読座は各テーマ全6回。今シーズンは2回まで終了しているが過去分はアーカイブ映像で確認可能なため、いつからでもご参加可能です。
◎4/27スタート◎Adoは新古今!?『古今和歌集』『新古今和歌集』両読みで日本語の表現の根本に迫る【イシス唯一のリアル読書講座「輪読座」】
★空海が準備し古今が仕立てた日本語の奥★【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第一輪】
●日時 全日程 13:00〜18:00
2025年4月27日(日)→アーカイブ映像でご覧いただけます。
2025年5月25日(日)→アーカイブ映像でご覧いただけます。
2025年6月29日(日)
2025年7月27日(日)
2025年8月31日(日)
2025年9月28日(日)
●受講資格 どなたでも、お申し込みいただけます。
●受講料
◎本楼リアル参加◎ 6回分 55,000円(税込)
◎オンライン参加◎ 6回分 33,000円(税込)
*リアル/リモートともに全6回の記録映像が共有されますので
急な欠席でもキャッチアップ可能です。
●詳細・お申込はこちら
宮原由紀
編集的先達:持統天皇。クールなビジネスウーマン&ボーイッシュなシンデレラレディ&クールな熱情を秘める戦略デザイナー。13離で典離のあと、イベント裏方&輪読娘へと目まぐるしく転身。研ぎ澄まされた五感を武器に軽やかにコーチング道に邁進中。
山片蟠桃『夢の代』ってどんなもの?◎【輪読座】山片蟠桃『夢の代』を読む 第三輪
10月からの輪読座では山片蟠桃著『夢の代』を読んでいる。2025年12月21日(日)開催の第3輪で折り返しとなったが、山片蟠桃の致知格物っぷり、編集学校に関わる多くの人に知ってほしくなったので、少しだけお伝えしたい。 & […]
★空海が準備し古今が仕立てた日本語の奥★【輪読座「『古今和歌集』『新古今和歌集』を読む」第一輪】
『古今和歌集』『新古今和歌集』は誰が編纂したのだったろうか。パッと思い出せない。紀貫之や藤原定家という名前が浮かんだとして、そこにどんな和歌があるのかはピンとこない。そういう方々にこそドアノックしてほしいのが、この4月か […]
6世紀、動乱の南北朝から倭国を観る【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第六輪】
桜咲きこぼれる3月30日。本楼では輪読座記紀両読み、最終回となる第6輪が開催された。 半年前の第1輪では西暦200年代だった図象解説も第6輪では500年代に至る。記紀に加えて『三国史記』も合わせ読みしている背景もあり本シ […]
『古事記』で読む“古代史最大の夫婦喧嘩”【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第三輪】
大阪・堺市には、大小さまざまな古墳が点々としている。駅を降り、目的の古墳に向かっていくと次第にこんもりとした巨大な森のようなものを傍らに感じる時間が続く。仁徳天皇の陵墓である大仙古墳は、エジプトのクフ王のピラミッド、中国 […]
モスラと『古事記』のインタースコア【輪読座「『古事記』『日本書紀』両読み」第四輪】
松岡正剛校長の誕生日から一夜明けた1月26日。前日の42[花]敢談儀の残り香を味わいながらの開催となったのは輪読座『古事記』『日本書紀』両読み第四輪である。 輪読座の冒頭は恒例、前回の座を受けた宿題図象化の […]















コメント
1~3件/3件
2026-02-24

昆虫観察には、空間の切り取りに加えて、時間軸を切り裂くハサミをタテヨコ自在に走らせるのもおすすめ。この天使のようなミルク色の生き物は、数十分間の期間限定。古い表皮を脱ぎ捨てたばかりのクロゴキブリです。
2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。
2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。