草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。
「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。




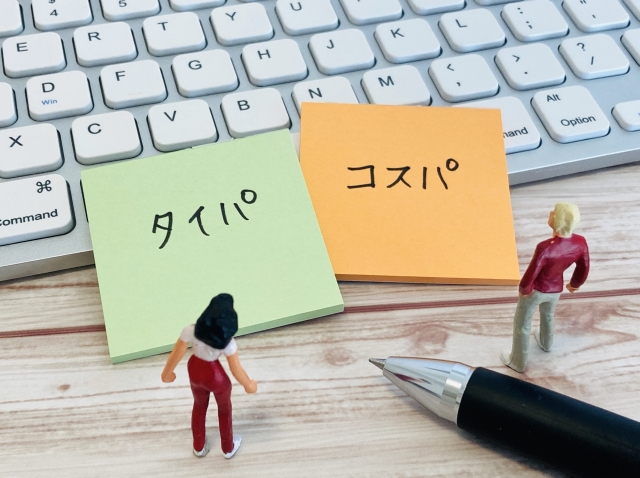
■Z世代の習慣
『映画を早送りで観る人たち』は、かなり衝撃的な本だった。面朕された本の帯には「2023年の新書大賞の第2位」とあり、なんとなくタイトルも気になったので他の本と一緒に購入したのが数週間前。読み始めたら、由々しき内容に後押しされ一気に最後まで読んだ。
稲田豊史『映画を早送りで観る人たち』光文社新書
Z世代とは、1995年から2011年、つまり阪神・淡路と東日本、ふたつの震災に挟まれた10年ほどの間生まれをいう。2010年から20年代に社会に進出する世代である。そんなZ世代ど真ん中の大学生にアンケートをとると、9割以上が、動画を倍速視聴したことがあるという。そういえば、高2の娘も横でスタディサプリの授業を倍速視聴していた。古典の女性の先生が甲高い声で、ピャカピャカと古文単語の活用形を連呼し、腕や首の動きもカクカクしていて、とてもせわしないのだが、なんとか言葉のひとつひとつは聞き取れる。
コロナ禍で大学の授業はオンデマンドが積極的に導入されることになったが、大学生が倍速視聴するコンテンツのトップは大学の講義だという。大学教授は比較的早口であるはずだが、倍速視聴に慣れた若者からすると、通常の授業で先生が話すスピードはかったるく感じるらしい。
それを聞いて、私はしばし考え込んでしまった。今度の病理学総論の講義どうしよう。ふつうにやったらかったるいのか。いっそのこと、倍速したら意味が聞き取れないくらいの超早口で講義してみようか。パワポもせわしなく変えて大量の情報をつめこんでみたらどうだろう。
「ねえ、ママさ、今度の講義、いつもの4倍速くらいでやってみようかな。」
「逆のこと、YouTuberがやってるよ。8倍速とかにしてふつうに見える動画を作るっていう企画」
東海オンエアの「編集で2,4,8倍速にしても普通に見えるように撮影しよう!!!」企画
つまり、スローモーションのように動いたり、低音でとんでもなくゆっくり発音することで、8倍速視聴したときに自然な話しぶりや動きになるような動画づくりへの挑戦である。YouTuber、さすが、時代に合わせて色々考えてるな。
「スタディサプリの授業の倍速視聴は、学校が推奨しているんだよ」
娘の発言にさらに驚く。いったい今の学校の先生は、どれだけ自分の授業に自信があるのだろう? 倍速視聴を推奨しつつ、自分の50分の授業は集中して聞いてもらえる自信があるのか? 私にはないぞ! MEdit Labのワークショップの開催を前に不安が増してくる。
■何より“タイパ”の良さ
Z世代は、“タイパ”を何より大切にする。タイパという言葉は、「三省堂辞書を編む人が選ぶ今年の新語2022」の大賞である。コスパから派生してタイパ、タイム・パフォーマンスの略で、時間が節約できるかどうかという価値基準である。
「もし2時間近くもかけちゃったら、おもしろさよりも後悔のほうが大きい」
リアルで先生と対話する楽しみよりも、無音で情景を映す映画のシーンの暗示的メッセージを読み解くよりも、タイパの方がZ世代にとっては重要である。講義は倍速視聴、ストーリーに関係ない場所は10秒飛ばし。さらに感情が揺さぶられるのは疲れるから、ハッピーエンドで終わるか否かや暴力シーンの有無など、あらかじめ超速で全体を視聴するか、ネタバレのファスト映画で確認してからにする。彼らはSNSを使いこなしながら、コスパとタイパが良いコトをがぶ飲みしていく。
映画や講義を倍速視聴する理由は、時間がないからだ。友人との会話やLINEトークに無難に参加できるように、あらゆる映画やドラマを軽く視聴しておく必要がある。大学の講義にバイトにサークル活動。わずかな時間を割いて、彼らは半ば強迫的にコンテンツを貪る。一昔前も、特に学生時代は、何かと同調圧力というか、友人との共通の話題を探さなくてはならないという一種の強迫的思考があっただろうけれど、今は、学校から帰宅してもLINEやインスタで友人とのつながりが切れることがない。みんなが大量の情報をよく咀嚼せずに次々取り込んでいる中、その焦りは学校の勉強にまで及び、先生までが動画教材を倍速視聴で見なさいと促す。「みんなが観てる、みんながやってる、だから私も」の連鎖だ。
イギリス人の研究者、フルーラ・バーディとギアナ・エカートは、Z世代に代表される現代的な消費行動について、「リキッド消費」と名付けた。2000年にポーランドの社会学者ジグムント・バウマンが発表した「リキッド・ソサエティ」を基礎にしたものである。賞味期限の短さ、レンタルやシェアリングなど所有ではなくアクセス・ベースの消費方法、そして、機能重視の脱物質的な消費。これら3つがリキッド消費の特徴である。Z世代にとって映画はもはやアートではなくコンテンツであり、鑑賞ではなく消費なのである。
■“エディパ”の時代
Z世代が哀れに思えてならなくなってくる。みんなと共感しなければと思うその生真面目すぎる他者配慮。自分のなさ。多様性というのは彼らにとっては、相手を不快にさせずに「いいね!」を連呼しなくては成りたたないものである。“のっぺらぼうの多様性”というお化けがZ世代の心を蝕む。
情報が大量に飛び交い、こういった世代の思考や行動パターンがどんどん中心になっていく世の中において、編集工学はどうなるのだろう。彼らに必要なのはタイパやコスパではなく、時間と、まさに”編集力”だと思うのだけれど、Z世代向けの編集術として、私は、そしてMEdit Labはどんなことを提示できるだろう。
先日、募集を開始した「「レッツMEdit Q !」リアル&ウェブワーク-医学をみんなでゲームする!-」は、医学をテーマにしながら、学び方を学ぶ。コンテンツではなく、方法を学ぶ。でも、単に「編集稽古をやりますよ」では、倍速視聴される。だから、医学をみんなでゲームすることにした。ゲームという具体例を持ち出しつつ、そこにシステム思考やネーミングやルール編集を組み込み、プレイヤーからクリエイターに回るワークショップである。
Z世代にかぎらず、今の日常に行き詰まりを感じている人すべてに、情報の見方はまだまだ未開拓なのだということを発信していきたい。倍速や10秒飛ばしではなくて、巻き戻しや切り出しや差し替えの方法だってあるんだってことを知ってほしい。タイパを気にするあまり、実は自分の生活自体を急いで消費してしまっているのに気づき、コンテンツを自ら創造する側にまわってほしい。
レッツMEdit Q! リアル&ウェブワーク 2023 「医学をみんなでゲームする」
すでに大学生や高校生が続々応募してきている。中には佐伯亮介さんのウェブデザインに惹かれて応募を決めた方も。Z世代と編集工学の可能性を模索できるまたとないチャンスに、おしゃべり病理医ほかMEditチームはわくわくしっぱなし。
これからはタイパより編集パフォーマンス、”エディパ”の時代なんだ、Z世代よ!
小倉加奈子
編集的先達:ブライアン・グリーン。病理医で、妻で、二児の母で、天然”じゅんちゃん”の娘、そしてイシス編集学校「析匠」。仕事も生活もイシスもすべて重ねて超加速する編集アスリート。『おしゃべり病理医』シリーズ本の執筆から経産省STEAMライブラリー教材「おしゃべり病理医のMEdit Lab」開発し、順天堂大学内に「MEdit Lab 順天堂大学STEAM教育研究会」http://meditlab.jpを発足。野望は、編集工学パンデミック。
「御意写さん」。松岡校長からいただい書だ。仕事部屋に飾っている。病理診断の本質が凝縮されたような書で、診断に悩み、ふと顕微鏡から目を離した私に「おいしゃさん、細胞の形の意味をもっと問いなさい」と語りかけてくれている。 […]
苗代主義と医学教育◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子
医学知識が2倍になるまでにかかる日数を調査した研究がある。1950年頃は、50年かかっていた試算が、私が医学部を卒業した2002年ころには5年、そして2020年の段階ではどうなっていたか。──なんと、73日である。 &n […]
漢方医学という方法◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子
干支は、基本的に中国やアジアの漢字文化圏において、年・月・日・時や方位、さらにはことがらの順序をあらわし、陰陽五行説などと結合してさまざまな占いや呪術にも応用される。東洋医学の中でも「中医学」は、主にその陰陽五行説を基盤 […]
クリスマスを堪能するドクターたち◢◤[遊姿綴箋] リレーコラム:小倉加奈子
◆メス納め?ガス納め? 365日、年中無休の医療機関。クリスマスも正月もない、というイメージをお持ちの方が少なくないと思うのですが、年末の院内行事はかなり華やかです。コロナ禍ではさすがにそんな余裕はありませ […]
現在、MEdit Labでは、高校生たちに医学をテーマにしたボードゲームづくりを体験してもらっている。私が書いたコラムに「いいね!」してくれた、ただそれだけを伝手に、強引にもお近づきになった山本貴光さんが、ずっとこのワー […]




コメント
1~3件/3件
2025-07-15

草むらで翅を響かせるマツムシ。東京都日野市にて。
「チン・チロリン」の虫の音は、「当日は私たちのことにも触れてくださいね」との呼びかけにも聴こえるし、「もうすぐ締め切り!」とのアラートにも聞こえてくる。
2025-07-13

『野望の王国』原作:雁屋哲、作画:由起賢二
セカイ系が猖獗を極める以前、世界征服とはこういうものだった!
目標は自らが世界最高の権力者となり、理想の王国を築くこと。ただそれだけ。あとはただひたすら死闘に次ぐ死闘!そして足掛け六年、全28巻費やして達成したのは、ようやく一地方都市の制圧だけだった。世界征服までの道のりはあまりにも長い!
2025-07-08

結婚飛行のために巣内から出てきたヤマトシロアリの羽アリたち。
配信の中で触れられているのはハチ目アリ科の一種と思われるが、こちらはゴキブリ目。
昆虫の複数の分類群で、祭りのアーキタイプが平行進化している。