棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。





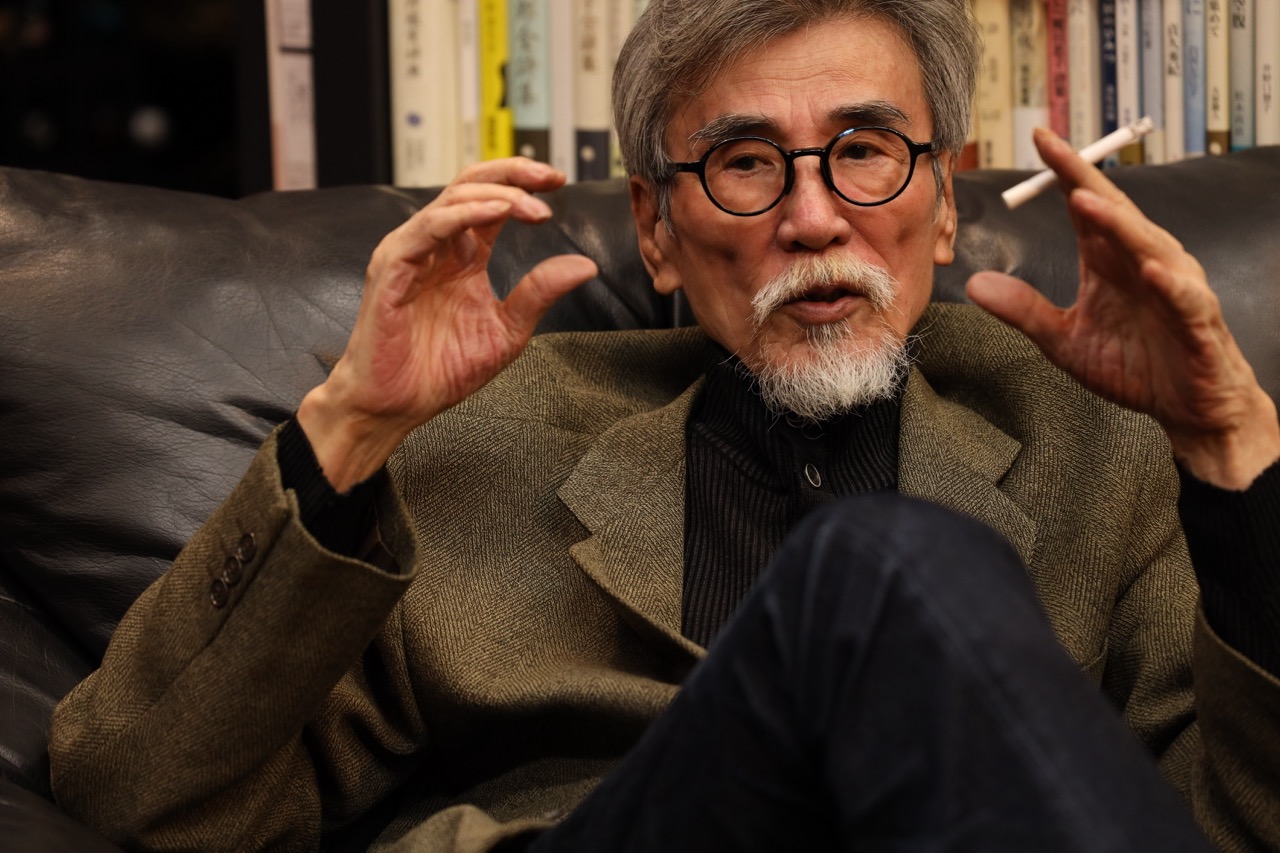
2020年3月、感門之盟の頃には、新型コロナへの警戒感がすでに強くなっていた。予定していた外の会場では開催できなくなり、本楼&オンラインでハイブリッド感門之盟をはじめて開催したのだった。カメラやスイッチャーといった機材をつかって配信するのもイシスの師範代たちだ。松岡校長は、新たなスタイルに意欲をもやし、テレビ番組を超えるような感門之盟や伝習座をディレクションしていった。
わたしは学匠になって3期目を終えたところだった。感門之盟の突破式で、校長は私を「学匠のすることが180あるとすれば178くらいはしている」と評した。褒められたような、まだまだ不足と言われたような、フクザツな評価である。褒められたと喜ぶか、「2」の残念を追求するか、よくよく考えざるをえない。
3期1年半、木村学匠(現・月匠)の仕事をなぞり、講座をつつがなく進めることを第一として、なんとかそれを果たしてきたのだった。そろそろ次へ向かいなさい、という校長の激励とも叱咤ともとれる「178」と「あと2」とともにコロナ禍に突入し、「今までと同じように」が不可能な与件のなかに放りこまれた。オンラインの学校を支えるのは、実はリアルで開催する伝習座や汁講や感門之盟である。師範代を引き上げ、指導陣の一座建立をはかる伝習座をリモートでどうつくれるのか。校長はリハーサルから伝習座に付き合ってくださるようになった。世界的な自粛ムードで外に出られないなか、校長も外に出ないで編集学校にいたというわけで、内部はものすごく充実した。
コロナ禍1回目となった44[破]伝習座のあと、校長に「破をどうしたいの?」と尋ねられて愕然とした。「私が破をどうしたいか考えていいんですか?」「そうだよ、学匠だもの」と校長。それまでは、学匠というロールを預かっていると考えていた。編集学校の続けてきたお題や方法を大切に守り、次の人に渡してゆくのだと。それならできそうだと思って引き受けたのだ。けれど、[破]をどうしたいかを考えて実行してゆくのか? わたしが? 就任4期目にやっとコトの重大さを理解し、断崖絶壁の前に立った気がした。わたしが[破]を別様にしてもいい、とは寛大だ。同時に果てしのないお題でもある。「あと2」は、178を凌駕する2だった。
2か月後の第2回の伝習座も、師範代は全員オンライン参加で、師範たちが本楼からの配信にのぞんだ。前日にリハーサルがあり、校長はオープニングをとびきりにしようと考えてくださった。音楽を流しながら、教室名を映し出し、校長がメッセージをのせる。その曲を何にしようか、あれこれ意見が出てSuperflyの楽曲になりそうだったが、私は「ジャズがいいです」とつぶやいた。校長は「いいよ。原田さんがジャズっていうなら、そうしよう」。「きれいなジャズというよりは、山下洋輔みたいな」「洋輔ね。破だからね」となり、校長は、山下洋輔のピアノと林英哲の太鼓によるボレロを選んでくれた。
ラヴェルのボレロが即興でどんどん激しく変化してゆくのを聴きながら、伝習座は始まった。このとき私の「破をどうしたいか」が初めて見えた。原曲を多様に自由に変化させていくジャズは、[破]の稽古のモデルにぴったりだ。ラヴェルへの愛と敬意の先に思い切った逸脱をみせるフリージャズは、わたしの[破]のヴィジョンとなった。
校長からは、学匠に就くときに「内なる編集的自由を持ちなさい。新しいしくみをつくることをおそれず、遠慮しないで」と言われていた。しかしそのために「どうしたいのか」のヴィジョンが必要だった。オープニングの曲を何にするかという小さなことをキッカケに、やっとヴィジョンが見えた。校長は、コロナ禍の内向き期間を最大限につかって、編集学校各所の不足を充足させてまわっていた。学匠の「あと2」もなんとかしようとしていたのだろう。
編集的自由を動かすためには、やはり少し勇気が必要だ。勇気を出すためにコレダ!と思える何か、外からのおとずれが必要なのである。校長がしてくださったように、誰かの編集が自由になるようなキッカケを、これからたくさんつくってゆきたい。校長の「あらわれているものを、あらわすものにする」編集は、人に対しても、礼節をもって繊細に、けれど臆することなく機を逃さずに施されてきた。その稀有な方法を、この身に入れて編集学校とともに歩み続ける。
イシス編集学校
[破]学匠 原田淳子
アイキャッチ写真:後藤由加里
校長のセレクトのボレロで始まった44[破]伝習座の模様は、こちらの記事でご覧ください。
破るためのイニシエーション 44[破]伝習座10shot
原田淳子
編集的先達:若桑みどり。姿勢が良すぎる、筋が通りすぎている破二代目学匠。優雅な音楽や舞台には恋慕を、高貴な文章や言葉に敬意を。かつて仕事で世にでる新刊すべてに目を通していた言語明晰な編集目利き。
【破 物語編集術先取りツアー 2/22開催】「はじめてのおつかい」に見入ってしまうあなたには、物語回路あり!!
お正月に日本テレビの「はじめてのおつかい」に見入ってしまった方、いますよね? 4~5歳の幼児が、ある日突然「おつかい」を頼まれる。ニンジンとお肉を買ってきて! これがないと今日のお誕生日パーティーに大好きなカレー […]
『ありごめ』が席巻!新課題本で臨んだセイゴオ知文術【55破】第1回アリスとテレス賞エントリー
開講から1か月、学衆たちは「5W1H+DO」にはじまり、「いじりみよ」「5つのカメラ」など、イシス人の刀ともいうべき文体編集術を稽古してきた。その成果を詰め込んで、1冊の本を紹介するのが仕上げのお題「セイゴオ知文術」だ […]
【55破開講】オールスターズ師範代とおもしろすぎる編集的世界へ!
師範代はつねに新人ばかりというのが、編集学校がほかの学校とすごーく違っている特徴である。それなのに、55[破]は再登板するベテランのほうが多いという珍しいことになった。9月20日の感門之盟で55[破]師範代10名が紹介さ […]
【破 エディットツアーオンラインスペシャル8月23日】イシスな文体編集術を先取り
文章を書くのが得意です! と胸を張って言える人は少ないと思う。得意ではない、むしろ苦手だ。でも、もしかして少しでも上手く書けたら、愉しいのではないか…、そんな希望をもって[破]を受講する方が多い。 [破]は […]
『ミッションインポッシブル』を翻案せよ!【54破】アリスとテレス賞物語編集術エントリー
全国的に猛暑にみまわれるなか、54[破]はアリスとテレス賞物語編集術エントリーの一日であった。この日、55[守]では佐藤優さんの特別講義があり、43期花伝所は演習の最終日であった。各講座の山場が重なるなか、54[破]学 […]




コメント
1~3件/3件
2026-02-19

棚下照生。この忘れられたマンガ家が、最近、X(ツイッター)で話題になっていた(なぜかは知らないが)。大人漫画のタッチで劇画を描くという、今となっては完全に絶滅した手法が、逆に新鮮に映るのかもしれない。代表作『めくらのお市物語』は、連載当時、大変な人気で、映画やテレビドラマにもなったのだが、現在では、タイトルに問題アリで、復刊の目途もない。もしも古本屋で見かけることがあったら絶対買いです。
2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。
2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。