小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。




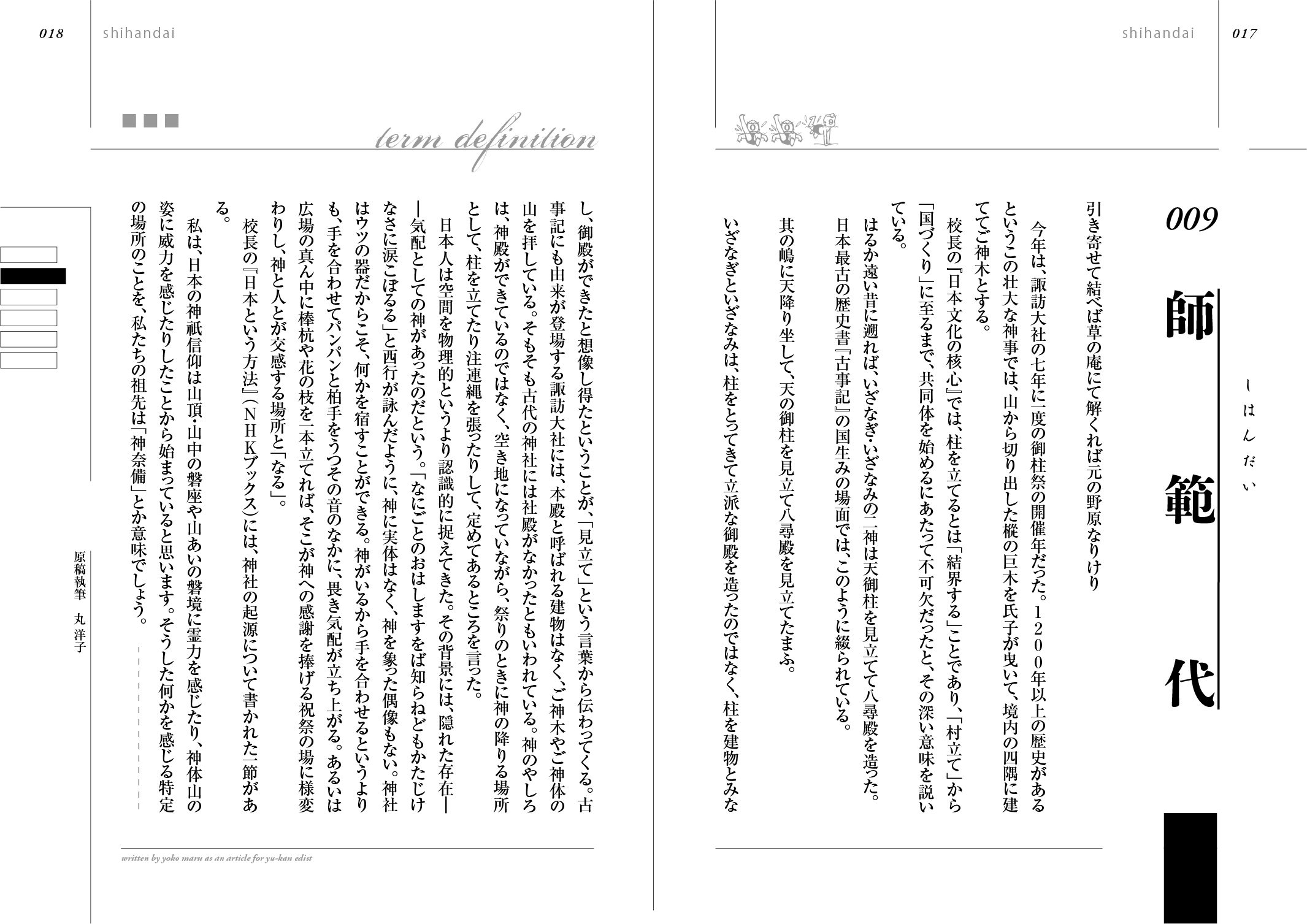
引き寄せて結べば草の庵にて解くれば元の野原なりけり
今年は、諏訪大社の七年に一度の御柱祭の開催年だった。1200年以上の歴史があるというこの壮大な神事では、山から切り出した樅の巨木を氏子が曳いて、境内の四隅に建ててご神木とする。
校長の『日本文化の核心』では、柱を立てるとは「結界する」ことであり、「村立て」から「国づくり」に至るまで、共同体を始めるにあたって不可欠だったと、その深い意味を説いている。
はるか遠い昔に遡れば、いざなぎ・いざなみの二神は天御柱を見立てて八尋殿を造った。
日本最古の歴史書『古事記』の国生みの場面では、このように綴られている。
其の嶋に天降り坐して、天の御柱を見立て八尋殿を見立てたまふ。
いざなぎといざなみは、柱をとってきて立派な御殿を造ったのではなく、柱を建物とみなし、御殿ができたと想像し得たということが、「見立て」という言葉から伝わってくる。古事記にも由来が登場する諏訪大社には、本殿と呼ばれる建物はなく、ご神木やご神体の山を拝している。そもそも古代の神社には社殿がなかったともいわれている。神のやしろは、神殿ができているのではなく、空き地になっていながら、祭りのときに神の降りる場所として、柱を立てたり注連縄を張ったりして、定めてあるところを言った。
日本人は空間を物理的というより認識的に捉えてきた。その背景には、隠れた存在――気配としての神があったのだという。「なにごとのおはしますをば知らねどもかたじけなさに涙こぼるる」と西行が詠んだように、神に実体はなく、神を象った偶像もない。神社はウツの器だからこそ、何かを宿すことができる。神がいるから手を合わせるというよりも、手を合わせてパンパンと柏手をうつその音のなかに、畏き気配が立ち上がる。あるいは広場の真ん中に棒杭や花の枝を一本立てれば、そこが神への感謝を捧げる祝祭の場に様変わりし、神と人とが交感する場所と「なる」。
校長の『日本という方法』(NHKブックス)には、神社の起源について書かれた一節がある。
私は、日本の神祇信仰は山頂・山中の磐座や山あいの磐境に霊力を感じたり、神体山の姿に威力を感じたりしたことから始まっていると思います。そうした何かを感じる特定の場所のことを、私たちの祖先は「神奈備」とか「産土」と呼んできました。なんとなく神々しい地、厳かな気分になる辺りという意味でしょう。
こうした特定の場所の一角に神籬や榊(境木)や注連縄(標縄)を示し、そこにちょっとした「社(やしろ)」をつくったのが、古代的な神社のスタートでした。これは、社という呼称がもとは「屋代」(屋根のある代)」であったことからも推測できるように、そこには「代=シロ」という考えかたがはたらいていたのです。
シロとは、「代」の文字をあてたことでも推察できるように、何か重要なものの代わりを担っているもののことです。エージェントのことです。
人が何かによって生かされていることを感じるとき、遍在する目に見えないスピリチュアル・エネルギーは霊性に感応する想像力を介して代(シロ)に宿る。代は仮の家ゆえに、別様の可能性に開かれている。
■イシスの代(シロ)
イシス編集学校の師範代とは、ネットの中の教室で十数人ずつの学衆を指南するエディティングコーチのことである。校長や師範の面影を「代」という器に映す、編集学校の中核を担う花形だ。みなそれぞれに職業は千差万別で、ふだんは別の仕事や家政を担いながら、複合的職能を発揮し、師範代に「なる」。ネット上の何もない空間に、校長が師範代の姿かたちや来し方行く末を込めて名付けた教室名をもって結界を引き、おもてを掃き清める。床の間に軸を掛けるようにウエルカムボードに心づくしの言葉を掲げ、アイコンを飾る。おもいおもいの趣向や創意工夫でおもてなしに心を砕き、学衆との問感応答返のなかで揺らぎ続ける。何度も仮設の空間を結んではほどき、「今」という偶然の瞬間を取り込みながら、一座建立へと向かう。
イシスの師範代は、なぜかくも凛々しく美しく、校長や師範のシロとしてふるまえるのだろうか。
■もう一人の私
The most sublime act is to set another before you.
先日アップされた千夜千冊第1811夜 ノースロップ・フライ『ダブル・ヴィジョン』は、珠玉のウィリアム・ブレイクの詩句との二重奏である。ブレイクは、メタファーやアナロジーによって掴めるヴィジョンが想像力の本体であると見極めていたという。校長はこのように説明している。
われわれの想像力はけっして単一では動かない。目の前の花や人影や鳥を知覚しているときも、たえずゆらゆらしているし、何かを引きずったり、何かをそこに組みこもうとしている。想像力は複合的かつ輻輳的で、すこぶる編集的なのだ。
そこには最低でも一対の「型」(one)と「対型」(another)が同時に動いている。この一対性をダブル・ヴィジョンとみなすとすると、われわれの思索のおおもとには(白川静ふうにいえば「興」の起動には)、ダブル・ヴィジョンだけが光を放って先行しているのだということになる。
私たちの心を育み、意味や文化を発生させてきたダブル・ヴィジョンや見立て。それらを生み出す類化性能は、宗教的想像力だけではなく、もっと多くの認識や思索に出入りしているはずだし、出入りさせるべきでもあると校長は語る。そのことを紐解いていくために、ブレイクの次の詩句が引用されている。
「最も崇高な行為には、自分の前にもう一人を想定することだ」
この一夜はこんなふうに続いている。
この「自分の前のもう一人」は神や如来やスーパーエグジスタンスや鬼のようなもので目立つだろうけれど、実際には誰にもありうる“one”と“another”でもあろうし、フィギュアやアバターでもあろうし、何かの「代」や「別」であってもいいはずのものだ。
もしそうだとしたら、われわれはどんな場面でも“one-another”という一対の初速カーソルあるいは初発ブラウザーによって、想像力の最初の起動を始められるということなのである。
「自分の前のもう一人」を想定しながら思索したり表現したりすることが、世界を認識する方法的核心であるダブル・ヴィジョン(想像力の本体)をいつでも喚起できる秘密だった。このことを、ブレイクはインゲニウム(エンジンの語源にあたるラテン語)と呼んだという。インゲニウムとは、「われわれの心身のどこかに先駆的に備わっているだろう天賦状態を感じる才能」を指す。
自分を離れ、我見の奥に内在する「まこと」や「もちまえ」の本来を活性化していくエンジン。それは校長や師範に肖ることや、学衆の回答を方法的に受容し、エディティング・モデルの交換をしていくプロセスで漲っていくのだろう。自分の前のもう一人のanotherは、校長であり師範であり、学衆の声やようすでもある。
この一夜では、校長がこれまで多様な編集を続けてこられた一番の心がけについて、このように書かれている。
自分が「何かの代わり」なのではなく、何かが「自分の代わり」だと思えるように仕事をしてきたということだろうと思う(そのように仕向けて仕事をしてきた)。これは自分を主語にすることをさておくということで、そうするほうが何かがずっと混在しうるということでもあるけれど、もっと正確にいうと「自分の前のもう一人」をどんな難所においても想定できるようにするということであった。
教室では、教える者が教えられる人であり、教えられる者が教える人でもある。「問感応答返」のプロセスは、双方が不足や矛盾を抱える自己不完結な状態でありつづけることによって成り立つ。師範代は学衆の回答に深く潜り、自分なりに言い替える。この再編集によって、新しい気づきが相手の見方を通しておのずと生まれる。学衆も指南を受けて、新たな気づきを得る。お互いがお互いを含み合い、浸透させ、関連しあう相互編集で、思ってもみなかったようなことが引き出され、創造的な場を生成していく。
エディティング・セルフは、主語的世界と場所的(述語的)世界を往復しながら変容しつづける。場の生成に主体的に関わり合い、場を内側から捉え直す自他非分離の世界を生きる。それは古来、人が樅の巨木に霊性を感じ、物や自然を自己の内面的な心の動きや態度を巻き込んで捉えてきたことと重なっているようにも思える。自然も「自分の前のもう一人」も、「私」があるということと表裏一体なのである。
確固たる一義的な「I(私)とthe other(他者)」から、観自在、融通無礙な「one とanother」へ。まだ逢ったことのない新しい自分、内なるマレビト(客神)とのかけがえのない出会いとインタースコアが、師範代になるとおとづれるのである。
§編集用語辞典
09[師範代]
丸洋子
編集的先達:ゲオルク・ジンメル。鳥たちの水浴びの音で目覚める。午後にはお庭で英国紅茶と手焼きのクッキー。その品の良さから、誰もが丸さんの子どもになりたいという憧れの存在。主婦のかたわら、翻訳も手がける。
「この場所、けっこうわかりにくいかもしれない」と書かれた看板を手にした可愛らしい男の子のイラストが、展覧会場の入り口に置かれている。眉根を寄せて地図を見ているその男の子を通り過ぎ、中へ進むと「あなたをずっとまっていたのか […]
八田英子律師が亭主となり、隔月に催される「本楼共茶会」(ほんろうともちゃかい)。編集学校の未入門者を同伴して、編集術の面白さを心ゆくまで共に味わうことができるイシスのサロンだ。毎回、律師は『見立て日本』(松岡正剛著、角川 […]
陸奥の真野の草原遠けども面影にして見ゆといふものを 柩のようなガラスケースが、広々とした明るい室内に点在している。しゃがんで入れ物の中を覗くと、幼い子どもの足形を焼成した、手のひらに載るほどの縄文時代の遺物 […]
公園の池に浮かぶ蓮の蕾の先端が薄紅色に染まり、ふっくらと丸みを帯びている。その姿は咲く日へ向けて、何かを一心に祈っているようにも見える。 先日、大和や河内や近江から集めた蓮の糸で編まれたという曼陀羅を「法然と極楽浄土展」 […]
千夜千冊『グノーシス 異端と近代』(1846夜)には「欠けた世界を、別様に仕立てる方法の謎」という心惹かれる帯がついている。中を開くと、グノーシスを簡潔に言い表す次の一文が現われる。 グノーシスとは「原理的 […]










コメント
1~3件/3件
2026-02-17

小川の水底での波乱万丈を生き抜き、無事に変態を遂げた後は人家の周りにもヒラヒラと飛んできてくれるハグロトンボ。「神様とんぼ」の異名にふさわしく、まるで合掌するかのように黒い翅をふんわり広げては閉じる。
2026-02-10

ハンノキの葉のうえで、総身を白い菌に侵されて命を終えていたキハダケンモンの幼虫。見なかったことにしてしまいたくなるこんな存在も、アングルを変えてレンズを向けてみると、メルヘン世界の住人に様変わりする。
2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)