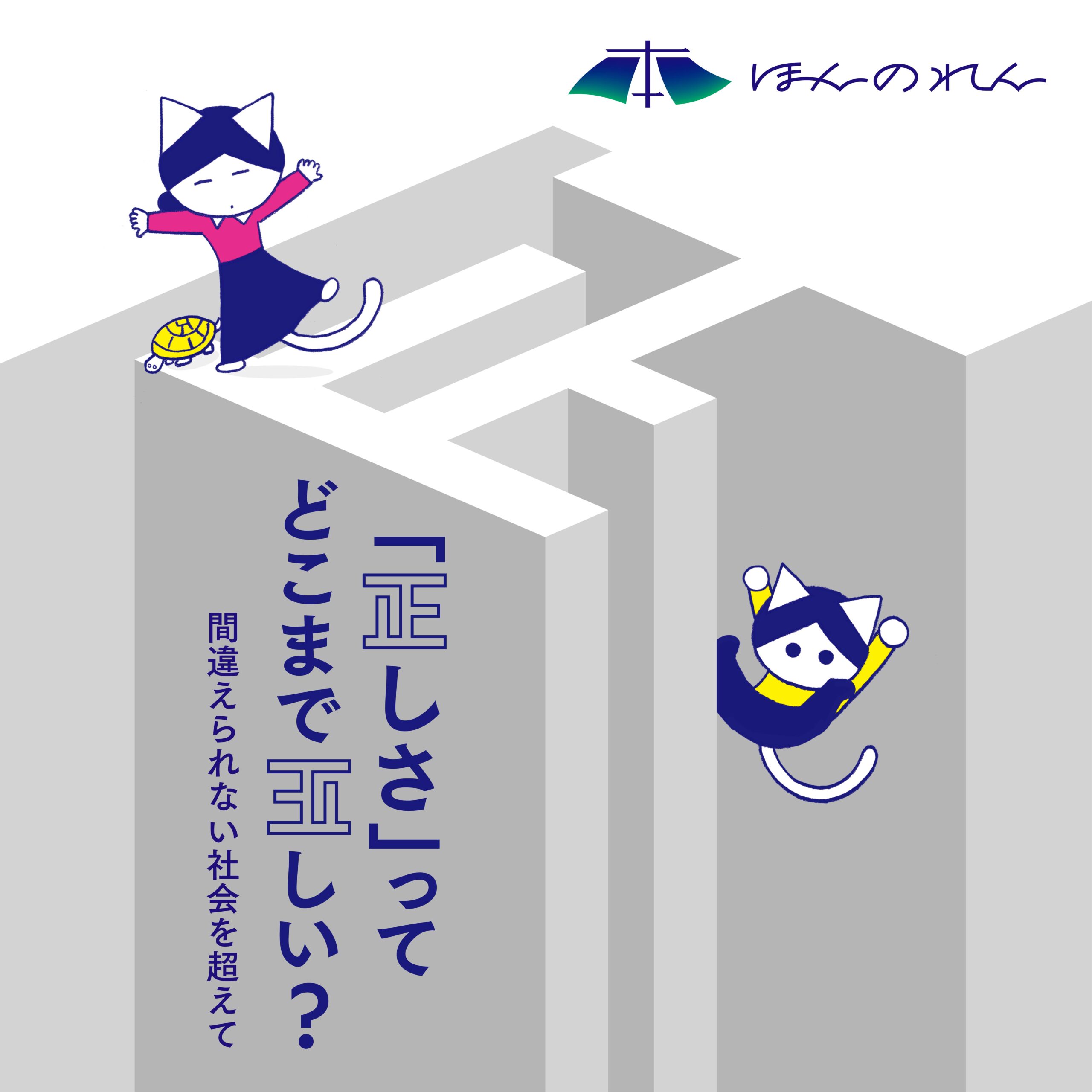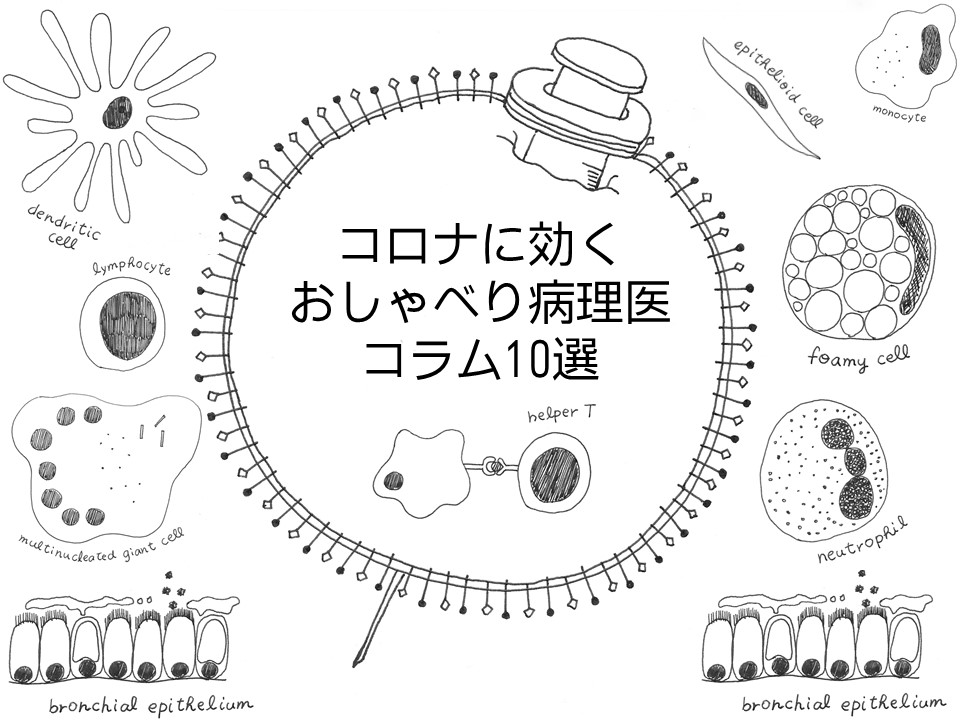-
【AIDA】シーズン1ボードインタビュー:佐倉統さん◆後編「間」を取り払う科学の役割
- 2023/05/06(土)08:32
-


今年度もハイパーエディティングプラットフォーム[AIDA]がはじまっている。「生命と文明のAIDA」を考えたSeason1から、Season2では「メディアと市場のAIDA」に向き合い、現在開講中2022年10月から始まったSeason3のテーマは「日本語としるしのAIDA」。新シーズンの展開とともに、過去シーズンのボードメンバーからの声に耳を傾けてみたい。
※内容は取材時のもの
前編 はこちら
編集工学研究所が主催するHyper-Editing Platform [AIDA]では、新しい時代の社会像を「編集的社会像」として掲げ、この問いをめぐる思索と活動を進めています。固定化された価値観から脱却し、本来の生き生きとした社会を描くために、いまわたしたちは何を考えるべきなのでしょうか。
1つのキーワードに「科学」があります。コペルニクスが地動説で明らかにしたのは地上世界と天上世界のつながりであり、ダーウィンは進化論で動物と人間の連続性を提示しました。科学は人間が別々の領域だと認識していたものに対して、そのつながりを指摘し続けてきたといえます。科学技術の存在意義を人間の進化の観点から位置づける東京大学教授 佐倉統さんに、科学的な視点からみた「編集的社会像」の輪郭を聞きました。
佐倉統(さくら おさむ):1960年8月13日生まれ。日本の科学技術社会論研究者。東京大学教授。専門は進化学を中心とする科学史、科学技術社会論、サイエンスコミュニケーションに関する研究。科学技術を人間の長い進化の視点から位置づけていくことを興味の根本として挙げている。NHKの科学教育番組「サイエンスZERO」コメンテーターも務めた。近年は脳神経倫理学や人工知能と社会の関係を中心に扱っている。東京大学科学技術インタープリター養成プログラムの教員も務めている。ほか、理化学研究所革新知能統合研究センターのチームリーダーも兼務。
科学が「間」を取り払ってきた
―― 新著「科学とはなにか」(講談社ブルーバックス)で、佐倉さんはご自身を「科学者ではない」と書かれていますね。
佐倉 私は特定の学問分野にどっぷりと浸かって研究者として活動してきたわけではないんです。だから自分のアイデンティティとしては、科学者ではないと思っています。そんななかで科学について語っているので、本職の科学者が考える「科学」とは、また違った見方をしている可能性もある、と示唆するためでもあります。そのような立ち位置に至ったのは意図してのことではありませんでした。大学院に入った時に感じたのは、「実験や調査は職人芸だ」ということ。研究活動では論文を執筆する手前の地道な作業が膨大にあります。それが実は性に合わなかったんですね。その代わり、ちょっと離れたところから全体像を捉えて語るのは得意だと感じました。科学史の集まりでサル学の研究動向について話すと面白がってもらえたり。そうした体験の積み重ねでここまでやってきました。
―― 複数の領域の「間」に自らを位置づけ、それらの関係性の意味を俯瞰的に見ていく方法は、松岡正剛の仕事の仕方とも似ている面があると思います。佐倉さんは「AIDA」のボードメンバーとして寄稿した文章(「見方集」と呼ばれる)のなかで、「科学は『間』を取り払ってきた」と書かれていました。
佐倉 コペルニクスの地動説は地球が太陽の周りを回っていると明らかにしました。それ以前は地上世界と天上世界は別々のものでした。しかし、その2つが実は連続した同じものであることを明らかにし、「間」にあった境界を取り払ったのがコペルニクスの地動説だったわけです。また、ダーウィンの進化論は動物と人間の「間」を、フロイトの精神分析は意識と無意識の「間」を、それぞれ連続のものだと解明しました。
このように人間が別々の領域だと認識していたものに対して、違いは表層的な部分だけであり、実はつながっていると指摘し続けてきたのが科学の営みです。逆に言えば、科学は人間が世界の中心にいるという錯覚を否定し、特権性を剥ぎ取ることで人間を端へ追いやってきたともいえます。だから科学は人に優しくないとか、非人間的なものだとも批判されてきました。それが科学史の1つの大きな流れでもあります。
ただ、一方で、人間がその特権性を剥ぎ取られるということは、自然に対して謙虚になれるということでもあると思います。「自分たちはつまらない存在である」と認識することと、「自然に対して謙虚である」こととは違うはず。謙虚になれれば、人間の特殊性を信奉して資源を酷使したり、環境を破壊するのは間違っていることだと分かるはずでしょう。その上でもう一度、これまで積み上げてきた科学の体系を「編集」しながら、人間の意味や面白さを物語として編み直す必要があると思います。
―― そのような仕事に携わるとなると、確かに特定の学問領域に活動範囲を限定していては難しいかもしれませんね。
佐倉 そうですね。特に今の大学制度では、ある分野でたくさん論文を書いて評価されないと研究者としての就職が難しい状況です。だから、どうしても視野が狭くなってしまう。しかし、世の中的には幅広い視野が必要とされているのです。大学が社会の要請に答えるのはどんどん難しくなっています。
一時期、『銃・病原菌・鉄』(ジャレド・ダイアモンド、倉骨彰、草思社)がよく読まれましたが、こうしたタイプの総合的な知のあり方への渇望は常にあると思います。つまり、従来、哲学の領域で問題とされていたことを、現在の科学的な成果を取り入れながら語っていくスタイルです。しかし、さきほどもいったように、分野横断的な知のあり方を構築するのは、現状の大学制度ではなかなか難しいように思います。
―― 「AIDA」では『表象は感染する』(ダン・スペルべル、菅野盾樹、新曜社)をよく取り上げています。情報や観念、ミーム(文化伝達や模倣の単位を表す概念)と呼ばれているものは、ウイルスに感染するように社会の間で広がっていくと同書では指摘されています。そして近代化以降、観念やミームが社会で固定化されてしまっているため、そこを動かしていくことも「編集的社会像」の意義と考えています。この視点で、現在固定化されている概念について、何か思い当たるものはありますか?
佐倉 大学にいて感じるのは、「正統『○○学』」というものに対するアイデンティティやこだわりがどんどん強くなっているということです。たとえば生物学について語る時にも、生物学外への横への広がりを嫌うような壁があると感じます。しかし、横へ感染していく、種を飛び越えていく動きは知には必要です。大学を出てベンチャー企業を起業するような人も増えてきていますが、そうした人たちとも
一緒に知を生み出していくことが大学の使命ですし、課題でもあると考えています。
ミームという概念はリチャード・ドーキンスが提唱しましたが、このことに関連して、今、私が個人的に面白いと思っているのは梅棹忠夫の仕事です。実は彼は『文明の生態史観』(中公文庫)で、ドーキンスより前に「宗教はウイルスだ」と書いているんですね。分野を横につないだ先例として、梅棹イズムは受け継がれているのか。個人的に掘り返してみようと思っています。

さまざまな「間」を越えていくために
―― 現在、新型コロナウイルスの蔓延を契機に日常生活が損なわれる人も増えています。「我々は何のために生きているのか」という根本的な問いかけもさまざまな場所で提起されています。
佐倉 今回の新型コロナウイルス禍を文明論的なかたちで捉え、深い考察ができるようになるのはもう少し先のことだと思います。少しずつ言説が出てきていますが、どれもまだありきたりに思われます。いまはまだパンデミックが進行中(*)ですし、分析にはもう少し時間がかかるでしょう。
*本インタビューは2021年2月中旬に行われました。
ただし、1つ言えるのは、複雑きわまる現代社会の問題を解決に導くためには科学の専門的な知見は必要不可欠だということです。そもそも日本には、首相の科学顧問もいなければ、その分野の専門的知見を集約している集中センターもない。有事の際にはそのつど臨時で当該分野の専門家を集めた会議体が形成され、権限や責任があいまいなまま対応が進みます。
10年前の東日本大震災の時もそうでしたが、なかばボランティアのようにして関係省庁や関係者たちがものすごい頑張りをみせ、どうにかこうにか難局を乗り越えていく。日本らしいといえば日本らしいのですが、専門知をうまく活用する方法を考えなければ、これから先、さらに大規模な未知の事態が発生した時に破局を招いてしまう危険性もあると思います。
―― いま大学の研究現場はどのような状態なのでしょうか?
佐倉 大変な状況です。特に心理学の実験など、リアルの場で人と会う必要がある分野では苦労が絶えません。また、一時期は図書館も閉鎖されてしまい、資料の渉猟も難しい状態でした。ただ、Zoomで手軽に離れた所にいる人たちにもインタビューや質問ができるようになりました。このメリットをどう伸ばしていくか、あるいは、デメリットをどのように少なくするかは本当にこれからの課題です。
一方、講義のリモート化の流れもあり、「大学はどうあるべきか」の議論が活発化してきています。これまでは新しい学部を作ろうと思うと、予算や人員や制度面で動きが取りづらかったのですが、今後は変わっていくかもしれません。オンラインでの講義も一般的になりましたし、若い世代に知を伝えていくにはどういうやり方があるのか、リアルとオンラインの使い分けはどうすべきかなど、仕切り直しをする機運は高まってきています。
―― 最後に1つお聞きします。感染症対策により、個人と社会の間や、マイノリティとマジョリティの間、あるいは多様な価値観の間で、隔たりが生じている状況です。それらの「間」を超えていくための佐倉さんなりの視点をお聞かせください。
佐倉 マイノリティとマジョリティに関して、現在の日本社会では、社会的弱者への理解不足は依然としてあると思います。以前、義足装具士の方に取材して衝撃を受けたのですが、いまでも国内の一部の地方では義足をつけて歩くのを恥ずかしいことだとする空気があるそうです。そのような意識は、たとえばパラリンピックの開催によって徐々に変わっていくかもしれません。義足というのは、五体満足、いわゆる「健常者」に近づけるように設計されています。それはよいことなのですが、一方で、何が「健常」かは捉え方次第でしょう。掃除が苦手なのも個性といえば個性です。デコボコは人それぞれであり、障がいは本来、健常と連続しているものだからです。技術的な解決だけではなく、地続きであると思ってもらう場や通念が必要だと思います。障がいは自分にとっての問題なんだという認識が定着していくと、相互理解は進みやすくなるのではないでしょうか。
ほかの「間」にも目を向けると、人工知能やロボットによって機械と人間の「間」がゆらぎ、環境問題は自然と文化の「間」に疑問をつきつけ、感染症対策は個人と社会の「間」に再考を迫っています。これらの「間」を科学技術は乗り越える力を持っていると私は考えます。あとは、科学の専門的知見をどのように社会に還元し、活かしていく仕組みを作っていくか。日本社会によく見られる「文化や文脈に依存した『場の力』」だけではなく、普遍的な場面でも効力を発揮し得る科学や技術の専門的知見に目を向け、それらを編み上げるかたちでの組織/社会デザインがこれからはもっと必要だと思います。

取材/執筆:弥富文次
取材/編集/撮影:谷古宇浩司(編集工学研究所)
※2021年4月26日にnoteに公開した記事を転載