昆虫の巨大な複眼は、360度のあらゆる斜め目線を担保する無数の個眼の集積。
それに加えて、頭頂には場の明暗を巧みに感じ取る単眼が備わっている。
学衆の目線に立てば、直視を擬く偽瞳孔がこちらを見つめてくる。






語りは、ときに他者を救い、ときに断罪する。検証されない善悪が暴力を正当化し、語りの快楽として社会に流通していくなか、沈黙する者、歪められる者、語りの形式を変える者たちが描き出すのは、語りそのものに抗う、“別様の仇討ち”だった。
大河ドラマを遊び尽くそう、歴史が生んだドラマから、さらに新しい物語を生み出そう。そんな心意気の多読アレゴリアのクラブ「大河ばっか!」を率いるナビゲーターの筆司(ひつじ、と読みます)の宮前鉄也と相部礼子がめぇめぇと今週のみどころをお届けします。
共同幻想としての「神」の誕生
人間は、不条理に直面したとき、そのままではいられない生き物です。とりわけ、愛する者の死、暴力、災害といった圧倒的な理不尽が、何の意味も与えられないまま放置されることに、私たちは本能的な拒絶を覚えます。だからこそ、たとえ明確な因果がどこにも見当たらなかったとしても、人は「理由」を求め、語り始めるのです。
偶然に意味を与え、混沌に秩序を与える「理由」が集められ、繋ぎ合わされてゆくと、それは「物語」になります。そしてその物語が繰り返し語られ、他者と共有されるうちに、その一部はやがて「神話」や「宗教」として定着していきます。
それは、因果関係の正しさを検証するより先に、「これは何を象徴しているのか」「何を語るために現れたのか」といった意味づけを先回りして与えようとする、極めて人間的な営みです。神とは、そうした営みのなかで、人々が不条理を超えて生き延びるために必要とした「説明」の体系であり、失われた意味を回復しようとするために作られた、もっとも人間的な編集装置なのかもしれません。
天明四年三月二十四日、江戸城内で若年寄・田沼意知が佐野政言に斬られました。しかしその死は、幕府によって徹底的に沈黙のうちに処理されます。公式記録には乱心とだけ記され、真相究明もされないまま、佐野は意次が亡くなった翌日に切腹。そこに残されたのは、血の生々しさと、誰も言葉を与えようとしない巨大な「空白」でした。
しかし、人々はこの「空白」を、空白のまま抱えてはいられませんでした。もともと民衆のあいだには、米が買えないことへの怒り、明日をも知れぬ飢えへの不安、積もり続ける生活の閉塞感といった感情がマグマのように溜まっていました。そのドロドロの感情が、「田沼の悪政がすべての元凶だ」という突拍子もない因果関係を(その正しさを検証するより先に)構築していったのです。それは現代における、「この暮らしにくさは総理大臣のせいだ」「今の総理大臣を辞めさせろ」という漠然とした怒りにも似ています。
米価の異常な高騰も、浅間山の噴火も、全てが「田沼のせい」とされていたなかで、意知の死は過熱していた物語に結末を与えてしまいます。「天が裁きを下した」「民の苦しみを晴らした」といった語りが、一気に社会を覆ったのです。
つまり田沼意知の死は、新しい語りを生んだというより、すでに飽和していた民意の物語を一挙に確定させ、「天誅」という形式へと自動的に結びつけてしまった──そう捉えるほうが、実相に近いでしょう。
「佐野が我々の恨みを晴らしてくれた!」「佐野が腐敗した権力に鉄槌を下した!」──そうした語りにちょうどよく接続されたのが、佐野政言の刃傷事件の翌日に起きた米価の下落という“偶然”でした。
人々は、その偶然にすがるようにして勝手に物語を作り出しました。「佐野の刃が天に届き、神が米価を下げさせたのだ」と。無関係な出来事をありもしない因果で結びつけ、神話へと変換していったのです。
記号論の研究で知られるローラン・バルトは『神話作用』のなかで、神話とは「歴史的・政治的な出来事に“自然”の衣を着せるプロセスである」と述べました。まさにこのとき、佐野の凶行はもはや個人的な怨恨による事件ではなくなりました。それは「世直しの刃」として意味を与えられ、民衆の願いが成就した証として神格化されていったのです。
語られぬ痛みと仇──安易な物語に抗う者たち
「佐野=善、田沼=悪」。そんな単純な勧善懲悪の物語が、田沼意知の死を境に、民衆のあいだで急速に広がっていきました。語りはいつも力を持ちます。そしてときにその力は、事実を超えて、他者の存在すら塗り替えてしまうのです。誰が正義で、誰が悪なのか──社会が「納得したい物語」を求めるとき、その物語の枠からこぼれる痛みは、容赦なく切り捨てられていきます。
そして、その語りの圧力のなかで、最も鋭くその痛みを引き受けさせられた存在がいました。田沼意知と心を通わせていた花魁・誰袖です。意知の遺骸が市中を運ばれる日、通りを埋め尽くす野次馬のなかに、痩せ衰えた誰袖の姿がありました。やがて、ひとりの大工が「天罰だ」と叫び、棺の乗った駕籠に石を投げつけます。その一投が引き金となり、群衆のあちこちから次々と石が飛び交い始めました。
誰袖は、地面に膝をつき、「やめておくんなんし」と何度も頭を下げて懸命に懇願します。しかし投石はやまず、「外道」「悪の女房」といった罵声が飛び交います。彼女はやがて立ち上がり、「どっちが外道なんだよ!」と叫びながら、石を拾って投げ返しました。その刹那、石の一つが彼女の顔面に直撃し、白粉の下から血がじわりとにじみ出ます。
異様な光景に、蔦屋重三郎はたまらず駆け寄ります。「この娘は、気鬱の病でして」とその場を取り繕いながら、誰袖の体を亡骸の前から引き剥がしました。裏手に身を隠すように退いたあと、誰袖は憤怒に震えながら蔦重に言葉を投げつけます。
「何をしんした。あの方が、石を投げられねばならぬほどの何を!」
彼女の声は、根拠のない語りによって愛する者の命が奪われ、さらにその名誉まで汚されることに対する、怒りと絶望そのものでした。
そして、しぼり出すように訴えます──
「仇を討っておくんなんし」
その一言は復讐の衝動ではありませんでした。彼女の怒りの矛先は、佐野政言という個人ではなかった。意知を「悪」と定義し、石を投げることを正義と信じて疑わない世間──その語りの構造にこそ、彼女は抗っていたのです。
そして、その語りの力に、もうひとりの男もまた抗おうとしていました。父・田沼意次です。意知の死後、蔦重に宛てた手紙のなかで、彼はこう記しています──
「手短にいえば、俺は仇を討つことにした。生きて、あいつが成したであろうことを成していく。それが、俺の仇の取り方だ。おまえがどのように仇を取るのか、よければ、そのうち訊かせてくれ」。
意次にとっての仇とは、佐野でも、事件の黒幕でもありませんでした。田沼派を「悪」と決めつけ、改革を潰そうとする勢力と世論のすべて、それこそが彼の抗うべき敵だったのです。だからこそ彼は、「語られる田沼」ではなく、「語り返す田沼」として、生きて語りを更新することを選んだのです。
そして蔦重もまた、誰袖の叫びと意次の挑発を受けて、自らに問いかけることになります──自分の敵とは何か?それは佐野ではない。投石する群衆でもない。「佐野=善、意知=悪」という構図に安心し、暴力を正義として消費する語りの構造こそが、彼の抗うべき敵ではないか──と。
誰袖、田沼意次、蔦重。三人はそれぞれ異なる仕方で「仇」という言葉を引き受けました。ある者は語られすぎる語りに身体で抗い、ある者は信念を貫くことで語りを更新し、ある者は新たな語りの形式を探し始める。それぞれが見据えていたのは暴力そのものではなく、暴力に意味を与え、断罪と快楽を生む語り──歪んだ物語の構造そのものでした。
語りの魔術をほどく──蔦屋重三郎の仇討ち
第二十八回のラスト、山東京伝(北尾政演)が一枚の戯画を差し出します。その絵を見たとき、蔦屋重三郎のなかに、ある確信が灯りました──新たな黄表紙を出すタイミングだと。黄表紙の内容は伏せられていましたが、その意図は明白です。
「佐野=善、意知=悪」という単純で耳障りのよい勧善懲悪の物語。それを、笑いと滑稽さの力で、根底から編み替えること。暴力に意味を与え、正義の衣をまとって快楽として流通するその語りを、笑いの形式でほどいていくこと。それこそが、蔦重にとっての「仇討ち」だったのです。
彼にとって「仇」とは、佐野政言という一人の人物ではありません。「仇」とは、暴力を意味づけ、快楽とともに流布していく「語りの構造」そのものでした。そしてそれに抗うために、蔦重はあえて黄表紙という娯楽性の高い形式を選びました。民衆に受け入れられやすいメディアを通じて、同じ語りの中に足を踏み入れながら、その水脈を変えていくのです。
ここで思い出されるのが、南アフリカの作家J.M.クッツェーの『恥辱(Disgrace)』です。
この物語では、大学教授の父が娘ルーシーの農場に身を寄せるなか、彼女は性暴力の被害に遭います。にもかかわらず、ルーシーは語ることを拒み、加害者を訴えることもせず、ただその土地に「残る」と決意します。語れば、誰かが意味を与え、物語が始まり、断罪が生まれてしまう。だから彼女は沈黙する──その選択は、語りの暴力に抗する、最後の尊厳のかたちでした。
クッツェーが描いたのは、「語らないこと」で自らの痛みと尊厳を守るひとりの人物です。沈黙のうちにこそ、言葉では包みきれぬ傷の深さが滲む。一方、蔦重は「語ること」そのものを捨てませんでした。むしろ語りの暴力性を引き受けたうえで、語りの“かたち”を変えることで、その力を別の方向へと導こうとしたのです。
やがて蔦重は気づきます。──本来、誰袖は、意知と共に笑っていたはずの存在だった。であれば、民衆の語りによって笑いを奪われた誰袖が、再びふと笑うことができたなら、それこそが「語りに打ち勝った」証になるはずだと。その気づきは、「もし意知が生きていたなら、誰袖はどうしていただろうか」という問いに端を発しています。それは、「息子が生きていたら果たしていたであろう改革を、私がやり遂げる」と語った田沼意次の姿勢と、同じ構えに他なりません。
黄表紙という娯楽の器で、民衆が信じる善悪とは逆の善悪を有する物語を流通させる。それによって人々が当然のように信じていた正義の構図に揺さぶりをかけ、笑いを通して無自覚な快楽に違和感を差し込む。偽りの語りを駆逐し、語りが孕む暴力性を浮かび上がらせる。田沼意次が、息子の志を継ぐことで「仇討ち」を果たそうとしたように、蔦重もまた、誰袖の時間を取り戻すために、「ズラされた語り」を編み直すことによって、「語りの魔術」に抗おうとしたのでした。
語りすぎる社会の中で──単純化された「報い」と語りの臨界点
2025年の私たちの社会もまた、因果関係の正しさが検証されていない物語で溢れています。不安、怒り、孤独、疲弊──そうした感情がSNSという増幅装置を通して肥大化し、「わかりやすい敵」や「救世主」をめぐる物語が、日々、生まれては消費されていきます。
そこではしばしば、「おまえに語る資格はない」という言葉が、正義のかたちをして投げつけられます。「不法な外国人に怯えたことがないから、そんなことが言えるのだろう」「マナーの悪い観光客に迷惑したこともないくせに、多文化共生を語るな」。そうした言葉が繰り返されるたびに、「当事者でなければ語れない」という正しさは、やがて「他者を黙らせる力」へと転じていきます。そしてその延長線上で、異なる文化や存在を「語るべきでないもの」として排除し始めるのです。
実際、「日本人の誇りを取り戻そう」「自国を守るのは当然だ」といった耳触りのよいスローガンが、複雑な現実を都合よく単純化し、差別や排他を正当化する場面に、私たちは日々出会っています。安直な語りは、正義が悪を一掃する爽快感をもたらしながら、異なる声や痛みを削ぎ落とし、ひたすらに「わかりやすく」を呪詛のように唱えながら、複雑であること自体を否定していくのです。『べらぼう』第二十八回が描いたのは、まさにその臨界点でした。
佐野政言の刃傷は、民の苦しみを代弁した英雄として神話化され、世直し大明神として祀られていきました。暴力は「報い」や「天誅」といった名を与えられ、意味と快楽をまといながら、正義の姿をして流通していきます。その語りのなかで、田沼意知と誰袖は、単なる被害者ではなく、報いを受けて当然の悪として描かれていきます。意知は政治的傲慢の象徴として、誰袖は松前藩の弟をたぶらかした女として。
彼らはそれぞれ、「わかりやすい悪」の型に押し込められ、民衆の語りの中で断罪されていきました。その構造に対して、『べらぼう』の脚本家は明確に対峙しています。人間は語る動物です。ゆえに、語りは避けられない営みであると同時に、それがいかに他者を排除し、暴力の媒介となりうるかを、脚本家は一貫して問い続けています。
「自分=善、他者=悪」という単純な構図は、人々にとって分かりやすく、慰めにもなりえます。だがその慰めが、やがて快楽となり、排除と断罪のシステムへと変貌していく──『べらぼう』は、その欲望の回路を鋭く可視化してきました。だからこそ、蔦重は「佐野=善、意知=悪」という語りを、鵜呑みにすることはできなかったのです。
誰袖の跳躍もまた、その語りへの異議申し立てでした。愛した者が「報いを受ける悪」として石を投げられる──その理不尽に抗うように、彼女は棺の前へとその身を投げ出します。声を発さず、物語の回路から身を引きはがすように跳ぶことで、彼女は語りきれぬ痛みを現前させました。ジュディス・バトラーの言葉を借りるなら、「語りから排除された存在は、その身体の現前によって主張を持つ」のです。
誰袖は、意知の政治的志を助けるため、松前藩の弟君をたぶらかした人物でもあります。つまり、語りの構造をなぞれば、彼女自身もまた「語る資格のない者」「断罪される側」として扱われうる立場にありました。それでも彼女は跳躍したのです。その行為には、「悪には語らせるな」という安直な時代の風潮への、痛烈な批判が込められていました。脚本家は、キャラクターに善と悪を同居させることで、語りがいかに他者を単純化し、断罪していくのかという構造そのものを炙り出そうとしているのです。
そして、それは蔦重自身にも重なります。彼は第六回で、「鱗形屋が摘発されたとき、心のどこかでそれを喜んでいた。代わりにのし上がれると思っていた」と自らの野心を告白しました。善悪で割り切れない感情、自らの中にある欲望と恥を見つめながら、それでもなお語ることを手放さない。それが、蔦重という語り手の覚悟なのです。
「悪は語るな」「語るには資格がいる」──そんな言葉が飛び交う時代にあって、脚本家は、語りのもつ暴力性を直視しつつも、なお語りを諦めない。そのうえで「どう語るか」という語りの“形式”そのものに問いを差し出しています。
蔦重が手がけようとする黄表紙は、語りすぎる社会の中で、語る者・語られる者・語りを拒む者という三者の配置をずらし、新たな構図を立ち上げる試みです。そこには、「報い」という語りの快楽を逸らし、「痛み」が安易な正義に使われることを防ごうとする、倫理的な工夫が込められています。
物語とは、正義を叫ぶための装置ではなく、本来、語りえぬものに触れるための試みである──『べらぼう』第二十八回は、その極限にまで語りの本質を追い詰め、なお物語ることの意味を問う、極めて現代的なドラマだったのです。
べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十七
べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十六
べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十四
べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十三
べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十一
べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その十
べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その九
べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その八(番外編)
べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その八
べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その六
べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その五
べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その四
べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その三
べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その二
べらぼう絢華帳 ~江戸を編む蔦重の夢~ その一
大河ばっか組!
多読で楽しむ「大河ばっか!」は大河ドラマの世界を編集工学の視点で楽しむためのクラブ。物語好きな筆司たちが「組!」になって、大河ドラマの「今」を追いかけます。
どうしてここで来週の放映は「なし?」(選挙のため)と叫んだ人が多かったのではないでしょうか。花の下にて春死なん、は比喩ではなかったのか…。 大河ドラマを遊び尽くそう、歴史が生んだドラマから、さらに新しい物語を生み出そ […]
「語ること」が評価され、「沈黙」は無視される。けれど私たちは、ほんとうに語りきれているだろうか。語る資格を問う社会、発信する力に価値が置かれる現代。そのなかで、“語れなさ”が開く物語が、ふたたび私たちに、語りの意味を問 […]
え? 結婚していたの? ええ? 子どもがいたの? と今回、何より驚いたのは、あの次郎兵衛兄さんに妻と三人の子どもがいたことではないでしょうか。店先でぶらぶらしているだけかと思ったら…。そんな兄さんも神妙な面持ちで(しれ […]
名を与えられぬ語りがある。誰にも届かぬまま、制度の縁に追いやられた声。だが、制度の中心とは、本当に名を持つ者たちの居場所なのだろうか。むしろその核にあるのは、語り得ぬ者を排除することで辛うじて成立する〈空虚な中心〉では […]
二代目大文字屋市兵衛さんは、父親とは違い、ソフトな人かと思いきや、豹変すると父親が乗り移ったかのようでした(演じ分けている伊藤淳史に拍手)。 大河ドラマを遊び尽くそう、歴史が生んだドラマから、さらに新しい物語を生み出 […]







コメント
1~3件/3件
2025-07-29

昆虫の巨大な複眼は、360度のあらゆる斜め目線を担保する無数の個眼の集積。
それに加えて、頭頂には場の明暗を巧みに感じ取る単眼が備わっている。
学衆の目線に立てば、直視を擬く偽瞳孔がこちらを見つめてくる。
2025-07-27

ただ今フランスのマルシェあちらこちらで縦縞の赤肉メロンが山盛りだ。自然界が生んだデザインはじつに美しい。赤肉にくるりと生ハムを巻けば、口福ともいうべき大人の欲望が満たされる。
2025-07-25
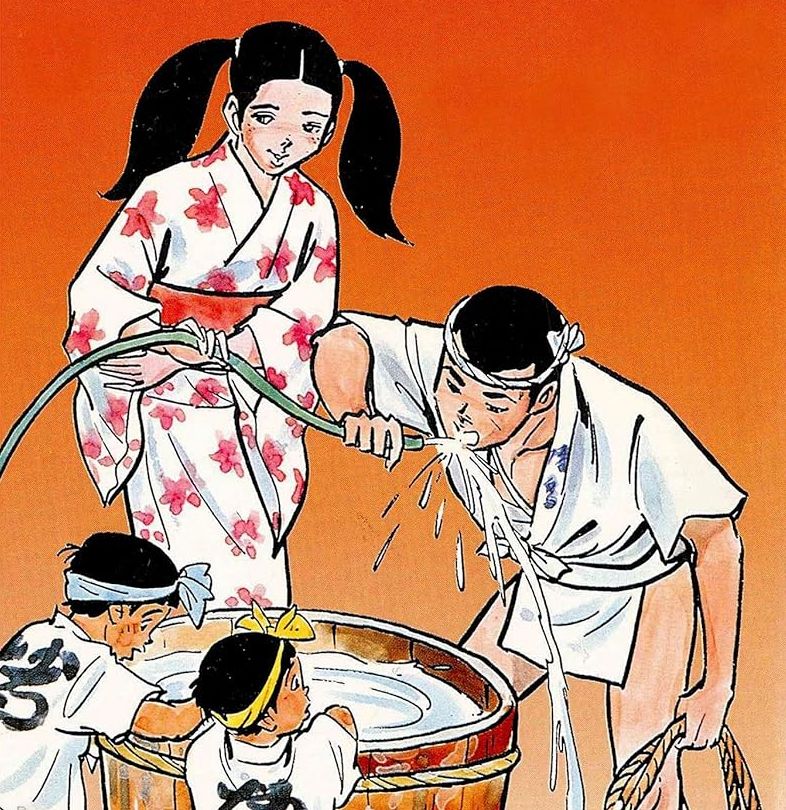
九州出身のマンガ家は数多いが、”九州男児”っぽさを前面に押し出している作家といえば、松本零士に小林よしのり、そして長谷川法世ということになるだろう(みんな福岡だが…)。なかでも長谷川法世『博多っ子純情』は、その路線の決定版!
これこれこの感じ。まさにこれが九州男児バイ!(…と、よそ者の目には見える…)