発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。





「子どもにこそ編集を!」
イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、
「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。
子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。
子供たちの遊びを、海よりも広い心で受け止める方法の奮闘記。
今日は何をしてたの
秋から冬にかけて、編集かあさんはイシス編集学校の基本コース[守]の稽古に取り組んでいた。
36番目のお題「バナナと魯山人」までたどり着いた日、寝る前の長女(8)から「今日は、わたしが学校に行ってる間、何してたの?」と尋ねられた。
その日心が湧きたったできごとを一つあげるとしたら、回答を仕上げて送信したことである。
「それってどんな問題?」
どう説明するか一瞬考えたあと、よしもとばななという現代の作家さんの文章と、北大路魯山人という少し前の美食家として知られる人の文章を、バラバラにして、混ぜて、並べ替えて、新しい意味を持つ文章にするお題だとストレートに伝えてみた。
長男(14)が妹にはまだわからないだろうという顔で見てくる。
予想に反して長女は「なにそれ。やってみたい」と起き上がった。とはいえ、もうパジャマである。今から紙と鉛筆を出すわけにもいかない。
「うーん、じゃあ、たとえばがまくんとかえるくんのお話と、スイミーを混ぜてみるとどうなるだろう。できるかな」
とっさに、こんなお題が口から出てきた。
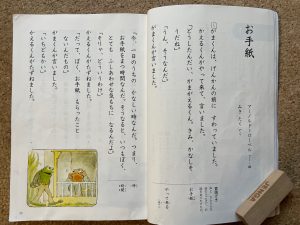
「お手紙」『こくご 二(下)』光村図書より
「スイミー」『こくご 二(上)』光村図書より
2つのお話が混ざる
がまくんとかえるくんの交友を描く『ふたりはともだち』シリーズの一つ「お手紙」と、海が舞台で一匹だけ黒いスイミーがなかまと一緒に大きな魚を追い払う『スイミー』。両方とも2年生の国語教科書に載っていて、何日もかけて読みといていた。
「できた!」
3秒ぐらいで長女の手があがった。
「川の中に100匹のカエルが住んでいました。そのなかで一匹だけ黒いカエルがいました。黒いカエルは他のカエルよりも足が遅いカエルでした」
元のお話では黒いスイミーだけ泳ぐのが速い。逆だねというと、そのほうがおもしろいからと返ってきた。
「ある日、オオサンショウウオがやってきて、100匹のカエルたちはぜんぶ食べられてしまいました。けれども黒いカエルだけは“まずそう”と思われて、食べられなかったのです」
「なるほど」長男が言う。
頬がゆるむ。この設定、どうやって浮かんだのだろう。
「それから黒いカエルは川の中を泳ぎ回って、前の仲間に似たカエルたちに出会いました。それで、力をあわせて敵を追い払いました」
話し終えた長女、「どうだった? おもしろかったでしょ」
100ぴきものカエルたちがみんなでおしあいへしあいして、大きなカエルの姿になっているところを想像すると、ヌルヌルモゾモゾしてきた。もとのお話とはだいぶ違う迫力がでたねと身振りもまじえて、感じたことを言葉にする。
お話がお話を生む
長女の話を聞いた後、長男が「あるいは2ひきの魚が主人公になるという選択肢もあるな」と言いだした。
そうそう、そういう入れ替え方もある。がまくんとかえるくんを変えるんだから、サカナくんとウオくんになるのかな。では、ふたりのあいだで手紙を運ぶカタツムリは何になるのだろう。
タニシ、エビ、はたまたウナギ? 水の中の生き物に注意のカーソルをむけ、何があてはまるのかを考えるのは[守]の【要素・機能・属性】や【地と図】とつながっている。
「うーん、思いつかない」。長男は、物語は少し苦手である。いっそカタツムリは登場しないというストーリーもあり得るのではないかという話になる。
思いつかないということもまた、物語の流れや雰囲気を変えていく。稽古以前の、幼な心の物語編集術だ。
かあさんなら、キーワードを『スイミー』の「ぼくが目になろう」にするかな。このセリフが入るようにお話を考えると前置きして、2匹のカエルが主人公のお話を作りながら話す。
長女はもともと夜型でいつまでも起きているが、ふだんよりもさらに遅くなった。これでお終いと遊びを締める。
お話からお話をつくる遊びが、これぐらいおもしろがれるようになっているということに「バナナと魯山人」がきっかけで気がついた。マインクラフトなどのゲームにこのところのめりこんでいることも関係しているかもしれない。
似た遊びをあちこちでやってみたい。リビングに戻って夜のお茶を飲みながら考え始めた。
『ふたりはともだち 』
アーノルド・ローベル (著), 三木 卓 (翻訳),文化出版局
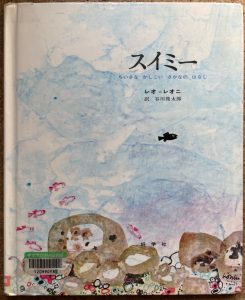
『スイミー―ちいさなかしこいさかなのはなし』
レオ・レオニ (著), 谷川 俊太郎 (翻訳),好文社
◆アイキャッチ画像:『こくご 二(上)』光村図書 より
松井 路代
編集的先達:中島敦。2007年生の長男と独自のホームエデュケーション。オペラ好きの夫、小学生の娘と奈良在住の主婦。離では典離、物語講座では冠綴賞というイシスの二冠王。野望は子ども編集学校と小説家デビュー。
「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩みQ&Aまで。 […]
【Archive】編集かあさんコレクション「月日星々」2025/4/25更新
「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る、編集かあさんシリーズ。 庭で、街で、部屋で、本棚の前で、 子供たちの遊びを、海よりも広い心で受け止める方法の奮闘記。 2025年4月25日更新 【Arch […]
編集かあさんvol.53 社会の縁側で飛び跳ねる【82感門】DAY2
「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩み […]
編集かあさんvol.52 喧嘩するならアナキズム【82感門】DAY1
「子どもにこそ編集を!」 イシス編集学校の宿願をともにする編集かあさん(たまにとうさん)たちが、「編集×子ども」「編集×子育て」を我が子を間近にした視点から語る。 子ども編集ワークの蔵出しから、子育てお悩み […]
校長に本を贈る 松岡正剛校長に本を贈ったことがある。言い出したのは当時小学校4年生だった長男である。 学校に行けないためにありあまる時間を、遊ぶこと、中でも植物を育てることと、ゲッチョ先生こと盛口満さんの本を読む […]




コメント
1~3件/3件
2025-07-01

発声の先達、赤ん坊や虫や鳥に憑依してボイトレしたくなりました。
写真は、お尻フリフリしながら演奏する全身楽器のミンミンゼミ。思いがけず季節に先を越されたセミの幼虫たちも、そろそろ地表に出てくる頃ですね。
2025-06-30

エディストの検索窓に「イモムシ」と打ってみたら、サムネイルにイモムシが登場しているこちらの記事に行き当たりました。
家庭菜園の野菜に引き寄せられてやって来る「マレビト」害虫たちとの攻防を、確かな観察眼で描いておられます。
せっかくなので登場しているイモムシたちの素性をご紹介しますと、アイキャッチ画像のサトイモにとまる「夜行列車」はセスジスズメ(スズメガ科)中齢幼虫、「少し枯れたナガイモの葉にそっくり」なのは、きっと、キイロスズメ(同科)の褐色型終齢幼虫です。
添付写真は、文中で目の敵にされているヨトウムシ(種名ヨトウガ(ヤガ科)の幼虫の俗称)ですが、エンドウ、ネギどころか、有毒のクンシラン(キョウチクトウ科)の分厚い葉をもりもり食べていて驚きました。なんと逞しいことでしょう。そして・・・ 何と可愛らしいことでしょう!
イモムシでもゴキブリでもヌスビトハギでもパンにはえた青カビでも何でもいいのですが、ヴィランなものたちのどれかに、一度、スマホレンズを向けてみてください。「この癪に触る生き物をなるべく魅力的に撮ってやろう」と企みながら。すると、不思議なことに、たちまち心の軸が傾き始めて、スキもキライも混沌としてしまいますよ。
エディスト・アーカイブは、未知のお宝が無限に眠る別銀河。ワードさばきひとつでお宝候補をプレゼンしてくれる検索窓は、エディスト界の「どこでもドア」的存在ですね。
2025-06-28

ものづくりにからめて、最近刊行されたマンガ作品を一つご紹介。
山本棗『透鏡の先、きみが笑った』(秋田書店)
この作品の中で語られるのは眼鏡職人と音楽家。ともに制作(ボイエーシス)にかかわる人々だ。制作には技術(テクネ―)が伴う。それは自分との対話であると同時に、外部との対話でもある。
お客様はわがままだ。どんな矢が飛んでくるかわからない。ほんの小さな一言が大きな打撃になることもある。
深く傷ついた人の心を結果的に救ったのは、同じく技術に裏打ちされた信念を持つ者のみが発せられる言葉だった。たとえ分野は違えども、テクネ―に信を置く者だけが通じ合える世界があるのだ。