誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)




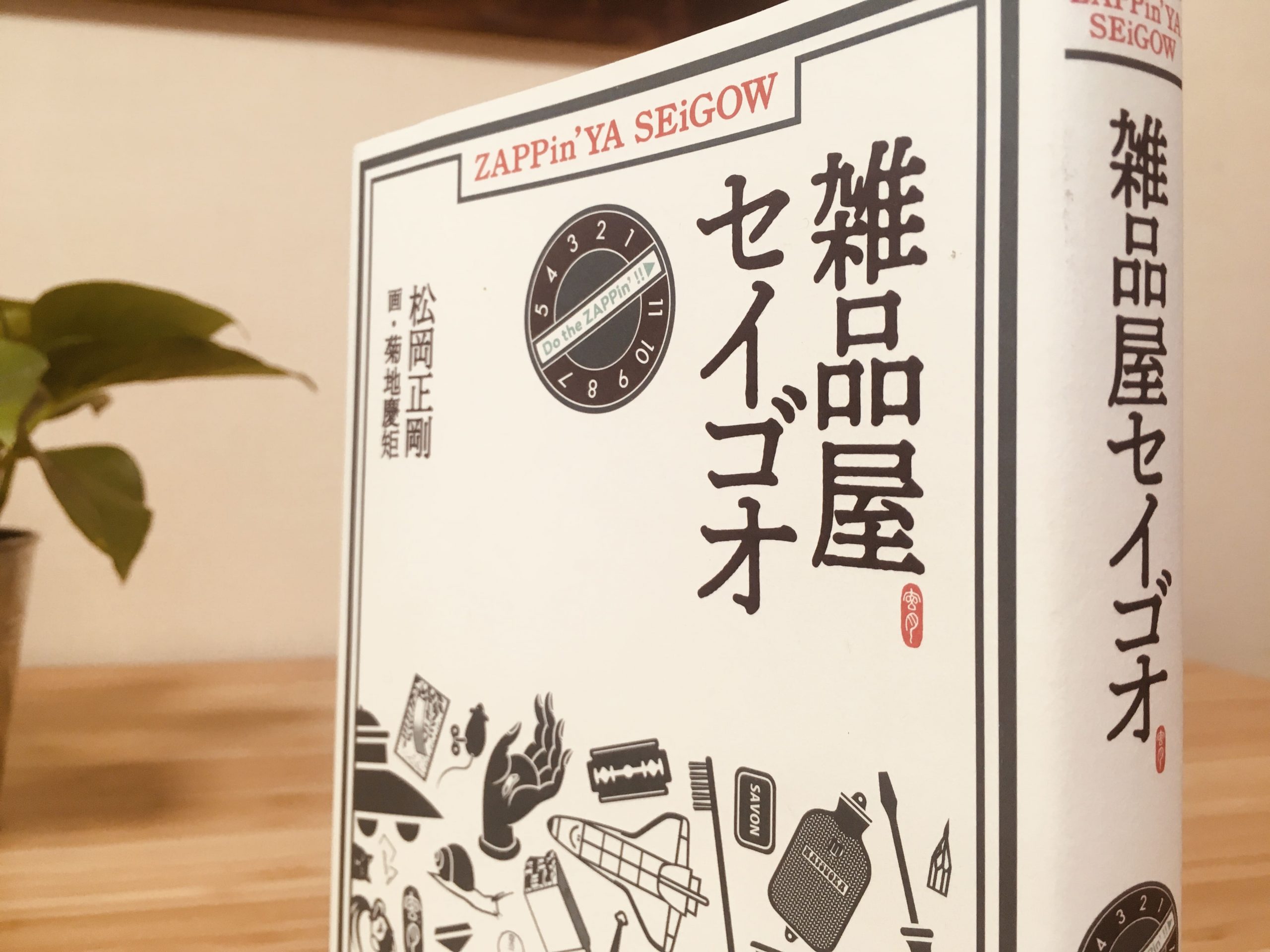
■ スーパーは世界を救うのか
スーパーマンはなんでもできる。迷子の女の子だって救えるし、カリフォルニア地震だって止められる。アメリカを旗振り役に、世界は「スーパー」になりたがっている。スーパーマーケットにスーパーカー。スパコンにスーパーシティ。スーパーはこの世の中を救ってくれるのだろうか。
「アメリカにはハイパーであってほしい」。松岡正剛はかつて、アメリカ出版社の幹部に乞われ、スーパーとハイパーの違いを論じた。スーパーとは「万能」の意。つまり「既存の全システムを包含して、さらによい」という意味だ。では、ハイパーとはなにか。松岡は「特定のものが全体を指示・案内できる」と説明し、例をあげた。黒人選手によるバスケットボールはハイパーである。しかし、その高い身体能力をもつ黒人選手であってもテニスは強いわけではない。けれどもそれでよい、スーパーになる必要はないのだ、と。原稿を読んだ幹部たちは、「マツオカはアメリカのスターになれる」と沸き立ったという。
■ なぜあなたのプランニングは
つまらないのか
4ヶ月にわたるイシス編集学校[破]を締めくくる最終課題は、「ハイパーミュージアムを作れ」というものだ。スーパーミュージアムとハイパーミュージアムは何が違うのか。VRなどの最新テクノロジーを使えばいいのか。あるいはSDGsなど誰しもが賛同する問題を扱えばいいのか。学衆は迷う。突破期限は一週間後に迫っている。師範新井陽大は師範代へむけて、4000字にわたる解題を付けた。「モノに託せ」との手がかりだった。
新井は「抽象的なテーマを選ぶと、具体的なディティールが捨て去られ、プランの雰囲気が似てきます」とありがちな例をまとめてみせた。いわく、こうだ。
1)【資本主義やグローバリズム、環境問題や数値化、コンプライアンスなど】による疲弊を問題視し、
2)【豊かな五感、前近代的な共同体のあたたかみ、宗教・神秘主義、自然とのつながりなど】を取り戻し、
3)人を癒やすためのスーパー装置が用意されたミュージアム。
なんと紋切り型であることか。これは、誰しも納得できる問題に、誰しも納得できる解決策をもちこんだ結果だ。新井は論じ詰める。
「結論ありきで、そこにあてはまる事例を導いておしまい。アブダクションなしの演繹では、関係の発見がないまま終わります」と手厳しい。
林頭吉村堅樹も「最初に大テーマを掲げる“スーパー系”プランは、4-00番を見た時点で05番までのオチがわかる」と見切っている。
■ ワインから宗教をのぞいてみれば
ではよくあるスーパーなプランを、ハイパーな企画へと転向させるにはどうすればよいのか。その方法、モノにある。蝋人形でもオモチャでもなんでも、世界のモノをかき集めても「スーパー」に留まる。しかし、モノから世界を見ればそれは「ハイパー」になる。校長松岡正剛のプランニングがそうなのだ。
松丸本舗や角川武蔵野ミュージアムは、本というひとつのアイテムを断点にし、それによって世界を語り、断然なスペクタクルを展開している。たとえば「宗教」をテーマにしたいのなら、抽象概念として宗教を語るのではなく、「ワインから宗教を見る」仕立てを考えてみればよい。
「そうすると、お酒と宗教のあいだに、煩悩と禁欲、日常と祝祭など、多様な《地》が浮かび上がり、新たなターゲットも発見できる可能性があります」と新井は一点突破の可能性を説く。
モノを持ち込むとなぜ、プランが広がっていくのか。
「モノとは情報の襞が幾重にも折りたたまれたブラックボックスです」
新井は番匠野嶋真帆の言葉を援用しながら、その理由へと迫ってゆく。
「モノは多様な情報が包み込まれた不透明な風呂敷であり、その人に固有の記憶やイメージまでがへばりついて、非線形な思考運動を誘います」
「だから、[守]の001番「コップは何に使える」では千差万別な回答があり、ハイパーな言葉のネットワークが数珠つなぎに出てくるのです。もし、あのお題が『美とは何か』『たくさんのSDGs』だったならば、内容は最大公約数的に収束していくでしょう」
■ フェチからハイパーへ
イシス編集学校は、フェチを大事にする。整髪料や陀羅尼助丸から自分を語ることもできれば、給水塔で守のお題用法1を解き明かすこともできる。入門前であっても、自分のフェチを緒に妄想本屋を作ることだって可能なのだ。蟻の巣穴のようなごく小さなピンホールから世界を見ることで、のっぺらぼうの一般論に侵されない、意外な景色が現出するのである。
ゴム製の月球儀、河原町のシュークリーム、松岡呉服店のホッチキス。1967年、松岡はSF雑誌に自身がフェチなるもののオブジェ感覚を『スーパーマーケット・セイゴオ』と銘打って連載した。スーパーでは大きすぎるとして、2018年『雑品屋セイゴオ』として新装開店を果たす。47[破]では学衆それぞれのフェチなるハイパーミュージアム80棟が急ピッチで建造中である。
▲『雑品屋セイゴオ』表紙より。菊池慶矩氏によるイラスト。
歯ブラシは洗面台から大工箱に、ホタルは草むらから手の中へ、八分音符は小川のほうへ、引き算はたとえば禅寺に、雲形定規はお母さんの鏡台に、移してみるわけだ。「転移性」というのは、知や情報というものは、AからBやCに移したときにこそ、躍るように身についてくるということをさしている。
学習は想像の分母や分子を動かして、初めてナンボというものになる。[…]
ぼくもその線に沿いながら、イシス編集学校で想像力を喚起してもらうべく、さまざまなお題やら対角線やら遊学的な尾鰭を付けたものだ。
※イシスのプランニング編集術を知るなら
※イシスの破を知るなら
『雑品屋セイゴオ』松岡正剛 画・菊池慶矩(春秋社)2018年
写真:梅澤奈央
梅澤奈央
編集的先達:平松洋子。ライティングよし、コミュニケーションよし、そして勇み足気味の突破力よし。イシスでも一二を争う負けん気の強さとしつこさで、講座のプロセスをメディア化するという開校以来20年手つかずだった難行を果たす。校長松岡正剛に「イシス初のジャーナリスト」と評された。
イシス編集学校メルマガ「編集ウメ子」配信中。
大澤真幸が語る、いまHyper-Editing Platform [AIDA]が必要とされる理由
Hyper-Editing Platform[AIDA]は、次世代リーダーたちが分野を超えて、新たな社会像を構想していく「知のプラットフォーム」です。編集工学研究所がお送りするリベラルアーツ・プログラムとして、20年にわ […]
【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】もし順天堂大学現役ドクターが本気で「保健体育」の授業をしたら
編集術を使って、医学ゲームをつくる! 「MEdit Lab for ISIS」は2025夏シリーズも開講します。 そして、7月27日(日)には、順天堂大学にて特別授業を開催。 クラブ員はもちろん、どなたでもご参加いただけ […]
【ARCHIVE】人気連載「イシスの推しメン」をまとめ読み!(27人目まで)
イシス編集学校の魅力は「人」にある。校長・松岡正剛がインターネットの片隅に立ち上げたイシス編集学校は、今年で開校23年目。卒業生はのべ3万人、師範代認定者数は580名を超えた。 遊刊エディストの人気企画「イシスの推しメン […]
イシス最奥の[AIDA]こそ、編集工学の最前線?受講した本城慎之介師範代に聞くSeason5。
イシス編集学校には奥がある。最奥には、世界読書奥義伝[離]。そして、編集学校の指導陣が密かに学びつづける[AIDA]だ。 Hyper Editing Platform[AIDA]とは、編集工学研究所がプロデュースする知と […]
【多読アレゴリア:MEdit Lab for ISIS】編集術を使って、医学ゲームをつくる!?
伝説のワークショップが、多読アレゴリアでも。 2025年 春、多読アレゴリアに新クラブが誕生します。 編集の型を使って、医学ゲームをプランニングする 「MEdit Lab for ISIS」です。 ■MEd […]






コメント
1~3件/3件
2026-02-05

誰にでも必ず訪れる最期の日。
それが、どのような形で訪れるかはわからないが、一番ありえそうなパターンの一つが終末介護病棟での最期じゃないだろうか。沖田×華先生と言えば、自虐ネタのエッセイマンガでよく知られるが、物語作家としても超一流だった。深く死に向き合いたい方は、是非ご一読を。
(沖田×華『お別れホスピタル』)
2026-02-03

鋸鍬形、犀兜、鰹象虫、乳母玉虫、碁石蜆、姫蛇の目、漣雀、星枯葉、舞妓虎蛾、雛鯱、韋駄天茶立、鶏冠軍配、鶉亀虫。見立ては、得体の知れないものたちを、手近に引き寄せたり、風雅に遊ばせることの糸口にもなる。
2026-01-27

タッパーウェアはそのまま飼育ケースに、キッチンペーパーは4分割して糞取り用のシートに。世界線を「料理」から「飼育」に動かしてみると、キッチンにあるおなじみの小物たちが、昆虫飼育グッズの顔を持ち始める。